在宅起訴とは?弁護士が語る実刑リスクと重要な5つのポイント
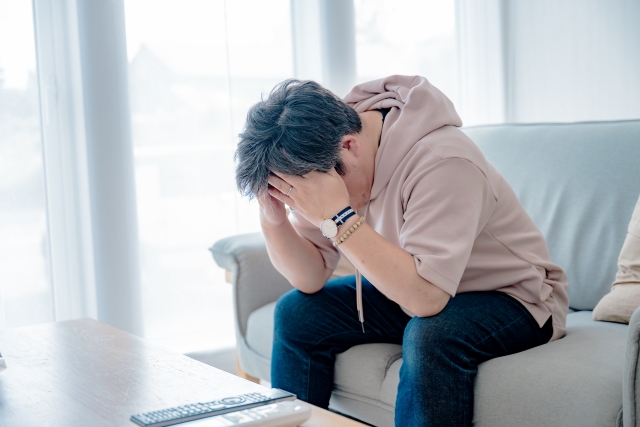
全国20拠点以上!安心の全国対応
初回相談0円
記事目次
在宅起訴、という言葉を聞いたことがありますか?
ニュースなどで耳にしたことがある方もいるかもしれませんが、具体的にどういう意味なのか、どういった場合に行われるのかをご存じの方は、もしかすると多くはないのかもしれません。
本記事では、在宅起訴の具体的な意味やその流れ等に加えて、在宅起訴された場合のその後の流れ等を含めて解説していきます。
在宅起訴とは?
在宅起訴とは、簡単にいうと、自宅で生活しながら刑事事件について裁判所による刑事裁判にかけられる状態のことです。
刑事事件を起こして警察に逮捕されると、通常は身柄事件として警察署の留置施設に身体拘束されます。
身体拘束を受けた状態で裁判を提起されるケースと、身体拘束を解かれた状態で、自宅でいままで通りの生活を行うことを許されつつ裁判にかけられる場合とに分類され、後者のケースが在宅起訴です。
在宅起訴をされると、通常どおり仕事や学校へ行くことが許され、基本的には日常生活に支障はありません。
ですが、当然ながら裁判期日には必ず出席することが求められます。
在宅起訴の流れ
1. 起訴状が届く
起訴状は罪名および被疑事実を記載した書面で、検察官が作成するものです。
在宅起訴されると、起訴状は自宅へ届けられることになります。
起訴状が届いたら、自身が認識している犯罪内容と起訴状に記載された事実とが一致しているか確認することが重要です。
2. 刑事裁判を受ける
起訴状が届いてからしばらくすると、刑事裁判の日付が通知されます。
刑事裁判には必ず出席しなければなりませんので、仕事等の予定については調整する必要があります。
刑事裁判の詳しい流れについては、その点に関する記事に割愛しますが、まずは起訴状の内容や人違いでないことが確認され、証拠をもって検察官が証明したい内容が確認された上で、当該証拠に関する被告人の意見を確認し、状況に応じて被告人質問ないし情状証人の尋問等が行われます。
3. 判決の言い渡し
判決期日は上記刑事裁判期日とは別日に指定されます。
判決期日は裁判期日の終わりに指定されますから、必ず確認してください。
判決の内容については大きく分けて、有罪のものの中には実刑判決、罰金刑の判決、執行猶予付き判決があり、それに加えて無罪判決があります。
在宅起訴されるケースでは、被告人自身犯罪事実を認めていることが多く、かつ、犯罪内容が軽微であることが多いでしょう。
すると、判決内容としても上記のうち、罰金刑の判決ないし執行猶予由貴の有罪判決が下されることが多い、ということができます。
在宅起訴のメリットとデメリット
在宅起訴をされることのメリットは、日常生活を通常通り送ることができるということです。
仕事にも行くことができますし、犯罪を起こす前とほぼ変わらない状況ということができます。
他方で、デメリットについては裁判所からの呼び出しには必ず応じなければならないということです。
在宅起訴が許されるのは、裁判期日に必ず出頭することができる前提ですから、裁判期日に来ないとなると、身柄拘束される可能性が十分に出てきます。
在宅起訴の要件
1. 比較的軽微な事件であること
在宅起訴されるということは、身柄拘束する必要がないということですから、逃亡ないし証拠隠滅のおそれがなく、かつ、身柄拘束(逮捕勾留)する必要性が認められないことが必要です。
軽微な事件の場合には、上記要件を充たすことが多く、逆に重大犯罪では身体拘束を行った上で裁判を行う必要性が高くなります。
2. 逃亡の恐れ、証拠隠滅の恐れがない
上記①に記載したとおりです。
3. 身体拘束により被疑者に生じるデメリットが大きい
逮捕勾留の必要性は、被疑者自身の事情についても考慮されます。
たとえば、被疑者が高齢で刑事施設での生活に耐えられないとか、重大な病気を患っており、主治医による定期的な治療等が必要な場合等は身体拘束を行わずに、在宅起訴する選択肢が検討されることになります。
在宅起訴となるための条件
在宅起訴となるための条件について、初犯で窃盗を行った若年の会社員Bさんのケースを挙げてみましょう。
Bさんはスーパーで商品を万引きし、防犯カメラの映像から犯行が発覚。
警察の任意出頭要請に素直に応じ、犯行を認めました。
被害品はすでに返却され、店舗側とも示談が成立しています。
Bさんは定職に就いており、逃亡や証拠隠滅の可能性も低いことから、逮捕・勾留されることなく、在宅での起訴が選択されました。
このように、在宅起訴は「事件の軽微性」「被疑者の態度」「社会的事情」などを総合的に考慮したうえで判断される処分です。
事件によっては、同様の罪でも態度や状況次第で身柄拘束となることもあり得ますので、状況ごとに慎重な判断が必要です。
在宅起訴になった場合も、決して軽視できるものではなく、適切な対応が求められます。
在宅起訴されるまでの流れ
1. 犯罪の認知
捜査機関が犯罪を認識することです。
通報、被害者による被害届の提出、犯罪を行った者による自首等、捜査機関が犯罪を認識する端緒には様々なものがあります。
2. 捜査機関による捜査
警察等の捜査機関が、認知した犯罪について捜査することになります。その上で、捜査結果を資料にまとめます。
この際、犯罪の嫌疑をかけられた本人の取り調べや被害者からの事情聴取、犯行現場の実況見分等が行われ、すべて書類にまとめられて、後の裁判の証拠となります。
3. 検察官送致
事件が警察から検察へ送られます。
ニュースでよく、書類送検、という言葉を耳にしますが、これは正確には法律用語ではありません。
事件が検察庁へ送られると、担当の検察官が事件の記録を検討し、被害者ないし被疑者自身から話を聞く等して、事件を起訴するかどうか判断します。
起訴後の対応
起訴には、正式起訴と略式起訴の2種類があります。
起訴された被告人が裁判所へ出頭して裁判所による刑事裁判を受ける手続きが正式起訴、書類のみの審査で終わり、裁判所へ出頭する必要がないものが略式起訴です。
略式起訴をするためには、軽微な犯罪であること(法定刑で罰金刑100万円までの犯罪であること)、および被疑者自身が略式裁判を受けることに同意していることが必要です。
正式裁判になる場合には、すでに説明した流れで起訴状を受け取り、裁判の日に裁判所へ出頭して、刑事裁判を受けることになります。
他方で、略式起訴の場合には裁判所へ行く必要はなく、判決がなされるのを待つことになります。
判決までの流れ
判決は裁判の日の当日に言い渡されるケースもありますが、判決期日を改めて指定されて判決の言い渡しが行われることもあります。
判決の内容には、懲役刑、禁錮刑、罰金刑等があり、懲役刑や禁錮刑には執行猶予が付くものと付かないものがあります。
執行猶予付き判決が下された場合、簡単にいうと刑務所に行く必要はありません。
注意しなければならないのは、執行猶予期間が満了するまでの間に何かしらの犯罪を起こしてしまいますと、前の執行猶予付きの刑の分とあわせて刑事罰を科される等、厳しい処分を受ける可能性があります。
したがって、執行猶予期間中は最新の注意をもって生活を送ることが必要となります。
他方で実刑判決を受けた場合、刑務所へ収監されます。
この場合において、在宅で起訴された状態から、判決言い渡し後直ちに刑務所へ収監することは多くはないでしょうから、判決から一定期間を経て刑務所での生活を開始することになります。
その他、罰金判決の場合には、罰金を納付することで刑事罰が完了することになります。
罰金は一括納付となりますので、資金を調達しておくことが必要となります。
なお、判決に不服がある場合、判決を受けた日の翌日から起算して14日以内であれば控訴することができます。
この期間を徒過しますと控訴できなくなりますので、上記期間を遵守することは極めて重要です。
在宅起訴と逮捕・勾留の違い
上記のとおり、在宅起訴は被告人の身柄拘束を行わない状態で事件を刑事裁判にかけることで、この場合、被告人は基本的に普段通り日常生活を送ることができます。
逮捕勾留は被疑者の身体を拘束して事件に関する取り調べ等を行い、事件を起訴するかどうか判断するための証拠集めを行う手続ですから、基本的に被疑者の身体の自由は制限されており、仕事等に行くこともできません。
そういった意味で、在宅起訴と逮捕勾留とは大きく状況が異なります。
弁護活動の違い
在宅起訴事件と身柄拘束を受けた状態で起訴される事件とを比べますと、弁護人が行う弁護活動にも違いがあります。
在宅起訴事件の場合には弁護人が被告人との打ち合わせを行う場合には警察署等の留置施設へ赴く必要がありません。
ですので、身柄拘束されている事件と比べると弁護人と被告人との打ち合わせはスムーズに行うことができます。
なお、被害者との示談交渉が必要となる事件では、被害者との交渉を行う役割を担うのが弁護人であることは両者ともに変わりません。
在宅の状態で起訴をされたあとに被害者との示談を試みる場合には、弁護人が被害者との接触等を試みて示談交渉を行い、無事示談が成立した場合には示談書等を弁護側の証拠として裁判所へ提出します。
示談書等の存在は通常、被告人の量刑を決める判断資料となります。
在宅起訴のリスク
在宅起訴といっても、必ずしも事件が軽微であることを意味しませんのでその点には注意が必要です。
たとえば、考えられるケースとしては当初逮捕勾留されて身柄事件として捜査されていた事件について、途中で勾留状態が解かれて在宅事件となったあとに刑事事件として起訴されるものです。
この場合、重大事件の場合には、被告人の前科前歴にもよりますが実刑判決を受け、結果的に刑務所へ収容される可能性も否定できません。
また、在宅事件のもうひとつのリスクとして考えられるのは、身柄事件と比べて裁判手続に時間がかかることが多いので、その分裁判を受ける被告人の精神的な負担が長引く、ということが考えられます。
実刑判決につながるケース
在宅起訴事件において、実刑判決につながり得るケースとして考えられるものには、次のものがあります。
1. 再犯の場合
同種前科がある場合、後に行われた事件に対しては裁判所が厳しく処罰を下す傾向があります。
したがって、この場合には在宅起訴事件であっても実刑判決がなされる可能性があがります。
2. 重大犯罪の場合
在宅起訴事件であっても、事件が重大である場合も考えられ、この場合には実刑判決がなされる可能性があります。
たとえば、被害者に対する詐欺事件等は、社会的にも重く処罰される傾向がありますから、実刑判決を受ける可能性があります。
3. 被告人に反省の意がみられない場合
裁判所が被告人の量刑を決めるにあたって、被告人の事件に対する向き合い方や反省態度も考慮にいれることが一般的です。
被告人において事件に対する反省の意が感じられないと裁判所が判断する場合には、他の要素とも相まって刑判決がなされることもありえなくはありません。
まとめ
本記事では、在宅起訴に関する様々な内容をみてきました。
在宅起訴という言葉それ自体はあまり聞きなれないかもしれませんが、刑事事件に関わってしまった場合にはだれにでも起こり得るケースといっても過言ではありません。
ご自身または周りの方が刑事事件を起こして在宅の状態で刑事裁判になった場合に、本記事が今後の見通し等を理解していただく一助になれば幸いです。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設




















