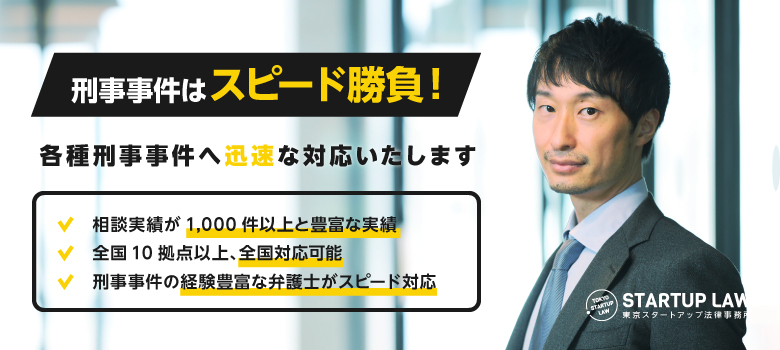執行猶予とは?前科がつく?執行猶予が得られる条件、実刑判決との違いを解説

全国20拠点以上!安心の全国対応
初回相談0円
記事目次
「執行猶予を得るためには、どのような条件を充たす必要があるの?」
「執行猶予と実刑判決には、どのような違いがあるの?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、刑の全部の執行猶予と刑の一部の執行猶予、保護観察制度の概要、実刑判決と執行猶予判決の違い、執行猶予を得られる可能性がある事件、執行猶予を得られる可能性が低い事件などについて解説します。
執行猶予とは
執行猶予とは、有罪判決が下された事件で、犯罪行為に関する具体的な事情により、必ずしも現実的な刑の執行を必要としないと判断された場合に、1年以上5年以下の期間その執行を猶予し、猶予期間経過後に当該事件についての刑罰権を消滅させる制度です。
執行猶予期間が満了すると刑の言い渡しの効力や資格制限等が、将来に渡って消滅します。
ただし、執行猶予中に犯罪を犯した場合など、一定の事由が生じた場合は、執行猶予が取り消される可能性があります。
執行猶予判決には、刑の全部の執行猶予と一部の執行猶予の2つの種類があります。
執行猶予がつく割合
事案によりますが、日本の刑事事件では、実刑判決のうち約6~7割に執行猶予が付されます。
特に、初犯や情状が考慮されるケースでは猶予付き判決となることが多いですが、再犯や悪質性が高い場合は実刑となる傾向があります。
執行猶予がつくとどうなるのか
執行猶予が付くと、判決で言い渡された刑の執行が一定期間猶予され、その間に再犯などがなければ刑の執行が免除されます。
つまり、刑務所に入らずに社会内で生活を続けることが可能です。
ただし、猶予期間中に再犯や重大な違反があれば、猶予が取り消されて実刑が執行されます。
執行猶予の具体例
執行猶予の具体例としては、詐欺罪で起訴された特殊詐欺の受け子の事案があります。
被告人は、組織的詐欺グループの受け子として被害者から600万円もの多額の現金を受け取っていました。
被告人は詐欺罪で起訴されましたが、弁護人が被害者と示談交渉を行い、被害金額の全額を弁償し、被告人を宥恕する内容での示談を成立させました。
この示談活動が裁判所にも評価され、裁判所は被告人に対し、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。
執行猶予が取り消しされる割合
執行猶予が取り消される割合は、執行猶予付きの判決が出た全体の割合でいうと、約10%程度とされています。
特に保護観察付き執行猶予の場合、取り消し率は約25%と高くなります。
罪名別では、常習性の高い犯罪でもある、覚せい剤取締法違反及び窃盗が高い傾向にあります。
執行猶予が必ず取り消しされるケース
執行猶予が必ず取り消されるのは、法律上「必要的取消し」とされているケースであり、次のような場合が該当します。
まず、執行猶予期間中に新たに犯した罪について「禁錮以上の刑」が確定したときです。
たとえば、猶予中に窃盗や傷害などで起訴され、有罪判決を受けて懲役刑や禁錮刑が言い渡された場合、その時点で刑の執行猶予が自動的に取り消され、新たに犯した罪の刑と併せて、刑務所に服役することになります。
次に、執行猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときも、執行猶予が取り消されます。
さらに、執行猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したときも、執行猶予が取り消されます。
執行猶予の必要的取消しとなる場合は、執行猶予中の再犯のケースがほとんどですので、執行猶予中の再犯については注意してください。
執行猶予が取り消しされる可能性があるケース
執行猶予が取り消される場合として、裁判所の判断による「裁量的取消し」と呼ばれるものがあります。
猶予期間中に罰金刑を受けた場合や、保護観察付きで指導命令に違反した場合、猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚した場合などです。
たとえば、交通違反で罰金を科されたり、保護観察中に定期報告を怠った場合などが挙げられます。
また、犯罪に至らなくても素行不良が続いた場合も対象となることがあります。
刑の全部の執行猶予の要件
刑の全部の執行猶予の要件は、初回の執行猶予(刑法第25条第1項)と再度の執行猶予(刑法第25条第2項)では異なります。
1.初回の執行猶予の場合
初回の執行猶予では、下記のいずれかに該当する被告人が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けたときに、裁判官の裁量により刑の全部の執行を猶予します。
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2.再度の執行猶予の場合
再度の執行猶予の要件は「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるとき」です。
執行猶予を受けられる刑の重さが「1年以下の懲役又は禁錮」に限定され、初回の執行猶予の要件よりも厳しくなっています。
刑の一部の執行猶予
刑の一部の執行猶予(刑法第27条の2)は、2013年の刑法改正で新設され、2016年6月に施行された制度です。
刑法第27条の2第1項が「犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるとき」と規定するように、特に再犯防止を目的とした制度です。
1.一部の執行猶予とは
一部の執行猶予とは、3年以下の懲役又は禁錮の言い渡しに対してその一部(例えば2年間の懲役)は実刑判決となり、残りの期間(例えば1年間)についてはその執行を1年以上5年以下の期間、猶予することを意味します。
これまでの執行猶予制度の下では、実刑判決を受けて服役中に仮釈放された人に対しては保護観察に付すことが可能でしたが、実刑判決の服役期間満了により刑務所を出所した人に対しては保護観察に付すことができず、刑期満了者による再犯事例が多いという問題がありました。
刑の一部の執行猶予により、実刑判決の一部を執行した上でその期間満了後に最長5年までの執行猶予期間を設け、その期間満了まで保護観察をつけることができることになりました。
薬物犯罪者や、精神的な疾患により万引きを繰り返す人など、保護観察により更生を支援して再犯を防ぐ必要性が特に大きい人に対する再犯防止効果が期待されています。
2.一部の執行猶予を受ける可能性があるケース
刑の一部の執行猶予を受ける可能性があるのは、下記のいずれかに該当する被告人が3年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときです。
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
- 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
保護観察制度の概要
刑の全部又は一部の執行猶予の判決を受けた場合に、裁判官の裁量あるいは法的義務により、執行猶予期間中に保護観察制度に基づく保護観察処分が付されます。
1.保護観察制度とは
保護観察制度は、犯罪行為者又は非行のある少年が社会の中で保護観察所の指導監督を受けながら更生を図る制度です。
2.保護観察の対象者
保護観察の対象者は、以下のように定められています。
- 非行により家庭裁判所から保護観察の処分を受けた少年
- 非行により家裁から少年院送致処分を受けて少年院を仮退院となった少年
- 懲役又は禁錮の刑に処せられていたが仮釈放となり更生保護法第40条の規定により保護観察処分を受けた者
- 刑の執行猶予と併せて保護観察付の言い渡しを受けた者
「刑の執行猶予」は、2016年6月より施行されている刑の一部の執行猶予を含みます。
3.保護観察対象者の遵守事項
保護観察処分を付された場合、更生保護法第50条が定める以下のような一般遵守事項(保護観察対象者全員の遵守事項)に従わなければなりません。
- 再犯・再非行をしないよう健全な生活態度を保持すること
- 保護観察官や保護司による指導監督を誠実に受けること
- 住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長に届け出をすること
- 届け出をした住所に居住すること
- 転居又は7日以上の旅行をするときはあらかじめ保護観察所の長の許可を受けること
すなわち、一定の住所で規則正しい生活を送ること、非行の傾向のある人との付き合いを避けること、保護観察官や保護司に対して定期的に近況報告を行うこと等が求められます。
これに加えて、保護観察処分付執行猶予判決を受けた者それぞれの犯罪傾向に応じて保護観察所長が個別に定めた「特別遵守事項」に従う必要があります。
実刑判決と執行猶予判決の違い
実刑判決も執行猶予判決も、裁判を経て下される有罪判決である点は同じです。
両者の違いは、刑が直ちに執行されるか、一定期間猶予されるかという点です。
1.実刑判決が確定した場合の効力
実刑判決が確定した場合、一定の例外の場合を除いてその刑が執行されます。
第一審・第二審の裁判で判決を言い渡されてから14日間は上訴することができるので、この期間は刑の執行は行われませんが、閉廷後ただちに身柄を拘束されて拘置所に移送されます。(保釈されていた場合は判決言い渡しと同時に保釈が失効し、勾留されていた場合は引き続き拘束されます。)
上訴せず、あるいは最高裁で上告棄却の判決を言い渡されてから14日が経過すると実刑判決が確定して拘置所から刑務所に移送されます。
ただし、死刑判決が確定した場合は法務大臣の執行命令が出されるまで拘置所に拘置されます。
なお、有期懲役・禁錮刑と拘留刑に対しては未決勾留日数を刑期に参入します。
未決勾留日数とは、最初に勾留されてから判決が確定する日の前日までの期間のうち実際に勾留されていた日数です。
期間の計算方法は法律で算入を義務付けられている期間(上訴の提起期間に関して刑訴法第495条が定める期間等)及び裁判官の裁量で算入可能な期間がありますが、起訴前の勾留期間は算入されません。
2.執行猶予判決が確定した場合の効力
①刑の全部の執行猶予の場合
刑の全部の執行猶予を付された判決が言い渡された場合、判決を受けた人は閉廷と同時に釈放されます。
判決前に勾留されていた場合は、一度拘置所に荷物を取りに戻ってから帰宅できます。
判決が確定した場合、保護観察処分が付せられている人は早期に保護観察官との面談を受け、定めた住居で保護観察官や保護司の指導監督を受けながら遵守事項を守った生活を始めることになります。
保護観察処分が付せられていない場合は、法律で禁止されている事項を除いて通常の生活を送ることが可能になります。執行猶予期間中に新たに犯罪行為で起訴され有罪判決を受ける等の事由で執行猶予を取消されることがなく猶予期間を経過した時点で、刑の言渡しは効力を失います(刑法第27条)。
②刑の一部の執行猶予の場合
刑の一部の執行猶予を付された判決が言い渡された場合、判決が確定するまでは実刑判決の場合と同様に拘置所に身柄を拘束されます。判決確定後は、猶予を受けなかった期間について懲役刑または禁錮刑が執行され服役することになります(刑法第27条の2第2項)。
その期間が終了すると執行猶予期間が始まり、刑の全部の執行猶予判決が確定した場合と同様、執行猶予が取り消されずに期間を経過した時点で「猶予を受けなかった期間を刑期とする懲役又は禁錮刑」の執行を受け終わったことになります(同法第27条の7)。
執行猶予を得られる可能性がある事件
1.刑の全部の執行猶予を得られる可能性がある事件
例えば、住居侵入罪(刑法第130条前段)で起訴された事件で初犯の場合等は、法定刑(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)及び第25条1項1号の要件を満たすので執行猶予を得られる可能性が高くなります。
また、法定刑の長期が懲役・禁錮3年/罰金50万円を超える犯罪を含む事件で、犯情や過去の事例からみて懲役・禁錮3年以下/罰金50万円以下の判決が見込まれ、かつ刑法第25条1項の要件を充たしている場合も刑の執行猶予を得られる可能性があります。
2.刑の一部の執行猶予を得られる可能性がある事件
刑の一部の執行猶予には特に再犯防止という目的があることから、刑法第27条の2に定める要件を満たすことに加え、刑の一部の執行猶予を付すことが必要かつ相当であるかという点が特に考慮されます。
薬物犯罪や窃盗罪の再犯等、保護観察処分の中で更生と再犯防止のためのプログラムが用意されていて、それを受講することが望ましい場合等が、刑の一部の執行猶予を得られる可能性がある事件に該当します。
執行猶予を得られる可能性が低い事件
刑の執行猶予を得られる可能性がない事件、可能性が低い事件も存在します。
具体的にどのような事件か説明します。
1.執行猶予を得られる可能性がない事件
法定刑の有期懲役の短期が3年を超える犯罪の被疑事件については、執行猶予を得られる可能性がありません。
例えば、殺人罪(刑法第199条)のように、法定刑が死刑・無期懲役若しくは5年以上の懲役と定められている場合は、犯情により情状酌量を最大限に行っても懲役5年となり、刑法第25条及び第27条の2の要件にあてはまらないことになります。
また、過去に禁錮以上の刑に処せられ保護観察処分付執行猶予を付された人が、その保護観察期間内に再び犯罪容疑で起訴され有罪判決を受けた場合は、その犯罪の処断刑の軽重を問わず執行猶予を得られる可能性がありません(刑法第25条2項但書)。
2.執行猶予を得られる可能性が低い事件
執行猶予を得られる可能性が低いのは、法定刑の長期が3年を超える懲役刑・禁錮刑または罰金刑の多額が50万円を超える犯罪の事件で犯情が重い場合です。
例えば、詐欺罪(刑法第246条)や業務上横領罪(刑法第253条)の事件で被害金額が数千万円に及ぶ場合や、その被告人が同一または複数の被害者に対して反復継続して詐欺行為・横領行為を行っていたような場合は3年を超える有期懲役の実刑判決が下される可能性が高くなります。
執行猶予に関するよくある質問と回答
最後に、執行猶予に関してよくある質問とそれへの回答をご紹介したいと思います。
1.執行猶予は最長で何年ですか?
執行猶予の最長期間は、裁判が確定した日から5年です。
執行猶予の期間は、刑事事件を担当した裁判官の裁量により、1年~5年の間の期間が定められます。
一般的には、懲役刑の2倍の期間を執行猶予期間として定めることが多いです。
2.執行猶予判決を得られた場合は前科はつきませんか?
執行猶予判決を得ることができても、前科がつくことは避けられません。
前科とは、有罪判決に処せられた履歴のことをいいます。執行猶予は、有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予する制度です。
そのため、執行猶予判決を得ることができても有罪判決を受けた事実が変わることはないため、前科は残ることになります。
3.執行猶予中に就職することはできますか?
執行猶予中は、弁護士、税理士など、一部の国家資格業務に就くことはできませんが、民間企業に就職することは法律上禁じられていないので可能です。
ただし、「賞罰」欄のある履歴書の提出が義務付けられている会社への就職を希望する場合は、賞罰欄に犯罪名や執行猶予中である旨を記載する必要があります。
また、賞罰欄のある履歴書の提出が義務づけられていない場合でも、書面または口頭で執行猶予中である旨を伝える必要があります。その事実を秘匿して採用された場合、発覚すれば懲戒解雇される可能性が高いです。
4.執行猶予中に海外旅行に行くことは可能ですか?
有罪判決を受けた場合に旅券を返納する義務や海外渡航の禁止等を定めた法律は存在しません。
既に取得した旅券の有効期限内は日本からの出国は可能です。
ただし、渡航先の国で入国を拒否される場合があるという点には注意が必要です。
旅券の有効期限が切れた場合に新たに旅券を取得できるかどうかという点について、旅券法は「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」について旅券を発給しないことができると定めています(同法第13条1項3号)。
したがって、3年以下の懲役刑または禁錮刑に処せられて執行猶予中である場合、旅券の発給を拒否される可能性があります。
5.執行猶予と保護観察の違いは?
執行猶予と保護観察は混同されがちですが、次のような違いがあります。
執行猶予とは、裁判で有罪判決を受けた場合に、刑の執行を一定期間猶予する制度です。
一方、保護観察は、その猶予期間中に再犯を防ぐため、保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら社会内で生活する制度です。
すなわち、執行猶予は「刑の猶予」であり、保護観察は「監督つきの更生支援」と言えます。
執行猶予が付されても必ず保護観察が付くわけではなく、裁判所の判断により決定されます。
| 執行猶予 | 保護観察 | |
|---|---|---|
| 定義 | 有罪判決後、刑の執行を一定期間猶予する制度 | 更生を目的とした社会内での指導・監督制度 |
| 対象者 | 一般的な有罪者 | 執行猶予中の者や再度の執行猶予者 |
| 実施主体 | 裁判所 | 保護観察官・保護司 |
| 目的 | 刑の執行を猶予し、社会復帰の機会を提供 | 再犯防止と社会復帰の支援 |
| 必要性の有無 | 任意(裁判所の判断による) | 再度の執行猶予には必須 |
| 遵守事項 | なし | あり(遵守事項の遵守が求められる) |
まとめ
今回は、刑の全部の執行猶予と刑の一部の執行猶予、保護観察制度の概要、実刑判決と執行猶予判決の違い、執行猶予を得られる可能性がある事件、執行猶予を得られる可能性が低い事件などについて解説しました。
ご本人またはご家族が、執行猶予を得られる可能性のある事件で逮捕された場合、執行猶予を得るためには、できる限り早急に、刑事事件に精通した弁護士に相談することが大切です。
私達、東京スタートアップ法律事務所は、刑事事件で逮捕されたなどの問題を抱えているご本人やご家族の気持ちに寄り添い、ご本人の大切な未来を守るために全力でサポートさせていただきたいと考えております。
検察官や捜査機関の考え方を熟知している元検事の弁護士も所属する刑事事件に強いプロ集団が、ご相談者様の状況やご意向を丁寧にお伺いした上で的確な弁護戦略を立て、迅速に対応致します。
秘密厳守はもちろんのこと、弁護士費用の分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設