養育費と財産分与は相殺できる?ルールや事例を紹介
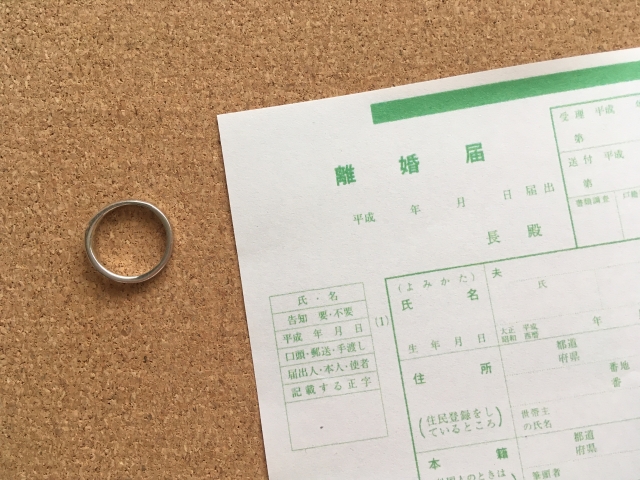
全国20拠点以上!安心の全国対応
60分3,300円(税込)
離婚とあわせて不貞慰謝料でも
お悩みの場合は無料相談となります
※
※
記事目次
離婚を考える際、「お金のことはなるべくシンプルにしたい」と感じる方は少なくありません。
「将来にわたって支払い続ける養育費と、離婚時に一括で受け取る財産分与を『相殺』して、一度に解決できないだろうか?」というご質問をよくいただきます。
しかし、結論から申し上げると、養育費と財産分与を当事者の都合で相殺することは原則として認められていません。
なぜなら、この二つのお金は「誰のためのものか」「何のためのものか」という根本的な性質が全く異なるからです。
この記事では、養育費と財産分与それぞれの法的な意味合いを解説し、なぜ相殺ができないのか、そして離婚時のお金に関する重要な注意点について、分かりやすくご説明します。
養育費とは何か
養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要となる生活費、教育費、医療費など、監護や教育のために必要な費用のことです。
親が子どもを扶養する義務は、たとえ離婚したとしてもなくなることはありません。
子どもを直接監護・養育していない親(非監護親)が、実際に子どもを育てている親(監護親)に対して支払うのが一般的です。
これは、あくまで「子どもの権利」として認められているものであり、親が勝手に放棄したり、受け取らないと決めたりすることはできません。
養育費の金額や支払いの終期について
養育費の金額や「いつまで支払うか」について、法律で一律に金額や年齢が定められているわけではありません。
基本的には、夫婦間の話合いによって自由に決めることができます。
話合いで合意できない場合は、家庭裁判所の調停や審判といった手続を通じて決定することになります。
養育費の金額について、家庭裁判所の調停や審判では、、後述する「養育費算定表」を参考に算出されるのが一般的です。
支払いの終期(いつまで支払うか)は、かつては「成人するまで(20歳)」とされることが多かったですが、民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられたことや、大学進学率の上昇などを背景に、「18歳に達した後の3月まで」や「大学を卒業する月まで」など、個別の事情に応じて柔軟に定められる傾向にあります。
養育費算定表とは
「養育費算定表」とは、裁判所が養育費の標準的な金額を簡易・迅速に算出するために作成し、公表している表のことです。(出典:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」)
この算定表は、支払う側と受け取る側の年収、そして子どもの人数・年齢に応じて、養育費の月額がどのくらいの範囲に収まるかを示しています。
法的な拘束力はありませんが、審判や裁判においては、この算定表が非常に重視されており、特別な事情がない限り、算定表に基づいた金額で養育費が決定されることがほとんどです。
夫婦間の話合いにより養育費を決定する場合にも、この算定表が参考にされることもあります。
財産分与とは何か
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた共有財産を、離婚時に当該共有財産の形成についてのそれぞれの貢献度に応じて公平に分配することを指します。(出典:e-Gov法令検索「民法」第七百六十八条
たとえ専業主婦(主夫)であっても、家事や育児を通じて財産の維持・形成に貢献したとみなされ、財産分与の割合は原則として2分の1とされており、2分の1以外の有利な割合を主張する者が、その主張する割合になるべき特別の事情を主張すべきとされています。
財産分与には、その目的によって以下の3つの種類があります。
- 清算的財産分与:婚姻中に夫婦で協力して得た財産を公平に清算・分配するもの。これが財産分与の基本です。上述の「財産分与とは何か」の解説も、基本的にはこの清算的財産分与について当てはまるものです。
- 扶養的財産分与:離婚によって一方の配偶者が経済的に困窮してしまう場合に、その生活を補助するために行われるもの。
- 慰謝料的財産分与:不貞行為やDVなど、離婚の原因を作った側が相手方に支払う慰謝料の性質を含むもの。
専業主婦の方の財産分与については、「【専業主婦だけど離婚したい】貧困生活に陥らない離婚成功術!財産分与の割合は」の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
財産分与の対象となるもの
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して得た「共有財産」です。どちらか一方の名義になっている財産でも、実質的に夫婦の協力によって得られたものであれば対象となります。
対象となるもの
- 預貯金:夫婦それぞれ名義の預貯金
- 不動産:住宅や土地など
- 自動車
- 保険:生命保険や学資保険の解約返戻金
- 有価証券:株式、投資信託など
- 退職金・年金:将来受け取る予定のものも含む
対象とならないもの(特有財産)
- 婚姻前から所有していた財産
- 婚姻中に親から相続した遺産や贈与された財産
財産分与の対象について、より詳しくは「離婚に伴う財産分与の対象となるものとは?分配割合や手続きの流れをわかりやすく解説」で解説しています。
養育費と財産分与は原則として相殺できない
養育費と財産分与を相殺(民法505条)することは、原則としてできません。
その理由は、養育費については相殺が禁止されていることと、子の権利を親が勝手に処分することができないからです。
まず、養育費は、生計を維持するために継続的に支給を受ける費用であり、監護親の非監護親に対する養育費分担請求権は民事執行法152条1項1号により差し押さえが禁止されています。
そして、民法510条により、差し押さえが禁止されている権利は相殺が禁止されています。
したがって、監護親の非監護親に対する養育費分担請求権について、相殺することはできないことになります。
次に、養育費分担請求権は親の権利でしたが、子も親に対して養育費支払請求権を有するところ、子の親に対する養育費支払請求権を相殺することは、子の扶養を受ける権利の処分に当たり、民法882条によって禁止されています。ここでは、法律が、子どもが養育され成長するための権利を重要視していることが見て取れます。
したがって、たとえ夫婦間で「財産分与を請求する権利と養育費を分担してもらう権利とを相殺する、打ち消す」といった合意をしたとしても、法律上の相殺(民法505条)とこの相殺の合意とは法律上の性質は異なるとしても、法律上の相殺が禁止されていることから、この相殺合意も法的に無効とされるおそれがあります。
また、子はそもそもこの合意の当事者ではないですし、子の養育費請求権を処分することはできないため、子の養育費請求権においては、その合意は法的に無効と判断される可能性が非常に高いです。
扶養的財産分与は養育費を含むのか
財産分与の一種である「扶養的財産分与」と養育費は、どちらも経済的に弱い立場にある側を支えるという点で似ているため、混同されることがあります。しかし、これらも全くの別物です。
扶養的財産分与とは何か
扶養的財産分与は、離婚によって夫婦の一方が経済的に著しく困窮する場合に、その生活を扶助する目的で支払われる財産分与です。
例えば、長年専業主婦(主夫)であったり、高齢や病気などの理由で、離婚後すぐに自立した生活を送ることが困難な場合に認められることがあります。
あくまで夫婦間の扶養の問題であり、清算的財産分与だけでは不公平が生じる場合に、それを補うための例外的な制度と位置づけられています。
支払い方法も、一括払いだけでなく、定期的な支払い(毎月〇万円など)が認められることもあります。
扶養的財産分与と養育費は目的が異なる
扶養的財産分与と養育費の最も大きな違いは、誰を扶養(サポート)するのかという点です。
- 扶養的財産分与:経済的に困窮する元配偶者を支えるためのお金
- 養育費:未成熟の子どもを育てるためのお金
このように、扶養の対象者が明確に異なります。したがって、扶養的財産分与が支払われたとしても、それは養育費の代わりにはならず、養育費は別途請求することができます。
養育費と財産分与に関する事例
養育費と財産分与の相殺について、類似の事案に関して裁判所がどのように判断したかを示します。
大阪高決昭和31年9月26日
その裁判例の事案は、父が母に対して財産分与として金銭を支払い、母が子の親権者となり、父母双方名義の如何を問わず何らの請求をしないことを内容とする調停をした場合において、子が父に対して養育費を請求したというものです。
裁判所は、父は子に対して養育費を支払うべきとの判断をし、その理由としては、父母間の調停があるとしてもそれは父母間の取り決めで子には関係のない事柄であり、また、「何らの請求をしない」という取り決めのなかに子の養育費請求権を含める趣旨であったとしても、民法881条により予め扶養に関する権利は処分できないとされていること等を挙げています。
つまり、一度は「養育費を請求しない」と合意したとしても、その合意は無効であり、後からでも養育費は請求できると示したのです。この事例からも、裁判所がいかに「子どもの利益」を重視しているかが分かります。
離婚時に財産分与の割合を決める方法
財産分与の割合は原則2分の1ですが、その具体的な分け方やどの財産をどう分けるかについては、以下の手続で決めていくのが一般的です。
1. 夫婦間の協議(話合い)
まずは夫婦で直接話し合います。財産リストを作成し、お互いが納得できる分け方を決めます。合意した内容は、後々のトラブルを防ぐためにも、必ず「離婚協議書」や「公正証書」といった書面に残しましょう。
2. 離婚調停
話合いで合意できない場合や、相手が話合いに応じない場合は、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚)」の申立てを行います。調停委員という中立な第三者が間に入り、合意形成を目指します。
3. 離婚訴訟(裁判)
調停でも話がまとまらない場合は、最終的に訴訟を提起し、裁判官に判断を委ねることになります。裁判では、提出された証拠に基づいて、裁判所が財産分与の方法や金額を決定します。
養育費と財産分与の問題を弁護士に相談するメリット
養育費や財産分与は、離婚後の生活設計に直結する非常に重要な問題です。しかし、感情的な対立も絡むため、当事者同士での冷静な話合いは難しいことも少なくありません。このような問題を専門家である弁護士に相談することには、多くのメリットがあります。
1. 適正な金額を算定・請求できる
弁護士に依頼すれば、財産調査や法的な知識に基づき、受け取るべき養育費や財産分与の適正な金額を算出してくれます。
相手方が財産を隠しているようなケースでも、弁護士会照会などの制度を利用して調査を進めることが可能です。
2. 交渉の代理による精神的負担の軽減
離婚の交渉は精神的に大きなストレスがかかります。弁護士が代理人として相手方と直接交渉することで、精神的な負担が大幅に軽減され、冷静に手続を進めることができます。
3. 法的に有効な合意書を作成できる
口約束や不備のある合意書では、将来的に「言った、言わない」のトラブルになりかねません。
弁護士は、法的に有効となる離婚協議書や公正証書の作成ができ、さらに将来の不払いを防ぐための強制執行認諾文言を入れるなど、実効性の高いものにすることができます
まとめ
今回は、養育費と財産分与の相殺について解説しました。
- 子どもの権利を守るため、養育費と財産分与を相殺することは原則として認められない。
- 「養育費を請求しない」という合意は、後から無効と判断される可能性が高い。
離婚時のお金の問題は、法律的な知識だけでなく、感情的な側面も大きく影響します。ご自身で判断に迷ったり、相手方との交渉がうまくいかなかったりした場合は、決して一人で抱え込まず、離婚問題に詳しい弁護士へお早めにご相談ください。
あわせて読みたい記事
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設


















