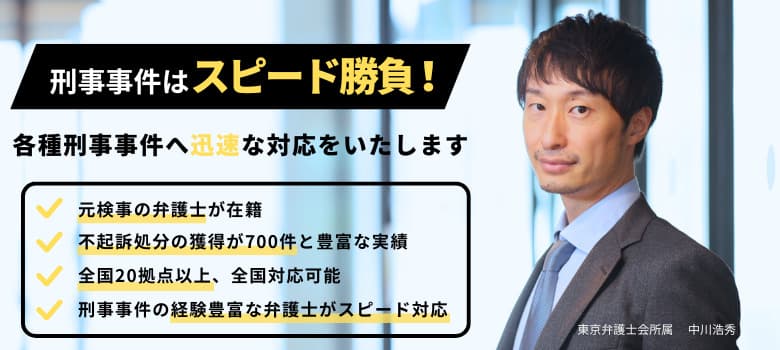身柄事件とは|在宅事件との違い・釈放のために家族ができることは?

全国20拠点以上!安心の全国対応
初回相談0円
記事目次
「身柄事件と在宅事件にはどのような違いがあるの?」
「身柄釈放のために家族ができることは?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、身柄事件と在宅事件との違い、身柄釈放や不起訴のために家族が取るべき対応、弁護士に相談するメリットなどについて解説します。
身柄事件とは
身柄事件とは、犯罪の被疑者が逮捕されて警察の留置所に身体を拘束されて取調べを受ける事件のことをいいます。被疑者が逮捕された後48時間以内に送検され、24時間以内に勾留請求されます。
身柄事件では、逮捕されてから起訴・不起訴の決定まで、最大23日間勾留されることになります。
在宅事件との違い
在宅事件とは、被疑者が身体を拘束されずに捜査上必要な場合だけ捜査期間に呼び出されて取調べを受ける事件をいいます。在宅事件と身柄事件にはどのような違いがあるのか説明します。
1.逮捕期間と併せて最大23日間身体拘束される
警察官が被疑者を逮捕した場合、逮捕から48時間以内に関係書類と共に被疑者の身柄を送検するかどうかを判断しなければなりません(刑事訴訟法第203条1項)。また、送検先の検察官は、24時間以内に被疑者の勾留状発行を裁判所に請求するかどうかを決定しなければなりません(同法第205条1項)。
被疑者が勾留されると原則10日間身体拘束されます(同法第208条1項)。
また、検察官が勾留延長を請求した場合、裁判所が「やむを得ない事由がある」と認めるときは、「通じて10日を超えることができない」期間の延長が認められます(同法第208条2項)。
つまり、逮捕・勾留期間を併せると最大23日間身体拘束されることになります。そのため、長期にわたって突然仕事に行けなくなったり、学校に通えなくなったりするおそれもあります。
これに対し、在宅事件では、取調べのために捜査機関に呼び出されて出頭する場合以外は自宅または定められた住居で通勤・通学も含めて通常通りの生活をすることができます。
(参考記事:在宅事件とは|身柄事件との違いや起訴される可能性を解説 *2021年7月納品)
2.勾留された場合は国選弁護人選任を依頼できる
被疑者は逮捕されてから勾留請求までの最大72時間の間は、私選弁護人を依頼していない限り外部者との接見が認められません。
しかし、勾留された場合は、経済的に私選弁護人を依頼することができない状況であれば国選弁護人の選任を請求することができます(刑事訴訟法第37条の2・第207条)。
ただし、国選弁護人の選任を請求するにあたっては、資力申告書を提出しなければなりません(同法第37条の3第1項)。この資力の基準額、すなわち国選弁護人の選任を請求できる基準額は刑事訴訟法第36条の2に基づく政令で「資産の合計額」として50万円と定められています。資力について虚偽の記載のある申告書を提出した者は10万円以下の過料に処せられます(同法第38条の4)。
これに対し、在宅事件では起訴・不起訴の決定が行われるまで、書類送検後も国選弁護人を依頼することはできません。
身柄釈放や不起訴のために家族が取るべき対応
被疑者が逮捕された場合、本人の身柄釈放のため、不起訴処分を得るために被疑者の家族はどのようなことをすべきなのでしょうか。家族が取るべき対応について説明します。
1.逮捕されたら早急に弁護士に相談する
被疑者が逮捕されると72時間以内に勾留される可能性が高いです。2019年の検察統計データを見ても、逮捕総数111,402件に対して92.7%にあたる103,269件で勾留請求され、却下された4,919件を除く90,359件(逮捕件数の81.1%)で勾留が認められています。
逮捕直後の72時間は、国選弁護人をつけてもらうこともできず、家族と面会することもできない状況です。この間、弁護士だけが被疑者と接見することが可能です。そのため、逮捕されたら、家族が早急に弁護士に相談することが大切です。
2.被害者側に謝罪文を渡してもらう
弁護士に依頼すると、被害者がいる場合には、被害者側に本人の謝罪文と併せて家族の謝罪文を渡してもらうこともできます。
本人が犯罪事実を認めて反省している場合、弁護士は被害者本人又はその弁護士に早急に示談交渉を申し入れます。被害者と示談交渉する上で本人の謝罪文は必ず必要になりますが、弁護士経由で家族の謝罪文を渡すことができれば、示談交渉を成立できる可能性が高くなります。示談交渉を成立させて不起訴処分や執行猶予付き判決を受ける上でも、本人と共に家族からの謝罪を書面で表明することは大きな意味があります。
身柄事件で弁護士に相談するメリット
身柄事件で私選弁護人を依頼する最終的な目標は、過度に不利益な処分を回避することですが、そのための手段は、被疑者が犯罪事実を認める場合(自白事件)と無実を主張する場合(否認事件)で異なります。
1.被疑者が罪を認める場合
①逮捕直後から被疑者と接見して勾留を免れることも可能になる
私選弁護人は逮捕直後から接見することが可能です。被疑者に事情と意向を聞き、被疑者が示談を希望すれば、すぐに被害者側と連絡を取り、示談交渉を開始するよう努めます。
勾留請求前の72時間以内に示談を成立させることは難しくても、少なくとも被害者が示談交渉に応じた事実があれば検察官に対する心証は良くなります。また、示談交渉を開始できたことで、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張できます。検察官が捜査を継続するとしても、勾留請求せずに釈放してもらえる可能性が高まります。
②勾留期間中に示談を成立させて不起訴処分を得ることが可能になる
被疑者が被疑事実を認める場合、最善策は勾留期間中に示談を成立させて不起訴処分を得ることです。
示談が成立すれば、被疑者の反省や示談金支払いの意思、被害者側が被疑者の処罰を求めない意思を証明できることになります。これにより不起訴処分(起訴猶予)を得られる可能性が高くなります。また、被疑者が定まった住居で定職に就いていて家族と同居しているような場合は、被疑者逃亡や罪証隠滅のおそれがないとして勾留取消請求(刑事訴訟法第87条)を行うことができます。
③執行猶予付き判決を得られる可能性もある
起訴された場合、示談書など、被告人に有利な証拠・証言を提示して執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
被疑者が起訴された場合は、執行猶予付き判決を得ることを目指して、最善のサポートを受けることができます。
また、勾留中に検察官から略式起訴(刑事訴訟法第461条)や即決裁判手続申立て(同法第350条の16)を検討している旨の告知があった場合、異議を申し立てるか同意するかについて適切なアドバイスを受けることができます。
2.被疑者が無実を主張する場合
①自白調書を取らせないためのサポートができる
犯罪行為を行った事実がないのに逮捕されてしまった場合、弁護士に相談する最大のメリットは勾留請求前から接見・弁護活動を行うことが可能であることです。
ただし、国選弁護人は検察官が勾留請求して裁判所による勾留状が発布されてから選任されるので、逮捕期間中は弁護活動ができないことになります。
無実を主張する場合、自白調書を取らせないことは非常に重要です。
刑事訴訟法上、強制、拷問、脅迫などによる自白や、不当に長く抑留または拘禁された後の自白、任意にされたものでない疑いのある自白を証拠として採用することは禁止されています。また、刑事訴訟の被告人にとって唯一の不利益な証拠が自白である場合は有罪とされないと規定されています(憲法38条3項、刑事訴訟法第319条2項・3項)。
他方で、日本では未だ自白調書が有罪認定の重要な証拠として用いられています。警察官や検察官は、被疑者から自白調書を取ろうとして執拗な取調べや誘導尋問を行うことが現在もないとはいえません。そのため、逮捕段階で弁護士を選任していない場合、逮捕段階で真実と異なることを自白してしまうおそれがあります。
一度自白調書を取られてしまうと、起訴された場合に公判廷での被告人尋問で被告人が色々説明しても、裁判官に嘘をついていると思われる可能性があります。これにより、実際に無実であるにもかかわらず有罪判決を受けてしまう可能性もあるのです。
逮捕直後から弁護士を依頼すれば、まず自白調書を取らせないため、警察や検察官に対して黙秘権を行使するようアドバイスを受けることができます。黙秘しないで取調べに答える場合でも「~したかもしれません」など、自白と受け取られるおそれがある供述をしないように、あくまで否認し続けるようにという助言を得ることができます。
逮捕や取調べの中で、「認めたら早く出られる」「黙秘していると不利になる」などのことを言われて不安になったときも、弁護士という味方がいれば適切な対応をすることができます。
被疑者が黙秘や否認を貫くことをサポートする一方で、弁護士は弁護人として取調べ担当の警察官や検察官と面会して意見書を提出するなど、被疑者の釈放を目指すための活動を行います。
②接見禁止処分が出された場合の対処ができる
否認事件では、勾留時に接見禁止処分が出される可能性が自白事件よりも高くなります。
接見禁止処分が出された場合、弁護士に相談することにより、接見禁止処分を解除あるいは緩和するために、準抗告や接見禁止の一部解除の申立などの手段を講じることが可能です。
③不起訴処分を得るための活動を行うことができる
被疑者の立場、そして被疑者の弁護人として一番の目標となるのが不起訴処分を得ることです。不起訴処分には親告罪の告訴が行われなかった等の形式的理由から、事実が犯罪に当たらないとわかったこと、証拠がなかったこと、検察官の判断に基づく理由など多種のものがあります。
このうち、割合として最も多いのが起訴猶予(刑事訴訟法第248条・事件事務規程第75条2項20号)です。
多くの場合、起訴猶予処分が得られるのが最善の結果となります。ただし、不起訴処分で前科がつくことはありませんが、無罪判決と異なり、捜査の対象となった事実として捜査機関に「前歴」として記録が残ります。同じ「前歴」でも、犯罪が成立していないという判断がなされた「罪とならず」「嫌疑なし」「嫌疑不十分」に対して、犯罪嫌疑が認められる「起訴猶予」の前歴が残ると、後日、別件で捜査の対象となった場合に不利に働く可能性があります。
犯罪類型の中では過失犯に嫌疑なし・嫌疑不十分の件数が比較的多くみられます。
検察統計の2019年のデータでも、特に刑法第28章の過失傷害の罪(過失傷害罪、過失致死罪、業務上過失致死傷・重過失致死傷罪)などは、嫌疑不十分で不起訴となっている割合が相対的に多くなっています。業務上過失致死罪をみると、不起訴処分総数312件のうち嫌疑不十分が166件あり、起訴猶予(120件)を上回っています。
特に被疑者が無実を主張する場合は、弁護士としては嫌疑なし・嫌疑不十分の判断を得られる可能性があれば、それを目指して証拠や証言を集めるという活動を行うことが可能です。
まとめ
今回は、身柄事件と在宅事件との違い、身柄釈放や不起訴のために家族が取るべき対応、弁護士に相談するメリットなどについて解説しました。
被疑者が逮捕されて身体拘束を受けている身柄事件では、勾留後は国選弁護人選任を依頼することができますが、逮捕直後は家族との面会も許されず留置場で孤独な状況に置かれます。また、被疑者本人は携帯電話等の通信手段を失うため、自身で法律事務所にアクセスすることはできません。そのため、できる限り早い段階で、ご家族が刑事事件に精通した弁護士に相談することが大切です。
私達、東京スタートアップ法律事務所は、刑事事件の被疑者となった方の大切な未来を守るために全力でサポートさせていただきたいと考えております。検察官や捜査機関の考え方を熟知している元検事の弁護士を中心とした刑事事件に強いプロ集団が、ご相談者様の状況やご意向を丁寧にお伺いした上で的確な弁護戦略を立て、迅速に対応致します。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設