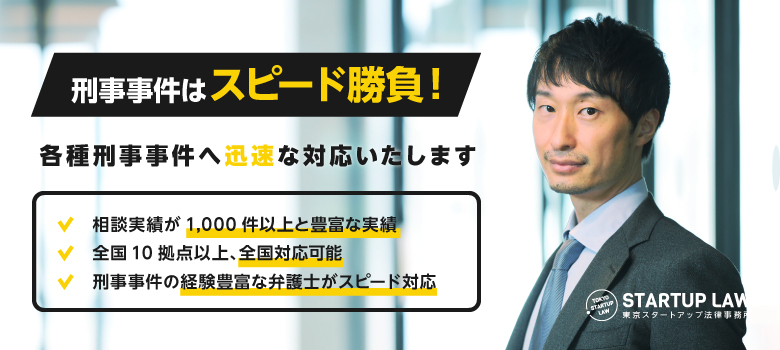住居侵入罪の構成要件・正当な理由や建造物の定義、罰則規定も解説

全国20拠点以上!安心の全国対応
初回相談0円
記事目次
「住居侵入罪が成立する要件である、正当な理由とは具体的にどのような理由が該当するのか知りたい」
「庭やマンションの共有部分などに侵入した場合も、住居侵入罪が成立するのか知りたい」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、住居侵入罪の定義や特徴、建造物侵入罪や不退去罪との違い、住居侵入罪の構成要件、住居侵入罪の刑罰、逮捕・起訴後の流れ、被害者と示談するメリットと示談金の相場などについて解説します。
住居侵入罪とは
住居侵入罪とは、法律でどのように定められている犯罪なのでしょうか。まずは、刑法の条文、住居侵入罪の特徴など基本的な内容について説明します。
1.刑法の条文
住居侵入罪は刑法第130条前段に定められた犯罪です。同条前段では、以下のように定められています。
“正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する”
2.牽連犯となることが多いことが特徴
住居侵入罪は、犯罪の手段または結果である行為が、他の罪名に触れる牽連犯(第54条1項後段)が成立する事例が多いことが特徴です。
牽連犯が成立するためには、犯罪結果とその手段となる行為との間に密接な因果関係があることが必要とされています。住居侵入とその後に発生した結果との間には密接な因果関係が認められることが多いため、牽連犯が成立する事例も多いです。
牽連犯が成立する典型例は、空き巣目的で留守宅に侵入して金品を盗む場合です。この場合、窃盗罪(刑法第235条)とともに、窃盗の手段である住居侵入行為について住居侵入罪が成立します。
他に住居侵入罪と牽連犯になる可能性がある犯罪として、以下のような犯罪が挙げられます。
- 強盗罪(同法第236条1項)
- 傷害罪(同法第204条)
- 殺人罪(同法第199条)
- 強制性交等の罪(同法第177条)
- 放火罪(同法第108・109条)
住居侵入罪と他の犯罪との牽連犯が成立する場合は、最も重い刑により処断されます(同法第54条1項)。例えば、空き巣の事例では、より法定刑の重い窃盗罪の刑により処断されることになり、住居侵入罪の刑で処断されることはありません。
3.住居侵入罪は非親告罪
住居侵入罪は非親告罪です。非親告罪とは、告訴権者(告訴できる権利を持つ者)による告訴がなくても公訴提起(起訴)できる犯罪のことをいいます。
非親告罪とは異なり、告訴権者による告訴がなければ公訴提起できない犯罪を親告罪といいます。刑法等の犯罪を定める法律の条文に「告訴がなければ公訴を提起することができない」と明記されているのが親告罪です。例えば、名誉棄損罪(第230条)や侮辱罪(第231条)の場合の第232条1項の規定です。この規定がない犯罪はすべて非親告罪です。
親告罪となるのは主に以下のいずれかに該当する犯罪です。
- 公訴提起によって被害者のプライバシーが侵害されるおそれが強い犯罪類型
- 犯罪の程度が軽く当事者の間で解決可能な場合が多い犯罪類型
住居侵入罪の場合は上記のいずれにも該当しないといえます。
非親告罪には、親告罪で定められている告訴期間の制限はありません。しかし、時間の経過により証拠が散逸して捜査が困難になるので、住居侵入された疑いがある場合は早急に被害届を警察に提出すべきだといわれています。
類似の犯罪との違い
住居侵入罪と似ている主な犯罪として、建造物侵入罪と不退去罪が挙げられます。住居侵入罪と建造物侵入罪・不退去罪との違いについて説明します。
1.建造物侵入罪との違い
住居侵入罪が「人の住居」に対する違法な立ち入り行為であるのに対して、建造物侵入罪は「建造物若しくは艦船」に対する違法な立ち入り行為に対して成立します(刑法第130条前段)。「建造物」に該当するのは、人が出入りできる建物のうち「住居」を除いたものです。具体的には、学校、鉄道の駅舎、市役所、公立体育館、病院等の公共施設や商業施設等が該当します。
2.不退去罪との違い
不退去罪(同法第130条後段)は、退去の要求を受けたにもかかわらず住居、邸宅、建造物、艦船から退去しなかった場合に成立します。
住居侵入罪との違いは、不退去罪の場合、立ち入り自体は適法な場合もあることです。
例えば、訪問販売業者が居住者の承諾を得てその住居に立ち入り、物品購入やサービスの利用契約締結を迫り続け、居住者が「出ていけ」と言っても出ていかない場合、住居侵入罪は成立せず、不退去罪が成立する可能性があります。
また、店舗に立ち入った客による執拗なクレーマー行為で、店側の退去要求に応じない場合も立ち入り自体は適法なので住居侵入罪は成立せず、不退去罪が成立する可能性があります。
住居侵入罪の構成要件
住居侵入罪の構成要件は、正当な理由がないのに、人の住居に侵入した者です。構成要件で問題となるのは、以下の3点です。
- 「住居」の範囲
- 誰のどのような立ち入り行為が「侵入」行為に該当するか
- どのような立ち入り目的が「正当な理由」に該当するか
それぞれのポイントについて説明します。
1.「住居」の範囲
①住居侵入罪における「住居」の定義
住居侵入罪の「住居」は、通説では、人の起臥寝食(寝泊り・生活)に使用される場所と定義されています。「住居」に該当するためには、一定の構造や設備が必要です。テントは「住居」に含まれるといえますが、長期に渡って起臥寝食に使用されていたとしても、地下道、段ボール箱、ドラム缶、山の横穴などは「住居」とみなすに足りる構造や設備を持たないため、「住居」に含まれないと考えられています。
②ホテルや病室は「住居」に含まれるか
ホテルの一室や入院中の病室などは、それが含まれる建造物(ホテルや病院)への立ち入り自体は違法ではないことと、通常は調理設備を備えていないこと等から「住居」に含まれるか問題となります。病室については「一時的ではあるがある程度継続的に利用している場合には利用者の住所となる」と認められた裁判例があります(東京高等裁判所平成11年7月16日判決)。ホテルの一室についても、認めるのが通説です。
③マンションの通路やベランダ等は「住居」に含まれるか
アパートやマンションの一室(居住区分)が「住居」に該当することは明らかですが、アパートやマンションの一室の玄関に許可を得て立ち入った後に、ある部屋のドアを勝手に開けて立ち入った場合、住居侵入罪が成立する可能性があります。
平屋の縁側やアパート・マンションの共用階段・通路・屋上や一戸建ての屋根の上等も、判例で「住居」にあたるとされています。このことから、ベランダ等も「住居」に該当すると考えられます。
④庭は「住居」に含まれるか
庭が「住居」に含まれるかについては判例や学説で争いがありました。庭のように、塀等の「全体として外界との交通を阻止する障壁によって囲まれている場所」は法律上「囲繞地」と呼ばれています。囲繞地について、判例ではかつて同条の「邸宅」と扱われていました(最高裁判所昭和32年4月4日判決)。「邸宅」とは、住居用に作られたが現在住まいとして使用されていない家屋のことをいいます。現在では、住居に含まれると考えてよいでしょう。
⑤空き家は「住居」に含まれるか
空き家については、現在住まいとして使用されていないため、「住居」ではなく「邸宅」にあたるといえます。シーズンオフに利用する別荘等も空き家に準じて「邸宅」にあたると考えられます。
ただし、「邸宅」は「人の看守する」もの、すなわち他人が事実上管理・支配しているものであることが必要です。例えば、管理人や監視員が置かれている、施錠してその鍵を保管する者がいる等です。そのため、管理や監視が行われず、鍵の保管者もいない廃屋は「邸宅」に含まれず、軽犯罪法第1条1号の対象となります。
⑥空き地は「住居」に含まれるか
空き地については、前述の「囲繞地」にあたるかが問題となります。「囲繞地」にあたるといえるためには、その土地が、建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が外部との境界に門塀等の囲障を設置することにより、建物の附属地として、建物利用のために供されるものであることが明示されていることが必要となります。
仮設の建物やフェンス等が存在していれば「囲繞地」といえるため、住居侵入罪の「住居」にあたるといえます。
2.「侵入」に該当する行為
どのような行為が「侵入」に該当するかを検討するためには、そもそも住居侵入罪が定められている理由、すなわち、住居侵入罪によって保護されている利益(保護法益)が何であるかが問題となります。そして、個々の立ち入り行為がそのような法益を侵害する侵入にあたるといえるかを検討することになります。
①住居侵入罪の保護法益に関する判例・通説の歴史
住居侵入罪の保護法益については、第二次世界大戦前は家父長権を基本とした法的住居権と考える「旧住居権説」が判例・通説になっていました。しかし、戦後、家父長権の考え方が憲法の理念に反することや、住居権の概念が不明確であるという批判が強まり、住居権に代えて「事実上の住居の平穏」が保護法益であるという「平穏(侵害)説」が判例・通説になりました。平穏説では、「侵入」は「平穏を害する立ち入り」とされています。平穏説に対しては、平穏侵害の判断のために侵入目的を重視することが、戦前の刑法理論から脱却できていない等の批判がありました。
その後、個人の自己決定権を重視して、戦前の「住居権」を「住居に誰を立ち入らせ、誰の滞留を許すかの自由」と説明し直すことにより住居侵入罪が個人的法益(個人の自由)に対する罪であることを明確にした「新住居権説」が有力になり、最高裁判例も平穏説から新住居権説に立場を変更したといわれています。新住居権説では、住居侵入罪の「侵入」とは、住居権者(建造物の場合は管理権者)の意思に反する立ち入りとされています。
②別居・離婚後の夫婦の一方の立ち入りは?
ただし、住居権者や管理権者の意思に反する立ち入り行為がすべて「侵入」に当たるとすると、店のチラシのポスティングのような行為まで「侵入」にあたることになり、処罰範囲が広がりすぎてしまいます。そのため、現在の判例は、新住居権説に拠りつつ、立ち入りが「私生活の平穏を侵害するかどうか」という観点も加味しているといわれています。
具体的に「侵入」にあたるかどうかで問題となるケースの典型例は、別居後や離婚後の夫婦の場合や、同居していない親族が断りなく立ち入った場合です。別居後や離婚後の夫婦の一方が他方の住居に立ち入る行為は、住居権者の意思に反することが明らかなケースも多いです。そこで、立ち入りの目的や態様が私生活の平穏を侵害するといえるかどうかを判断することになります。
別居直後で、自分の荷物を持ち出すという目的だけのために立ち入った場合などは、目的や態様が私生活の平穏を害するとはいえないでしょう。これに対して、復縁を迫る、暴力を振るう、家財道具等を壊すなどが目的の場合は、目的・態様ともに私生活の平穏を害するといえる可能性が高いです。
また、別居期間が長くなるほど、居住している側からみて相手の立ち入りは私生活の平穏を害する度合いが高くなることから、「侵入」にあたる可能性も高くなるといえます。離婚後の場合は、目的や態様を問わず「侵入」にあたる可能性が高くなります。
③同居していない親族の立ち入りは?
同居していない親族が居住者の承諾を得ずに立ち入った場合、居住者が複数いるケースでは、意思が異なることがあるため、問題になります。居住者全員の意思に反しなければ「侵入」にあたるとはいえませんが、一部の居住者の意思に反する場合は、その立ち入りの目的や態様が私生活の平穏を害するといえるかどうかという観点から検討されることになります。
④のぞき目的で塀に上った場合は?
のぞき目的で家の塀に上ったような場合は、塀の内側に立ち入らなかったとしても、住居権・平穏侵害の要件を満たすので「侵入」にあたります。
なお、住居侵入罪は未遂を処罰します(刑法第132条)。住居侵入罪の既遂時期は「身体の全部を客体に入れた時」とされています(通説)。そのため、未遂となるのは家の塀によじ登り始めた時です。
3.「正当な理由」とは
①正当な理由が認められる条件
第130条前段の「正当な理由」は、立ち入りの目的が住居権者の承諾を得ているか承諾を得られると推定される場合、あるいは法的に正当な根拠がある場合に認められます。
例えば、宅配業者が居住者の依頼した荷物を届けるために荷物を玄関先まで運ぶ場合や、捜査機関が捜索差押令状を得て住居に立ち入る場合などは「正当な理由」があると認められます。
②政治的広告の投函が目的の場合は?
「正当な理由」にあたるかが問題となるのは、政治的広告を投函するためにマンションの共用部分に立ち入る行為です。政治的広告を配布すること自体は、憲法第21条1項の「表現の自由」で認められている政治的表現の自由に含まれるため、それを目的としてマンションの共用部分に立ち入ることが「正当な理由」にあたるかについては判例・学説の見解が分かれています。
分譲マンションの各戸のドアポストに政党のビラを投函する目的でマンションの共用廊下に立ち入った事件において、一審の東京地方裁判所は、マンションの共用廊下は「住居」に該当すると判断しつつ、政党のビラ投函目的自体は「正当な理由がないとはいえない」として住居侵入罪の成立を否定しました。
しかし、控訴審ではこれを破棄して罰金5万円の有罪判決を下し、最高裁判所も上告を棄却しました(最高裁判所平成21年11月30日判決)。
この事件では、配達業者の立ち入りが通常認められているマンションの入り口のポストではなく、各戸のドアのポストにビラを入れていたという事情があったため、入り口のポストに政治的広告を投函する場合は「正当な理由」が認められると考えられます。
住居侵入罪の刑罰
住居侵入罪に対して科される刑罰は、被疑者の行為に対して成立する犯罪が住居侵入罪のみである場合と、住居侵入罪と共に別の犯罪(未遂罪の規定がある場合は未遂罪を含む)が成立する場合で処断方法が異なります。それぞれのケースについて説明します。
1.住居侵入罪のみの場合
成立した犯罪が住居侵入罪のみの場合は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。多数の前科がある等の例外を除き、他の犯罪が成立していない場合に執行猶予なしの実刑判決が下されることは少なく、初犯で前科がない場合は、ほぼ執行猶予付きの判決になります。
また、略式命令によって罰金刑が科される場合もあります。罰金刑となるのは、窃盗やわいせつ等他の犯罪の目的がなく、開錠されていた扉から侵入した場合などです。
2.窃盗目的の場合
窃盗目的での住居侵入の場合は、窃盗罪(未遂を含む)と住居侵入罪が成立して、両者が牽連犯となるため、重い方の窃盗罪の刑である10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
なお、窃盗罪が未遂(刑法第243条、第43条)の場合でも、裁判官の裁量により減軽された窃盗罪の刑が科されます。
3.盗撮などのわいせつ目的の場合
わいせつ目的での住居侵入の場合は、住居侵入罪と侵入後に行われた関連犯罪が成立します。強制性交等の罪(刑法第177条)の場合は牽連犯となり、重い方の強制性交等の罪の刑である5年以上の有期懲役で処断されます。未遂罪(同法第180条、第43条)の場合は、住居侵入罪と裁判官の裁量により減軽された強制性交等の罪の重い方の刑が科されます。
強制わいせつ罪(同法第176条)の場合も牽連犯となり、重い方の強制わいせつ罪の刑である6月以上10年以下の懲役で処断されます。未遂罪(同法第180条、第43条)の場合は住居侵入罪と裁判官の裁量により減軽された強制わいせつ罪の重い方の刑が科されます。
被害者が殺害され、あるいは負傷した場合は、強制わいせつ等致死傷罪(同法第181条1項)または強制性交致死傷罪(同法同条2項)が成立し、牽連犯となり強制わいせつ等致死傷罪の場合には、無期又は3年以上の懲役、強制性交等致死傷罪の場合には、無期又は6年以上の懲役で処断されます。
のぞき見・盗撮が行われた場合、軽犯罪法違反となり、牽連犯となります。軽犯罪法の罰則は1日以上30日未満の拘留または1,000円以上10,000円未満の科料なので、重い方の住居侵入罪の刑で処断されます。
4.ストーカー目的の場合
ストーカー目的の住居侵入事件の場合、侵入者が被害者に対して以前から行っていた行為がストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)で定める8つの「つきまとい行為」(同法第2条)に該当すると判断された場合は、同法のストーカー行為罪(同法18条)が成立します。
また、警察によって同法の定める「禁止命令」(同法第5条、つきまとい行為の反復を禁じる命令)が出されていた場合は、禁止命令等違反罪(同法第19条)が成立します。ストーカー行為罪・禁止命令等違反罪とは牽連犯となります。
同法の刑は一番重いストーカー行為に係る禁止命令等違反罪(同法第19条)が2年以下の懲役なので、重い方の住居侵入罪の刑で処断されます。
逮捕・起訴後の流れ
被疑者が住居侵入容疑で逮捕されるのは現行犯の場合と通常逮捕(逮捕状による逮捕)の場合があります。また、公訴提起(起訴)される場合は正式起訴と略式起訴のどちらかに拠ることとなり、行われる裁判手続が異なります。
1.現行犯の場合
現行犯で逮捕された場合(刑事訴訟法第212条)の手続の流れは以下のようになります。
(1) 捜査機関(警察)への引き渡し
住居侵入罪の場合、警備会社の職員等の私人が現行犯人を逮捕することが多いので、この場合は直ちに捜査機関(検察官もしくは司法警察職員、通常は後者)に引き渡す必要があります(同法第214条)。
(2) 被疑者取り調べ・送検・勾留の決定
逮捕された被疑者に対しては警察官(司法警察員、同法第202条)が取り調べを行い、逮捕理由とともに弁護人をつける権利(憲法第37条3項、同法第30条以下)を告知します。
警察は被疑者を拘束してから、留置の必要がないと判断した場合は直ちに被疑者を釈放し、必要があると認める場合は48時間以内に検察官に送致します(刑事訴訟法第203条1項)。送検された場合、検察官は留置の必要があると認める場合は被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に対して勾留請求し、必要がないと判断した場合は直ちに被疑者を釈放します(同法第205条1項)。
被疑者拘束から検察官の勾留請求までの72時間の間は、被疑者は弁護人以外と会うこと(接見)ができません。
裁判官が勾留を認めた場合、勾留期間は勾留請求した日から10日間です(同法第208条1項)。また、検察官が勾留延長を請求したときは、裁判官はやむをえない事情があると認める場合さらに10日間までの延長を認めます(同法同条2項)。したがって、勾留期間は最大で20日間です。
被疑者が勾留されずに釈放された場合は在宅で捜査が続き、捜査期間に制限はありません。
また、被疑者を勾留するかしないかにかかわらず、被害者や目撃者に対しても取り調べが行われるとともに、裁判所が検察官の請求により捜索差押令状を発行した場合は被疑者の家宅捜索・差押が行われます。(憲法第35条2項、刑事訴訟法第218条1項)
(3) 勾留
勾留中は検察官による取り調べが行われます。また、被疑者が経済的事情その他の理由によって弁護人を選任することができない場合は、裁判官によって国選弁護人が選任されます(同法第37条の2)。
(4) 起訴・不起訴
勾留期間中または在宅での捜査中に検察官は被疑者の起訴・不起訴の処分を決定します。
不起訴処分(同法第248条)が決定された場合、捜査手続は終了します。被疑者が勾留中である場合には、被疑者は直ちに釈放されます。
起訴する場合(同法第247条)、検察官は裁量により正式公判請求または簡易裁判請求のいずれかを行います。
(5) 正式裁判の公判手続
被疑者が起訴された場合、地方裁判所の公開の法廷(公判廷、同法第282条)で公判手続が行われます。
2.通常逮捕の場合
現行犯以外の場合は、警察が裁判所に逮捕状を請求し、逮捕の理由と必要性が認められれば裁判所の発行する逮捕状(刑事訴訟法第199条1項)による逮捕が行われます。
逮捕の理由と必要性は、具体的には被疑者が逃亡するおそれや罪証を隠滅するおそれがある場合に認められます。このため、被疑者の住所が明らかで証拠隠滅のおそれもない場合には逮捕の必要性がなく、在宅のまま取り調べ等の手続が行われます。逮捕状が発行されて被疑者が逮捕された場合のその後の手続は現行犯逮捕の場合と同じです。
3.略式起訴の場合
住居侵入事件が比較的軽微である場合、検察官の判断により略式命令請求(略式起訴、刑事訴訟法第462条)が行われます。
略式起訴が行われた場合、簡易裁判所で公判によらない略式裁判が行われます。略式裁判では原則として検察官の提出した資料のみに基づいて、公判を開かずに略式命令(同法第461条)により罰金または科料が課されます。
被害者と示談するメリットと示談金の相場
住居侵入罪は非親告罪なので、告訴権者による告訴がなくても公訴提起(起訴)される可能性があります。もっとも、被疑者が逮捕され、さらに送検された場合でも被疑者側が被害者側に示談を申し入れ、被害者側が申し入れを承諾すれば示談交渉することが可能です。
1.不起訴処分になる可能性も
示談が成立すれば被疑者にとっては検察官や裁判官の心証が良くなるため、不起訴処分になる可能性があるという大きなメリットがあります。また、被害者にとっても、その後の捜査機関による取り調べ・刑事裁判への出席・証言などの負担を免れることができるというメリットがあります。示談交渉は被疑者の弁護人と被害者側の弁護士により行われるのが通常です。
2.示談金の相場
住居侵入事件のみが捜査対象となっている場合は、有罪判決が科される場合の罰金が10万円以下であることから、相場は10万円から20万円程度と考えられます。
ただし、この場合でも、カメラを設置する、下着を物色するなど、盗撮等の他の犯罪目的が明確である場合や、宅配業者を装って侵入した場合などでは100万円以上になるケースもあります。
まとめ
今回は、住居侵入罪の定義や特徴、建造物侵入罪や不退去罪との違い、住居侵入罪の構成要件、住居侵入罪の刑罰、逮捕・起訴後の流れ、被害者と示談するメリットと示談金の相場などについて解説しました。
立ち入り行為が住居侵入罪の「侵入」に該当するか、また立ち入り行為に正当な理由があるかどうかの判断は難しいケースも少なくありません。「住居侵入罪で訴える」などと言われたけれど自分の行為が住居侵入罪に該当するのかわからない、被害者と示談をしたいけれど応じてもらえるかわからないなどという場合は、刑事事件に精通した弁護士に相談するとよいでしょう。
私達、東京スタートアップ法律事務所は、刑事事件で逮捕された、「刑事告訴する」などと言われ等の問題を抱えているご本人やご家族の気持ちに寄り添い、ご本人の大切な未来を守るために全力でサポートさせていただきたいと考えております。検察官や捜査機関の考え方を熟知している元検事の弁護士を中心とした刑事事件に強いプロ集団が、ご相談者様の状況やご意向を丁寧にお伺いした上で的確な弁護戦略を立て、迅速に対応致します。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
- プロフィール
- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務