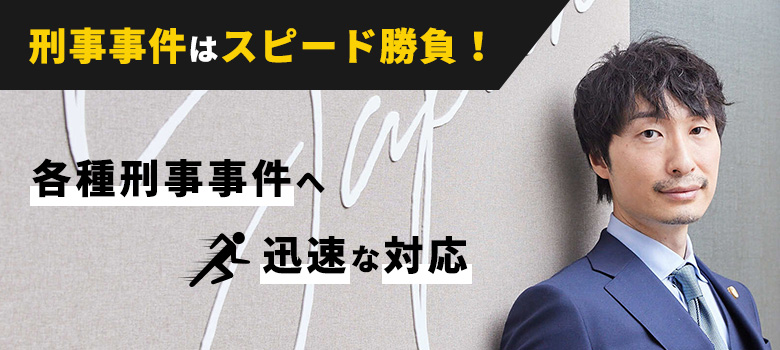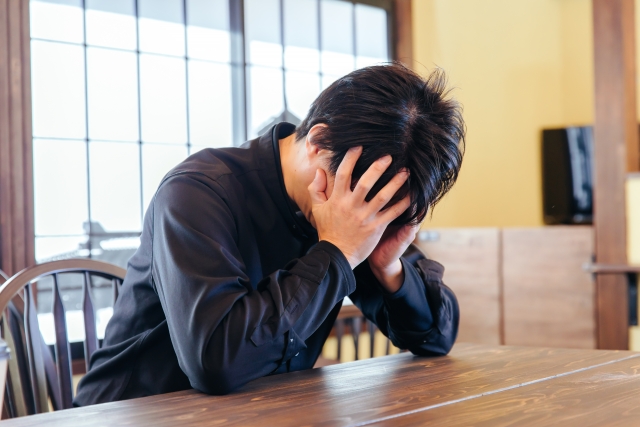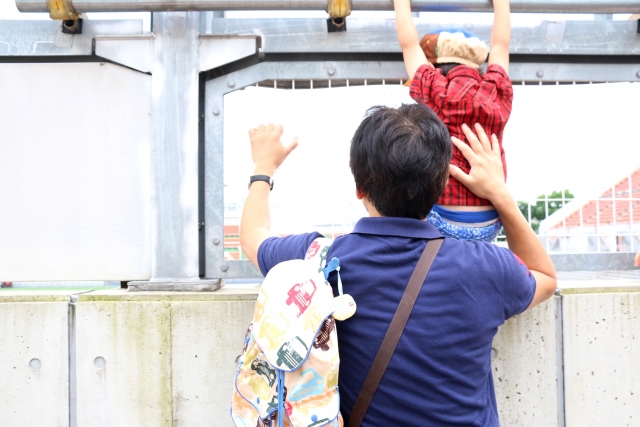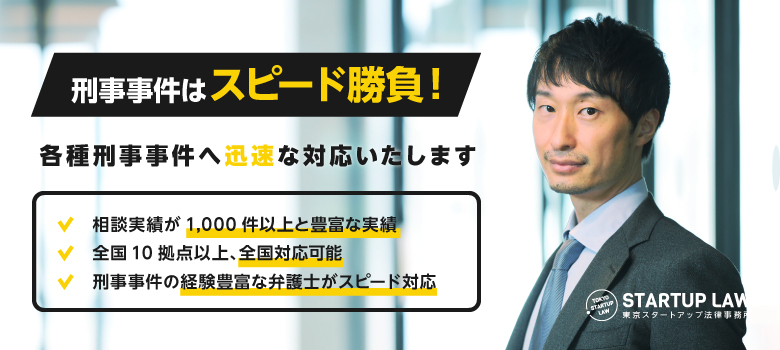詐欺罪の懲役は平均何年?執行猶予はつく?刑期や罰金の相場と減刑のポイントをチェック

全国20拠点以上!安心の全国対応
初回相談0円
記事目次
詐欺罪は、人を欺いて人の財産の交付を受けた場合に成立する可能性のある犯罪です。
詐欺罪は、比較的刑の重い犯罪で、罰金刑はありません。起訴されて有罪判決が確定すれば、10年以下の懲役が科せられます。
特殊詐欺や保険金詐欺など、知能犯の類の詐欺行為であれば、初犯や未遂であっても実刑判決となる可能性があります。
本記事では、詐欺罪で逮捕された方、詐欺罪の疑いをかけられている方やそのご家族に向けて、詐欺罪の法定刑等について解説します。
詐欺罪とは何か
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする犯罪です。
簡単に言えば、相手を騙して財物をだまし取る行為が該当します。
刑法第246条に規定されており、10年以下の懲役に処される可能性がある犯罪です。
詐欺罪の検挙率・起訴率はどれくらい?
令和5年における詐欺罪の認知件数は約88,000件、検挙件数は約38,000件で、検挙率は43.4%でした。さらに、検察統計によると、詐欺事件のうち約70%前後が起訴されています。被害額が高額であることや組織的犯行の場合、実刑を含む厳罰が科される傾向にあります。
詐欺罪の構成要件
まずは、詐欺罪の構成要件について説明します。詐欺罪は以下の4つの要件を満たす場合にのみ成立します。
欺罔行為
欺罔(ぎもう)行為とは、他人を騙したり、欺いたりする行為のことです。オレオレ詐欺のように、息子であるふりをして相手を騙し、財産を引き渡すように仕向けようとする行為などが該当します。
また、積極的に嘘をつかなくても、既に相手が騙されていることを知りながら、真実を告げないことにより利益を得ようとする場合も該当します。例えば、不良品であることを知りながら、購入者に知らせることなく販売した場合などです。
錯誤
相手の欺罔行為によって錯誤に陥ることも、詐欺罪の構成要件の一つです。錯誤とは、相手の欺罔行為によって、嘘を信じ込ませられた状態をいいます。平易な言葉に言い換えると、騙されている状態です。
財産の交付・移転
騙された被害者が、加害者に財産を渡してしまうことです。
因果関係
欺罔、錯誤、財産の交付・移転に因果関係があることも、詐欺罪の構成要件の一つです。
被害者に嘘をつき(欺罔)、その嘘を被害者が信じ(錯誤)、騙された被害者が加害者に財産を渡す(財産の交付・移転)という一連の流れがあることが求められます。
欺罔、錯誤、財産の交付・移転、因果関係のうち、一つでも欠けると詐欺罪は成立しません。
構成要件を理解するための例
刑法第246条の条文によると、詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた者」を罰する犯罪だと明記されています。
詐欺罪が成立する主な要件は、次の4点です。
| 要件 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 欺罔(ぎもう) | うそをついて相手をだます行為 | 欺罔行為があったかどうかが争いとなる場合も多く、詐欺罪の成否を考えるうえでもっとも重要な部分といえます。 |
| 錯誤 | 欺罔を受けた相手がうそを信じ込んだ状態 | たとえば「うそだとわかっていたがお金を渡した」といった場合だと、たとえお金が返ってこなくても法律上は詐欺罪の成立が否定されます。 |
| 交付(処分行為) | 錯誤に陥った相手が、自らお金などの財物を差し出す行為 | 財物が加害者のもとへと渡った方法によって罪名が変化するので、詐欺罪の成立を左右する重要な要件だといえます。 |
| 財物または財産上の利益の移転 | 欺罔行為によって、財物または財産上の利益が行為者や第三者に移転すること |
上記の行為が一連となり詐欺罪が成立します。
詐欺罪の法定刑

それでは、詐欺罪が成立すれば、どのような刑が科されるのでしょうか。
刑法で規定されている詐欺罪の法定刑や初犯の場合の刑罰について確認しておきましょう。
詐欺罪の法定刑
詐欺罪の法定刑は「十年以下の懲役」(刑法第246条1項)です。
詐欺罪には罰金刑がありません。執行猶予がつかなければ刑務所で服役することとなります。
詐欺罪の中でも特に厳罰化が進んでいるのが、オレオレ詐欺等の特殊詐欺と呼ばれるものです。
特殊詐欺を行った場合は起訴される可能性が高く、かつ実刑判決が言い渡される可能性が高いといわれています。
初犯や未遂の場合も懲役実刑になるのか?
詐欺罪においては、初犯や未遂であっても実刑判決が言い渡される事例があります。
特殊詐欺や保険金詐欺といった知能犯と呼ばれる類型です。
例えば、特殊詐欺の首謀者的立場で組織的に詐欺を行っていた場合は、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性が高いです。
特殊詐欺や組織的な詐欺の末端の役割を担っていた場合でも、初犯で実刑判決が言い渡されるケースがあります。
詐欺行為を行って執行猶予付き判決が言い渡される可能性があるのは、以下に該当するような詐欺の場合です。
- 無銭飲食や釣り銭詐欺等の詐欺
- 特殊詐欺の末端であり犯行が未遂であった場合
- 初犯であり被害者との示談が締結されている場合
詐欺罪の懲役の中央値は1年から3年
詐欺罪で有罪になった場合に言い渡された刑期を、平成30年版犯罪白書で確認してみましょう。
| 懲役6か月未満 | 4 |
|---|---|
| 懲役6か月以上1年未満 | 104(執行猶予29) |
| 懲役1年以上2年未満 | 1217(執行猶予812) |
| 懲役2年以上3年以下 | 2270(執行猶予1361) |
| 懲役3年を超え5年以下 | 461 |
| 懲役5年を超え7年以下 | 78 |
| 懲役7年を超え10年以下 | 18 |
| 懲役10年を超え15年以下 | 4 |
実際に言い渡された刑期は6か月未満から15年以下までと幅広くなっておりますが、最も多いのは懲役1年から3年です。
全体の約83.9%が懲役1年から3年となっています。
被害額を弁償しており、犯罪行為の悪質性が高くなければこの範囲内におさまる可能性が高いといえます。
詐欺罪で執行猶予がつく可能性は?
先ほどご紹介したデータから分かるとおり、詐欺罪においても執行猶予付き判決が言い渡されるケースは多数存在します。
執行猶予は3年以下の懲役の場合のみつけることができますので、懲役3年を超える場合はすべて実刑判決となります。
懲役1年以上2年未満の場合、執行猶予付き判決が言い渡された割合は約66.7%、懲役2年以上3年以下の場合は約59.9%です。
ただし、先述したように特殊詐欺等の知能犯や組織的な詐欺で中心的役割を担っていた場合は、執行猶予付き判決は期待できません。
公訴時効は7年
詐欺罪の公訴時効は7年です。
公訴時効とは、犯罪行為が行われてから一定期間が経過すれば、検察が起訴できなくなる制度のことをいいます。詐欺行為から7年が経過すれば、時効が成立し、処罰されることはありません。
余罪がある場合
詐欺罪の中でも、オレオレ詐欺等のいわゆる特殊詐欺の事案では、複数の被害者がいるケースも多く、逮捕されている件とは別の余罪についても捜査が進んでいることもあります。
そして、余罪についても捜査が進み、例えば別々の日に行った複数の詐欺行為について起訴された場合、それらの詐欺行為が「併合罪」として処罰される可能性もあります(刑法第45条)。
複数の犯罪が「併合罪」となった場合、「その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたもの」が法定刑の上限となります(刑法第47条)。
例えば、2件の詐欺行為が併合罪として処罰されることとなった場合、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役とされているので、これの1.5倍の15年が懲役刑の上限ということになります。
詐欺罪で略式起訴になる場合があるのか?
略式起訴というのは、事案が明白かつ簡易で、100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について、正式な裁判を経ることなく、検察官が裁判所に提出した書類に基づいて刑事処分が決められる手続です。
詐欺罪の法定刑には、罰金や科料はなく、懲役のみであるため、詐欺罪で起訴される場合には略式起訴ではなく正式な裁判となります。
詐欺罪の量刑判断|詐欺罪の量刑はどのような事情で決まるのか?

では、詐欺罪の量刑はどのように判断されるのでしょうか。詐欺罪の刑期を決める判断基準について説明します。
詐欺の結果の重大性
詐欺の結果の重大性とは、詐欺の結果としてもたらされた被害の度合いのことをいいます。
例えば、詐欺によって被害者から1000万円の交付を受け、被害者に弁済していない場合は結果が重大であるといえますので、刑期が長くなるおそれがあります。
逆に、被害者から奪ったものが、「銀行通帳のみ」で現金の引き出しもできないような場合は、銀行通帳を第三者に売却する等の懸念はあるものの、金銭的な被害は小さいといえます。
そのような場合は、短い刑期や、施行猶予付き判決が言い渡される可能性が高くなります。
犯行の悪質性
詐欺罪においては、単純な詐欺なのか、知能犯の意味合いが強い特殊詐欺なのかによって量刑判断や執行猶予の有無が異なります。
無銭飲食や釣り銭詐欺であれば、量刑が短く執行猶予付き判決も望めます。
しかし、特殊詐欺や会社として詐欺を行っていた場合は、悪質性が高いと判断されるケースが多いです。
被害者との示談成立の有無
被害者との示談が成立しており、被害者の処罰感情が和らいでいる場合は、執行猶予付き判決を望める可能性があります。
一方、被害者との示談が成立していない場合や交付を受けた財物を返していない場合は、処罰が重くなる傾向です。
執行猶予付き判決が言い渡される可能性も低くなります。
被告人の反省度合い
詐欺事件だけでなく刑事事件全般にいえることですが、被告人が罪を認めて反省しているかどうかが量刑判断に大きな影響を与えます。
反省していれば再犯のリスクが低いと判断されますし、反省していなければまた同種の罪を犯すおそれがあると判断されてしまいます。
再犯防止のための取り組み
詐欺事件においては、被告人が再度罪を犯さないための環境が整っているかどうかも量刑判断に大きな影響を与えます。
オレオレ詐欺等の特殊詐欺の末端要員だった場合は、組織との関わりを断つべく、職場や学校、家族がサポートをすることが大切です。
再度同じ罪を犯さないために、本人だけでなく周囲がサポートしている場合は、執行猶予付き判決が言い渡される可能性があります。
詐欺事件の主な種類

詐欺事件として扱われる事件には、具体的にどのような事件があるのでしょうか。
主な詐欺事件の種類をご紹介します。
保険金詐欺・給付金詐欺
保険会社や自治体などを騙して、保険金や還付金を不正に受け取ろうとする行為です。
実際には起きていない事故をでっちあげて保険金を請求したり、事業をしていないのに事業者対象の給付金の申請をしたりするなどして、実際に受け取った場合等が該当します。
特殊詐欺
親族を名乗って現金を騙し取る「オレオレ詐欺」や、医療費や税金などの還付金があるといって、被害者にATMからお金を振り込ませる還付金詐欺などのことです。
他にも、警察官や銀行協会職員などを装って、キャッシュカードと暗証番号を聞き出して預貯金を騙し取る預貯金詐欺などもあります。
結婚詐欺
結婚するつもりがないのに、マッチングアプリや婚活サービスなどを通して異性に近づき、結婚する意志があるかのように見せかけて、相手から金品を騙し取る詐欺行為です。
架空請求詐欺
有料サイトの利用料金が未納である旨のショートメッセージを携帯電話に送ってくるなどして、実際には利用していない料金の支払いを請求する詐欺行為です。銀行振込のほか、電子マネーの購入を促して送金させるケースもあります。
電子計算機使用詐欺
他人のコンピュータなどに虚偽の情報を与えて、不正な記録を作り、利益を騙し取る詐欺行為のことです。例えば、インターネットバンキングに不正な情報を与え、自分の預金口座の残額を増額させるなどの行為が該当します。
準詐欺罪
準詐欺罪とは、未成年者の知慮浅薄や、心神耗弱状態にある人を利用して、財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする犯罪です。
刑法第248条で規定されており、10年以下の懲役が科されます。
詐欺罪は、人をだまして(欺罔行為)錯誤に陥れ、財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする罪です。
一方、準詐欺罪は、詐欺罪のように相手をだます行為(欺罔行為)は必要ありません。
未成年者の知慮浅薄や心神耗弱状態に乗じ、誘惑的な手段で財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりすることで成立します。
詐欺罪の裁判例まとめ
では、実際に詐欺罪で裁判になった事例を確認してみましょう。
ボートの修理代を架空請求して105万円をだまし取り懲役2年執行猶予4年
ボート整備業を営む男性と市役所職員が結託して、市に対して架空のボート修理費用を請求し、6回に渡り公金をだまし取った、という事例では、ボート整備業の男性に対して懲役2年、執行猶予4年の有罪判決が言い渡されました。
犯行自体は計6回行われており常習性があるものの、すでに共犯者とともに105万円の被害弁償金とそれに対する遅延損害金を弁済していることや、交通事故による罰金刑以外の前科がないこと、本件を深く反省していることや、岐阜市に犯罪事実を申告したことなどから、執行猶予付き判決となりました。
保険会社の元従業員が顧客から1億5420万円をだまし取り懲役3年執行猶予5年
保険会社の元従業員が、退職後も保険会社の社員を装い顧客と虚偽の保険契約を結んだ上で、保険料相当額1億5420万円をだまし取ったという事件では、保険会社の元従業員に対して懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました。
被害額が巨額であったにも関わらず、執行猶予付き判決が言い渡された大きな理由が、被害者への全額の被害弁償が済んでいることです。
この事件では、保険会社の顧客が被害を受けたことから保険会社が顧客に対して被害金額を全額支払いました。
元従業員は各被害者に合計187万円、保険会社にも30万円を支払い、今後も謝罪と弁償を続けることを誓っています。
被害を弁済したのは保険会社ではありますが、被害者の被害は回復されていることが量刑を決める上で評価されました。
また、元従業員には前科もなく、父親らが出廷して今後の元従業員に対する監督について誓っていることから、更生を見込むことができるとして執行猶予付き判決となりました。
勤務先に水増し請求を行い約4500万円をだまし取り懲役3年6か月
建設会社の営業部長である男性が、1年以上にわたって架空会社を通じて架空請求や水増し請求を行い、約4500万円をだまし取った事件では、男性に対して懲役3年6か月の実刑判決が言い渡されました。
男性は500万円を弁済しているものの、全額は弁済できていません。
また、架空請求や水増し請求で手にしたお金は遊興費等に使われており、悪質性が高いと判断されました。
ただし、男性が犯行を反省しており、男性の妻も今後男性を監督することを誓約していることから、懲役3年6か月という判断がなされたとのことです。
詐欺罪で弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼した場合、弁護士は、まず本人に会いに行って具体的な事情等を確認すると共に、捜査に関するアドバイスをしたり、家族への伝言等を預かったりすることができます。
また、早期の身柄解放に向けて、検察官や裁判所に対して釈放してもらうよう働きかけたり、被害者と示談を行う等して最終的な刑事処分を軽くするための活動をしたりといったことも行います。
①逮捕されたばかりでも、弁護士であれば本人と面会できる
逮捕された直後は、原則として家族でも本人と会うことはできませんが、弁護士であれば、逮捕された直後であっても、本人と面会(接見)することができます。
また、この接見に警察官は同席することはできません。
そのため、弁護士は、弁護士と本人だけで話をすることができるので、本人からしっかりと話を聞いた上でアドバイスをしたり、家族からの伝言を伝えたりすることができます。
突然逮捕されて精神的にダメージを受けている本人にとって、家族からの言葉やこうした弁護士との面会は、精神的にも大きな支えになります。
②早期に身柄が解放される可能性が高まる
本人が逮捕されると、逮捕した時から72時間以内に、更に10日間身柄を拘束するか否か(勾留の有無)を決めるための手続きが行われます。
この手続きに際して、弁護士は、検察官や裁判所に意見書や資料を提出する等して勾留すべきでないことを主張し、早期の身柄解放のため尽力します。
また、もしも勾留されることが決まった場合でも、弁護士は、裁判所に対して、その勾留の決定を取り消すべきことを主張して早期の釈放を求めるための活動を行います。
こうした活動を行うことによって、早期に身柄が解放される可能性が高まります。
③示談の成立により有利な結果となる可能性が高まる
詐欺罪において、被害者との示談が成立しているか否かは、検察官が起訴するか否か(≒前科がつくか否か)を判断する際や、起訴された後に裁判官が量刑を判断する際に重要な要素の一つとなります。
そして、被害者との示談を進めるためには、専門家かつ第三者である弁護士を代理人として立てることが一般的です。
詐欺罪の懲役に関するお悩みは弁護士に相談
詐欺罪の法定刑は懲役10年以下であり、罰金刑はありません。
悪質性が高い場合や被害者との示談が成立していない場合は執行猶予がつかず、実刑判決が言い渡されるおそれがあります。
詐欺罪において執行猶予付き判決や刑の減軽を求めるためには、弁護士に依頼して被害者との示談を締結することとが重要です。
また、再び罪を犯さないための環境構築も求められます。
詐欺罪に問われている方、詐欺罪で逮捕されている方のご家族は、問題をご自身で抱えずに弁護士にご相談ください。
詐欺罪の被害者は被害者感情が強く、加害者を処罰したいと強く考えている方が多いため、コミュニケーション能力が高い弁護士による示談交渉が必要です。
私達、東京スタートアップ法律事務所は、刑事事件で逮捕された方の大切な未来を守るために全力でサポートさせていただきたいと考えております。刑事事件に強いプロ集団が、ご相談者様の状況やご意向を丁寧にお伺いした上で的確な弁護戦略を立て、迅速に対応致します。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。
| 〈参考資料〉 ・平成30年版 犯罪白書 |
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
- プロフィール
- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務