保護観察とは?対象者や処分の内容・期間をわかりやすく解説

全国20拠点以上!安心の全国対応
初回相談0円
記事目次
保護観察とは、犯罪をした人や非行少年に科される処分の一つであり、一般の方々も一度くらいは耳にしたことがあるのではないでしょうか。
一方で、実際の保護観察制度について知っているという方は少ないかもしれません。
そこで、今回の記事では、どのような場合に、どのような人が、どういった保護観察を受けることになるのかを弁護士が解説します。
保護観察とは何?
保護観察とは、刑事処分や家庭裁判所の保護処分に基づき、一定期間、社会内で生活しながら保護観察官や保護司の指導・監督・援助を受け、再犯防止と社会復帰を促す制度です。
刑務所や少年院などに収容される「施設内処遇」と異なり、「社会内処遇」と呼ばれます。
具体的な保護観察の内容については、対象者の状況に応じて個別的な支援が行われることになります。
保護観察が実施されている背景
保護観察は、「更生保護法」に基づいて実施される制度であり、その根底にある理念は、犯罪者や非行少年を社会の中で適切に支援・指導しながら、更生の道へと導くことにあります(同法第1条)。
刑務所や少年院といった施設内での矯正処遇には一定の更生効果が見込まれるものの、それらの運営には多大な財政的・人的コストがかかるうえ、当事者自身にとっても社会からの隔絶や生活環境の急激な変化といった精神的負担が大きいのが現実です。
このような施設処遇は、確かに高い効果を持ちうる一方で、本人への影響も大きく、慎重な選択が求められます。
また、刑罰として収容させる必要までではないが、何もしないと本人のためにも社会のためにもならないといったケースも少なからず存在します。
そのため、このようなケースについては、社会生活を維持しつつ、更生支援を行う「保護観察」という制度が活用されているのです。
保護観察の対象者
保護観察の対象者は、主に(1)仮釈放中の受刑者、(2)保護観察付き執行猶予者、(3)家庭裁判所による保護処分の少年、(4)少年院仮退院者、(5)特定少年の一部です。
令和6年末現在、保護観察対象者は成人・少年ともに約1万人です。
出典:https://www.moj.go.jp/content/001432725.pdf
| 対象者 | 概要 |
|---|---|
| 仮釈放中の受刑者 | 刑務所から仮釈放され、残刑期間中に保護観察を受ける者 |
| 保護観察付執行猶予者 | 裁判で執行猶予が言い渡され、その期間中に保護観察を受ける者 |
| 保護観察処分の少年 | 家庭裁判所の決定により保護観察となった少年 |
| 少年院仮退院者 | 少年院から仮退院した後に保護観察となった少年 |
保護観察は誰が実施する?
保護観察は、保護観察の事務を管轄する役所である保護観察所の指導・監督の下で行われます。
具体的には、国家公務員である保護観察官と、法務大臣の委託を受けた民間ボランティアである保護司によって共同で実施されます。
保護観察官
保護観察官は法務省所属の国家公務員で、対象者の生活状況を把握し、再犯防止のための計画立案と運用を担います。
家庭訪問や面接、就労支援などの援助も行い、保護司の活動を補完・指導します。
重大な違反があれば、処遇の変更や取消しを裁判所・検察へ報告・提案する役割も果たします。
保護司
保護司は、地域に暮らす民間人が無報酬で取り組む公的ボランティアで、法務大臣からの委嘱により職務を担います。
対象者と継続的に関わり、面談や生活支援を通じて社会復帰を後押しします。
保護観察官と協力しながら、日常に寄り添う立場で孤立を防ぎ、更生を地域の中で支える重要な役割を果たします。
保護観察の内容
保護観察は、対象者が地域社会の中で安定した生活を送れるよう、「指導監督」と「補導援護」の二つを軸に、規律と支援の両面から更生を促す制度です。
指導監督
指導監督とは、保護観察中の人がまっとうな生活を送れるよう、保護司や保護観察官が見守りながら日常生活を把握し、必要な指導を行う活動です。
たとえば、「学校にちゃんと通っているか」「仕事は続いているか」「約束を守れているか」などを確認し、問題があれば注意したり話を聞いたりします。
再び悪いことをしないように支えながら、社会の一員としてしっかり生活できるように手助けする役割です。
補導援護
補導援護は、対象者の社会復帰を支えるために行われる生活全般をサポートする取り組みです。
就労・就学支援、生活相談、地域資源との連携などが含まれます。
保護司や保護観察官は行政機関や福祉機関との橋渡しを行い、自立の促進を図ります。
また、家族関係の調整や社会的孤立の防止にも取り組み、再犯防止と円滑な社会復帰を実現するための重要な支援手段です。
保護観察の種類とは?
保護観察の内容は、大きく二つ、交通違反事件と、それ以外の一般的な刑事事件で分けられます。
そして、それぞれが短期と一般で分けられているので、合計4つの種類があることになります。
一般保護観察
一般保護観察とは、交通事故以外の一般事件で付される保護観察で、社会内で更生を支援する処遇です。
対象者は保護司や保護観察官の指導・監督を受けながら生活し、再犯・再非行の防止と社会復帰を目指します。
対象者の属性や経緯に応じた支援が行われ、重大な違反があれば処遇の見直しが検討されることもあります。
一般短期保護観察
交通短期保護観察に対応する制度で、一般的な非行を対象とした比較的軽微なケースに適用されます。
保護処分決定後、短期間で観察され、早期に自立可能と判断された対象者に対し、効率的に更生支援を行います。
特に交通以外の非行について、初発事案であったり反省状況が良好である場合に用いられます。
交通保護観察
自動車やバイクによる重大な交通違反・事故などを起こした対象者に対して適用される処遇です。
道路交通法違反が中心で、交通法規の遵守意識形成などが行われることになります。
専門的な交通指導プログラムを取り入れるケースもあり、運転適性の評価と再違反防止が主目的といえます。
交通短期保護観察
交通違反の中でも特に軽微な事案に対して適用される処分です。
意外とも思えますが、集団講習などの集団処遇を行うことが一般的であるといえます。
指導内容は主に運転マナー、遵法意識、交通ルール理解に重点が置かれます。
保護観察とは異なる?試験観察とは
試験観察とは、家庭裁判所が保護処分決定に先立ち、対象者の生活状況や更生の見込みを評価するために一定期間観察する制度です。
正式な保護処分ではなく、観察の結果に基づき最終的な処遇が決定されます。
観察期間中は保護観察官や保護司が関与し、家庭や学校等での生活態度・非行傾向を評価します。
少年が指導に従い自立した生活を送れる見込みがあれば審判不開始や不処分となることもあります。
一方で改善が認められなければ、保護処分(例:保護観察、少年院送致)に進む場合もあります。
保護観察の期間
保護観察の期間は、対象者の属性や観察の種類により異なります。
少年の場合は20歳までが原則で、成人は仮釈放・執行猶予の期間に対応します。以下に対象別の期間を示します。
対象者:成人の場合
成人の保護観察は、仮釈放中の者については残刑期の満了までとなったり、保護観察付き執行猶予者については猶予期間中となるなど裁判官によって言い渡された期間となります。
対象者:特定少年以外の少年の場合
一般保護観察の場合、原則として保護観察期間は少年が20歳に達するまでとされます。
ただし、生活状況が安定し、再非行の可能性が低いと判断された場合は、家庭裁判所の決定により早期終了も可能です。
その他一般短期保護観察であれば半年程度、交通保護観察では半年程度、交通短期保護観察であれば4か月程度で解除を検討することになることが一般的です。
対象者:特定少年の場合
特定少年の保護観察期間は、家庭裁判所の審判により「6か月」又は「2年」と定められています。
対象事件の重大性や改善状況に応じて柔軟に運用されます。
保護観察中は何をする?
保護観察中は、対象者は保護司や保護観察官と定期的に面談・訪問を受け、生活状況の確認と指導を受けます。
就学・就労の継続や生活習慣の安定、遵法意識の育成が求められ、違反行為があれば厳正な指導が行われます。
更生に必要な支援も積極的に活用されます。
保護観察の遵守事項
保護観察中には、対象者が守るべき「一般遵守事項」と「特別遵守事項」が定められ、観察官・保護司によってその履行が確認されます。
一般遵守事項
一般遵守事項とは、すべての保護観察対象者に共通して課される基本的義務です。
内容としては健全な生活態度を保持することなど、日常生活の安定と遵法意識の形成を目的としています。
特別遵守事項
特別遵守事項とは、対象者の個別の事情に応じて定められる追加的義務です。
たとえば、「飲酒禁止」「異性関係の制限」「夜間外出の禁止」「ギャンブルの禁止」などがあり、対象者それぞれの事情に応じて臨機応変に設定されることになります。
保護観察の遵守事項を違反した場合の措置
保護観察中に遵守事項に違反した場合、保護観察官は家庭裁判所や検察庁に報告し、必要に応じて不良措置等を受けることになります。
少年の場合は、保護観察の延長や少年院送致に切り替わる可能性があります。
成人の場合、執行猶予が取り消され実刑となる場合もあり、仮釈放者は刑務所に再収容されることもあります。
違反の程度や改善の余地に応じて柔軟に判断されますが、軽微な違反の繰り返しでも重大と評価されることがあります。
保護観察に関するQ&A
保護観察に関して、よくある疑問を5つ紹介し、それぞれ分かりやすく解説していきます。
Q1. 保護観察とは?
犯罪をした人や非行のある少年が、社会の中で更生できるように、保護観察所の指導や監督を受けながら生活する制度です。刑務所や少年院に収容するのではなく、社会の中での立ち直りを専門家やボランティア(保護司)がサポートします。
Q2. 保護観察は大人にもありますか?
はい、あります。保護観察は少年の事件だけでなく、成人の刑事裁判で「執行猶予」が付いた際や、刑務所から「仮釈放」された際などにも対象となることがあります。
Q3. 保護観察は前歴になりますか?
保護観察自体は前科ではありませんが、一定の法的記録には残ります。
少年の場合、記録は家庭裁判所で管理されることになります。成人についても、仮釈放や執行猶予中の記録が残るため、裁判や再犯時には考慮されることがあります。
ただし一般に就職や資格取得の際に不利益が生じるとは限りません。
Q4. 保護観察はどこで受けるのですか?
保護観察は基本的に対象者の自宅や職場、学校など、日常生活の場で実施されます。
保護司が対象者の生活圏を定期的に訪問し、保護観察官との連携のもとで指導・援助が行われます。
観察はあくまで社会内での更生を前提とした処遇であり、施設に拘束されることは原則としてありません。
Q5. 保護観察中に引っ越しできますか?
結論から言えば可能です。
しかし、事前に保護観察官・保護司への届出と許可が必要となるでしょう。
そして、居住地の変更は、指導体制や生活環境に影響するため、慎重に判断されます。
転居先でも適切な保護司の配置ができるかが確認され、新たな地域の保護司が支援を引き継ぐことになります。
Q6. 保護観察中に仕事を辞めても大丈夫ですか?
やむを得ない理由があれば退職は可能です。
ただし、その後の就職活動や生活状況について説明が求められることになるでしょう。
そのような状態が長期化することは更生支援上望ましくないため、保護司・保護観察官と相談しながら次の就労先を探すことが考えられます。
離職後の支援についてはよく相談した方がよいと言えます。
Q7. 保護観察は途中で終了できますか?
保護観察の進捗が良好であると判断された場合など、家庭裁判所等の判断により、観察を予定より早く終了することがあります。
特に少年保護観察では、生活安定や遵守状況を踏まえた「解除決定」が用いられることも珍しくありません。
まとめ
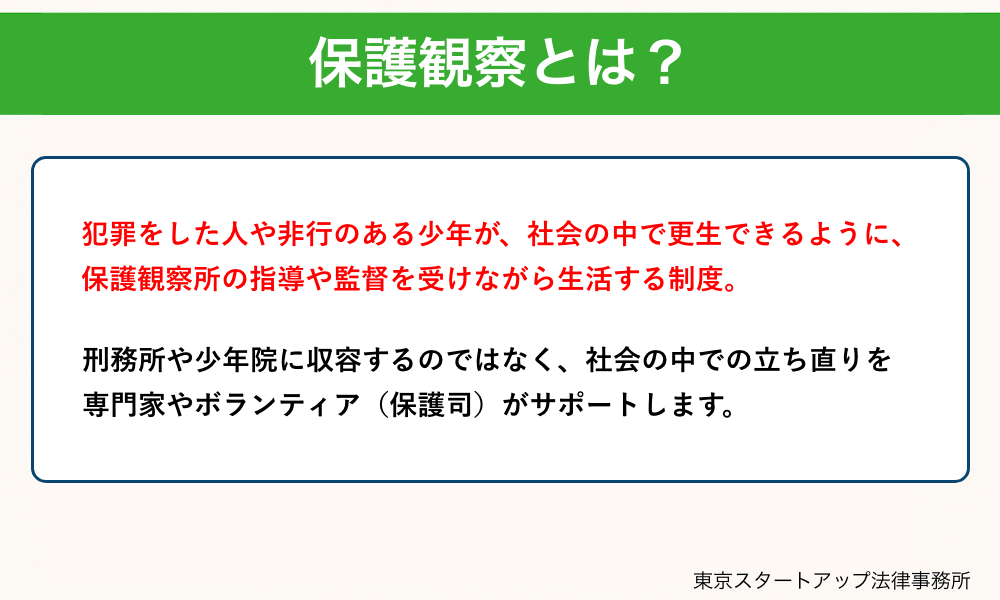
保護観察制度は「監視」そのものを目的としているわけではなく、あくまで対象者本人の自立や更生を目的としています。
少年事件においては、少年が保護観察となるのか施設収容となるのかが判断できないケースなどがあり、付添人としての活動が必要となるケースが多くあります。
もしそのようにお困りの場合などはお気軽に弁護士にお問い合わせください。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
- プロフィール
- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務




















