別居中にしてはいけないこととは?違法にならないために準備すべきことや注意点を解説
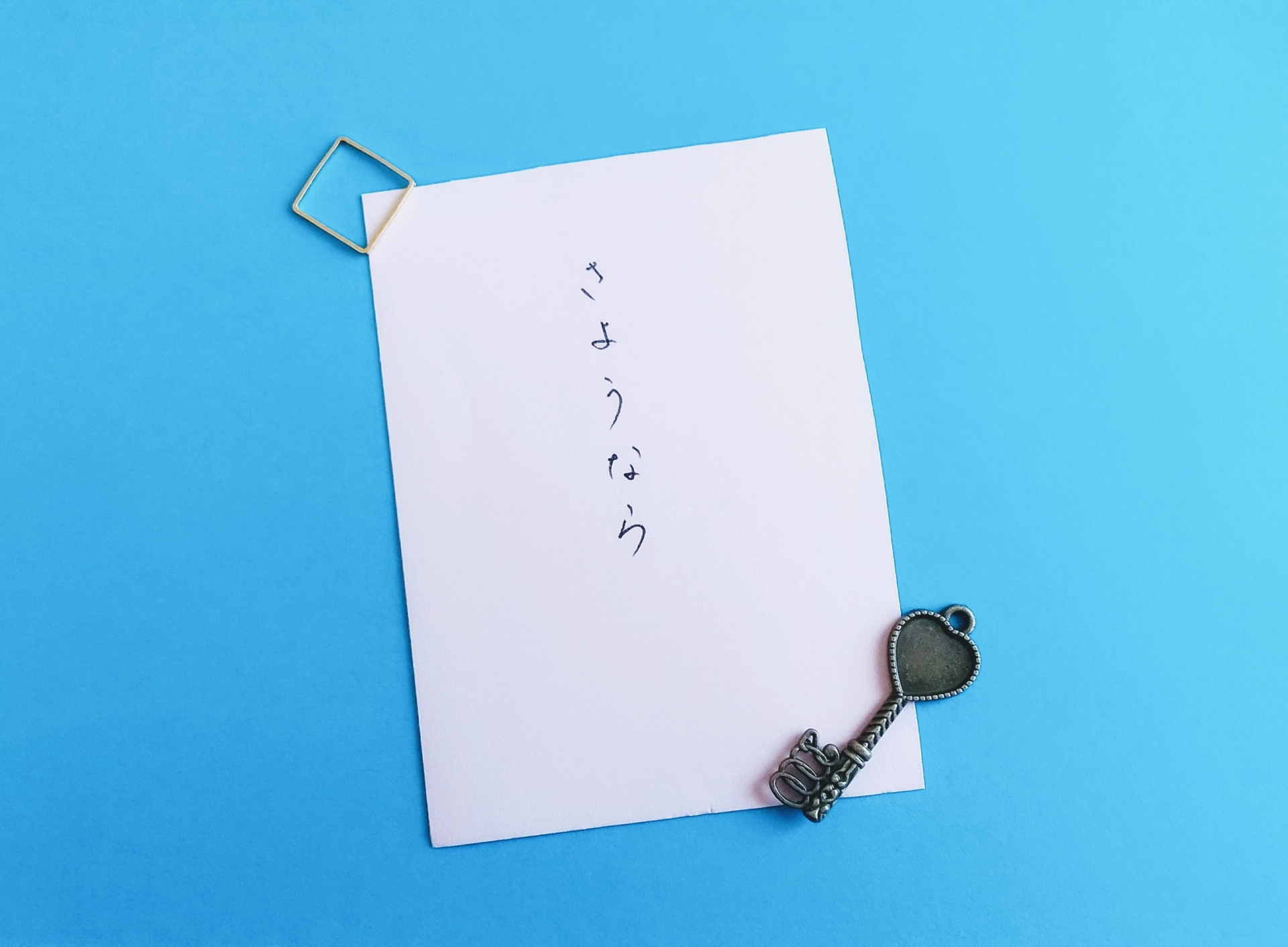
全国20拠点以上!安心の全国対応
60分3,300円(税込)
離婚とあわせて不貞慰謝料でも
お悩みの場合は無料相談となります
※
※
離婚に関するご相談の中で多くあるトピックとして、別居に向けた準備や、別居中の注意点に関することが挙げられます。「離婚に向けて話し合いを進めていきたい」、「DVやハラスメントを受けていて早く逃れたい」、「夫婦関係を修復するために冷却期間を設けたい」などと、別居をする理由は様々です。
とはいえ、別居をするということは、いまの生活環境をガラリと変えることになります。きちんと準備をしなければ生活に苦労することになります。
また、やってはいけないことに抵触してしまうと、却って不利な状況に置かれてしまう可能性もあります。
今回の記事では、離婚に向けて別居をするにあたって準備をするべきポイントや、別居中にしてはいけないことについて、ご紹介します。
離婚のために別居することは違法?
民法上、夫婦には同居義務と協力扶助義務が課されています(民法第752条)。つまり、同じ住居で生活を共にし、お互いに助けあうことが、法律上の義務とされているのです。そうだとすると、夫婦が別居することは違法とも評価できそうです。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
| 出典:e-Gov法令検索・民法 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_4-Ch_2-Se_2 |
この点、夫婦間で別居することの合意があるならば、違法とはなりません。問題は、一方が別居に同意していない場合です。
この場合、別居したくない配偶者は、相手方に対して、同居義務に基づいて同居を請求することが可能です。この請求にも相手が応じなければ、同居を求める調停を申し立てることができます。この申立てを受けて、家庭裁判所が、調停や審判によって別居継続の可否や、それに伴うルール等を取り決めることになります。
離婚調停の場合
調停とは、家庭裁判所の調停委員と呼ばれる、男女一名ずつの合計二名を間に挟みつつ話合いを行うものです。この話合いの結果、別居を継続するか同居を再開することに合意した場合には、その内容に従うことになります。
離婚審判の場合
調停がまとまらない場合、家庭裁判所が、別居を認めるべきか同居を命じるか判断をすることになります。この判断を、審判と呼びます。
この審判では、裁判所が、別居に正当な理由があるか否かを判断することになります。別居に正当な理由があると判断されれば、その別居は違法ではないということになりますし、他方で同居を求める内容の審判がされた場合には、その別居の正当な理由がない、つまりは違法であるということになります。
正当な理由の有無においては、特に先述した「協力扶助義務」を果たしているか否かが重要と考えられます。別居後に相手方に生活費を渡していないといった場合には、別居が「悪意の遺棄」に該当すると判断され、違法と評価される可能性があるのです。このようにして、別居が違法と判断されると、別居した方の配偶者が離婚原因を作出した「有責配偶者」と評価されてしまい、離婚請求が認められないおそれが生じます。また、慰謝料を支払わなければならない可能性もあります。
なお、審判で同居を求める判断がされたとしても、これを直接強制の形で実現することはできませんし、同居しないことを理由に金銭を支払わせる「間接強制」の方法も取れない点には注意が必要です。
正当な理由のある別居とは?
別居に正当な理由がある、すなわち「協力扶助義務」に違反しないと判断されるケースにはどのようなものがあるのでしょうか。
相手方から暴力を受けている場合や、モラル・ハラスメントといった精神的虐待がある場合には、そのことをもって正当な理由があると評価されるのが一般的です。正当な理由の有無が特に問題になるケースとしては、暴力やモラル・ハラスメントはないものの、夫婦間での会話がまったくなく関係が冷め切っていることや、性格や価値観が合わないことといった、明確に離婚原因に該当するかがはっきりしない場合です。
このような場合でも、夫婦の協力扶助義務に違反しない方法での別居であれば、少なくとも違法な別居であると評価される可能性は低くなるでしょう。具体的には、夫婦が同程度の生活水準を維持できるように婚姻費用を払うことが必要です。ここでは、いくつかのケースに分けて、夫婦の協力扶助義務に違反しない別居の方法について紹介します。
夫が定職を持ち、妻が専業主婦の場合
この場合は、夫の収入だけで家計が支えられている状態といえます。
このケースで夫側が別居を考える場合には、協力扶助義務を果たしていると評価されるために、妻側が夫側と同程度の生活を送れるように婚姻費用を支払う必要があります。この金額は、夫側の年収に応じて決められます。具体的には、裁判所が公開している算定表がありますので、これに従った金額を支払っておけば、問題はないといえるでしょう。ただし、住宅ローンを支払っている等の場合は、特段の考慮が必要ですので、弁護士への相談をお勧めします。
他方、妻側が別居を考える場合には、夫に対して、婚姻費用を請求することができます。
夫が定職を持ち、妻がパート勤務もしくはアルバイトをしている場合
この場合も、夫の収入の方が妻の収入よりも高い場合が多いと思いますので、夫側が別居を望む場合には、原則として算定表に従って決まる婚姻費用を、妻側に支払う必要があります。反対に、妻側が別居を希望する場合には、夫側に婚姻費用を請求することができる点も同様です。
夫婦共働きだが、夫の収入が妻に比べて多い場合
夫婦共働きの場合でも、夫の収入の方が妻の収入と比べて多いならば、夫が別居したい場合には、妻に対して、算定表に従った婚姻費用を支払う必要があります。夫婦としての協力扶助義務を果たすためには、夫婦間で同程度の生活水準を保つ必要があり、そのためには収入の高い方が低い方に対して生活費を負担する必要があるためです。
逆に、妻が別居を望む場合も同様に、妻から夫に対して婚姻費用を請求可能です。
夫婦共働きかつ双方が同程度の収入の場合
この場合は、別居に当たって相手方に婚姻費用を支払う必要は、基本的にはないといってよいでしょう。双方の収入が同程度であれば、特に生活費のフォローをしなくても同程度の生活を維持できるため、協力扶助義務に違反しないと考えられるからです。ただし、このパターンの場合も、住宅ローンを支払っている場合には、その自宅に住むのがどちらかによって別途考慮が必要となります。また、子どもがいる場合も、その人数や年齢によって金額が異なります。
以上のとおり、相手方に離婚原因に当たり得る要因があったり、暴力やモラル・ハラスメントがあったりすれば、別居には正当な理由があると判断されます。他方でそうした理由がない場合でも、適切な婚姻費用を支払うことで協力扶助義務を果たしていると評価されれば、別居自体の違法性が問題となる可能性は、ほとんどないといってよいでしょう。
別居中にしてはいけないこととは?
別居している場合でも、法律上は婚姻関係が継続しているので、安易に「別居しているから夫婦関係は終わっている」、「離婚前提だから」などと安易に考えることは適切ではありません。ここでは、別居中といえど避けるべき行動についてご紹介します。
配偶者以外の相手と不貞行為をする
別居中であっても、婚姻関係が破綻していたと法的に評価できない限り、貞操義務が認められます。したがって、別居期間中に配偶者以外の異性と肉体関係を持つことは、この貞操義務に違反するものとして、慰謝料を支払わなければならないおそれも生じます。
また、不貞行為は、親権や財産分与といった、慰謝料以外の離婚条件にも影響を与える事象であり、離婚問題がより複雑になってしまう要因となりますので避けるべきでしょう。
配偶者以外の相手と食事に行ったり、出かけたりする
肉体関係や性行為まで至らなくても、異性と二人きりで食事に行ったり、遊びに出かけたりすることも回避するのが賢明です。というのも、こうした行動だけでも、配偶者から不貞行為を疑われる可能性は十分あり、誤解を招く結果、話合いが困難となってしまうリスクがあるためです。
どうしても食事に行くことが避けられない場合には、あらかじめ配偶者に説明するなどして、理解を求めるのが重要でしょう。
執拗に連絡を取ろうとする
別居期間中にお互い話合いをすることもあるでしょうが、その範疇を超えて過度に連絡をすることも避けた方が良いでしょう。
特に、相手方が連絡をしないでと要望しているのに何度も連絡を取ったり、相手方が希望する連絡方法を守らず連絡したりする(電話はやめてほしいといわれていたのに、何度も電話をかける、等)といったことは、相手方に無用なストレスを与えてしまうばかりか、度を越せばストーカー行為と評価されるおそれもあります。
基本的には配偶者の意思を尊重し、必要な範囲での連絡にとどめるようにしましょう。場合によっては、弁護士を通して連絡を取ることも一案です。
子どもを連れ戻そうとする
相手方が子どもを連れて別居した場合、なんとかして連れ戻したいと考える心情は理解できないではありません。
しかし、強引に連れ戻してしまうと、子どもの心身に大きな負担を与えてしまう危険があります。結果として親子関係にも悪影響が生じ、親権・監護権や面会交流で不利に判断されることもあります。
また、その態様によっては、未成年者略取誘拐罪(刑法第224条)に該当する可能性もあります。いずれにせよ誰にとっても良いことはないので、避けるのが良いです。
生活費を支払わない
先にもご説明したように、別居中であっても夫婦間の協力扶助義務がありますので、生活費を分担して支払う必要があります。これを支払わないと、協力扶助義務に違反するものとして離婚協議において不利な材料となるだけでなく、ひどいケースでは「悪意の遺棄」に当たるとして、離婚ができなくなる・慰謝料を支払わなければならなくなるといった事態にも陥りかねません。
夫婦間の話合いを拒否する
関係改善を考えているのであれば、別居中であっても離婚や夫婦関係の再構築に向けた話合いには応じるようにすべきです。また、離婚をしたいと考えている場合でも、その条件や子どものことについて話し合うことで、より早期に解決を図れる確率も高まりますし、逆に話合いに応じなければ、それ自体が不利な要素と評価されるおそれもあります。
離婚するにせよ、あるいは再構築を目指すにせよ、しっかりと話合いをすることは不可欠というべきでしょう。
別居する前に準備すべきポイント
別居を決断したら、その時点で少しでも早く別居の準備を進めていくことが肝心です。最も重大な関心事である別居後の生活費についてもきちんと考えておく必要はありますが、それだけではありません。ここでは、別居前の準備事項について解説します。
配偶者の財産を可能な限り把握しておく
離婚を進めていくことになれば、婚姻期間中に築き上げた財産を財産分与によって清算する必要があります。この財産分与を少しでも有利に進めるためには、配偶者の財産を可能な限り把握しておくことが必要となります。別居してしまうと、相手方が任意に出してくれない限り、相手方の財産を特定するのは難しくなるため、同居期間中に準備しておくことが重要です。
主に把握しておくべき財産としては、以下があります。
- 預貯金口座の口座情報(銀行名、支店名、口座番号、通帳残高)、現金
- 不動産(土地や建物)の取得金額や現在価値が分かる資料、住宅ローン残債額の資料
- 株式、社債等の有価証券に関する資料
- 生命保険や学資保険等の資料
- 自動車の車検証
- 退職金の有無、ある場合にはその勤務先の勤務年数
- 借金の有無とその残債額
また、婚姻費用の金額を決めるにあたっては、配偶者の収入も必要な情報となります。したがって、配偶者の給与明細(会社員の場合)や決算書・確定申告書(自営業の場合)も確認できるのが望ましいでしょう。
生活費を準備・確保する
別居後の生活を安定させるには、まずは生活費を確保することが肝要です。別居前に、配偶者との間で生活費の分担や、その支払方法についてしっかり話し合いましょう。
別居をする配偶者が生活費を支払ってくれない場合でも、婚姻費用を請求することも可能です。具体的には双方の収入や支出、子どもの年齢・人数によって決まります。話合いが難しい場合は、弁護士へ相談していただくのも有効です。
別居のルールを取り決めておく
別居後に円滑に生活を送るためには、別居中のルールを配偶者との間で取り決めておくことが重要です。別居の期間や、離婚の条件、子の監護権や面会交流に関する事項について、しっかり話し合って決めておくと、別居中でもスムーズに生活を送ることが可能です。取り決めた内容は、合意書等の書面にしておくと安心です。
とはいえ、双方でルールを取り決められるほどにまっとうに話合いができないような場合には、弁護士等の第三者に間に入ってもらうのも良いでしょう。
別居先を確保しておく
別居するには、もちろん別居するための住居を探すことも大切です。別居を決断した段階で、まずは別居に適した住居を確保するのが重要です。
別居先としては、別途借家を契約して借りる、マンスリーマンションに入る、実家に戻る等が代表的ですが、いずれにせよ重要なのは、自分にとって最もよい別居先を選択することです。通勤や通学の便利、予算やプライバシー・防犯の確保等、慎重に吟味して消えることをお勧めします。
別居日を確定する
別居後の生活費も確保し、別居先も確保できれば、あとはいつ別居を開始するかを決めるだけです。これについては、引越業者との日程調整や別居先の入居可能日の確認が必要となるほか、配偶者との話合いが可能であれば、事前に伝達しておくとスムーズに話合いに入りやすいでしょう。
他方で配偶者から暴力やモラル・ハラスメントを受けて別居する場合には、秘密裡に別居を進めていく必要があります。そのためには、相手方が不在にしている日に合わせて、これらの引越しに向けた作業を進めていくよう手配する必要もあります。話合いができない場合には、別居にあたって置き手紙を用意するのも一案でしょう。ただ、その内容には注意すべき点もありますので、弁護士に相談されるのが良いでしょう。
別居中にしてはいけないことに関するよくある質問
質問1:別居した方が離婚はしやすいの?
別居がそのまま婚姻関係の破綻に直結して評価されるとは限りませんが、少なくとも客観的に、婚姻関係に何らかの問題があると評価されるケースが多いため、離婚を認める理由の一つにはなると思います。特に、不貞行為や暴力といった明確な離婚原因がない場合には、別居していることやその期間自体が、離婚を認める重要な要素となる場合が多いため、より重要といえます。
また、夫婦関係について冷静に話し合うには、別居をした方が話し合いやすいというのもあると思います。
いずれにせよ、別居は離婚に向けた大きな最初の一歩であるといえますので、離婚に向けて進めていきたい場合には、別居を検討するのは有効でしょう。
質問2:別居期間がどのくらいになれば離婚できるの?
離婚が認められるのに必要な別居期間は、別居の原因が不貞行為等の離婚原因にあるのか、それとも単に性格の不一致なのか、双方の経済状況等の事情によって異なります。重要なのは、婚姻関係が破綻しており、その回復も見込めない状態に至っているか否かという点です。
一概にはいえませんが、あくまでも肌感覚としては、離婚が認められるには少なくとも3年間は別居を継続している必要があると感じます。これに加え、たとえば別居を望む側に不貞行為等の有責性がある場合には、必要とされる別居期間がより長期化する、という傾向にあるといえるでしょう。
質問3:別居することは相手方に伝えないといけないの?
相手方には、別居することを伝える必要はありません。もちろん円満に話合いができる状況であれば伝えても良いでしょうが、基本的には、事前に伝えることで相手方から妨害を受けるおそれもあるため、あえて伝える必要はないといえます。
特に、暴力やモラル・ハラスメントを受けているケースでは、より慎重に、秘密裡に進めることが必要です。
質問4:別居後、相手方には連絡先を教えた方が良い?
別居後に連絡先を相手方に伝えてよいかは、相手方のタイプや別居理由によって異なるでしょう。
相手方との話合いが冷静に行えそうであれば、連絡先を教えてあげる方が、その後の離婚協議をスムーズに進めていくことが可能と言えます。一般的にも、離婚協議をするには双方の連絡先を知っておく必要があるので、教えることで以下のような問題がないのであれば、連絡先を伝えるのがベターではあります。
しかし、相手方が別居先に押しかけてくることが予想される場合には、別居先の住所を教えることは絶対に避けるべきです。また、時間を問わず電話してくる可能性が高い相手方についても、電話番号を教えることは避けるべきでしょう。また、暴力やモラル・ハラスメントを受けているケースでも、住所や連絡先を教えることは絶対にやめましょう。
このような理由から連絡先を教えることができない・適切ではない場合には、当事者間で離婚協議をすることはかなり難しくなります。その場合には、弁護士に依頼・相談していただくか、調停申立てをすることが必要となるでしょう。
質問5:別居中に性交渉をするとどうなる?
すでに説明したとおり、別居中であっても、貞操義務は存続します。そのため、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つと、不貞行為に該当するとして、慰謝料支払義務が発生する可能性が高いです。
この点、別居していることからすでに婚姻関係が破綻していると主張するケースが散見されますが、実際に裁判所が婚姻関係の破綻を認めるケースは多くありません。ハードルは極めて高いものと考えておくべきで、安易に他の異性と関係を持つことは避けるのが賢明でしょう。
質問6:別居中は連絡を取ってはいけないの?
別居する目的として、離婚協議や婚姻関係の修復が挙げられますが、その場合には、相手方と連絡を取る必要がある場面も少なくないと思います。もちろん、必要な連絡であれば別居中であっても禁止されないのが原則ですし、相手方も特に連絡を取ること自体に拒絶反応を示していないならば、連絡を取っても問題ないでしょう。
もっとも、相手方が連絡を取ることを控えてほしいと要望している場合には、過度な連絡は却って不利になる可能性があるので、避けるのが良いでしょう。また、相手方が弁護士に依頼している場合には、交渉窓口は弁護士になるのが基本ですから、相手方本人に連絡することはやめるべきです。さらに、裁判所からの接近禁止命令や退去命令等が発令されている場合には、連絡を取ること自体がこの命令に違反することになるので、絶対に避けましょう。
まとめ
別居をすること自体は、離婚原因がある場合や、そうでなくても夫婦の協力扶助義務をきちんと果たしていると評価されるのであれば、違法とはならないケースがほとんどです。しかし、別居をするには事前の準備が極めて重要ですし、他方で別居をされる側にとっても、慎重に行動すべき場面があることは、しっかり理解しておくのが良いと思います。
別居中には、以上のほかにも、離婚協議をどう進めるべきか等、悩むポイントは多いと思います。そうした場合には、弁護士に是非お気軽にご相談頂けたらと思います。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
- プロフィール
- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務


















