子供の認知とは?認知されないとどうなる?認知の効果や期限を紹介
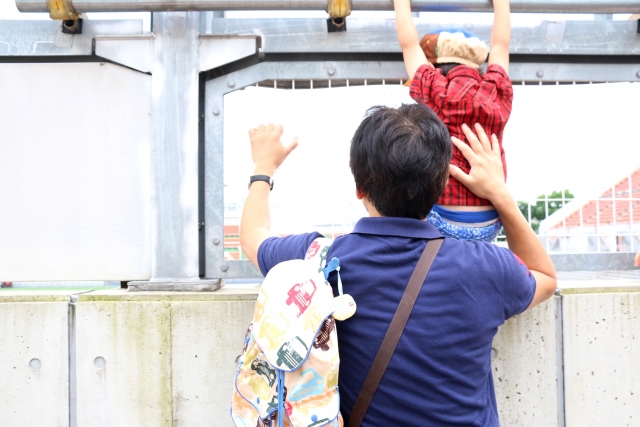
全国20拠点以上!安心の全国対応
60分3,300円(税込)
離婚とあわせて不貞慰謝料でも
お悩みの場合は無料相談となります
※
※
記事目次
「親子関係を法的に確定したい」「戸籍に父親の名前を記載したい」とお考えの方はいませんか?
実は、未婚のまま子どもが生まれた場合や、父親が不明な場合など、法的な手続きは意外と身近な問題です。
「子の認知」とは、父親が自分の子どもであることを認め、法的な親子関係を成立させる手続きを指します。
この制度は、子どもの権利や相続、養育費の支払いなど、様々な場面で重要な役割を果たします。
ここでは、専門家である弁護士が、認知の基礎知識や手続きの流れを分かりやすく解説します。
子供の認知とは何か
子の認知とは、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子(非嫡出子)と父親との間に、法律上の親子関係を成立させる手続きをいいます。
そもそも血縁上の父子関係と法律上の父子関係は異なります。
母子関係においては、ほとんどの場合、分娩(胎児が母体から娩出されること、つまり出産。)によって、血縁上の母子関係が明確に判明し、それがそのまま法律上の母子関係となります(例外として、母が身を隠して出産し、子を放棄した、いわゆる捨て子の場合等には、母による認知が行われるときがあります。)。
しかし、父子関係は、分娩がないため、子とのDNA鑑定をしない限りは明確には血縁上の父親を定めることができません。
ところが、そうであっては子の父親が確定するまで時間がかかり、子の養育にとって不利益となります。
そこで、妻が婚姻中に妊娠した子や、婚姻を基準に一定期間内に生まれた子は夫の子と推定され(嫡出推定。その推定の及ぶ子を嫡出子といいます。)、認知がなくとも法律上の父親が定まります。
他方で、この嫡出推定が及ばない子に関しては、父親を定めるためには、父による認知というプロセスが必要になっていきます。
嫡出推定制度とは
嫡出推定制度とは、上記概要で触れたとおり、子が嫡出子であることの推定を及ばせる制度のことをいいます。
具体的にこの制度は、民法772条1項において、「妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。」として規定されています。
また、この規定に当てはまらない場合でも、同条2項において、「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消(離婚)若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻期間に懐胎したものと推定する。」とされており、同2項を通じて同1項の嫡出推定がなされるように規定されています。
この嫡出推定制度によって、早期に扶養義務を負う父親が確定し、子の身分関係の安定に資することになります。
子供を認知しないと父子関係が生じない
仮に上記嫡出推定の及ばない子がいた場合、その子について父子関係を創設するためには、父による子の認知が必要になっていきます。
当然には父子関係は創設されないのです。
ただ、上記民法の嫡出推定に関する規定は、嫡出推定によって推定される父が多くの場合血縁上の父と相違ないことも考慮して作られています。
なお、父の方から子の認知をしない場合には、子や母は認知調停の申立てや認知訴訟の提起によって、認知を争うことができます。
これは、父の方から子を認知する場合を任意認知というのに対して、強制認知と呼ばれます。
認知が必要なケースとは
上記民法772条1項、同2項をみると、夫婦が婚姻中に妻が懐胎、つまり妊娠した子は夫の子と推定されるため、認知は不要です。
また、妻が婚姻外で子を妊娠したとしても、それが婚姻前の妊娠であって婚姻後200日より後の婚姻中の出生であれば認知は不要です。
また、離婚後300日以内に出生した場合も認知は不要です(離婚した元夫について認知が不要という話であり、再婚した場合には再婚後の夫についての話となる。)。
逆にこれ以外のケースにおいては認知が必要となりますし、嫡出推定がなされた場合の父以外の者による認知を望む場合には、まずは嫡出否認の手続き(調停、訴訟)をとったうえで、新たにその者による認知をする必要があります。
子供が認知されるとどうなる?
子の認知がなされると、民法上父子関係が創設されます。
そのことにより、直接又は間接的に様々な効果が発生します。
たとえば、①戸籍上の父子関係創設、②扶養義務の発生、③親権者の確定がなされます。
戸籍上の父子関係
子の出生に基づき母が出生届を出しても、戸籍上は母の欄のみに記載がなされるのであり、父の欄は空白のままです。
しかし、認知届出がなされると、子の父欄に認知の情報(認知日、認知者氏名、認知者の戸籍、認知届の受理者等)が記載され、父の戸籍にも認知の情報(認知日、認知した子の氏名、認知した子の戸籍等)が記載されます。
扶養義務
親は子に対して扶養をする義務があります。
これを扶養義務といい、民法730条において「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」と規定されています。
子は、ここでの直系血族に含まれます。
ただ、ここから直ちに養育費を支払う義務が出てくるわけではありません。
なぜなら、扶養の具体的方法は法律上特には定まってはいないためです。
婚姻している夫婦間の子であれば、かたや働いて稼ぎ、かたや食事を作るという形もあり得るのです。
しかし、婚姻をしていない場合には、結局は、親権又は監護権を有する者に対し、そうでない者が扶養義務としての金銭的支出をすることを果たす必要がある場合があります。
子や実際に監護養育する者にとっては、扶養義務の態様としての金銭的支出を受けるための策として、認知があり得るのです。
親権
子の親権者となれるのは、法律上子の親となる者です。
したがって、いくら血縁上の親であることが分かっても、法律上の親であることが定まっていない場合には親権者にはなり得ません。
非嫡出子の父親になろうとする者は、少なくとも子を認知する必要があるのです。
そして、婚姻中は共同親権、離婚後であれば単独親権(共同親権も選択肢になる法律改正がなされ、2026年5月までに施行される予定。)となりますが、いずれにしろ親権者変更の手続きを踏む必要はあります。
相続権
認知によって法的に父子関係が成立すると、子は父親の法定相続人となります。
これにより、子は嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦の子)と同様に、父親が亡くなった際にその財産を相続する権利を得ます。
具体的には、民法で定められた相続順位に従い、他の相続人(配偶者や他の兄弟姉妹など)と共に、父親の遺産を分け合うことになります。
この相続権は、子の生活の安定や将来の保障において非常に重要な意味を持ちます。
また、父親が遺言を残していた場合でも、子には遺留分(遺言によっても奪われない最低限の相続割合)が保障されており、この点でも子の権利は保護されます。
子供の認知の3つの種類
認知の方法としては大きく二つあり、任意認知と強制認知と呼ばれる違うものがあります。
前者は、認知をする者がその意思に基づき認知をすることで、さらに届出による認知と遺言による認知に分かれます。
これまでは数が多い届出による認知を念頭に置いていましたが、遺言による認知も存在します。
強制認知については、認知者の意思に基づかず、裁判所の関与の下認知がなされるものです。
1.届出による任意認知
届出による認知は、認知をする者が、認知届を役所に提出して行う認知方法です。
認知届には、認知する子や認知をする者の本籍等情報を記して提出します。
ただ、全てが任意認知として認められるのではなく、認知をする子が成年であればその子自身の承諾が必要であり、その子が胎児である場合には母の承諾が必要であり、その子が死亡している場合にはその直系卑属(直接的に親子関係で繋がる後世代の血族)がいることが必要です。
2.遺言による任意認知
遺言による認知は、生前、認知をする者が遺言としてその意思を遺し、その者の死亡によって遺言の効力を生じさせ、認知をするという方法です。
届出による認知とは方法は異なりますが、その他遺言による認知全てが任意認知として無条件に認められるわけではないことは、届出による認知と同様です。
3.強制的な認知
強制認知とは、父親が任意で子の認知をしない場合に、裁判所の手続きを通じて法的な父子関係を確立する方法です。
これにより、子の権利と法的地位が保障されます。
これは、子の福祉を守る上で非常に重要なプロセスとなります。
認知調停の申し立て
強制認知の第一歩は、家庭裁判所へ認知調停を申し立てることです。
この調停は、裁判官や調停委員が間に入り、父親と子(または子の母親)が話し合い、合意による解決を目指す手続きです。
調停では、子の最善の利益を考慮しながら、双方の意見が聞き入れられ、父子関係の有無について議論されます。
もし話し合いがまとまり、調停が成立すれば、その合意内容に基づいて認知が認められます。
しかし、残念ながら話し合いが平行線をたどり、調停が不成立に終わった場合は、次の段階である認知訴訟へと進むことになります。
認知訴訟の提起
認知調停が不成立に終わった場合、次に家庭裁判所に認知訴訟を提起します。
この訴訟は、裁判所が提出された証拠に基づいて父子関係の有無を判断し、強制的にその関係を確定させる手続きです。
訴訟では、原告側(子、または子の母親)が、その子が被告である男性の血縁上の子であるという証拠を提出し、それを証明する責任を負います。
この際、最も有力な証拠となるのはDNA鑑定の結果です。
その他、関係者の証言や過去のやり取りなども証拠として提出されることがあります。
最終的に、裁判所が父子関係を認める判決を下した場合、その判決に基づいて強制的に認知が成立し、子の戸籍にも父親の情報が記載されることになります。
認知の訴えはいつまで可能?
認知の訴えは、子らが父(又は母)を相手に起こすものです。
そして、基本的には訴えが認められる期間の制限はありません。
しかし、その父(又は母)が死亡してから3年を経過したときには、認知の訴えを起こすことはできなくなります。
この規定の趣旨は、死後3年も経てば人それぞれ新たな権利関係が築かれるなかで、相続による権利関係の混乱を避けようとするものです。
子供の認知を取り消せる?
子の認知をした父や母は、原則としてその認知を取り消すことはできないとされています。
このことは民法785条に規定されています。この趣旨は、父子関係が不安定な状況は、子にとって好ましくないというものです。
ただ、詐欺又は強迫によってなされた認知は取り消すことができる可能性があります。
これはそもそも当初の認知が、意思に基づくものといえないためです。
また、成年の子を認知するなどの場合のような承諾がないときや、血縁上の父ではないのに認知がなされた場合等では、認知の無効を争うことができます。
これらの取り消しや無効は、まずは調停の申立てによって争い、それでも解決しなかった場合には訴訟による解決が図られます。
血縁関係のない子を認知してしまった場合どうなる?
血縁関係のない子を認知してしまった場合、その認知は原則として無効を主張できます。
これは、認知が真の親子関係を反映していないためです。
認知の無効を争うには、まず家庭裁判所に調停を申し立て、話し合いで解決を図ります。
調停が不成立の場合、「認知無効確認の訴え」を提起し、裁判で争います。
裁判ではDNA鑑定が重要な証拠となり、血縁関係がないと証明されれば、認知は無効と判断されます。
認知請求が認められた事例
DNA鑑定により父子関係が証明されることで、父に対する認知請求が認められた事例もあります。
他方で、そのような鑑定の証拠がなくとも、肉体・交際関係の存在や自ら子の出産費用を負担し、出生届も自分の子で届け出ようとしたことなど、実父としての行動を取っていたことなどを理由に認知請求を認めた事例も存在します。
他にも、その者以外の者とは肉体関係を持たなかったことも考慮して認知請求を認めた事例もあります。
認知請求権の放棄とは
認知請求権の放棄とは、認知をすることを請求する権利を放棄することで、認知請求を今後することができなくなるものをいいます。
この認知請求権の放棄はできないこととされています。
これは、認知請求権は、子と親に関する身分関係を律するための請求権であり、任意に放棄できる性質のものではないためとされています。
よくある質問
認知請求をしたい、認知請求をされた場合はどうすればよい?
まずは、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
たとえば、認知請求をしたいのであれば、基本的に、最初は口頭等で認知をお願いするでしょうが、それを拒否された場合にはどうしても調停や訴訟という法律的な手続きになっていきます。
その場合には、相手方との交渉はもちろん、裁判所に認知を認めてもらうための法的な主張をすることになります。
そのなかにはDNA鑑定といった一般の方には馴染みのないことや、他の関係のありそうな事情から有利な事実を取り出して主張することをしていく必要があります。
このようなことは弁護士に相談して行ってもらうことが解決の近道です。
認知請求をされたら、受け入れなければならないのか?
必ずしも認知請求を受け入れる義務があるわけではありません。
父でもないのに自らの子と認める必要はありませんし、基本的に自らの意思で行うべき認知を法律に反して強迫等されて行うべきではありません。
ただ、もし実際に自分の子であるならば認知をする必要も出てきます。
しかし、100%自分の子であるとは判断できない事例は、少なからずあるのではないでしょうか。
もし、認知請求をされ、認知をするか迷っている場合には、ぜひ弊所弁護士へご相談ください。
認知をすると父の性になるのか?
回答としては、当然には父の姓にはなりません。
裁判所に子の氏の変更許可申立てをして認められ、その後父の戸籍に入る必要があります。
この手続きは、子本人がすることができます(子が15歳未満のときは、その法定代理人により行います。)。
認知をすると親権は変わるのか?
回答としては、変わりません。
親権者を変えるには、認知ではなく裁判所に親権者変更の申立てをする必要があります。
そこで、子の利益を踏まえて親権者の変更が相応しいかを裁判所が判断して、相応しい場合には親権者の変更がなされることになります。
したがって、認知をしたからといって当然には親権者は変わりません。
ただ、親権者の変更をするためには、まず親である必要がありますから、その場合には認知をする必要が出てきます。
まとめ
これまで、認知とは何か、認知と関わる嫡出制度とは何か、認知方法の種類やその違い、認知請求の事例等をみていきました。
認知は一般の人にとっては難しい概念で、法律の学問としても議論がある分野です。
特に、最近は認知についての民法上の規定の改正もありました。
今回はその改正法の内容に基づき解説をしましたが、今後も議論が生じる部分もあると思います。
一人で悩むのではなく、ぜひ専門家である弁護士を頼ってみてください。
認知やそれに関係することで迷われた方がいらっしゃれば、お気軽に弊所弁護士へご相談ください。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設


















