離婚の財産分与にかかる税金とは?税金がかかるケースや注意点を徹底解説
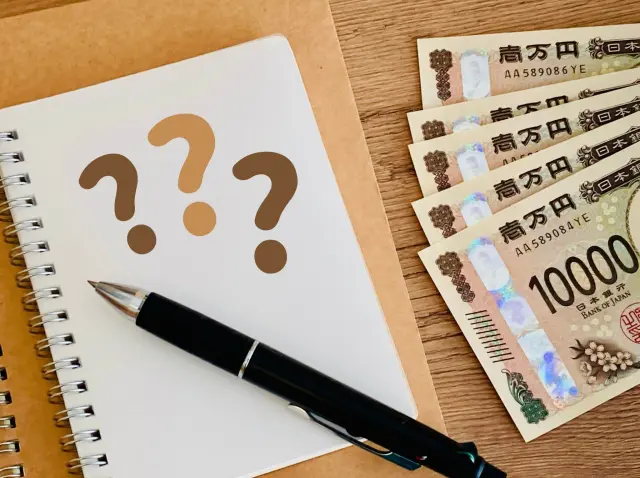
全国20拠点以上!安心の全国対応
60分3,300円(税込)
離婚とあわせて不貞慰謝料でも
お悩みの場合は無料相談となります
※
※
記事目次
離婚に伴う財産分与は、夫婦が築いた財産を公平に分け合う大切な手続ですが、
「税金はかかるのか?」という疑問を抱く方も多いでしょう。
実際には現金や預貯金の分与には通常税金はかかりませんが、不動産や株式などを分与する場合には譲渡所得税や登録免許税などが発生するケースがあります。
また、贈与税の対象と誤解されやすいため注意が必要です。本記事では、財産分与にかかる税金の仕組みや課税される具体的なケース、さらに注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
そもそも財産分与とは?
夫婦が離婚をするに至った場合、夫婦でこれまで築き上げてきた財産を清算しなければなりません。
基本的には夫婦で稼いだお金は、どちらか一方のお金ではなく、夫婦としての財産となるからです。このように夫婦の財産を分けることを財産分与と言います。
離婚時の財産分与に税金はかかる?
基本的に、夫婦の財産を分けるという手続である以上、所得税や贈与税などの税金はかからないこととされています。
しかし、一部の場合には税金が発生するケースもありますので、本記事ではどのような場合に税金が発生するのか等について解説していきます。
財産分与を受けた側
上記の通り、基本的に税金が課されることはありませんが、後述の通り、多すぎる財産を受けた場合や、不動産を財産分与として取得した場合では、一部発生するケースも存在します。
財産分与を支払った側
こちらの場合も、金銭で支払った場合には基本的には税金が課されることはありません。
もっとも、金銭以外の資産を譲り渡す場合には、譲渡所得の有無によって、所得税や住民税が課されるケースもあることに注意が必要です。
離婚時に財産分与を受けた側に税金が課されるケースとは?
財産分与を受け取った側に税金が課される代表的なケースは下記3つがあります。
- 多すぎる財産分与を受けた場合
- 不動産の財産分与を受けて登記手続をした場合
- 慰謝料の代わりに不動産を譲り受けた場合
次よりそれぞれについて解説いたします。
多すぎる財産分与を受けた場合
受けた財産分与の額が、共有財産の2分の1を大幅に超えている場合には、財産分与の名を借りた贈与であると税務署により判断されるおそれがあります。
財産分与は原則2分の1を受け取る形になりますが、特段の事情もないにも関わらず2分の1を超えるようなケースでは、実質的に贈与であるとみなされるからです。
不動産の財産分与を受けて登記手続をした場合
不動産は単に双方の合意のみで手続が終わるわけではなく、法務局又は地方法務局において所有権移転登記手続を行い、所有者を登記する必要があります。
登記そのものは法律上の義務ではありませんが、不動産の権利を主張することができなくなる可能性が高くなりますので、実質的には義務と考えた方がいいでしょう。
そして、登記申請を行う際には、不動産の種類や固定資産税評価額に応じた額の登録免許税を納付しなければなりません。
慰謝料の代わりに不動産を譲り受けた場合
慰謝料については、夫婦間で合意があれば、不動産によって代物弁済をすることが可能です。
そして、財産分与の中には慰謝料的財産分与といい、慰謝料の性質も含む財産分与が行われることも多く、実質的には財産分与の性質も併せ持つケースがあります」に変更してください。
もっとも、慰謝料として不動産を受け取る場合には、不動産所得税の課税対象となることがあります。
また、慰謝料としての適正な金額と比較してあまりにも高額な不動産を受け取っている場合には、贈与とみなされ、贈与税が課される可能性もあります。
離婚時に財産分与を支払う側が税金について確認すべきポイント
財産分与を支払う側においては、譲渡所得税が課されるか否かを検討すべきことになります。
控除で実質的に支払い義務を負わないケースもありますが、どのように検討すべきか考えてみましょう。
譲渡所得税の課税の有無・金銭
譲渡所得税とは、不動産や株式などを譲渡した際に発生する税金であり、内訳には「所得税」「住民税」「復興特別税」があります。
そして、近年の不動産価格の高騰に影響し、不動産の購入価格よりも売却価格が高くなってしまった場合、財産分与のために売却すると、譲渡所得税がかかる可能性があります。
-
- 基本的に譲渡所得税は下記の計算式で課されることになります
課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
収入金額:
原則として、資産の譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額となります。尚、財産分与として不動産そのものを譲り渡す場合は、不動産の時価が収入金額となります。
取得費:
不動産を取得するために要した費用です。資産の購入代金のみならず、購入手数料、設備費や改良費などが含まれます。但し、減価償却の対象となる資産については、所有期間中の減価償却費相当額が取得費から差し引かれることになります。
譲渡費用:
不動産を譲渡するために直接かかった費用です。第三者に売却した場合における仲介手数料などがここに含まれます。
特別控除額:
一定の要件を満たす場合に受けることができる所得控除の金額です。
一例として、後述の3000万円の特別控除などがあります。
これらを踏まえた上で、譲渡所得が課されるかどうかを検討し、課税される恐れがある場合には、納税資金の準備が必要です。
3000万円特例の適用の可否
財産分与として、居住用財産を分与することに至った場合には、一定の要件を満たすと、
譲渡所得から3000万円の特別控除を受けることができるようになります。
-
- 下記項目に該当している場合には適用されることになります。
①マイホームであり
②引っ越しから3年以内の年末に売却を行い
③売却相手が親族ではなく
④過去3年以内に3000万円特例を受けておらず
⑤マイホームを過去一度も「賃貸・事業用」にしていない
離婚において気を付けるべきは、③であり、離婚成立前であれば夫婦という関係性が残っている状況であるため、配偶者に譲り渡すと特例を受けることができなくなります。
離婚時の財産分与に課される税金を軽減する方法
財産を清算したのですから、できる限り手元に金銭を残したいと誰もが思うと思います。
次は、どのような方法で税金を減らすことができるか、その対抗策について検討してみようと思います。
極端に多額の財産分与を受けない
基本的には財産分与は2分の1であり、それより多額の財産分与を受けてしまうと、贈与であるとみなされるわけですから、多額に過ぎる財産分与とはしないことが無難です。
特に贈与税については、申告期限経過後に追徴課税を受けるケースも多くそうなると過少申告加算税や延滞税などを含めると、単に贈与税に限らない数字とならざるを得ないケースもあります。
勿論、事情によっては割合を変える必要もあるケースもありますので、弁護士や税理士のアドバイスを受けながら進めていくことが望ましいです。
離婚成立前に自宅を配偶者へ譲渡することは避ける
先ほども述べた通り、3000万円の特例を受けるためには、親族等の関係性のない方への譲渡が必要不可欠です。
そして、離婚成立以前であれば、法的には夫婦である以上、親族関係は継続していますので、3000万円の特例を受けることが出来ないことになります。
従って、マイホームを財産分与で配偶者に渡す場合、手続関係については全て離婚成立後に行う事が求められることになります。
各種控除を利用する
財産分与を行う上で課される可能性のある税金としては、贈与税や所得税などです。
これらのうち、贈与税については、毎年110万円までの基礎控除が設けられています。
そのため、110万円までであれば申告をした上で控除を受けることができます。
また、確定申告を行う際にも、所得税などについては、各種控除を受けることができるケースもあります(3000万円特例は一例です)。
これらについては、要件を満たす必要があるため、税理士のアドバイスを受けた上で進めていくことをお勧めいたします。
離婚時の財産分与に課される税金に関するよくある質問
Q1. 財産分与について揉めている場合には誰に相談をすべきか?
基本的には、法律上の問題や税金に関する問題など、多岐に渡って考えなければなりません。
その中でも、財産分与については、単なる相談のみならず、代理人として配偶者との交渉や裁判所における手続を一任できる弁護士への相談をおすすめ致します。
他方、税金については、弁護士も一定の知識を有しているものの、毎年出される通達などにまで精通している税理士への相談が最も確実です。
弁護士が連携している税理士であれば、網羅的にアドバイスが可能となりますので、おすすめ致します。
Q2. 財産分与で3000万円の控除は受けられる?
先にも触れさせていただいた通り、第三者に対して自宅を売却する場合には3000万円の控除を受けることができる可能性が高いです。
他方、配偶者へ譲渡する場合には、離婚成立後であれば3000万円の控除は可能ですが、離婚成立前であれば3000万円の控除を受けることは出来ない形となります。
また、それ以外の要件もありますので、ご不安な方は弁護士ないしは税理士へのご相談をおすすめ致します。
Q3. 確定申告での各種控除を受けることができるのか
仮に贈与税が発生するケースで、確定申告を行う場合、税法上どのような扱いとなるのかは注意が必要です。
贈与税の中でも、基礎控除に該当する年間110万円以外にも、様々な特例措置が存在しております。
ただ、これらは基本的に申告をして初めて認められる特例となりますので、計算上は贈与税がかからないケースであったとしても、申告が必要となります。
そして、そのためには贈与者の住民票の写しなどを取得する必要があるため、離婚成立前に予め配偶者に伝えておく必要があります。
まとめ
本記事では、財産分与にかかる税金について解説致しました。
本記事で解説したものは主に問題となりうるものであり、税金自体は多岐に渡ることから、注意が必要な点もまだまだ多くあります。
もし、ご自身の財産分与について不安に思われる方や、財産分与の進め方に不安がある方は、ぜひ一度東京スタートアップ法律事務所までお問合せ下さい。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設


















