熟年離婚を成立させるために必要な準備とは?
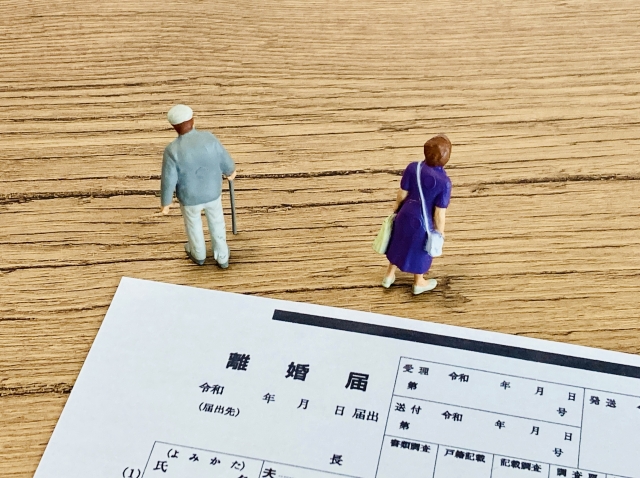
全国20拠点以上!安心の全国対応
60分3,300円(税込)
離婚とあわせて不貞慰謝料でも
お悩みの場合は無料相談となります
※
※
記事目次
熟年離婚が年々増加していると言われていますが、長年連れ添った夫婦が離婚を決断する背景には、長いからこその夫婦の間に積み重なった不満や、老後への不安等が潜んでいるようです。ただいきなり熟年離婚をすることは現実的ではなく、そのための経済的な備えや法的な手続きの確認、身の回りの人たちとの関係についての構築や見直しなど、離婚後の生活を見据えた準備が必要不可欠です。本記事では、熟年離婚を考えるうえで知っておくべき原因や準備、進め方のポイントをわかりやすく解説します。
熟年離婚をする原因とは?
近年、長年連れ添った夫婦の「熟年離婚」が増加傾向にあります。その背景には、さまざまな問題が積み重なってきた結果があります。
長年のストレス
まず挙げられるのは、「長年のストレス」です。結婚生活の中で相手への不満を言えず我慢を重ねる中で、将来もこのままの生活を続けることについて考える中で、定年や子どもの独立を機に、夫婦生活に限界を感じて離婚に踏み出すケースがあります。
お金のトラブル
次に「お金のトラブル」です。夫婦の金銭感覚の違いや、浪費癖、知らない間に借金する、生活費を勝手に使い込むなど、経済的な問題は夫婦の間でも信頼関係を揺るがすものでしょう。特に老後資金への不安が高まる時期には深刻な問題となります。
ハラスメントなどの夫婦間のトラブル
「ハラスメントなどの夫婦間のトラブル」も離婚の原因になります。いわゆるモラハラやDVといった精神的・身体的な暴力は、長年続き常態化することで深刻なダメージを与えます。
親の介護
また、「親の介護」を巡る考え方の違いも深刻化する問題となります。どちらが親を介護するか、どこまで協力するか等すれ違いが生じやすい問題で双方の関係が悪化することもあります。
家庭のことに非協力的
最後に「家庭のことに非協力的」なパートナーへの不満です。子どもが大きくなるまで家事や育児に非協力的な姿勢であっても我慢してきたものの、子どもが自立し老後の生活まで共にすることまで考えたときに、それは避けたいと感じる人が多くいます。
熟年離婚前におさえるべきポイント
熟年離婚は、長年築いた生活基盤を一変させる大きな決断です。後悔のない選択とするためにも、以下の3つのポイントは必ずおさえておきましょう。
1. 財産分与・年金分割の基本を理解する
まずは離婚にあたって、夫婦の共有財産をどのように分けるかという財産分与が重要な検討事項となります。双方の有する預貯金や不動産、自動車、退職金などは財産分与の対象になりますが、「婚姻期間中に築いた財産」が原則とされるため、結婚前に築いた財産や相続財産などは対象外です。また、年金についても「年金分割」という制度があり、専業主婦(夫)であっても婚姻期間中に配偶者が負担してきた年金について分割できる場合があります。これらの制度の理解と、財産分与や年金分割のための手続きのために必要となる書類の準備も重要です。
2. 離婚後の生活設計を立てる
熟年離婚では「離婚後の生活」が最大の不安材料です。例えば自分の今後の収入の見込みや、自分の住まい、医療・介護のための備えなど、離婚後に必要な生活資金を試算し、自立した生活を送れるかを現実的に考える必要があります。また、どちらが家を出るか、離婚後の周囲の家族や友人のサポート体制も含めて確認することが大切です。
3. 離婚する理由を確認する
熟年離婚では、長年連れ添っている以上、相手が離婚を拒否するケースもよく見受けられます。夫婦の間での協議での離婚成立が難しい場合には、法に定められた離婚事由に該当することが必要です。民法上の離婚事由としては、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病で回復の見込みがないことなどが挙げられます。感情的に離婚を決める前に、まずはこれらの条件に該当するか、該当するとしても客観的な証拠があるかを確認しましょう。事前に専門家に相談することも有効な手段です。
熟年離婚の前に準備しておくこと
熟年離婚をスムーズに進めるにあたって、次のような事前の準備は欠かすことができないでしょう。
生活費を確保しておく
まず「生活費を確保しておく」ことが重要です。離婚後すぐに収入がない状況では、生活が立ち行かなくなります。貯金や就労の計画を立てましょう。
住居を構える場所を確保しておく
次に「住居を構える場所を確保しておく」ことも重要です。離婚や離婚に向けた協議の間に自分は実家に戻るのか、賃貸を借りるのかなど、離婚後に安心して暮らせる場所の見通しをつけることが必要です。
離婚をするための証拠の準備
そして、「離婚をするための証拠の準備」も重要です。例えば相手の不貞やDV、生活費を入れないことの証拠は、調停や裁判になった際に非常に有効です。日記や写真、音声、LINEの履歴など第三者に対しても客観的にその事実を示すことのできるものが特に証拠になり得ますので大切に管理しておくことをおすすめします。
熟年離婚によって受け取れるお金
熟年離婚が成立した場合には、以下のようなお金を受け取る可能性がありますので確認しておきましょう。
1. 財産分与
婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、原則として半分ずつに分けるのが基本です。対象となるのは、預貯金、不動産、株式、保険の解約返戻金、車などです。財産分与には、清算的な意味合いでの財産分与の他に、慰謝料的な分与や扶養的な分与(残された配偶者が生活困難に陥るのが明らかな場合に支払われる配偶者への援助)も含まれる場合があります。退職金も分与対象になることがありますが、実際に支給されたかどうかなどで判断が分かれることになります。
2. 年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金の「年金保険料」を離婚時に分け合う制度です。配偶者より収入が低かった場合や専業主婦をしていた場合は、年金分割をしておくと将来年金を受け取る際に年金受給額が加算されるため、「年金分割」は将来の重要な財産といえます。年金分割は、離婚することによって自動的に行われるものではありません。離婚条件を決定する際に、「合意分割」とするか「3号分割」とするか等分割の方法を定めた上で、年金分割の手続きを行う必要があります。また分割のためには所定の手続きが必要で、年金事務所での書類提出や、合意書の準備が必要になります。
3. 慰謝料
相手に不貞行為やDVなどの不法な行為が認められる場合、相手に対して慰謝料を請求することができます。その不法行為の性質や内容によりこれによって被った精神的苦痛に対する賠償として数十万円〜数百万円が認められる場合があります。ただし、性格の不一致や価値観の違いだけでは慰謝料は認められにくい点に注意が必要です。
4. 退職金
退職金は、婚姻期間中に形成された将来の資産として、財産分与の対象になることがあります。すでに支給済みであれば金額が明確ですが、退職前の場合は見込額を算出する必要があります。企業によって退職金制度が異なるため、在職証明書や規程の確認が必要です。
配偶者に熟年離婚を申し出るタイミング
熟年離婚を切り出すタイミングは様々考えられますが、主に以下のような節目は、離婚を切り出す機会としてよくある機会として挙げられます。
1. 親元を子どもが離れた
子どもが独立し、親としての役目を終えたと感じるタイミングは、夫婦関係を見直す大きな節目でしょう。例えば子どもが成人したり、子どもが結婚をして新たに家庭を築いたことを機に離婚をすることが考えられます。夫婦の間でも心理的にも経済的にも離婚の申し出が行われやすい時期といえるでしょう。
2. 自身で収入元を確保した
特に専業主婦(夫)だった場合、離婚後の収入が問題となって離婚を諦めることもあるでしょう。しかし就職や資格取得、副業などで自立できる見通しが立った段階であれば、生活面の不安が軽減され、離婚後の計画も立てやすくなります。
3. 退職金や年金をもらえるタイミングになった
配偶者の退職が近い場合、その時期を待って離婚する人も少なくありません。退職金は財産分与の対象になるため、離婚前に支給されることで財産が明確になり、有利な条件で交渉できる可能性があります。また、年金分割も婚姻期間中の記録が必要になるため、タイミングを見計らって申し出ることが重要です。
熟年離婚は子どもに影響がある?
子どもが成人している場合でも、熟年離婚は心理的に少なからず影響を与えることはあるでしょう。特に長年夫婦として生活してきた両親の離婚に対して、ショックや不安を抱く子どもも少なくありません。
しかし、夫婦の間で関係が悪化し夫婦関係が破綻した状態を続けることも子どもにとっては不安やストレスを感じる要因となります。離婚を決断する際には、子どもに対しても丁寧な説明や配慮を示すことが必要です。離婚後であっても親子であることに変わりないため家族としてのつながりを大切にしつつ、今後の関係性を見据えて話し合うことが重要です。
熟年離婚の流れ
熟年離婚の一般的な流れは以下のとおりとなります。
1. 夫婦間での話し合い(協議離婚)
2. 離婚調停(家庭裁判所への申し立て)
3. 離婚訴訟(調停が不成立の場合)
まずは夫婦間で話し合いや協議の場を設けて、お互いに話し合った末、離婚することについて話がまとまり合意に至れば「協議離婚届」を市区町村役場の窓口に提出することで離婚が成立します。これがいわゆる協議離婚となります。
その一方で夫婦の間で離婚について話し合ったとしても話がまとまらない可能性もあります。その場合は家庭裁判所に離婚についての調停を申立てることになります。調停では、第三者である調停委員を交えて離婚条件の調整を行います。
離婚調停を経てもなお離婚について合意できない場合には、離婚訴訟へと手続きを進めていくことになります。離婚訴訟の中で財産分与や年金分割など離婚と同時に決めてほしい事項について申し立てることができ、これらについて裁判官が判断を下すことになります。
また双方にとっても離婚のための手続きが長引くことも負担となるため、まずは円満な解決を目指すことも重要です。その際には、話し合いに先立って事前に準備をすることや、感情的になりすぎないよう冷静な話し合いを行うことのできる環境作りも大切な要素となります。
熟年離婚を有利に進めるためのポイント
熟年離婚を少しでも有利に、かつスムーズに進めるためには以下の2点が重要です。
1. 感情的になりすぎない
お互いに長年生活をともにしてきているため、相手への不満や怒りをぶつけたくなることもあるでしょう。ただ話し合いの中で、あまりに露骨に感情をぶつけたり態度で示すことは自分が責められてしまう展開を招き、その後の交渉において不利に働く可能性が高いでしょう。相手に非があっても、まずは冷静に事実と証拠に基づいた話し合いを心がけましょう。
2. 弁護士を挟んで話し合いをする
離婚に関しては法律の専門知識や交渉経験が必要な場面が訪れます。そのような場面では、弁護士の力を借りることが得策でしょう。特に財産分与や年金分割、慰謝料請求などで有利な条件を引き出すためには、専門家の法的なサポートが不可欠です。また自分の味方になり相手との交渉の窓口になる弁護士の存在は離婚について交渉や手続きを進める中で生じるであろう精神的な負担を軽減することにもつながるでしょう。
まとめ
熟年離婚は、人生の後半を大きく変える選択です。不安や課題も多い問題ですが、正しい知識や事前の準備、冷静な態度と判断があれば、自分らしい第二の人生につながる一歩となりえるでしょう。一人で悩まず、まずは必要に応じて専門家に相談しながら、自分にとって納得のいく判断は何なのか検討をしていくことをおすすめします。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
- プロフィール
- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務


















