調停離婚とは何?協議離婚との違いや流れ、費用、期間中にやってはいけないことを解説
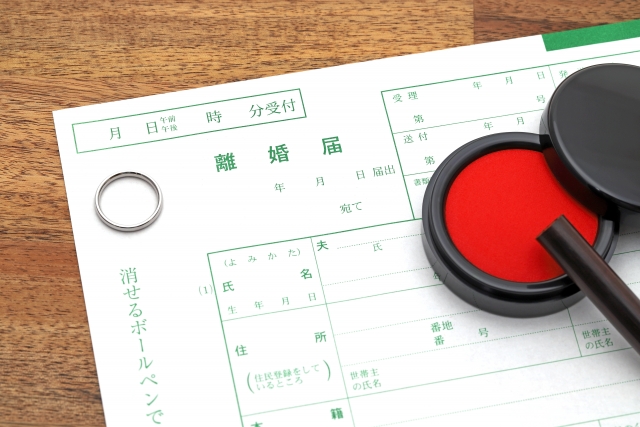
全国20拠点以上!安心の全国対応
60分3,300円(税込)
離婚とあわせて不貞慰謝料でも
お悩みの場合は無料相談となります
※
※
記事目次
離婚を考え始めたとき、「調停離婚」がどんなものか分からず不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
協議離婚とは何が違うのか、費用や期間はどれくらいかかるのか、そして調停中にやってはいけないことはあるのか…。
この記事では、調停離婚の基本から実際の流れ、注意点までをわかりやすく解説します。後悔しない離婚のためには、正しい知識を身につけることが重要です。
調停離婚とは何?
調停離婚は、夫婦間で話し合いがまとまらないときに、家庭裁判所で調停委員を交えて解決を目指す離婚手続です。
調停委員を交えるとは言っても、夫婦が同じテーブルにつき、調停委員と一緒に話し合いを行うというものではなく、双方が交互に調停委員と話し合い、調停委員が双方の意向を聞いた上で、第三者としての立場からすり合わせを行うという形で解決を図っていきます。
夫婦だけでは離婚を合意できないケースに利用され、特に親権や財産分与などの争点がある場合に有効な手続だといえます。
冷静に話し合える場を設けることで、感情的な対立を避け、公正な合意形成を支援します。
調停離婚と裁判離婚の違い
調停離婚と裁判離婚は、いずれも夫婦間で協議がまとまらない場合の手続ですが、解決の方法と性質に明確な違いがあります。
調停離婚は、家庭裁判所の調停委員を交えた話し合いによって合意を目指す手続であり、当事者同士が最終的に合意することで成立します。
一方、裁判離婚は、調停で合意に至らなかった場合に行われる訴訟手続で、裁判官が証拠や主張をもとに離婚の可否を法的に判断します。
調停では柔軟な合意形成が可能ですが、裁判では、民法770条1項に定める「法定離婚原因」が必要で、主張が認められなければ離婚が成立しない場合もあります。
また、裁判離婚は手続が長期化しやすく、費用や精神的負担も大きくなる傾向があります。
このように、両者の違いは「話し合いによる合意」か「裁判官の判断による解決」かという点に集約されます。
調停離婚で話し合う内容とは?
調停離婚では、離婚に関する全てのことを話し合いますが、特に、夫婦間で合意できなかった離婚条件については重点的な話し合いがされます。
具体的には、親権や養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用の分担などが主な項目です。
調停委員が間に入り、それぞれの主張を聞きながら合意点を探ります。
特に子どもに関する取り決めは慎重に進められ、将来にわたる生活への影響を考慮して判断されます。
感情的な対立を避け、冷静に話し合う場として、調停は重要な役割を果たします。
調停離婚のメリット・デメリット
調停離婚は、離婚を目指す上で非常に有用な手続ですが、メリットとデメリットがあるため、それぞれ比較検討した上で手続を選択する必要があるでしょう。
メリット
調停離婚の大きなメリットは、夫婦だけではまとまらなかった話し合いを、第三者である調停委員がサポートしてくれることです。
感情的になりがちな場面でも、冷静に進めやすくなります。
また、非公開の場で行われるため、プライバシーが守られるのも安心材料の一つ。
子どもの親権や養育費など、将来に関わる大切なこともじっくり話し合えます。
「話し合いはしたいけど、当事者同士ただとうまくいかない…」そんなときに、調停は心強い選択肢です。
デメリット
調停離婚のデメリットの一つは、調停が平日の昼間に行われるため、仕事や家事との調整が難しくなることです。
また、合意に至るまでに複数回の調停期日が必要なことが多く、時間や精神的な負担がかかりやすい点も気をつけたいところです。
さらに、調停で合意できなければ離婚は成立せず、その場合は裁判に進むことになるため、すぐに解決したい方には向かない場合もあります。
調停離婚を行ったほうがいいケース
離婚をするためには、まず当事者同士による協議の形で進めることがほとんどです。
しかし、双方で希望する条件に乖離がある場合や、感情的になって話し合いができない場合などには、もはや協議を行っても意味がないと感じることもあるでしょう。
そのような場合は、離婚調停を申立てるべきです。
調停は話し合いで進めるものですし、時間もかかる手続のため、いきなり訴訟を提起したいと思う方もいるかもしれませんが、離婚訴訟を提起するためには必ず離婚調停を行っていることが必要なので、当事者だけでは解決できないと感じた時点で、まず離婚調停を申立てるべきだといえるでしょう。
離婚調停を申立てる前に知っておくべきこと
離婚調停を申立てる前には、必要書類や費用、手続の流れをしっかり確認しておくことが大切です。
申立てに必要な書類
離婚調停を申立てる際には、家庭裁判所にいくつかの書類を提出する必要があります。
準備不足のまま裁判所に行くと、手続が進まなかったり、再提出が必要になったりすることがあるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
以下が主な提出書類です。
| 書類名 | 内容・備考 |
|---|---|
| 申立書 | 調停を申立てるための基本書類。裁判所の窓口やHPで入手可能。 |
| 夫婦の戸籍謄本 | 申立人の現在の戸籍(全員分)が記載されたもの。発行から3か月以内が目安。 |
| 事情説明書 | 離婚に至る経緯や、争点となっている内容を具体的に記入。任意提出だが重要。 |
| 連絡先等の届出書 | 相手方に知られたくない住所がある場合などに利用。裁判所指定の様式あり。 |
| 進行に関する照会回答書 | 調停を円滑に進行するために参考とする書類。裁判所のHPで入手可能。 |
| 年金分割のための情報通知書 | 年金分割を請求する場合に提出。最寄りの年金事務所で取得可能。 |
| その他関連資料 | 財産資料、子どもに関する資料など。調停内容によって任意で提出。 |
特に戸籍謄本は、多くの方が直前まで準備を忘れがちですが、申立てには必須です。
市区町村役場で450円程度の手数料で取得できますし、多くの市区町村では、マイナンバーカードを利用したコンビニでの交付に対応しているため、お早めに準備するといいでしょう。
また、「事情説明書」は任意とはいえ、調停委員が事情を把握するための大切な参考資料になりますので、できるだけ具体的に記入しましょう。
書類は不備がないように正確に記入することが大切です。
不安がある場合は、事前に家庭裁判所へ問い合わせるか、弁護士へ相談すると安心です。
申立てにかかる費用
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 収入印紙代 | 1,200円 |
| 郵便切手代 | 約800~1,200円 |
| 戸籍謄本代 | 450円程度 |
これらの費用だけで、離婚調停の申立ては可能です。
つまり、合計でおよそ2,500円前後で済むケースがほとんどです。
裁判と比べると、かなり負担が軽いのが特徴です。
ただし、弁護士に依頼する場合は、これに弁護士費用が加わりますので別途検討が必要です。
離婚調停の流れとは?
離婚調停は、家庭裁判所で行われる公的な話し合いの場です。
申立てから調停終了までは「①申立て→②第1回調停→③第2回以降→④調停終了」という流れで進みます。
順を追ってみていきましょう。
調停申立て
申立て先は、原則として「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」です。
書類を提出すると、裁判所が内容を確認し、第1回目の調停期日が指定されます。
申立人と相手方には、調停期日通知書(呼出状)が郵送で届き、指定された日時が通知されます。
なお、この通知書は、申立てから届くまでに、2週間前後かかります。
また、初回の調停までには通常1か月から2か月程度かかるのが一般的です。
時間に余裕を持って準備を進めましょう。
第1回目の調停期日
初回の調停期日では、申立人・相手方がそれぞれ呼び出され、別々に事情を聞かれます。
調停委員(男女1名ずつ)と裁判官1名で構成される調停委員会が進行役となり、どんな経緯で離婚を考えるようになったのか、どんな点で折り合いがついていないのかを丁寧に聞き取ってくれます。
このとき、原則として夫婦は直接顔を合わせることはありません。
相手に言いにくいことでも、安心して話すことができます。
話し合いの内容は「親権」「養育費」「面会交流」「財産分与」「慰謝料」など多岐にわたりますが、調停委員が中立の立場から双方の意見を整理していきます。
第2回目以降の調停期日
離婚調停は1回で終わることはほとんどなく、2回目以降の期日が設けられるのが一般的です。
回数はケースによって異なりますが、2~5回程度に及ぶこともあります。
期日は約1~2か月に1回のペースで設定され、都度、調停委員が前回までの内容をもとに進行していきます。
双方が歩み寄りの姿勢を見せることで、徐々に合意点を見つけていく流れになりますが、一方的に相手が応じない場合は、調停が長期化することもあります。
話し合いを重ねる中で、調停委員からアドバイスや現実的な提案がされることもあり、感情的な対立を乗り越えるきっかけになることもあります。
調停終了
調停で合意に至ると「調停調書」という書類が裁判所によって作成され、法的効力のある離婚が成立します。
これは協議離婚とは異なり、改めて市役所に離婚届を出す必要はありません。
一方、どうしても合意に至らなければ「調停不成立」として終了し、次のステップとして離婚訴訟を提起することになります。
調停はあくまで「話し合い」による解決を目指す手続なので、双方の合意がなければ成立しません。
とはいえ、訴訟よりも費用負担が少なく、柔軟な解決を図れるため、可能な限り調停での解決を目指すことが望ましいといえます。
離婚調停にかかる期間の目安
離婚調停の期間は、通常半年から1年程度かかることが多いです。
調停は1〜2か月に1回のペースで複数回行われ、話し合いが難航したり、相手の出席が遅れたりするとさらに延びます。
争点が多い場合や複雑な事情が絡むと長期化しやすく、精神的な負担も増えます。
焦らず準備をし、冷静に臨むことが大切です。
離婚調停を有利に進めるためのポイント
離婚調停を有利に進めるには、以下に説明する通り、証拠の準備、冷静な対応、優先順位の整理、相手の主張の予測、調停委員への印象、弁護士の活用といった6つのポイントを意識することが重要です。
事実関係を整理し、証拠を集める
調停では、「言った・言わない」の争いにならないように、客観的な証拠が重要です。
たとえば、
・不貞行為の証拠(メール、写真など)
・DVの記録(診断書、LINEの履歴など)
・収入や財産の資料(源泉徴収票、預金通帳、ローン明細など)
これらを事前に整理しておくと、調停委員への説明がスムーズになります。
冷静な態度を保つ
感情的になってしまうと、調停の雰囲気が悪化し、調停委員からの印象も悪くなるおそれがあります。
特に相手を非難しすぎたり、声を荒げたりすると、不利に働くことも。
逆に、冷静に自分の主張を整理して話すことで、信頼されやすくなり、自分の立場を理解してもらいやすくなります。
感情は大切ですが、調停の場では理性的な対応を心がけましょう。
優先順位を明確にする
調停では、すべての希望が通るとは限りません。
どこを譲れて、どこを譲れないか、自分の中で優先順位をはっきりさせておくことが大切です。
たとえば、「親権は絶対に取りたい」「養育費は相場で構わない」など、交渉に柔軟さを持たせることで、合意に至りやすくなります。
重要なのは、自分にとって本当に必要なものを見極めることです。
相手の主張や立場を想定しておく
相手がどのような主張をしてくるか、事前にある程度予想しておくと対策が立てやすくなります。
たとえば、相手が財産分与を拒否する可能性がある場合、その根拠に反論できる準備をしておきましょう。
また、親権や面会交流に関する主張にも備えておくことが必要です。
相手の出方を想定しておくことで、突然の主張にも冷静に対応でき、有利に進められます。
調停委員に信頼される受け答えを心掛ける
調停は家庭裁判所の中立的な第三者である調停委員が進行役を担います。
そのため、調停委員から信頼されることが非常に重要です。
誠実で一貫性のある受け答えをすることで、あなたの主張が信用されやすくなります。
逆に、事実をあいまいにしたり、ウソがバレたりした場合は、大きく信頼を失い、調停全体が不利に傾くこともあるので注意が必要です。
必要に応じて弁護士に相談する
離婚調停は法的な知識と交渉力が求められる場です。
相手が弁護士をつけている場合や、争点が複雑な場合(親権、慰謝料、高額な財産分与など)は、弁護士に相談することで大きな助けになります。
弁護士は法律に基づいて適切な主張を整理し、あなたの立場をしっかり代弁してくれます。
調停に不安があるなら、早めに専門家の力を借りるのが賢明です。
離婚調停中で不利になる発言や行動
離婚調停中に不利になる発言や言動として、まず挙げられるのが感情的な態度です。
相手を強く非難したり、怒鳴ったりすると、調停委員から「冷静に話し合えない人」と見なされ、信用を失うおそれがあります。
また、事実と異なることを言ったり、証拠のねつ造を疑われるような発言も非常に危険です。
さらに、「子どもに会わせない」「慰謝料は絶対払わない」など一方的な主張も、調停の進行を妨げる原因になります。
調停では誠実で協調的な態度を見せることが、信頼を得る鍵になります。
まとめ
離婚調停は決して簡単な道ではありませんが、第三者の調停委員があなたの気持ちや主張をしっかり聞いてくれるため、離婚成立のためには非常に重要な場だといえます。
冷静に準備をし、自分の優先順位を見極めることで、納得のいく解決に近づけることができます。
困ったときには専門家の力も借りつつ、一歩ずつ前に進んでいくことが肝要です。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
- プロフィール
- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務


















