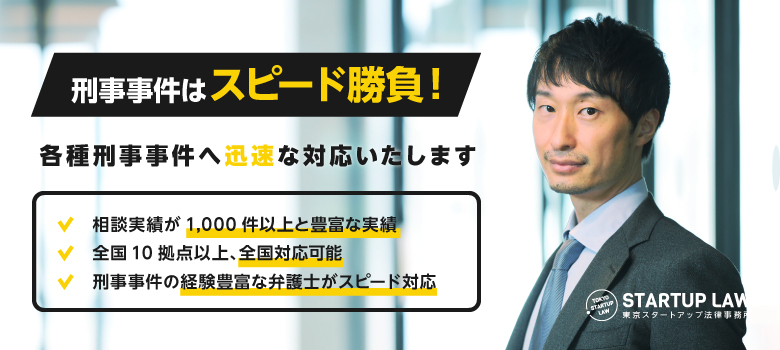業務上横領罪で逮捕されるケースと逮捕されないケース・刑事手続の流れも解説

全国20拠点以上!安心の全国対応
初回相談0円
記事目次
「職場で管理していたお金を着服したことが発覚した場合、全額返金しても業務上横領で逮捕されてしまうのだろうか」
「業務上横領罪で逮捕された場合、取調べや勾留などはどのような流れで行われるのだろうか」
このような不安や疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、業務上横領罪で逮捕されるケースと逮捕されないケース、業務上横領罪で逮捕された場合の刑事手続の流れや刑罰などについて解説します。
業務上横領罪とは
業務上横領罪(刑法第253条)は刑法第38章「横領の罪」に規定されている犯罪です。
第253条は単純横領罪(同法第252条)の特別規定で、委託に基づき、業務上、自己の占有する他人の物を横領する行為を特に重く処罰するとされています。
業務上横領罪で逮捕されるケース
業務上横領罪は親告罪ではないので、告訴がなくても検察官が被疑者を起訴することが可能です。
ただし、警察が被疑者を逮捕するには、法律上、逮捕状請求の要件として被疑者が罪を犯したことを認めるに足りる相当の理由(逮捕の理由)があることを要します。
さらに、逮捕状を発行する裁判官の判断に基づく逮捕の必要性が認められなければなりません(刑事訴訟法第199条1項2項)。
業務上横領罪は被害法益が財産に限られる経済犯罪であるため、民事上の損害賠償等により当事者間で解決することが望ましいことから逮捕の理由と必要性は厳格に解する必要があります。
そのため、横領行為が発覚しても、被害者による被害届が警察に提出されていない場合は、逮捕の理由と必要性は認められず、被疑者が逮捕されることは通常ありません。
被害届が警察に提出されていることを前提として、逮捕される可能性が高いケースについて説明します。
1.業務上の占有者による横領行為の疑いがある場合
①被害金額が10万円を超える場合
横領罪での逮捕の要件に被害金額についての明文の定めはありませんが、警察による調査を経た上で、被害金額が10万円を超える場合は逮捕される可能性が高いといえます。
なお、ここでいう被害金額は、被害者側が申し立てた金額ではなく、被害申告を受けた警察が事情聴取・調査した結果、割り出した金額の総額をいいます。
②横領した金額を全額返還した場合
業務上横領罪は、業務上委託信頼関係に基づいて財物を占有する者が横領行為を行った時点で既遂(犯罪成立)となります。
そのため、行為者が横領した金銭の全額を被害者に返還したとしても、業務上横領罪に該当する犯罪行為を行った事実は残ります。
逮捕の理由と必要性を判断する上で被害金額とともに、被害届が出された時点で既に全額返還されていたか、被害届受理後に返還されていたかの違い等が問題となります。
特に、被害金額が10万円以下の場合、被害届を出した時点では返還されていなかったが、その後全額返還されたという事情の変化があると、被害金額に鑑みて、逮捕の理由と必要性は認めにくくなります。
ただし、被害金額が数万円で既に全額返還されていてもなお被害届を出した場合は逮捕の理由と必要性が認められる可能性があります。
なお、被害金額が数十万円あるいは100万円以上に上る場合は、上記の事情を問わずに逮捕の理由と必要性が認められます。
2.非業務者・非占有者が横領行為に加担した疑いがある場合
業務上横領罪の行為者は、「業務上他人の物を占有する者」という刑法上の身分のある者に限られます。
したがって、委託信頼関係に基づく占有や「業務上」という要件を欠く者が単独で横領行為を行った場合、遺失物横領罪または単純横領罪が成立する可能性がありますが、業務上横領罪が成立することはありません。
ただし、非業務者・非占有者が共犯として業務上の占有者による横領行為に加担した場合は、業務上横領罪の共犯として逮捕される可能性があります(刑法第65条1項)。
もっとも、この場合に共犯として逮捕する理由と必要性が認められるためには、以下の2つの点がその時点で明らかであることが必要です。
- その業務上占有者が横領行為を行っているという認識(故意)があること
- 横領行為に対して積極的な関与を行っていること
これが特に問題となるのは、客観的に業務上横領罪の幇助犯(刑法第62条1項)にあたる行為を行っている場合です。
例えば、配偶者や友人が会社名義の現金を預かっていると知りながら、その者や自己の名義の口座に入金したという事実が明らかである場合は、業務上横領罪の幇助犯として逮捕される可能性があります。
3.業務上横領に加えて他罪への関与の疑いがある場合
業務上の占有者が、横領行為と同時に、あるいは別途に他の犯罪に関与した疑いがある場合、通常は逮捕の理由と必要性が認められます。
例えば、経理担当者が会社名義の預金を勝手に自己名義の口座に移転した事実とともに社用車を私用で使っていた事実が発覚したような場合は、業務上横領罪とともに窃盗罪(刑法第235条)の疑いもあるため、逮捕される可能性が高くなります。
業務上横領罪で逮捕されないケース
被害者から被害届が提出され、業務上横領罪に該当する行為を行った疑いがあっても、被疑者が逮捕されない場合もあります。
どのような場合に逮捕されない可能性が高いのか、具体的に説明します。
1.業務上の占有者による横領行為の疑いがある場合
①被害金額が10万円以下の場合
警察の調査を経た被害金額が10万円以下の場合は、通常被疑者逃亡や証拠隠滅のおそれも少ないため、逮捕されないことが多いです。
ただし、被疑者に対して窃盗・詐欺・偽造等他の犯罪行為を行っていた疑いがあるなどの事情がある場合は、在宅で捜査を継続することになります。
また、会社から貸与を受けて使用していた文房具等の備品を持ち帰ったような場合も、被害届が出されていたとしてもその事実のみを理由に逮捕される可能性は低いです。
②出張費で得たマイルやポイントを私用で使った場合
会社の経費で出張した従業員が、出張費によって得た航空会社のマイルや飲食店等のポイントを私用に使うという事例は少なくありません。
この場合、そもそも会社側に損害を与えているとはいえないため、就業規則等でマイルやポイントの私用消費を禁止していて、会社から被害届が出されていたとしても、その事実のみを理由に逮捕される可能性は低いです。
2.非業務者・非占有者による関与が疑われる場合
①同僚の横領行為を知っていながら見て見ぬふりをした場合
前述した通り、非業務者・非占有者が共犯として業務上の占有者による横領行為に加担した場合は、業務上横領罪の共犯として逮捕される可能性がありますが、共犯として逮捕する理由と必要性が認められるのは、以下の2つの要件を満たす場合のみです。
- 業務上占有者が横領行為を行っているという認識(共犯者としての故意)があること
- 横領行為に対して積極的な関与を行っていることが明らかであること
上記の要件は、特に幇助犯の場合に問題となります。
例えば、業務上占有者である同僚が会社の金銭を使い込んでいることを知っていながら、非業務者・非占有者である従業員が黙っていたような場合は、共犯者としての故意は認められます。
しかし、積極的な関与が認められるためには、その者が横領行為の実現を容易にするような行為を行ったことが必要です。
黙っていた、見て見ぬふりをしたというだけでは、積極的な関与を行ったことにはなりません。
そのため、この場合は、業務上横領罪の幇助行為の疑い自体が認められず、逮捕される可能性は低いでしょう。
②横領した金銭を用いた接待を受けていた取引先の会社社長
甲社の従業員が会社の金銭を着服し、それを取引先の乙社の社長との接待費用に充てていたという場合は、共犯者としての故意、すなわち接待費用が横領した金銭であることを知っていたとしても、業務上横領罪の幇助とは言えない可能性は低いといえるでしょう。
また、仮に故意があったとしてもその費用で接待を受けていたという事実は横領行為が行われた後のものなので、接待の前に横領行為が既遂となっています。
従って、乙社の社長が甲社の従業員による横領行為を容易にしたことにはならないので、この事実のみでは業務上横領罪の幇助行為の疑い自体が認められず、逮捕される可能性は低いです。
業務上横領罪で逮捕された場合の刑事手続の流れ
刑事訴訟法上、警察による逮捕は、以下の3つの種類があります。
- 通常逮捕(同法第199条)
- 現行犯逮捕(同法第213条)
- 緊急逮捕(同法第210条)
緊急逮捕は、死刑・無期・長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪の明確な容疑があり、急速を要する場合にのみ認められます。
業務上横領罪の場合、通常は、横領行為発覚後の被害届提出、被害届受理後の警察による捜査によって、被害総額やその他の事情を把握するという経緯を経て逮捕が行われます。
したがって、現行犯逮捕や緊急逮捕が行われることはほとんどなく、専ら通常逮捕によることになります。
また、業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役で罰金刑が定められていないため、簡易裁判所で100万円以下の罰金刑または科料の判決のみが下される略式裁判手続(同法第六編第461条以下)がとられることはありません。
1.逮捕後の捜査手続
①被疑者取調べ・送検・勾留の決定
逮捕された被疑者に対しては警察官(司法警察員、刑事訴訟法第202条)が取り調べを行い、逮捕理由とともに弁護人をつける権利(憲法第37条3項、刑事訴訟法第30条以下)を告知します。
警察は被疑者を拘束してから、留置の必要がないと判断した場合は直ちに被疑者を釈放し、必要があると認める場合は48時間以内に検察官に送致します(同法第203条1項)。
送検された場合、検察官は留置の必要があると認める場合は被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に対して勾留請求し、必要がないと判断した場合は直ちに被疑者を釈放します(同法第205条1項)。
業務上横領罪は経済犯罪であるため、逮捕の時点で可罰性につき、慎重な判断がなされています。
そのため、逮捕された被疑者に対しては勾留請求される可能性が高いです。
平成30年版犯罪白書(平成29年統計)によると、横領罪全体での逮捕率は11.4%ですが、逮捕された場合の勾留請求率は92.9%となっています。
この中での業務上横領事件の勾留請求率はさらに高いと考えられます。
被疑者が拘束された場合、検察官の勾留請求までの72時間の間は、被疑者は弁護人以外と会うこと(接見)ができません。
裁判官が勾留を認めた場合、勾留期間は勾留請求した日から10日間です(同法第208条1項)。
また、検察官が勾留延長を請求したときは、裁判官はやむをえない事情があると認める場合さらに10日間までの延長を認めます(同法第208条2項)。
したがって、勾留期間は最大で20日間です。
被疑者が勾留されずに釈放された場合は在宅で捜査が続きます。
また、被疑者を勾留するかしないかにかかわらず、被害者に対しても取り調べが行われるとともに、裁判所が検察官の請求により捜索差押令状を発行した場合は被疑者の家宅捜索・差押が行われます。(憲法第35条2項、刑事訴訟法第218条1項)
②勾留
勾留中は検察官による取り調べが行われます。
また、被疑者が経済的事情、その他の理由によって弁護人を選任することができない場合は、裁判官によって国選弁護人が選任されます(刑事訴訟法第37条の2)。
③起訴・不起訴
勾留期間中または在宅での捜査中に、検察官は被疑者の起訴・不起訴の処分を決定します。
不起訴処分(刑事訴訟法第248条)が決定された場合、捜査手続は終了し、被疑者は釈放されます。
業務上横領罪の被疑事件で起訴する場合(同法第247条)、前述した通り、罰金刑が定められていないため、地方裁判所に訴訟提起します。
平成29年の検察統計年報によると、業務上横領罪の起訴率は42.6%となっています。
④保釈請求と保釈
被疑者が業務上横領罪で起訴された場合、裁判所は被告人を勾留することができます(刑事訴訟法第60条)。
ここで、勾留された被告人またはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系親族若しくは兄弟姉妹は保釈請求をすることができます(同法第88条)。
保釈請求があった場合に行われる保釈には必要的保釈(同法第89条)と職権保釈(裁量保釈、同法第90条)があります。
必要的保釈は、罪証隠滅や、関係者に危害を加えるおそれ、住所不定等の事情がなければ保釈が認められることになります。
また、仮に上記事情があったとしても、第90条の裁量保釈が認められる可能性があります。裁量保釈の判断は、被告人の逃亡・罪証隠滅のおそれの程度や、身体拘束継続により被告人が受ける諸般の不利益の程度などを総合考慮して行われます。
業務上横領事件の場合、逃亡や罪証隠滅のおそれが少なく、示談が成立している等の事情があれば裁量保釈は認められやすくなります。
保釈が認められた場合、裁判官が犯罪の性質、情状や被告人の性格・資産等を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額の保証金を定め、被告人側が保証金を納付すれば被告人は身体拘束を解かれて、保釈の際に定められた住居に戻ることができます。
2.正式裁判の公判手続
被疑者が起訴された場合、地方裁判所の公開の法廷(憲法37条)で公判手続が行われます。
業務上横領罪の刑罰
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。量刑判断は、被害金額、横領行為の態様、その他の横領行為に関わる事情に基づいて行われます。
1.単独犯の場合
業務上占有者が単独で横領行為を行った場合、初犯で被害金額が100万円以下、同じ被害者との関係で他罪が成立していない、示談が成立している等の事情があれば執行猶予付きの懲役刑が下される可能性もあります。
被害金額が100万円を超える場合は、その他の事情次第で実刑判決となる可能性があります
2.共犯の場合
複数の業務上占有者が共謀の上、共同で横領行為を行った場合は業務上横領罪の共同正犯(刑法第60条)として起訴され、量刑判断はそれぞれの行為の内容に応じて個別に行われます。
共同正犯の場合、一般的に被害金額が大きく、犯情も重いことから、主犯者には実刑判決が下る可能性が高いです。
業務上横領罪の場合は、教唆行為が行われる、あるいは教唆犯として起訴されることは稀ですが、非業務非占有者が幇助犯として起訴された場合は、正犯者の単純横領罪の刑を減軽した刑で処断されます(同法第65条2項、第63条、第68条三号)。
また、執行猶予が付く場合が多いです。
3.刑事処分を軽くするには
可能な限り刑事処分を軽くするためには、横領行為が発覚した直後に弁護士に相談し、被害者側との示談の成立を目指すことが大切です。
示談が成立すると、逮捕や勾留を回避できる可能性があります。
また、逮捕された場合も、検察官・裁判官の心証形成が良くなり、不起訴処分・執行猶予付き判決を得られる可能性が高くなります。
特に検察官は勾留請求や起訴するか否かの判断をする上で、示談成立の有無やその内容を非常に重視するので、示談成立によるメリットは非常に大きいといえます。
まとめ
今回は、業務上横領罪で逮捕されるケースと逮捕されないケース、業務上横領罪で逮捕された場合の刑事手続の流れや刑罰などについて解説しました。
業務上横領罪で逮捕されると、多くの場合は勾留されます。
また、起訴された場合、ほとんど有罪となり、執行猶予が付されるケースもありますが、実刑判決が下されるケースも多いです。
刑事処分をできる限り軽くするためには、早い段階で弁護士に相談して、示談成立を目指すことが大切です。
私達、東京スタートアップ法律事務所は、刑事事件で逮捕された、あるいは「刑事告訴する」などと言われた等の問題を抱えているご本人やご家族の気持ちに寄り添い、ご本人の大切な未来を守るために全力でサポートさせていただきたいと考えております。
検察官や捜査機関の考え方を熟知している元検事の弁護士を中心とした刑事事件に強いプロ集団が、ご相談者様の状況やご意向を丁寧にお伺いした上で的確な弁護戦略を立て、迅速に対応致します。
秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
- プロフィール
- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務