熟年離婚の財産分与はどうなるの?退職金や年金は対象になる?請求方法や注意点を解説
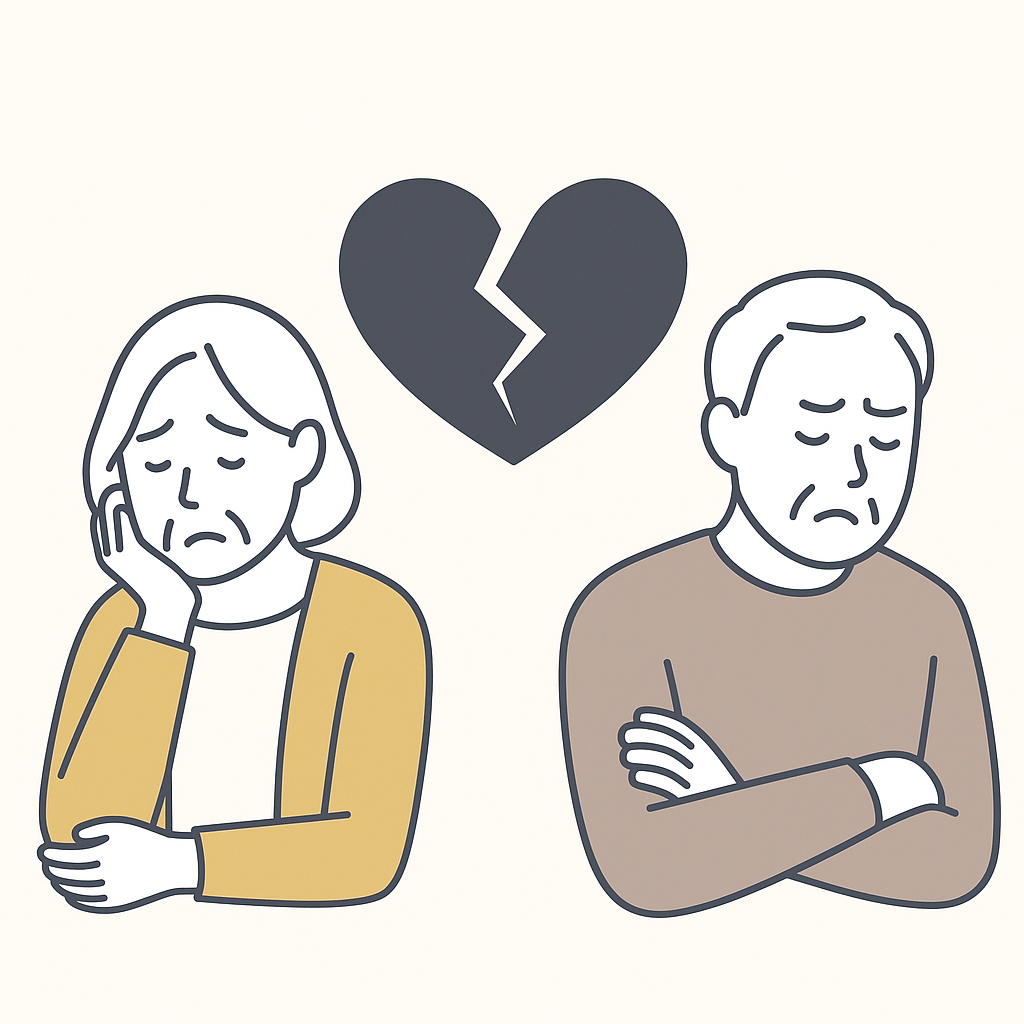
全国20拠点以上!安心の全国対応
60分3,300円(税込)
離婚とあわせて不貞慰謝料でも
お悩みの場合は無料相談となります
※
※
記事目次
長年連れ添った夫婦でも、年月とともに価値観が変わったり、日々のすれ違いが積み重なったりして、離婚を選ぶケースは珍しくなくなっています。中でも熟年離婚では、持ち家のローン残高や退職金、年金など、これからの生活を支える大切な資産が関わるため、どのように財産を分けるかは非常に大きなポイントです。誤った知識のまま進めてしまえば、老後の暮らしに深刻な影響を及ぼす恐れもあります。
この記事では、熟年離婚における財産分与の基礎知識から、分ける対象となる財産の種類、退職金や年金の扱い方、手続きの進め方、注意しておきたいポイントまでを、初めての方でもわかるように丁寧に解説します。
●監修者情報
東京都立大学法科大学院修了。埼玉弁護士会所属。離婚事件を含む家事事件、刑事事件に力を入れている。
熟年離婚した場合、財産分与はどうなる?
熟年離婚では、婚姻期間中に築いた財産を公平に分けるのが原則です。そして、熟年離婚では、夫婦共有の財産が高額となり、財産分与によって獲得できる金額が高額になるケースが多くあります。
婚姻期間ごとの財産分与の相場
下の図を見ればわかるように、婚姻期間が長ければ長いほど、財産分与の金額も増加する傾向が見られます。
財産分与の種類
財産分与には大きく3つの要素があるといわれております。
1つ目は「清算的財産分与」です。これは婚姻中に夫婦で築いた財産を精算し、公平に分けるという考え方で、一般的に最も多く適用されます。
2つ目は「扶養的財産分与」です。離婚後に当事者の一方が生活に困窮するおそれがある場合、一定期間の生活費を補う意味合いで支払われます。特に、専業主婦で収入基盤がない場合などに認められることがあります。
3つ目は「慰謝料的財産分与」です。不貞行為やDVなど、離婚原因を作り出した配偶者からもう一方の配偶者に対して、精神的苦痛を補うために慰謝料を含めて分与する形式です。ただし、慰謝料として認められる金額は相場がある程度決まっており、あらゆるケースで慰謝料的財産分与が認められるわけではありません。
熟年離婚における財産分与の割合
熟年離婚では、片方の配偶者が長い間専業主婦であるケースなどがあります。どのようにして財産分与の金額が決められるのかを説明いたします。
共働き夫婦の場合
共働き夫婦の場合も、基本的な分与割合は2分の1が目安となります。双方が収入を得ている分、財産分与の額が大きくなる可能性が高いでしょう。
ただし、夫婦の片方のみが高収入で資産形成に大きく貢献していた等の事情により調整されるケースもあります。
一方で、専業主婦(専業主夫)の場合も、家庭内での役割分担や家事労働は経済的貢献と評価されます。
収入がなくても財産分与の対象となり、基本的には2分の1を目安に受けられるのが一般的です。
熟年離婚の財産分与の対象になるもの
熟年離婚の場合、財産分与の対象は多岐に及ぶ場合がありますが、以下では代表的なものを取り上げます。
持ち家や土地
持ち家や土地は、熟年離婚における財産分与の中でも特にトラブルになりやすい資産です。不動産は現物分割が難しいため、売却して現金化し、分割する方法が一般的です。
しかし、年齢的に住む場所を失うリスクもあるため、持ち分を買い取る形で一方が住み続けるケースもあります。この場合、適正な時価評価をすることが大切です。住宅ローンが残っている場合はより複雑になりますが、熟年離婚の場合、住宅ローンについては完済していることが多いです。その場合であっても、上記のような難しさは残ります。
退職金
退職金は、婚姻期間中に積み立てられた部分が対象になります。そして、熟年離婚の場合、退職がある程度現実的なものとなっており、支給される見込みが高いものとして、財産分与の対象になる可能性が高いので、忘れずに財産分与するようにしましょう。
へそくりは財産分与の対象になる?
へそくりは婚姻期間中に形成された財産であるといえるため、共有財産に該当します。したがって、原則として財産分与の対象となります。ただし、隠し財産として発覚しないケースは多いですので、離婚するまでの間で相手の預貯金の動きやタンス預金の存在を把握することが重要です。
熟年離婚の財産分与の対象にならないもの
一般的にすべての財産が分与対象になるわけではありません。結婚前から所有していた個人資産や、婚姻期間中に相続や贈与で取得したものは「特有財産」として基本的に分与の対象外となることがあります。特に、熟年離婚の場合、相続によって資産を得ているケースもあるので、どの時点でいくらを相続によって受けとったのか、などは明確にしておくべきです。
熟年離婚における財産分与の流れ
財産分与の流れとしては、熟年離婚に限った話ではないですが、一般的に、
①共有財産の洗い出し
②財産目録の作成
③評価額の算定
④分与方法の協議
⑤合意書作成
という流れで進んでいきます。
熟年離婚の場合、それぞれの資産がどこにいくら存在するのかがはっきりしないことがあります。
また、株式や不動産についてはその評価が困難なケースもあるので、専門家に評価を依頼することもでてくるでしょう。
そして、合意に至った場合は、必ず合意書を作成し、必要に応じて公正証書化しておくと安心です。
財産分与の請求は拒否できる?
原則として、財産分与の請求を一方的に拒否することはできません。離婚後も2年以内であれば請求可能で、相手が応じない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。ただし、特有財産と認められるものまで請求することはできないので注意が必要です。
熟年離婚で財産分与を請求する際の注意点
財産分与を請求する際、いくつか注意すべきポイントがあるので、以下で紹介します。
①財産分与には時効がある
財産分与の請求には2年の時効があります。離婚成立後2年を経過すると、財産分与請求権は時効によって消滅してしまいます。そのため、できるだけ早めに協議を開始しましょう。相手が協議に応じない場合でも、期限内に調停を申し立てれば時効による請求権の消滅を防ぐことができます。
②離婚後の生計を考えておく
熟年離婚は、離婚後の生活資金をどう確保するかが大きな課題です。特に専業主婦だった場合、再就職という点で壁が高く、年金受給までに収入が途絶えるリスクがあります。そこで、財産分与のみならず、年金分割や慰謝料請求についても検討し、収入源を確保することが重要です。また、年金受給をするとしても思ったよりも年金額が低いことがあります。そのため、たとえ財産分与によって持ち家を確保できたりした場合であっても、生活費とのバランスを考慮する必要があります。老後の生活設計を見据え、必要に応じて公的年金や生活保護などの制度の活用も視野に入れ、無理のないライフプランを組み立てておきましょう。
③不法行為による離婚の場合は慰謝料を請求する
相手の不貞行為やDVなどの不法行為が原因で離婚に至った場合は、財産分与とは別に慰謝料を請求するようにしましょう。慰謝料の金額は、精神的苦痛の大きさや婚姻期間、経済状況などを総合的に考慮して算定されます。ただし、必ず認められるわけではなく、証拠が不十分だと十分な慰謝料が認められなかったり、そもそも慰謝料自体が認められないこともあります。そのため、相手方に不法行為があったことを証明する客観的な証拠を準備しておくことは、とても重要なポイントとなります。
熟年離婚の財産分与を弁護士に相談するメリット
熟年離婚の場合、財産関係が複雑なケースが多く、どのように離婚を進めていくべきか判断が難しいケースがあります。そこで、自分がどのように離婚を進めていくべきなのかを整理し、しっかりと自分の権利を主張できるように弁護士に相談した方がよいといえるでしょう。
熟年離婚の財産分与を弁護士に相談したことで解決した事例
以下では、あくまで一例ですが、熟年離婚によって解決した事例を紹介します。
事例①
共働きの60代夫婦で、へそくりの有無が争点になりました。口座履歴を調査した結果、使途不明の隠し財産が発覚。相手方が最終的にへそくりの存在を認め、最終的に調停でへそくり部分も含めて財産分与することができ、なんとか財産を確保することができました。
事例②
長年専業主婦だった50代女性が、夫名義の不動産の財産分与で争っていました。弁護士の助言で不動産鑑定を依頼し、持ち分を適正評価。最終的に自身が住み続ける形で合意し、安心して老後を過ごせる住居を確保できました。
事例③
専業主婦であった60代女性が、財産分与の額で納得できずに揉めていました。最終的に、扶養的財産分与も認めさせ、慰謝料、年金分割も合意できたため、当初受け取る予定であった金額の1.5倍の金額が財産分与によって手に入ることになりました。
熟年離婚の財産分与に関するよくある質問5つ
①Q熟年離婚の財産分与の平均額はいくら?
一般的に婚姻期間20年を超えてくる場合、金額にして数百万円から数千万円規模になることが多いです。ただし、財産の種類や住宅ローンの残債などで大きく変動します。
②Q財産分与で損をしない熟年離婚のタイミングは?
特にタイミングによって大きく損をすることは少ないですが、退職金の支給時期前後は注意が必要です。受給前に離婚したとしても、離婚時点で予定される退職金を財産分与の対象に含めるケースがあります。
③Q財産分与以外に年金分割もしたい。年金分割の手続きはいつまでに行えばいい?
年金分割の請求期限は離婚した日の翌日から2年以内です。これを過ぎると権利を失うため、しっかりと請求しておきましょう。特に、3号分割は相手の同意が不要なので、専業主婦の方は忘れずに申請しましょう。
④Q隠し財産があった場合はどうする?
財産分与の後で相手方に隠し財産が発覚した場合、時効の期間内であれば、隠し財産を財産分与するように請求できるケースもあります。ただし、証拠集めが不可欠となり、専門家なしでは難しいケースが多いです。そのため、その際は弁護士へ相談するのが安心です。
⑤Q財産分与と慰謝料は同時に請求できる?
財産分与と慰謝料は別の性質のものですので、同時に請求することが可能です。どちらもお金に関する権利ですので、同時に請求することで全体金額を相手に突き付けていくことがよいでしょう。
まとめ
熟年離婚だからといって、一般的な財産分与と大きく制度が異なるようなことはありませんが、熟年離婚だからこそ気にしておくべきポイントが存在するのは事実です。一人で進めていくことに少しでも不安があれば、弁護士に相談してみましょう。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
- プロフィール
- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務


















