子どもがいる方が離婚前後にやっておくべきことは?離婚方法やタイミングも紹介
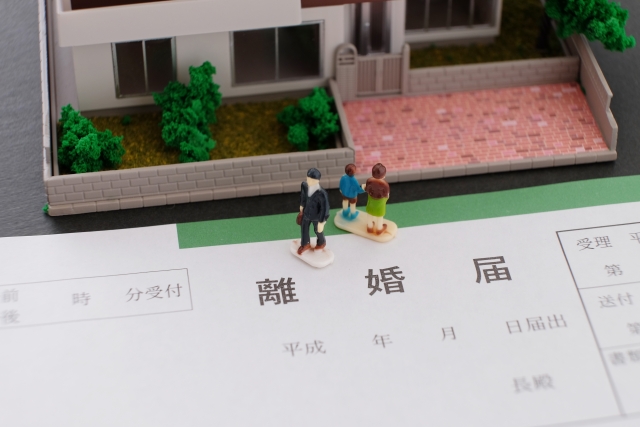
全国20拠点以上!安心の全国対応
60分3,300円(税込)
離婚とあわせて不貞慰謝料でも
お悩みの場合は無料相談となります
※
※
記事目次
お子さんがいらっしゃる中で離婚を考えると、「子どもの将来はどうなるのだろう」「親権や養育費はどう決めたらいいの?」「何から手をつければいいのか分からない」といった不安や疑問が次々と湧き上がってくるのではないでしょうか。
特に、離婚がお子さんの心に与える影響を考えると、一歩を踏み出すことにためらいを感じる方も少なくありません。
この記事では、お子さんがいらっしゃる方が離婚を決意した際に、離婚前から離婚後にかけて「やっておくべきこと」を順序立てて詳しく解説します。
また、適切な離婚のタイミングや、ひとり親家庭が利用できる支援制度についてもご紹介します。お子さんの健やかな未来を守るために、そしてご自身の新しい人生を穏やかにスタートさせるために、ぜひ最後までお読みください。
子どもがいる方が離婚前にやっておくべきこと
お子さんがいる場合の離婚は、夫婦だけの問題ではありません。
お子さんの生活環境や将来に大きな影響を与えるため、感情的に進めるのではなく、計画的に準備を進めることが極めて重要です。
離婚届を提出する前に、お子さんのために必要なことを一つひとつ着実に進めていきましょう。
1.離婚の条件を決める
離婚を決意したら、まず夫婦間で離婚に関する様々な条件を話し合う必要があります。
ここで決めた内容は、お子さんの将来やご自身の離婚後の生活の基盤となる非常に重要なものです。冷静に、そして具体的に話し合いましょう。
親権者をどちらにするか
未成年の子どもがいる場合、離婚届には必ず親権者を父母のどちらか一方に定める必要があります(単独親権)。
親権は、子どもの財産を管理する「財産管理権」と、子どもの身の回りの世話や教育を行う「身上監護権」からなります。
どちらを親権者にするかは、従前の監護状況、親の監護能力、子どもの年齢や意思などを総合的に考慮して判断されます。
単に経済力があるというだけでは決まりません。どちらが親権者となることが、子どもの健やかな成長にとって最も良い環境かを第一に考えて話し合うことが大切です。
なお現在、離婚後の共同親権を認める改正民法が成立し、公布されました。
令和7年9月時点において、改正民法は施行されておらず、令和8年5月までに施行される見込みです。
令和7年時点の現行法では、離婚後の親権者は父母のどちらか一方となります。法改正の動向によっては、今後の選択肢が変わる可能性がありますので、最新の情報にご注意ください。
養育費
養育費は、子どもが経済的に自立するまでに必要となる生活費、教育費、医療費などの費用です。
親権者とならない親であっても、「子の監護に要する費用」を分担する立場にありますから、養育費を支払う義務があります。
養育費の金額は、一般的に裁判所が公表している「養育費算定表」(出典:裁判所「養育費・婚姻費用算定表」)を基準に、夫婦双方の収入に応じて決められます。
具体的に、「いつまで」「毎月いくらを」「どのように支払うか」を明確に取り決めておくことが、将来のトラブルを防ぐために不可欠です。
面会交流
面会交流とは、親権者とならない親が子どもと定期的・継続的に会って交流することです。
離婚によって夫婦関係は解消されても、親子関係がなくなるわけではありません。子どもの健全な成長のためには、離れて暮らす親とも適切な交流を持つことが重要と考えられています。
「月に何回」「どこで」「どのように会うか」といった具体的なルールを決めておきましょう。
宿泊を伴う交流や、学校行事への参加、誕生日やクリスマスなどのイベント時の対応についても話し合っておくと、後のトラブルを避けやすくなります。
財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚時に分配することです。
預貯金、不動産、自動車、生命保険、有価証券などが対象となり、専業主婦(主夫)の貢献も考慮されることもありますが、原則として2分の1の割合で分けられます。
相手がどのような財産をどれくらい持っているか分からない場合は、預金通帳のコピーを取ったり、保険証券や不動産の権利証などを確認したりして、事前に財産を把握しておくことが重要です。
慰謝料
慰謝料は、相手の不貞行為(不倫)やDV(ドメスティック・バイオレンス)、モラハラといった有責行為によって精神的苦痛を受けた場合に請求できる金銭です。
離婚原因が性格の不一致など、どちらか一方に明確な責任がない場合は、慰謝料の請求は難しいでしょう。
慰謝料を請求する場合は、その原因となった行為を証明するための客観的な証拠(メール、写真、診断書など)が重要になります。
年金分割
年金分割は、婚姻期間中の厚生年金や共済年金の保険料納付実績を、当事者からの請求によって分割できる制度です。
これにより、婚姻期間中に専業主婦(主夫)であったり、パートタイムで働いていたりした側も、将来受け取る年金額を増やすことができます。
年金分割には、夫婦の合意によって分割割合を決める「合意分割」と、国民年金の第3号被保険者であった側が請求することで一律2分の1に分割される「3号分割」があります。
2.離婚協議書の作成
上記で話し合った離婚の条件は、必ず書面に残しておくことが重要です。
口約束だけでは、後になって「言った」「言わない」といったトラブルに発展しかねません。
この書面を「離婚協議書」と呼びます。離婚協議書には、決定した親権者、養育費の金額と支払方法、面会交流のルール、財産分与の内容などを具体的に記載します。
特に養育費など金銭の支払いについては、単なる私的な契約書である離婚協議書だけでは、支払いが滞った際に直ちに強制執行(給与や預金の差押えなど)をすることができません。
そこで、作成した離婚協議書を公証役場に持ち込み、「強制執行認諾文言付きの公正証書」として作成することをおすすめします。
これにより、万が一支払いが滞った場合に、裁判を経ずに強制執行の手続が可能となり、より確実にお子さんのための養育費を確保できます。
3.離婚後の生活に向けての準備
離婚後の生活を具体的にイメージし、経済的、物理的な準備を進めることも非常に大切です。
特に、これまで専業主婦(主夫)だった方や、収入が不安定だった方は、離婚後の生活基盤をしっかりと整える必要があります。
仕事を探す・収入を安定させる
離婚後の生活費や養育費を安定して確保するためには、定職に就き、安定した収入源を確立することが最優先です。
ハローワークやマザーズハローワークなど、国や自治体が提供する就労支援サービスを活用するのも良いでしょう。
資格取得支援制度などを利用して、スキルアップを図ることも将来の安定につながります。
離婚後の生活をシミュレーションし、どの程度の収入が必要かを把握した上で、計画的に仕事探しを進めましょう。
住まいを確保する
離婚後に住む場所を確保することも急務です。
実家に戻る、公営住宅への入居を申し込む、新たに賃貸物件を探すなど、選択肢はいくつか考えられます。
お子さんがいる場合は、保育園や学校の転園・転校も考慮しなければなりません。
学区や周辺環境、家賃などを総合的に検討し、無理のない範囲で新生活の拠点となる住まいを見つけましょう。
各種シミュレーション
離婚後の生活を具体的に数字に落とし込んでシミュレーションしてみましょう。
養育費や公的支援(後述)を含めた収入と、家賃、食費、光熱費、教育費などの支出をリストアップし、毎月の家計が成り立つかを確認します。
これにより、漠然とした経済的な不安が解消され、必要な準備がより明確になります。子どもの進学など、将来必要となる大きな出費についても計画に入れておくと安心です。
子どもがいる方が離婚後にやるべきこと
離婚届の提出は、ゴールではなく新しい生活のスタートです。
離婚後も、お子さんのために行わなければならない手続が数多くあります。忘れてしまうと不利益を被る可能性もあるため、一つひとつ確実に進めましょう。
離婚届の提出
まずは市区町村役場に「離婚届」を提出します。
協議離婚の場合は、夫婦双方と証人2名の署名・押印が必要となります。
戸籍や姓(氏)に関する手続
離婚すると、婚姻時に姓を変えた側は原則として旧姓に戻り、元の戸籍に戻ります(復氏)。
しかし、「婚氏続称届」を離婚後3か月以内に提出すれば、婚姻中の姓を名乗り続けることも可能です。
お子さんの戸籍は、何もしなければ親権者に関わらず筆頭者(多くは父親)の戸籍に残ったままです。
親権者である母親が旧姓に戻り、子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てを行い、許可を得た上で「入籍届」を役所に提出する必要があります。
健康保険・年金の手続
相手の扶養に入っていた場合、離婚後は国民健康保険に加入するか、ご自身の勤務先の社会保険に加入する手続が必要です。
また、国民年金の第3号被保険者だった方は、第1号被保険者への種別変更手続を行わなければなりません。これらの手続は、お住まいの市区町村役場で行います。
各種名義変更
運転免許証、パスポート、預貯金口座、クレジットカード、生命保険、不動産など、氏名や住所が変更になった場合は、速やかに各機関で名義変更の手続を行いましょう。
特に、児童扶養手当など各種手当の振込先となる口座の名義が旧姓のままだと、振込ができない場合があるので注意が必要です。
ひとり親家庭向けの公的支援の申請
離婚が成立し、ひとり親家庭となった場合、様々な公的支援を受けられる可能性があります。
後述する「児童扶養手当」などを申請し、離婚後の生活基盤を安定させましょう。
申請しなければ受けられないものがほとんどですので、ご自身が対象となる制度を積極的に調べることが大切です。
ひとり親への支援制度3選
離婚後の生活、特に経済面での不安は大きいものです。国や自治体は、ひとり親家庭を支えるための様々な支援制度を用意しています。ここでは代表的なものをいくつかご紹介します。
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です(出典:こども家庭庁)。
所得に応じて支給額が変動しますが、離婚後の生活を支える重要な収入源となり得ます。お住まいの市区町村役場の担当窓口で申請手続ができます。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の親と子どもが、病気やけがで医療機関にかかった際に、医療費の自己負担分の一部または全部を自治体が助成してくれる制度です。
制度の名称や助成内容は自治体によって異なりますので、お住まいの市区町村役場のウェブサイトや窓口で確認してください。
児童育成手当
これは、東京都など一部の自治体が独自に行っている制度で、ひとり親家庭などの子どもを養育している方に手当を支給するものです。
児童扶養手当とあわせて受給できる場合もあります。お住まいの自治体に同様の制度がないか、確認してみましょう。
その他の支援制度
上記以外にも、以下のような様々な支援があります。
- 自立支援教育訓練給付金:就職に有利な資格取得のための講座受講費用の一部を支援
- 高等職業訓練促進給付金等事業:看護師など専門的な資格取得のために養成機関で修業する期間の生活費を支援
- 公営住宅への優先入居
- 粗大ごみ処理手数料の減免
これらの制度は、ご自身の状況を大きく助けてくれる可能性があります。一人で抱え込まず、役所の窓口などで積極的に相談してみましょう。
子どもがいる方が離婚する方法
離婚に至る手続には、主に「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法があります。
- 協議離婚:夫婦間の話し合いで離婚に合意する方法です。離婚する夫婦の約9割がこの方法を選んでいます。当事者の合意のみで成立するため、時間や費用を最も抑えられますが、感情的な対立があると話し合いが進まないこともあります。
- 調停離婚:話し合いがまとまらない場合や、相手が話し合いに応じない場合に、家庭裁判所で調停委員を介して話し合う方法です。調停で合意に至れば、調停調書が作成され離婚が成立します。
- 裁判離婚:調停でも合意できなかった場合に、最終的に裁判所に離婚を認めてもらう方法です。法律で定められた離婚原因(不貞行為、悪意の遺棄など)が必要となり、時間も費用もかかります。
まずは夫婦での協議離婚を目指し、それが難しい場合は調停離婚を申し立てるのが一般的な流れです。
子供が自立するまで離婚を待った方がいい?
「子どものために、成人するまでは離婚を我慢すべきだろうか」と悩む方は非常に多くいらっしゃいます。
確かに、子どもへの影響を考えれば、すぐに結論を出すのは難しい問題です。
一概に「待つべき」「すぐ離婚すべき」と言えるものではなく、それぞれの家庭の状況によって判断は異なります。
冷静にメリットとデメリットを比較し、ご自身とお子さんにとって最善の道は何かを考えることが大切です。
子供が自立するまで離婚を待つメリット
離婚を先延ばしにすることには、いくつかのメリットが考えられます。
経済的な安定を維持できる
最大のメリットは、経済的な安定でしょう。
離婚すれば世帯収入は減少し、生活水準が下がる可能性があります。
離婚を待つことで、これまで通りの生活レベルを維持し、子どもの教育費や習い事などにお金をかけ続けることができます。
子どもを取り巻く環境を変えずに済む
離婚に伴う転居や転校は、子どもにとって大きなストレスとなります。
離婚を待てば、子どもは慣れ親しんだ家や学校、友人と離れることなく、思春期などの多感な時期を過ごすことができます。
両親が揃っているという安心感
形の上だけでも両親が揃っていることは、子どもに一定の安心感を与えるかもしれません。
特に幼い子どもにとっては、「お父さんとお母さんがいる」という日常が続くことの精神的なメリットは大きいと考えられます。
世間体を保つことができる
周囲に離婚の事実を知られずに済むため、親戚付き合いやご近所、子どもの学校関係などで、余計な気遣いや詮索をされずに済むという側面もあります。
子供が自立するまで離婚を待つデメリット
一方で、我慢して婚姻生活を続けることには、深刻なデメリットも存在します。
両親の不仲が子どもに悪影響を及ぼす
仮面夫婦を続けても、家庭内の冷たい空気や緊張感は子どもに伝わります。
両親が常にいがみ合っていたり、会話がなかったりする環境は、子どもの情緒的な発達に深刻な悪影響を与え、「自分のせいだ」と心を痛めてしまう可能性もあります。
親自身の精神的な消耗
愛情のない相手との生活を我慢し続けることは、親自身の精神を大きく消耗させます。
ストレスから心身の健康を損なったり、子どもに対して優しく接することができなくなったりしては、本末転倒です。
親の再出発が遅れる
年齢を重ねるほど、離婚後の就職や新しいパートナーとの出会いの機会は少なくなっていく傾向があります。
子どもの自立を待った結果、ご自身の新しい人生をスタートさせることが困難になってしまうリスクも考えなければなりません。
財産分与で不利になる可能性がある
離婚を先延ばしにしている間に、相手が夫婦の共有財産を使い込んでしまったり、隠してしまったりするリスクがあります。
いざ離婚する際に、本来受け取れるはずだった財産が減ってしまう可能性も考慮すべきです。
財産分与は別居日を基準としますので、別居期間が長期化すると、別居開始時点の財産状況について精査することが困難になる可能性があります。
また、別居開始後の相手の収入や費消は基本的に財産分与の対象外となりますが、同居を続けたまま家庭内別居の状態を維持する場合、財産の管理が難しくなるケースがあります。
問題が解決するわけではない
離婚を先延ばしにしても、夫婦間の根本的な問題が解決するわけではありません。
問題を先送りにすることで、かえって夫婦関係が悪化し、最終的により複雑な状況に陥ってしまう可能性もあります。
よくある質問
お子さんがいる方の離婚に関して、よく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 親権は母親が有利と聞きましたが、父親は親権者になれないのでしょうか?
確かに統計上は母親が親権者になるケースが多いですが、「母親だから有利」というわけではありません。
裁判所が重視するのは、「これまで主として子どもの面倒を見てきたのはどちらか(監護の継続性)」や「子どもの年齢や意思」、「今後の監護能力」などです。
そのため、例えば父親が主に育児を担ってきたようなケースでは、父親が親権者として認められることも十分にあります。詳しくは、以下の記事もご覧ください。
Q2. 10歳の子どもが「パパ(ママ)と暮らしたい」と言っています。子どもの意見はどのくらい尊重されますか?
子どもの意思は、親権者を決める上で重要な要素の一つです。
特に、おおむね10歳以上になると、その意思が尊重される傾向が強くなります。
家庭裁判所の調停や審判では、調査官が子どもから直接話を聞くこともあります。
ただし、子どもの意思だけですべてが決まるわけではなく、これまでの監護状況なども含めて総合的に判断されます。
Q3. 離婚することを、子どもに何歳くらいで、どのように伝えればいいですか?
子どもに離婚を伝えるタイミングや方法に、唯一の正解はありません。
重要なのは、子どもの年齢や発達段階に合わせて、分かりやすい言葉で伝えることです。
そして何よりも、「離婚はパパとママの問題であって、あなたのせいでは決してない」「パパとママの愛情はこれからも変わらない」というメッセージを、両親が揃って伝えることが、子どもの心のケアにつながります。
Q4. 離婚後、夫(妻)が養育費を支払ってくれません。どうすればいいですか?
A4. まずは電話や書面で支払いを督促します。
それでも支払われない場合は、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てることができます。
離婚時に養育費について公正証書を作成していれば、裁判を経ずに相手の給与や預貯金を差し押さえる「強制執行」の手続が可能です。泣き寝入りせず、法的な手続を検討しましょう。
Q5. 離婚して子どもがかわいそう、という罪悪感があります。
お子さんを想うからこそ、罪悪感を抱くのは自然なことです。
しかし、両親が不仲な姿を見せ続けることが、かえってお子さんにとって辛い環境である場合も少なくありません。
大切なのは、離婚という選択をした後、離れて暮らす親とも適切な交流を持ち、両親からの愛情を子どもが実感し続けられる環境を作ることです。
親が笑顔でいることが、子どもの幸せにもつながります。
Q6. 離婚の条件について、夫婦の話し合いがまとまりません。どうすればいいですか?
A6. 当事者同士での話し合いが感情的になり、進展しないことはよくあります。
そのような場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てることを検討しましょう。
調停委員という中立的な第三者が間に入ることで、冷静な話し合いが期待できます。
また、早い段階で弁護士に相談すれば、法的な観点から有利な条件で交渉を進めたり、相手との交渉をすべて任せたりすることができます。
まとめ
お子さんがいる中での離婚は、決断にも準備にも大きなエネルギーを要します。
しかし、お子さんの将来とご自身の新しい人生のために、乗り越えなければならない大切なプロセスです。
離婚を決意したら、まずは親権、養育費、面会交流といった重要な条件を冷静に、かつ具体的に取り決めることが何よりも重要です。
そして、その内容を「公正証書」として法的な効力を持つ形で残しておくことが、将来の安心につながります。離婚後の生活設計や行政手続、利用できる支援制度についても事前に調べておきましょう。
離婚に関する問題は、法律の専門知識が必要となる場面が多く、また感情的な対立から当事者だけでは解決が難しいケースも少なくありません。
一人で抱え込まず、ぜひ一度、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。専門家がお子さんとあなたの未来のために、最善の解決策を一緒に考えます。
あわせて読みたい記事
- 離婚時の親権獲得は弁護士に依頼するべき?弁護士をつけるメリット・デメリット、費用を解説
- 養育費とは?仕組みや相場、いつまで請求できるのかを徹底解説
- 面会交流権とは|決め方と具体的内容・注意点などについて解説
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設


















