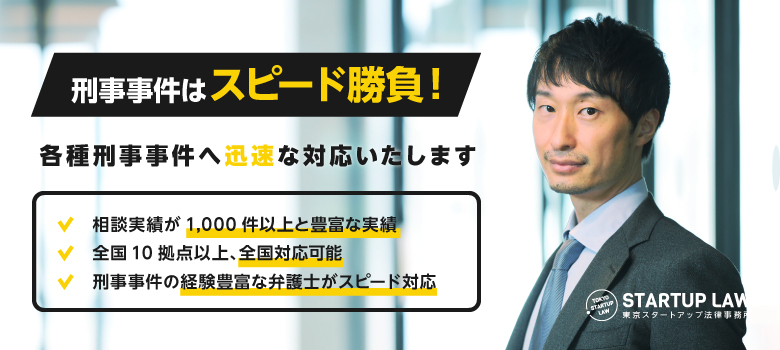在宅事件の起訴率・不起訴率は?身柄事件と流れの違いを解説

全国20拠点以上!安心の全国対応
初回相談0円
在宅事件は、留置場に拘束されて家族や親しい人との面会も制限される身柄事件と異なり、事件前と変わらずに家族と一緒に生活することも友人知人と会うことも許されているので、被疑者本人にとっての精神的ストレスは身柄事件に比べると少ないといえます。
他方、在宅事件では捜査期間に法的な定めがないため、捜査が長期化することも多く、先行きが見えないことで不安が生じやすくなります。
また、在宅事件では、略式命令請求や即決裁判手続による執行猶予付き判決が多いとはいえ、起訴されて有罪判決を下され、前科がついてしまう可能性は決して低くはありません。
今回は、在宅事件と身柄事件との違い、手続の流れ、起訴される可能性、弁護士に相談するメリットなどについて解説します。
在宅事件とは
まず、在宅事件とは、刑事事件の被疑者の身体が拘束されずに、捜査される事件をいいます。
刑事事件の被疑者というと、逮捕されて留置場に拘束され、警察や検察の取調べを受けるというイメージをお持ちの方が多いと思いますが、実際の刑事事件では、在宅事件の割合の方が多いです。
法務省が公表している検察統計の2019年のデータによると、刑事事件として受理された289,399件のうち、逮捕されなかった事件数は177,997件(61.5%)で、送検後、検察で釈放されたケースと合わせると3分の2近くが在宅事件ということでした。
在宅事件には、以下の3つのケースがあります。
- 捜査の開始から一度も身体拘束を受けない場合
- 逮捕後、あるいは送検後に身柄を釈放され、その後在宅で捜査が継続される場合
刑事事件で捜査機関が被疑者を逮捕・勾留という形で身体拘束するのは、その理由と必要性があると裁判所が認める場合です(刑事訴訟法第199条、第207条、第60条)。
逮捕・勾留の理由と必要性は、犯罪容疑が相当程度確からしいことの他、被疑者の住所不定、逃亡・罪証隠滅のおそれがあることです。
そのため、被疑者に定まった住居があり、家族と同居していて、定職に就いているような場合は、逮捕・勾留されずに在宅事件として捜査が行われることが多いです。
在宅事件と身柄事件の違い
在宅事件と身柄事件の違いは、身体が拘束されているかどうかです。
身柄事件の場合は、留置場に拘束されます。仕事や学校には行けず、家族や友人にも自由に会えません。
他方、在宅事件の場合は身体拘束を受けないため、捜査機関から取調べのために出頭を要求された時以外は、自宅で通常通りの生活を送ることができます。普段通りに、勤務先や学校に通うこともできます。
1.在宅事件は捜査の期限が不明瞭で長期化する
在宅事件の場合は、身柄事件とは違い、身体を拘束されることはありませんが、捜査の期限が不明確で、起訴するか不起訴にするかの判断まで長期化しやすいです。
身柄事件の場合は、逮捕されると、48時間以内に証拠・関係書類と共に身柄が送検されます(刑事訴訟法第203条1項)。
送検後、検察官は被疑者に弁解の機会を与えた上で24時間以内に裁判官に勾留請求するか否かを決定します(同法第205条1項)。
このように、逮捕から勾留請求までは72時間を超えることができません(同法第205条2項)。
さらに、勾留された場合、原則として10日以内に起訴しないときは、被疑者を釈放しなければならないと定められています(同法第208条1項)。
やむを得ない事由があると裁判所が認める場合は10日間を限度として延長が認められます(同法第208条2項)。
従って、身柄事件では最大23日間警察署の留置場に拘束されてしまいますが、逮捕・勾留及び勾留延長の各期間は刑事訴訟法により定められているため、捜査機関が恣意に、あるいは無期限に延長することは認められません。
しかし、在宅事件の場合、起訴・不起訴の決定までの期間に法的な定めがありません。
警察や検察は、他の事件との兼ね合いで捜査を進めるため、身柄事件と比べると捜査のペースが遅くなります。
事件によっては捜査開始から書類送検まででも1か月以上かかることもあり、送検から起訴まで半年以上かかることもあります。
2.起訴前は国選弁護人選任を依頼できない
身柄事件では、検察官の勾留請求を受けた裁判官が勾留質問を行うときに、被疑者が弁護人を選任することができる旨、及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができない時は国選弁護人の選任を請求することができる旨を告げる義務があります(刑事訴訟法207条2項)。
つまり、身柄事件の勾留後は、弁護人による弁護を受ける権利が保障されているのです。(ただし、国選弁護人選任を請求する場合は、資力申告書を提出しなければなりません。)
これに対して、在宅事件の場合は、私選弁護人を選任することはどの時点からでも可能ですが、起訴されるまでは国選弁護人による弁護を受けることはできません。
そのため、私選弁護人を選任しない限り、起訴回避するための弁護活動を行ってもらう事ができません。
在宅事件になることが多い犯罪事件
在宅事件として扱われるのは、過失犯や比較的軽微な故意犯の事件が多いです。
ここからは、具体的にどのような場合に在宅事件として扱われることが多いのかについて説明します。
1.交通事故で被害者が重症を負っていない場合
被害者が重傷を負っていない場合の交通事故では、在宅事件となることが多いです。
ただし、ひき逃げや飲酒運転による事故の場合は、加害者の行為態様からみて逃亡や罪証隠滅のおそれが大きいため、逮捕される可能性が高いです。
2.交通事故以外の過失犯事件
過失犯の場合も、在宅事件になる可能性が高いです。
一般的に逃亡や罪証隠滅のおそれが小さく、被疑者が反省していて示談交渉を進める意思がある場合が多いからです。
3.早期に示談が成立する見込みがある故意犯事件
被疑者が初犯で反省しており、被害者との示談が成立しているか、被害者側が示談交渉に応じる意向を示しており早期に示談が成立する見込みがある故意犯事件も、在宅事件となることが多いです。
例えば、普段は素行に問題がない会社員が酔った勢いで突発的に暴行事件を起こしてしまった場合や、定職のある男性が面識のない女性に対して起こしてしまった痴漢事件、衝動的に行ってしまった少額の万引き事件などは、在宅事件となる可能性が高いです。
4.公職選挙法違反事件
国会議員や地方自治体の議員等の政治家による公職選挙法違反事件等も、在宅事件となる場合が多いです。
検察統計の2019年のデータでは公職選挙法違反事件725件のうち逮捕されなかった事件が649件、警察で身柄釈放7件、送検後身柄釈放4件となり、9割以上が在宅事件として扱われています。
在宅事件の起訴率・不起訴率
在宅事件となることが多い犯罪事件は法定刑が比較的軽い罪の事件ですが、起訴されないとは限りません。
むしろ、身柄事件を含めた刑事事件全体の起訴率とあまり変わらないのです。
在宅事件だからといって罪が軽くなるわけではなく、情状が良くなるわけでもないため、注意してください。
在宅事件で起訴される可能性について、ケース別に説明します。
1.交通事故の場合
交通事故の加害者は、比較的逮捕・勾留されないことが多いですが、以下のような悪質性の高い類型の事件では起訴される可能性が高いです。
- 危険運転致死傷罪(自動車運転致死傷行為処罰法第2条)
- 無免許運転致死傷罪(同法第6条)
これらの犯罪は、法定刑が懲役刑のみであるため略式起訴が行われることはなく、正式裁判請求となります。
検察統計の2018年のデータでは、平成30年は過失運転致傷罪の総数442,740件に対して、起訴は44,476件(正式3,032件、略式41,444件)で起訴率10.0%、同致死罪の総数4,850件に対して起訴は2,263件(正式1,393件、略式870件)で起訴率46.6%となっています(致傷罪・致死罪を合計すると起訴率10.44%)。
他方、危険運転致死傷罪の総数512件に対して、起訴は342件(正式342件、略式0件)で起訴率66.8%、第6条の無免許運転致死傷罪事件は総数38件に対して起訴19件(正式19件、略式0件)で起訴率50%となっています。
(これらのデータは身柄事件・在宅事件の両方を含みます。)
2.業務上過失致死傷事件等の過失犯事件の場合
過失犯事件では在宅事件となることが多いですが、傷害結果が生じている場合に略式起訴される可能性があるほか、被害者が死亡した場合は正式裁判請求される可能性もあります。
検察統計の2019年のデータを見ると過失傷害罪(刑法第209条)・重過失傷害罪(刑法第211条後段)での起訴率は4~5%です(過失傷害罪では全て略式起訴)。
他方、業務上過失傷害罪は21.3%、業務上過失致死罪は20.1%、過失致死罪は26.5%、重過失致死罪は42.3%(検挙数26件に対して起訴11件)となっています。
3.軽微な故意犯事件等の場合
軽微な故意犯事件でも、略式起訴や正式起訴における即決裁判手の申立てが行われる可能性は低くありません。
検察統計の2019年のデータを見ると暴行罪の起訴率は23.8%で、起訴件数に対する正式起訴率は16.1%です(傷害罪の場合は、起訴率は26.5%、正式起訴率は38.9%)。
また、公職選挙法違反や性犯罪事件等では検察官の判断と市民感覚のずれが指摘されることが多く、検察官が不起訴(起訴猶予)の決定をした場合に無作為に選出された市民11人で構成される検察審査会による審査が行われることがあります(検察審査法第2条)。
2021年6月8日には、前経済産業大臣が自身の選挙区で行った有権者に対する香典代等、総額80万円の寄付行為が公職選挙法違反で略式起訴されたというニュースが報道されました。この事件は当初東京地検が不起訴(起訴猶予)処分にしたところ、東京検察審査会が起訴相当という議決を行ったのを受けて、東京地検が再捜査し、略式命令請求を行ったものです。
在宅事件の手続の流れ
在宅事件と呼ばれる事件には、以下の2つのケースがあります。
- 捜査開始から一度も身体拘束を受けない場合
- 逮捕後、あるいは送検後に身柄を釈放され、その後在宅で捜査が継続される場合
後者は、割合としては少ないですが、検察官が勾留請求をしない場合、裁判所が勾留決定をしない場合、送検後勾留されたが、勾留中に示談が成立した等で弁護人等が勾留取消請求を行い、これが認められた場合(刑事訴訟法第87条1項)などが該当します。
それぞれのケースの手続の流れについて説明します。
1.逮捕されずに書類送検される場合
①任意の取調べ
送検前は、捜査のために取調べが必要な場合に警察署から呼び出されます(刑事訴訟法第198条1項)。
②検察官送致(送検)
刑事訴訟法上の原則として、警察署が捜査した刑事事件は全て送検しなければなりません(全件送致主義:同法第246条)。
例外として、警察官が「留置の必要がないと思料するとき」(同法第203条1項)は、被疑者を釈放します。
被疑者が逮捕されている場合は証拠物・書類と共に被疑者の身柄も送検しますが(身柄送検)、逮捕されていない場合は証拠物と書類のみを送検します(書類送検)。
身柄送検では逮捕から48時間以内(同法第203条1項)という時間制限がありますが、書類送検の場合、法律上の制限時間はありません。
在宅事件では警察が必要な捜査を終えると、検察官に対して処分に関する意見を付して書類送検を行います(犯罪捜査規範第195条)。処分意見としては下記の4種類があります。
- 厳重処分(起訴を求める)
- 相当処分(起訴・不起訴の判断を検察官に委ねる)
- 寛大処分(厳しい処分を求めない・起訴猶予を求める)
- しかるべき処分(起訴できないと考える)
処分意見はあくまで参考で、検察官が警察官の意見に拘束されることはありません。
③書類送検後の取調べ
書類送検後は検察官から取調べのために管轄の検察庁への出頭を要求されます。
呼び出しに応じないと、逃亡のおそれがあるとして逮捕される可能性があります。
取調べの通知は手紙または電話で行われます。私選弁護人の弁護を受けている場合は示談書や示談交渉関係の書類等被疑者に有利な書類の提出は弁護士が行いますが、弁護人がいない場合はそれらの書類は被疑者が自ら持参します。
起訴の告知は必ず行われますが、不起訴処分の告知は被疑者の請求があったときのみ行われます(刑事訴訟法第259条)。
取調べの際に検察官から「不起訴の方向で検討しています」「何月何日までに連絡がなければ不起訴と考えて下さい」などと言われた場合、手続としては上司の決裁を得る必要があるものの、不起訴になる可能性が高いでしょう。
2.逮捕後に身柄釈放されて在宅で捜査が続く場合
①送検前釈放・送検後釈放
被疑者が逮捕された場合でも、微罪処分として送検前に釈放される場合と、送検から24時間以内に勾留請求されることなく検察官により釈放される場合があります。
割合としては少ないですが、勾留された後、勾留取消が認められて在宅事件に切り替わる例もあります。
②身柄釈放後の取調べ
身柄釈放後、検察官による起訴・不起訴の決定までは1と同様です。
3.在宅で起訴された場合
①正式裁判と即決裁判手続
在宅事件で起訴される場合は、略式起訴(略式命令請求)によるか正式裁判で即決裁判手続(刑事訴訟法第350条の16)が行われる事件が多いです。
即決裁判手続は、検察官が、事案が明白でありかつ軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれること等の事情を考慮して相当と認められる場合に、起訴と同時に書面にて申立てを行うことができます。
ただし、法定刑が死刑、無期、短期1年以上の懲役、禁錮に該当する場合、即決裁判手続はできません。
即決裁判手続には、被疑者及び弁護人の同意(同法第350条の16第4項:意見を留保している場合も含む)が必要です。
即決裁判手続では、できる限り即日(第1回公判の当日)に判決が下され、全ての場合に刑の全部の執行猶予付き判決が下されます(同法第350条の29)。
即決裁判手続により行われた判決に対しては上訴することができません(同法第403条の2第1項)。
②略式起訴(略式命令請求)
略式起訴は、被疑事実に係る犯罪の法定刑が100万円以下の罰金刑または科料刑を含む場合に、検察官が簡易裁判所に対して罰金刑または科料を科す命令を出すことを請求するものです(刑事訴訟法第461条)。
略式命令請求を受けた裁判所は100万円以下の罰金刑又は科料を言い渡します。裁判官の判断により、刑の執行猶予、没収、その他付随の処分を科すことができます(同法第461条)。
略式命令は、迅速に罰金刑・科料刑が言い渡され、身柄事件の場合には、被告人は執行猶予の有無にかかわらず、すぐに釈放されるというメリットがあります。
他方で、手続が非公開で行われることや、被疑事実を争うことなく有罪判決が下されて、正式裁判の有罪判決と同様の前科がつくというデメリットもあります。
そのため、略式命令請求を行う場合、検察官は事前に被疑者に異議がないことを書面で確認しなければなりません(刑事訴訟法第461条の2)。
略式命令が行われること、あるいは命令の内容に不服がある場合は被告人・検察官とも正式裁判の請求ができます(同法第465条)。
在宅事件で不起訴処分になるための方法
在宅事件で捜査が進んでいた場合でも、起訴されて刑事裁判にかけられる可能性がある以上、不起訴処分となるための対策をしっかりしておく必要があります。
早急に被害者と示談する
暴行事件や詐欺事件など、被害者がいる事件の場合には、早急に被害者と示談を成立させることを心がけてください。
事件の捜査が進む前に被害者との示談を成立させ、告訴や被害届を取り下げてもらうことで、起訴される可能性を、限りなく低くすることができます。捜査機関に、「被害者との示談交渉がまとまっていて、被害者の処罰感情もそこまで強いものではないのであれば、これ以上刑罰を与える必要はない」と判断してもらうためには、被害者との示談交渉を早期にまとめることが非常に重要なのです。
示談の際には、事件について真摯に謝罪をすることはもちろん、窃盗事件であれば盗んだものを返却したり、場合によっては示談金や解決金、医療費なども支払うことで、交渉をスムーズに進めることができるでしょう。
ただし、示談交渉が必ずしもうまくいくわけではなく、加害者に対して嫌悪感や恐怖感を抱いていたり、処罰感情が強いケースでは、加害者が直接被害者のもとを訪れても、全く話し合いに応じてくれないケースも少なくありません。また、そもそも被害者の連絡先を知らないような場合、被害の拡大を防ぐ観点から、警察が被害者の連絡先をすんなり教えてくれることはまずありません。
そのため、警察から被害者の情報を聞き出すことができ、冷静に示談交渉を進めることができる弁護士に相談することが、早期に示談交渉をまとめるためには非常に重要になるのです。
事件の捜査に協力する姿勢を見せる
在宅事件の場合、必要に応じて捜査機関の捜査に協力することになりますが、その際は積極的に捜査に協力することで、反省している態度や逃亡のおそれがないことを、捜査機関にアピールすることができます。
もちろん、身に覚えのない事件で逮捕されそうになっているのであれば別ですが、そうでない限り、素直に容疑を認めて捜査協力をしていれば、不起訴処分となる確率を上げることができます。
ただし、捜査に協力するとは、約束した日時に警察に赴いて、積極的に取り調べを受けることなどを指し、やってもいない犯罪行為を認めることではありません。早く捜査を終わらせたいからといって適当に返事をしていると、いつの間にか犯人に仕立て上げられてしまう可能性がないとは言えません。
もし、警察や検察から違法な取り調べを受けそうになった場合には、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
在宅事件で弁護士に相談するメリット
在宅事件だから、とくに何も対応しなくても起訴される可能性は低いだろうと考えていると、あっという間に逮捕、起訴まで進んでしまう可能性があります。
起訴されて前科がついてしまうのを避けるためにも、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
1.不起訴処分を得るために示談交渉できる
捜査開始直後に弁護士に依頼をすれば、送検前の早い段階で被害者との示談交渉を進められ、処分意見で最も軽い「しかるべき処分」の意見をつけてもらえる可能性があります。
送検に間に合わなかった場合でも、在宅捜査中に示談を成立させて示談書上で被害者に「被疑者の処罰を求めない」旨の記載をしてもらうことにより、検察官の心証を良くして不起訴処分を得られる可能性が高くなります。
示談交渉を行う際に必要な被害者の連絡先は、弁護士でなければ検察官から入手することは非常に難しいですので、比較的早い段階で弁護士に相談したほうが良いでしょう。
2.略式命令請求・即決裁判手続申立てに同意すべきか助言が得られる
起訴される場合も、在宅事件で示談が成立していれば、罰金刑・科料刑のある犯罪では略式命令請求になる可能性があります。
ただし、略式命令では前科がついてしまう等の不利益を受けることになります。
在宅中に弁護士を依頼していれば、どのような不利益を受ける可能性があるかを説明してもらい、略式命令請求に同意するべきかどうかについて適切な判断ができるようアドバイスを受けることができます。
また、即決裁判手続の申立ての際にも事前に被疑者とよく相談し、同意すべきか助言を得ることができます。
3.起訴後に勾留された場合は保釈請求を行うことができる
在宅事件でも、起訴後に勾留される場合(刑事訴訟法第60条)があります。この場合、弁護士を依頼することにより、速やかに保釈請求(同法第88条)を行うことが可能です。
まとめ
今回は、在宅事件と身柄事件との違い、手続の流れ、起訴される可能性、弁護士に相談するメリットなどについて解説しました。
在宅事件であっても弁護士のサポートを受けることにより、捜査の見通しを得やすくなるとともに、在宅捜査中に確実に示談を成立させて書類送検の際に軽い処分意見を得て不起訴処分を得る・略式起訴・即決裁判手続に進む可能性が高くなるなどのメリットがあります。
私達、東京スタートアップ法律事務所は、刑事事件の加害者となってしまった方の大切な未来を守るために全力でサポートさせていただきたいと考えております。
検察官や捜査機関の考え方を熟知している元検事の弁護士を中心とした刑事事件に強いプロ集団が、ご相談者様の状況やご意向を丁寧にお伺いした上で的確な弁護戦略を立て、迅速に対応致します。
秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。
| 【参考リンク】 検察統計年報 2019年 検察統計年報 2018年 検察統計年報 2015年 |
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設