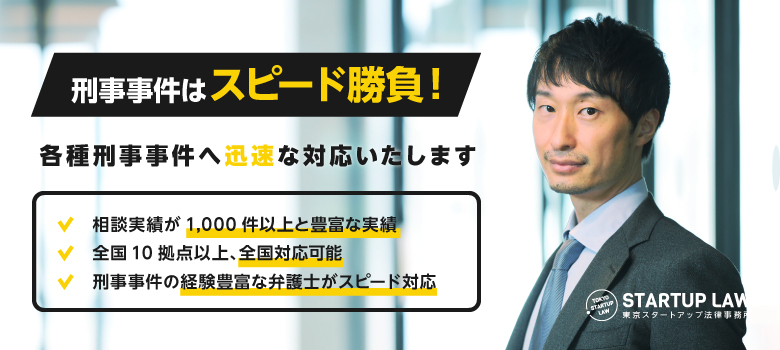恐喝罪とは|構成要件、逮捕された場合の手続の流れを解説

全国20拠点以上!安心の全国対応
初回相談0円
記事目次
ご家族が恐喝事件で逮捕された際、この先どうなってしまうのか不安だという方は多いかと思います。恐喝事件で逮捕されると、長期間勾留されて家族とも面会できない状況が続き、懲役刑の実刑判決を受ける可能性もあるため、できる限り早期に弁護士に相談することが得策です。
今回は、恐喝罪の構成要件、脅迫罪や強要罪との違い、恐喝罪で逮捕された場合の手続の流れ、弁護士に相談するメリットなどについて解説します。
恐喝罪とは
恐喝罪(刑法第249条)は刑法に定められた財産犯の一種で、第37章「詐欺及び恐喝の罪」に含まれる犯罪です。
財産犯の中でも、恐喝罪は被害者の意思に反して財物を奪取する窃盗罪や強盗罪と異なり、行為者に支配されている状態での「瑕疵ある意思」に基づいて財物を交付する、あるいは財産上の利益を移転するという点で詐欺罪と共通しています。
ただし、詐欺罪の場合は行為者の欺罔行為によって錯誤に陥った者が財物を交付する/財産上の利益を移転する(処分行為を行う)のに対して、恐喝罪は行為者に暴行・脅迫されて畏怖した者が処分行為を行うところに違いがあります。
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役です。
なお、恐喝罪の行為者と被害者が直系血族又は同居の親族である場合は、刑が免除されます(親族間の犯罪に関する特例:刑法第251条1項、同第244条)。また、直系血族・同居の親族以外の親族の関係にある場合は、告訴がなければ起訴することができません(同・親告罪:刑法第251条2項)。刑の免除とは、有罪判決の場合に刑を科さないことをいいます。
恐喝罪の構成要件
恐喝罪の構成要件は「人を恐喝して財物を交付させた」(刑法第249条1項)または「人を恐喝して財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた」(同法第249条2項)ことです。
つまり、恐喝罪が成立するには、恐喝行為と交付行為が必要となります。恐喝行為と交付行為の具体的な内容について説明します。
1.恐喝行為
恐喝罪が成立するには、暴行・脅迫により相手方が畏怖状態に陥り、その結果として財物を交付した、または利益を移転したという因果関係(因果的連関)が必要です。
恐喝罪における脅迫は、相手方の反抗を完全には抑圧しない程度のもので、財物・財産上の利益を得るために用いられるものをいいます(最高裁判決昭和24年2月8日)。また、相手方の反抗を抑圧しない程度の暴行も恐喝に含まれます。
脅迫の内容は脅迫罪(刑法第222条)と異なり、相手方またはその親族の生命・身体・名誉・事由・財産に関する害悪の告知に限定されません。また、害悪の内容そのものが犯罪行為にあたる必要はなく、例えば、相手の犯した犯罪事実を捜査機関に申告する旨告げる行為も、それにより口止め料として金銭を交付させた場合は恐喝罪が成立します(最高裁判決昭和29年4月6日)。
また、暴行や脅迫によって金銭を交付させた場合に、その目的自体が債権取立のように正当なものであったときもその暴行や脅迫が恐喝行為にあたるかという「権利行使と恐喝罪」の問題が学説上長年争われ、判例も変化してきました。
学説は、無罪説と恐喝罪説、手段のみが違法であるとして脅迫罪が成立するという中間説(脅迫罪説)に分かれています。
判例も時代と共に変化してきましたが、戦後の昭和30年10月14日の最高裁判決は、債務残額3万円に対して脅迫により6万円を交付させた事案について、行為自体は恐喝罪の構成要件に該当するとした上で、以下の3つの判断基準により違法性阻却事由の有無を判断しました。
- 正当な権利を有しているか
- 権利の範囲内で権利を行使しているか
- 手段が相当なものといえるか
上記の判断基準により、本事案では②と③を逸脱しているとして全額についての恐喝罪成立を認めました。
この判例が示した上記の判断基準が後の判例に影響を与えています。
2.交付行為
恐喝罪は、上記の暴行または脅迫を手段として、人に財物を交付させた、財産上の利益を行為者に移転させた時点で既遂となります。
なお、刑法第249条2項の「財産上の利益を得る」とは、債務を負担させたり、債務を免れたり、サービスを提供させたりすることです。
刑法第249条2項条文における「財産上不法の利益」の「不法」とは、利益を取得する手段が不法であることで、得られた利益自体が不法であることは意味していません。
「交付」行為(財産的処分行為)は、詐欺罪の場合は被害者が(騙されて錯誤に陥っている状態で)自ら交付・処分することを意味していますが、恐喝罪の場合は判例上、不作為の処分行為を認める傾向があります。例えば、飲食店で客が飲食代金の支払いを免れようと店主を脅して畏怖させてその請求を一時的に断念させて支払いを免れた場合も、交付行為が認められています。
3.恐喝罪となる脅迫の程度とは
恐喝罪が成立するには、加害者の脅迫によって被害者が従わざるをえないほどの恐怖を感じたことが要件の一つとなります。具体的にどの程度のことをすれば、被害者が恐怖を感じたとされるのでしょうか。
恐喝罪が成立するほどの恐怖があったか否かは裁判官が判断します。相手を脅した時の言葉、脅迫した時間や場所、周囲の状況、被害者の年齢や職業、地位など、さまざまな要因を加味し、一般的に恐怖を感じるといえるかを検討することになるでしょう。
例えば、大柄な男性が夜の遅い時間に人通りの少ない道で、小柄な中学生に「金を出さないと思いきり殴るぞ」などと言ったケースでは、恐喝罪が成立する可能性が高いでしょう。一方、昼間に人通りの多い場所で、小柄な女性が、体格の良い男性数人に対して「金を出さないと思いきり殴るぞ」と言ったとしても、男性たちが恐怖を感じたとは判断されず、恐喝罪は成立しないとされる可能性が高いです。
脅迫罪や強要罪との違い
恐喝罪は、客体が財産(財物又は財産上の利益)である点で脅迫罪や強要罪と異なります。恐喝罪と脅迫罪・強要罪との具体的な違いについて説明します。
1.脅迫罪(刑法第222条)との違い
恐喝罪の構成要件である「恐喝」とは、暴行または脅迫を用いて、反抗を抑圧しない程度に相手方を畏怖させることをいいます。
脅迫罪は、害を加える旨の告知そのものによって成立します。恐喝罪は、暴行または脅迫行為を手段として財物交付または財産上の利益を受ける点で脅迫罪と異なり、財産権侵害と利得が加わる分、法定刑が脅迫罪よりもかなり重く定められています(脅迫罪は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)。
また、脅迫罪の場合は被害者本人に害悪を加える旨の告知(刑法第222条1項)に加えて、被害者の親族に害を加える旨を被害者に告知する場合にも成立する(刑法第222条2項)旨が明文で規定されている反面、害を加える対象が本人と親族以外である場合は認められません。この点、恐喝罪の「脅迫」の内容は条文には記載されていないものの脅迫罪より広く、例えば、被害者の交際相手や婚約者に対して害悪を加える旨の告知も含まれます。
2.強要罪(刑法第223条)との違い
強要罪は脅迫罪と共に刑法第32章「脅迫の罪」に規定されている犯罪で、脅迫罪の構成要件と同様の脅迫または暴行を手段としている点で恐喝罪と共通しています。
ただし、強要罪の場合は暴行又は脅迫を手段として被害者に対して「義務のないことを行わせる」点が恐喝罪と異なります。「義務のないこと」が料金の支払い等、財産的処分行為に該当する場合は恐喝罪が成立します。
恐喝罪で逮捕される可能性
恐喝は、ほとんどの場合、他の人の目に触れない状況で行われます。そのため、現行犯逮捕されるケースは非常に稀で、後日、被害者が被害届を提出することで犯罪が発覚するケースが多いです。
被害者と加害者が顔見知りであるケース、被害者が被害を受けている最中に加害者をある程度確認しているケースが多く、後日でも比較的容易に逮捕に至ります。
また、以下のような場合でも逮捕される可能性はあります。
1.正当な理由があっても逮捕される可能性がある
相手が貸したお金を返さなかった、交通事故の慰謝料を支払わなかった等、正当な理由があったとしても、「支払わないと殺す」「家族を傷つける」などと脅迫してお金を交付させた場合は、恐喝罪が成立し、逮捕される可能性があります。
相手にお金を支払ってもらえず、腹を立てる気持ちもわかりますが、脅迫的な言動はしないように気を付けましょう。このような場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、あなたに代わって相手と交渉してもらえます。また、状況によっては法的手段を講じてお金を回収してもらえる可能性もあります。
2.未遂でも逮捕される可能性がある
相手からの交付行為がなくても、恐喝未遂として逮捕される可能性があります。起訴された場合は減刑される可能性はあるものの、犯罪が成立することに変わりはないため、逮捕される可能性は十分にあります。
3.告訴がなくても逮捕される可能性がある
犯罪の中には、被害者から刑事告訴されない限り逮捕や起訴されることのない「親告罪」というものがあります。親告罪であれば、警察に被害届を提出しただけでは犯人の訴追はできず、逮捕に至ることはありません。名誉棄損罪や侮辱罪、過失傷害罪などが親告罪に該当します。
しかし、恐喝罪は親告罪ではありません。被害者が警察に被害届を提出しなくても、捜査機関が犯行を知って捜査に乗り出せば逮捕される可能性があります。
恐喝罪で逮捕された場合の手続の流れ
恐喝罪は共犯者が存在するケースもあり、証拠隠滅や逃亡のおそれが小さくないことから、恐喝事件の被疑者が逮捕される可能性は高いです。2019年の検察統計年報では、同年に刑事事件として処分された恐喝事件のうち、被疑者が逮捕された事件の割合は77%でした。
通常、恐喝事件では恐喝の被害者が被害届を出すことにより捜査が開始されるので、後日逮捕状により逮捕されるケースが多いです。もっとも、被害者を脅して金銭を巻き上げようとしている現場を目撃した人の通報により現行犯逮捕される事例も、件数は多くありませんが存在します。
1.後日逮捕(通常逮捕)の場合
①送検・勾留された場合
恐喝事件の場合は、被害届の提出を受けた警察署が捜査を開始するものが多いです。証拠や目撃者の証言等から被疑者を特定した場合、被疑者に任意で警察署への出頭を求めて取調べを行います(刑事訴訟法第198条1項)。
任意の取調べでは、警察官は被疑者に対して自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならず(同法第198条2項)、被疑者は出頭を拒むことも、出頭後に退去することも認められています(同法第198条1項但書)。
任意の取調べを行ったか否かにかかわらず、恐喝容疑が固まった場合は裁判所に対して逮捕状を請求します(同法第199条)。
恐喝容疑で逮捕状により逮捕された場合、被疑者は警察署で取調べを受けて留置場に収容されます。警察官は被疑者に弁解の機会を与えた上で、留置の必要があると判断した場合、逮捕から48時間以内に関係書類・証拠物とともに被疑者を検察官に送致する手続を行います(同法第203条1項)。
留置の必要がないと判断された場合、被疑者は釈放されます(微罪処分:同法第203条1項)。
被疑者が送検された場合、検察官は被疑者に弁解の機会を与えた上で、留置の必要があると判断した場合、24時間以内に裁判所に対して勾留を請求します(同法第205条1項)。逮捕から勾留請求までの72時間以内は、被疑者の私選弁護人あるいは被疑者側の依頼を受けた当番弁護士以外は被疑者と接見することはできません。
検察官がこの24時間の間に被疑者を起訴することも認められています。この場合、勾留請求する必要はありません(同法第205条3項)。
勾留請求するか否かは、主に逃亡や罪証隠滅のおそれの有無によって判断されます。検察官が被疑者留置の必要がないと判断した場合、被疑者は釈放されます。ただし、検察官が起訴・不起訴の判断を行うまでの間、在宅事件としての取調べは継続します。
検察官が勾留請求した場合、裁判官が被疑者に対して勾留質問を行った上で、勾留状を発布します。勾留質問の際、被疑者に私選弁護人がいない場合は国選弁護人を選任することができる旨を告げます(同法第207条2項)。
勾留期間は原則10日(同法第208条1項)ですが、検察官の請求により、裁判官がやむを得ない事由があると認めるときは最大10日間延長されます(同法同条2項)。
この勾留期間中に検察官が起訴を相当と判断した場合は、当該事件を管轄する地方裁判所に起訴状を提出して公訴提起します(同法第247条・第256条)。恐喝事件の場合は罰金刑がないため略式命令請求はできず、正式裁判請求のみ行うことになります。前出の検察統計年報の2019年のデータによると、恐喝事件の起訴率は32%です。
被疑者と被害者が刑法第251条2項に該当する親族関係にある場合に被害者が告訴しなかった・告訴を取り下げていた等の不起訴事由(事件事務規程第75条2項)や、勾留中に示談が成立していた等の起訴猶予事由(事件事務規程第75条2項20号・、刑事訴訟法第248条)が存在する場合、検察官は不起訴処分を下します。
②起訴された場合
恐喝事件で起訴された場合、裁判所が被告人を勾留する必要性を判断します。刑事訴訟法第60条が定める以下の3つの事由のいずれかに該当する場合は被告人を勾留することができます。
- 被告人が定まった住所を有しない
- 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある
- 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある
勾留期間は公訴提起の日から原則2か月です。特に勾留を継続する必要がある場合は具体的な理由を附した決定で1か月ごとに更新することができます。更新は原則1回限りですが(刑事訴訟法第60条2項)、実務上は複数回にわたり更新されることも少なくありません。
逮捕以来の長期間拘束が続くことにより被告人が社会生活上著しい不利益を受けることから、勾留された場合に被告人または弁護人、配偶者、直系親族など、刑事訴訟法第88条が認めた保釈請求権者は保釈請求を行うことができます(同法第88条1項)。
恐喝事件の場合は法定刑が長期10年の懲役で短期の定めがないことから、刑事訴訟法第89条1号の保釈除外事由には該当しません。そのため、同条2号3号の定める再犯者に該当せず、4号~6号が定める罪証隠滅・被害者に危害を加えるおそれや氏名不詳・住所不定等の事由がない限り保釈が認められます(権利保釈:同法第89条)。
公訴提起の日から第1回公判までの期間については法的な定めはありませんが、通常1か月から2か月の間に第1回公判が行われます。
2.現行犯逮捕の場合
現行犯逮捕の場合は、逮捕したのが私人であるときは直ちに被疑者を司法警察職員(警察署の警察官)または司法巡査(交番の警察官)に引き渡さなければなりません(刑事訴訟法第214条・第215条)。逮捕したのが司法巡査の場合は、直ちに警察署に引き渡さなければなりません(同法第215条)。
警察署に引き渡された後の手続の流れは通常逮捕の場合と同じです。
恐喝罪で逮捕・勾留・起訴される確率
法務省が発表している令和4年版の犯罪白書によると、令和3年度に警察が認知した恐喝事件の件数は1,237件、うち検挙に至ったのは1,072件、検挙率は86.7%でした。恐喝罪を犯した場合、警察が認知さえすれば、かなり高い確率で逮捕されるといえるでしょう。
また、逮捕後の勾留請求率は97.8%であり、勾留請求が認容される確率は99%以上です。恐喝罪で逮捕されると、ほとんどの場合、勾留されることになるでしょう。
一方、起訴率は比較的低く、30%以下となっています。
被害者に対して示談や謝罪を行うなど、犯した罪にきちんと向き合って償えば、不起訴となる可能性が高く、たとえ起訴されても減刑が期待できるでしょう。
恐喝で逮捕された場合に弁護士に相談するメリット
恐喝事件で逮捕された場合、長期間勾留されて家族とも面会できない状況が続き、懲役刑の実刑判決を受ける可能性もあります。そのため、家族が恐喝容疑で逮捕された場合は可能な限り早期に弁護士に相談することが得策です。弁護士に相談することにより得られる可能性のあるメリットについて具体的に説明します。
1.勾留を免れる可能性がある
逮捕直後に家族が弁護士に相談すれば、まず警察署に接見に駆けつけてくれます。また、被害者側との示談交渉を開始することも可能です。示談交渉開始に加えて、被疑者の家族に被疑者の行動を管理する旨の誓約書を書いてもらった上で、検察官に対して勾留しないでほしい旨の意見書を提出する等、勾留回避に向けての活動を行います。
被疑者が勾留され、さらに接見禁止処分が出た場合も、弁護士だけは制限なく被疑者との接見が可能です。家族との手紙のやり取りや差し入れの受け渡し等、家族との橋渡しも弁護士が行います。
2.不起訴処分や執行猶予付き判決を得る可能性が高くなる
逮捕直後から弁護活動を行うことで、弁護士なしでは難しい示談交渉を進めることができます。勾留中に示談を成立させ、被害者に「被疑者を処罰することを求めない」旨を示談書に記載してもらうことができれば、起訴猶予を得られる可能性も高くなります。
また、起訴された場合も、初犯で公判中に示談を成立させていれば執行猶予付き判決を得られる可能性が高くなります。
まとめ
今回は、恐喝罪の構成要件、脅迫罪や強要罪との違い、恐喝罪で逮捕された場合の手続の流れ、弁護士に相談するメリットなどについて解説しました。
恐喝罪で逮捕された場合、ご家族が弁護士に相談することにより、逮捕直後から弁護活動が可能となり、早期に示談を成立させて不起訴処分や執行猶予付き判決を得られる可能性も高くなります。
私達、東京スタートアップ法律事務所は、刑事事件で逮捕されたなどの問題を抱えているご本人やご家族の気持ちに寄り添い、ご本人の大切な未来を守るために全力でサポートさせていただきたいと考えております。検察官や捜査機関の考え方を熟知している元検事の弁護士を中心とした刑事事件に強いプロ集団として、ご相談者様の状況やご意向を丁寧にお伺いした上で的確な弁護戦略を立て、迅速に対応致します。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設