離婚にかかる費用とは?弁護士に相談した場合の目安や内訳を徹底解説
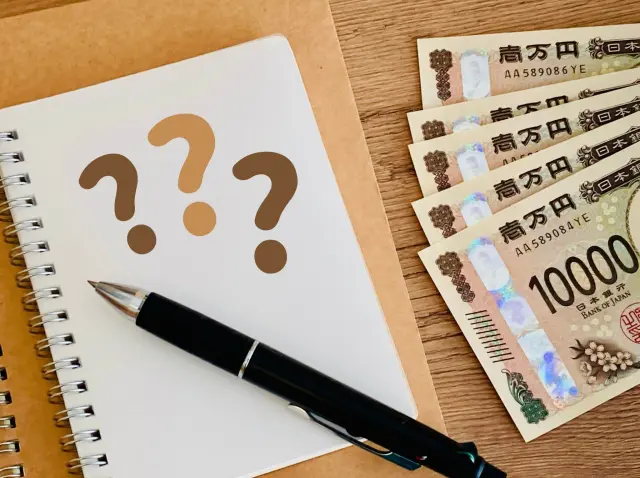
全国20拠点以上!安心の全国対応
60分3,300円(税込)
離婚とあわせて不貞慰謝料でも
お悩みの場合は無料相談となります
※
※
記事目次
離婚一つとっても、手続きにかかる費用、弁護士費用、離婚後に必要な費用、離婚の取り決めにあたって請求するべき費用など、様々なお金の問題がつきまといます。
そして、離婚に向けた話し合いを進めていく中では、感情的な対立や将来の不安を抱える方が大半であり、お金の問題は精神的な不安として重くのしかかることが多いでしょう。
そのため、離婚を考えたときには、どのくらいのお金が必要になるかを事前に知っておくことが最善といえます。
そこで、この記事では、離婚にかかる費用について解説していきます。
離婚の費用は離婚方法によって異なる?
あなたが離婚をしようと考えたとしても、単に離婚届を役所に提出するだけでなく、様々な手続きや対応が必要になることがほとんどです。
そして、離婚を進めるための方法は、夫婦間の協議で離婚を成立させる協議離婚と、調停又は裁判離婚に分かれます。
そこで、以下、①協議で離婚する場合、②調停や裁判で離婚する場合に分けて離婚に必要になる費用について解説します。
離婚にかかる費用【協議で離婚する場合】
協議離婚とは、夫婦間での話し合いによって離婚を成立させることをいいます。話し合いによって離婚を合意できた際には、離婚届を提出することで手続きが完了するため、費用がかかることはありません。
もっとも、離婚条件に関して公正証書を作成する場合には、手数料が必要になります。
離婚にかかる費用【調停や裁判で離婚する場合】
夫婦間の話し合いによって離婚することができなかった場合には、裁判所での調停や訴訟といった手続きを利用して離婚を進めることとなります。
必要な費用としては、①調停や訴訟に要する費用、②弁護士に依頼する際にかかる弁護士費用があげられます。
以下、各費用について解説します。
調停に必要な費用
離婚調停にかかる費用については、以下のとおりとなります。
申立ての種類にもよりますが、だいたい3000円~4000円程度となることが多く、離婚調停の申立てにかかる費用は、申し立てた側が支払うことになります。
なお、調停の申立手数料については、「婚姻費用」や「面会交流」など離婚に付随する事項に関する調停を別途申し立てる場合には、それぞれの調停についても各1200円分の申立手数料を納付する必要があります。
| 申立費用 | 収入印紙代 1200円 ・郵券代 約1000円(切手の金額ごとに裁判所から枚数を指定されることが多いです。そのため、事前に裁判所に必要な切手の種類と枚数を確認するようにしましょう。) ・夫婦の戸籍謄本取得費用 450円(離婚調停のほか、婚姻費用や面会交流の調停を一緒に申し立てる場合には、戸籍謄本は一通で足り、他の申立てごとに用意する必要はありません。) |
| 実費 | 課税証明書などの必要書類の取得費用 各資料による ・裁判所に出廷する際の交通費 ・調停調書の交付手数料 約1000円 |
各調停の申立書については、裁判所のホームページでダウンロードすることができます。
弁護士に依頼した場合に発生する弁護士費用について、以下で解説します。
裁判に必要な費用
離婚裁判にかかる費用については、以下のとおりとなります。
費用の内訳については、概ね離婚調停を同じですが、財産分与や慰謝料等を請求する場合には、請求内容に応じて金額が異なることになります。
| 申立費用 | 収入印紙代 離婚のみ 1万3000円 財産分与を請求する場合 追加で1200円 年金分割を行う場合 追加で1200円 慰謝料を請求する場合 離婚請求と比較して印紙代が高い方の金額 養育費を請求する場合 追加で子供1人につき1200円 ・郵券代 5000円~6000円程度 ・夫婦の戸籍謄本取得費用 450円 |
| 実費 | 課税証明書などの必要書類の取得費用 各資料による ・裁判所に出廷する際の交通費 ・証人等が必要になった際の日当 |
弁護士に支払う費用
離婚調停や離婚訴訟にあたって弁護士に依頼する場合には、別途弁護士費用も発生することとなります。
費用の内訳としては、大きく①法律相談料、②着手金、③報酬金に分かれます。
弁護士費用に関しては、依頼した内容や依頼した弁護士事務所によっても金額が異なりますが、相場に関しては次のようになります。
※市民のための弁護士報酬の目安(日本弁護士連合会)参照
| 法律相談料 | 初回1時間無料または1時間1万円程度 |
| 着手金 | 20万円から50万円程度 |
| 報酬金 | 20万円から100万円程度 |
| 日当 | 無料~5万円程度 |
①法律相談料
法律相談料については、30分5000円~1時間1万円程度となっている事務所が多く、中には初回の法律相談を1時間無料としている事務所もあります。
②着手金
着手金とは、事件を弁護士に依頼する際に発生する費用をいいます。
固定で●●万円とされている場合が多いですが、申立内容や事案の難易度によって追加の着手金を設定している事務所も多いです。
③報酬金
報酬金の目安としては上記のとおり幅が広いことが分かりますが、これは、固定の報酬金に加えて、成功報酬を設定することが多いことによります。
成功報酬に関しては、財産分与や慰謝料などの金額が変動するような請求が認められた場合に、獲得できた経済的利益に応じた割合による金額が定められることが多く、親権の獲得など結果が明確な事項に関しては、一定金額を成功報酬として設定することが多いです。
④日当
弁護士が裁判所に出廷する際に、必要な時間に応じて日当が発生することもあります。
日当は、1時間あたり1万円程度に設定している事務所が多いです。
なお、遠方の裁判所への出廷が必要になった際には、日当とは別に交通費や宿泊費が発生することがあります。
離婚方法が異なる場合でも共通して必要な費用
離婚にかかる費用といっても、離婚を進めるための手続き費用だけではありません。
離婚にあたっては、別居に際して多額の費用がかかることが多いです。
転居に要する費用ついては、初期費用、引っ越し業者の要する費用、生活家電や家具の購入費用などが考えられます。これらについては、数十万円から100万円程度を要することが多く、決して安い出費ではありません。
そのため、転居に伴う費用や当面の生活費について事前に検討しておく必要があります。
離婚の費用以外に検討しておくべきお金に関すること
離婚の手続きに要する費用や弁護士費用以外にも、離婚手続き中や離婚後に得るお金や支払うべきお金を検討しておく必要があります。
そこで、以下離婚に伴って検討しておくべきお金について解説します。
別居中の生活費(婚姻費用)
婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を維持するために必要な費用をいいますが、離婚を前提として別居する場合にも、原則として婚姻費用を支払わなければなりません。
婚姻費用については、基本的に収入が高い方の配偶者が、収入が低い方の配偶者に支払うこととなります。
婚姻費用の具体的な金額は、家庭裁判所が公表している「婚姻費用算定表:に基づいて算定されることが一般的で、夫婦双方の収入や子供の年齢・数といった要素をもとに算定されることとなります。
なお、婚姻費用には、子供の養育に必要な費用も含まれることとなります。
財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた共有財産を、離婚時に分け合う制度をいいます。
財産分与をせずに離婚することもできますが、その場合には離婚後に財産分与を巡って揉めることも多いため、あらかじめ対象財産を調査してから離婚を検討すると良いでしょう。
対象財産としては、婚姻期間中に購入した家や土地といった不動産、預貯金、株式、解約返戻金が生じる保険、退職金といったものがあげられます。
実際に離婚に伴って財産分与を行う場合には、上記財産に関する資料をお互いに開示して協議を進めることとなります。
養育費
養育費とは、子供を育てない方親が、子供を育てる方親に対して支払う、子育てのための費用をいいます。
離婚時に養育費の取り決めをしておかないと、離婚後に争いが生じることも多いため、事前に取り決めをしておいた方が良いといえます。実際に、離婚後に養育費を支払ってもらえていない母子家庭が半数以上に上るとも言われています。
養育費の算定にあたっては、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」に基づいて算出されることが一般的で、算定にあたっては、夫婦双方の収入、子供の年齢・人数をいった要素が考慮されます。
また、養育費の支払終期としては、多くの場合子供が20歳になるまでとし、大学や専門学校などに在籍している場合には延長するといった取り決めになることが多いです。
離婚慰謝料
離婚慰謝料とは、離婚によって生じた精神的苦痛を慰藉するために支払う必要がある損害賠償金をいい、離婚の原因を作った配偶者が他方の配偶者に支払うこととなります。
離婚に伴って慰謝料を請求できるケースとしては、主に以下のものがあげられます。
・DVやモラルハラスメント
・不貞行為
・セックスレスなど
離婚慰謝料の相場としては、50~300万円程度となりますが、離婚原因の悪質性によってはそれ以上の金額になることもあります。金額を決めるにあたっては、婚姻期間、子供の年齢・人数、夫婦の収入、離婚原因の悪質性といった要素が考慮されることとなります。
離婚慰謝料の請求を検討している方は、事前に弁護士に相談してみることをおすすめします。
年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が納付した厚生年金の「年金保険料」を離婚時に分け合う制度をいいます。
年金分割は離婚時に自動的に行われるものではなく、離婚の際に年金分割を行うことを合意してその割合を決定した上で、年金分割の手続きを行う必要があります。
年金分割の請求にあたっては、原則として離婚した日の翌日から起算して2年以内という期限が定められていることから、できるだけ離婚時までに分割の合意を行い、必要書類を用意しておくことが望ましいといえます。
なお、離婚した日の翌日から2年を超える前に、分割割合を定める調停または審判を申立てることで、その結果が出た日の翌日から6か月間は年金事務所に年金分割を請求することができます。
離婚には費用がかかる!離婚後の生活に不安がある場合のポイント
離婚後には引越しや当面の生活費など費用が多くかかる場合があることは、すでに解説した通りです。
実際に離婚後にかかる費用を見積もり、自立した生活が困難な場合には、国や地方自治体等の公的支援を検討しましょう。
離婚の費用に関するよくある質問
質問①離婚調停は弁護士なしでも問題ない?
離婚調停にあたって、夫婦双方が弁護士に依頼しない夫婦の割合は約43.3%となっており、約半数は弁護士に依頼していないのが現状です。
たしかに、弁護士に依頼せずに自ら調停に臨むことで、費用が最低限で済むというメリットがあります。
しかし、財産分与や慰謝料といった何らかの金銭請求をする場合には、専門的な知識を要することが多く、弁護士をつけることでより有利な条件で離婚を成立させることができ、最終的には経済的にプラスになることも多々あります。
そのため、離婚調停を申立てる前に、弁護士に相談した上で、弁護士に依頼せずに離婚調停を申立てるメリットとデメリットを検討することが最善です。
質問②弁護士に依頼したいけどお金がない場合はどうすればいい?
弁護士費用の支払いが難しい場合には、「法テラス」を利用することを検討しましょう。
法テラスとは、国が設置した法的サービスの提供を行う機関で、弁護士に依頼するための金銭的余裕が無い方であっても、離婚調停や離婚訴訟にかかる弁護士費用を立て替えてもらうことができます。
法テラスを利用する際には、一定の資力要件が必要になりますので、法テラスに確認してみましょう。
質問③弁護士に依頼するタイミングはいつ頃がいいのでしょうか
弁護士を入れるべきタイミングが明確に定められているわけではありませんが、当事者間で離婚協議を進めることに不安を感じたり、話し合いが進まないといた事情がある場合には、早期に弁護士に依頼すると良いでしょう。
弁護士という第三者が話し合いに入ることで感情的にならずに話し合いを進めることが期待でき、専門的な知識を駆使してより有利に離婚を進めやすいといえます。
まずは、不安を感じたら弁護士に相談してみましょう。
まとめ
今回は、離婚にかかるお金について解説しました。
これから離婚を進めていこうとしている方にとっては、離婚それ自体だけでなく、お金の問題も重い負担となることが多いことがお分かりいただけたと思います。
そのため、実際にかかる費用についてはあらかじめ検討することが重要です。
離婚にかかるお金の問題は、離婚の手続きや離婚条件とも不可分な問題となりますので、お悩みの方は、お早めに弁護士に相談してみることをおすすめします。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設


















