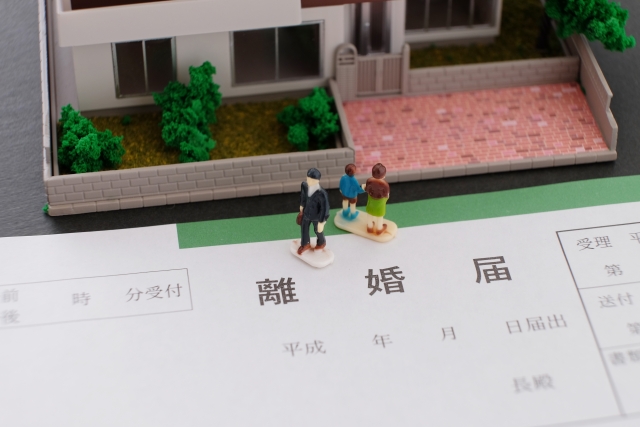風営法違反とは?刑事事件の罪状と逮捕の可能性を弁護士が徹底解説!

全国20拠点以上!安心の全国対応
初回相談0円
記事目次
今回は、風営法違反について解説します。
風営法に違反すると、違反内容に応じて、懲役刑や罰金といった刑事罰、営業停止や許可取り消しといった行政処分が科される可能性があります。
一度違反が発覚すれば、店舗の信用失墜や営業継続の困難だけでなく、経営者が従業員個人にも大きな法的リスクが及びます。
そのため、風営法の規制内容を正しく理解することが大切です。
風営法とは
風営法の正式名称は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。
この法律の目的は、風俗営業や性風俗関連特殊営業などの業務の適正化を図ることで、善良な風俗の保持および青少年の健全育成、さらに公共の安全と平穏を確保することにあります。
規制対象には、キャバクラやホストクラブ、パチンコ店、ゲームセンター、深夜営業のバー・クラブなどが含まれ、営業時間や立地、営業方法などについて厳格な規制が設けられています。
風営法が規制する4つの営業形態
風営法は、主に「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」「深夜酒類提供飲食店営業」「特定遊興飲食店営業」の4つを対象にしています。
「風俗営業」とは、キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターなど、接待を伴う飲食や遊戯を提供する営業形態を指します。
公安委員会の許可が必要で、営業時間や営業場所に制限があります。
「性風俗関連特殊営業」は、ソープランドやアダルトビデオ試写室等、性的サービスを提供する営業を指します。届出制であり、より厳格な規制が課されています。
「深夜酒類提供飲食店営業」は、バーや居酒屋など、午前0時以降に酒類を提供して営業する飲食店をさします。警察署への届出が義務付けられています。
「特定遊興飲食店営業」は、クラブやダンスホールなど、深夜にダンスや演奏等の遊興を伴って酒類を提供する店舗を指します。
風俗営業には含まれませんが、公安委員会の許可が必要で、設備や管理体制に厳しい基準が定められています。
風俗営業と性風俗関連特殊営業の違い
「風俗営業」と「性風俗関連特殊営業」とは、その性質・目的に明確な違いがあります。
「風俗営業」とは、遊興や接待を提供する営業です。「性風俗関連特殊営業」とは違い、性的サービスを提供するわけではなく、飲食や遊戯を通じて客に娯楽を提供する形態です。
営業するには、公安委員会の許可を得ることが義務付けられています。
一方、「性風俗関連特殊営業」は、直接または間接的に性的サービスを提供する営業を指します。営業するには、公安委員会への届出が必要とされています。
飲食店経営者が知っておくべき規制内容
一般の飲食店であっても、一定の条件を満たすと風営法の規制対象となります。
そのため、飲食店経営者の方は、具体的な規制対象や内容等について、きちんと把握しておくことが大切です。
規制対象で特に問題となるのは、「接待行為」「深夜営業」です。
「接待行為」とは、店員が客の隣に座ったり、飲食をともにしたりして、歓楽的雰囲気を盛り上げる行為を指します。たとえ居酒屋やレストランであっても、接待が行われると風俗営業に該当し、公安委員会の許可が必要となりますので、注意が必要です。
「深夜営業」に関しては、午前0時以降に酒類を提供して営業を続ける場合、「深夜酒類提供飲食店営業」として警察署への届出が義務付けられています。
もしこの届出を行っていないまま深夜営業を継続してしまうと、風営法違反となり、行政処分や罰則の対象になります。なお、この届出業態では、接待行為は一切禁止されているため、行った場合は風俗営業への無許可営業とみなされ、より重い処分を受ける可能性があります。
無許可営業の罪
風営法における無許可営業とは、風俗営業や特定遊興飲食店営業等、公安委員会の許可が必要な業種を許可なく営むことをいいます。
無許可営業は、風営法に違反する違法行為であり、営業停止や罰金、懲役刑などの厳しい刑事罰の対象となります。社会的影響も大きく、警察による摘発の対象となりやすいため、厳重な注意が必要です。
許可が必要な営業とは?業種別の具体例
繰り返しですが、公安委員会の許可が必要な営業は、風営法上の「風俗営業」「特定遊興飲食店営業」に該当する業種です。具体的には、以下のように定められています。
「風俗営業(風営法第2条1項)」
・第1号 キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
・第2号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより測った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
・第3号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
・第4号 まあじゃん屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業
・第5号 スロットマシン、ゲーム機その他の遊戯施設で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において、当該遊戯施設により客に遊戯をさせる営業(前号に該当する営業を除く)
「特定遊興飲食店営業(風営法第2条第11項)」
深夜0時以降に客に遊興をさせ、かつ酒類・飲食を提供する業種
例)ナイトクラブ、ディスコ、ダンスバー
無許可営業が発覚するケースとその調査方法
風営法に基づく無許可営業が発覚する典型的なケースとしては、一般市民や近隣住民からの通報が挙げられます。騒音や不審な出入り、未成年者の立ち入りなどが契機となり、警察に情報提供がなされることがあります。また元従業員やトラブルになった客等からの内部告発も少なくありません。
警察は、こうした通報を受けると「立入調査(風営法第27条)」を実施します。立入調査では、営業実態や接待行為の有無、営業時間、設備の状況などを確認し、必要に応じて従業員や客への聞き取りも行うようです。おとり捜査を行う場合もあり、警察官という身分を秘して密かに調査がすすむこともあります。特に、深夜に接待を伴う営業を行っているバーやラウンジは、形式上「一般飲食店」として届出されていても、実質は風俗営業に該当する場合が多く、監視対象とされやすいと思われます。
客引き行為はなぜ違法になるのか?
風営法第22条は、風俗営業者およびその従業員に対し、客引き行為を禁止しています。この規定では、道路や公園、駅前など公共の場所において、通行人に対し呼びかけたり、つきまとったりして店舗への誘引を図る行為が禁止されています。また、他人に客引きを委託することも禁止されています。
この規制の目的は、公共の秩序と通行の安全を守るとともに、迷惑行為や違法な営業につながるリスクを未然に防ぐためです。特に繁華街などでは、過度な客引きがトラブルや犯罪の温床となることがあり、風俗営業に対する社会的な不安を高める原因にもなります。
そのため、風営法では客引きを厳しく規制し、違反した場合には処罰の対象となります。
風営法違反の罰則と処分
次に、風営法違反の罰則と処分について、解説します。
風営法違反に対しては、刑事罰と行政処分の両面からの制裁が科されます。
刑事罰には、無許可営業や客引き行為に対する懲役・罰金等があります。
行政処分としては、営業停止命令、許可取り消し処分、指示処分等があり、違反の内容や頻度に応じて段階的に措置されます。営業の継続に重大な影響を及ぼすため、法令遵守が重要です。
風営法違反で科される罰金額の相場
主な違反類型別の罰金相場を見ていきましょう。
まず、最も重大な違反とされている無許可営業については、法改正が行われ(令和7年6月28日より施行)、風営法第49条1号により、個人に対しては「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、または併科」、法人に対しては「3億円以下の罰金」が科されると定められました。改正前と比べると、大幅な引き上げとなりました。改正前では、50万~150万円程度の罰金が科されることが多い印象ですが、今回の改正により相場も引き上げられると思われます。
次に、他人名義で営業するいわゆる名義貸し(名義使用営業)についてです。
無許可営業同様、法改正により厳罰化され、「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、または併科」となりました。相場としては、30~100万円前後ですが、こちらも改正により引きあがるでしょう。
なお、上記はあくまで相場であり、最終的には、違反内容や悪質性、前科の有無等の個々の事情を踏まえ、金額が決まります。営業の規模や悪質性によっては、上限近い金額になることもあります。
業種別・違反形態別の罰則一覧
風俗営業と性風俗関連特殊営業に関する主な違反別の罰則を、以下整理しました。
(テーブル)
1年以下の懲役または100万円以下の罰金、または併科
経営者と従業員、それぞれの責任範囲
風営法において、経営者(営業主)と従業員の法的責任は明確に区分されています。
特に経営者は、営業許可の取得から施設・従業員の管理、法令の遵守体制の構築など、店舗運営全体に対する包括的な責任を負います。たとえ自ら違法行為に手を染めていなくても、無許可営業や名義貸し、営業時間外営業、接待の黙認などがあれば、管理責任として刑事・行政の両面での処分対象となります。
一方、従業員も単に「指示されたから」という理由で免責されるわけではありません。
接待禁止の業態で接客を行ったり、客引き行為をしたりした場合、自身の行為として直接の刑事責任を負います。
このように経営者は全体管理の責任を、従業員は自己の行為に対する責任を負うという点で異なります。
逮捕後の流れ
実際、風営法違反で逮捕されてしまった場合の流れについてみていきましょう。
風営法違反で逮捕された場合、逮捕後、警察署で取調べが行われ、送検(検察への送致)されます。その後検察官が必要と判断すれば、裁判所に勾留請求を行い、裁判所が認めれば勾留されます。そして、勾留中に検察官が起訴・不起訴を決定します。
風営法違反で逮捕されるケース
風営法違反には、行政処分や軽微な罰金にとどまるものもあれば、逮捕されるケースもあります。どの場合に逮捕されるのかはケースバイケースですので一概にはいえず、違反の態様や悪質性、継続性、営業の規模、公共の安全への影響などによって判断されます。
逮捕から釈放までの期間等
先ほど、逮捕後の流れを簡潔に説明しましたが、もう少し具体的にみていきます。
逮捕されると、警察署で取調べが行われます。逮捕されると、警察署の留置場に拘束され、外部との交通が遮断されます。携帯は使えませんし、勾留までは家族との面会も出来ません。
逮捕後48時間以内に、検察庁に送致され、その後検察官は24時間以内に、勾留請求の可否を判断します。検察官からの勾留請求を裁判所が認めると、最大20日間、勾留されます。
そして、この勾留期間中に、検察官は起訴・不起訴の判断をします。
このように勾留されると、逮捕から数えると最大23日間の身体拘束が続きます。
他方で、検察官が勾留請求をしない、もしくは裁判所が勾留を認めない場合は、釈放されます。また勾留をされても検察官が不起訴の決定をすれば、釈放されます。
逮捕されてしまっても早期の釈放に向けた活動を開始するべく、できる限り早く弁護士に相談しましょう。
起訴・不起訴の分かれ目となる要素
風営法違反で摘発された場合、起訴されるか否かは、違反の内容や悪質性、本人の反省状況、再犯のおそれ等により大きく異なります。
不起訴(起訴猶予処分)が得られるのは、違反が軽微であること、初犯であること、また本人が十分に反省し、再発防止の体制が整っているといえる場合です。
他方、起訴される可能性が高いのは、常習性があるなどの反復継続性や計画性のある違反の場合です。さらに、過去に同様の違反歴があり、警察の指導に従わなかった、組織的な関与が疑われる場合には、公益性の観点から厳正に起訴される傾向が強くなるでしょう。
まとめ
今回は風営法違反について解説しました。
風営法は、風俗営業や性風俗関連特殊営業等の業種に対して、公共の安全等を目的に規制を設けています。違反すると刑事罰や行政処分の対象となり、経営者・従業員いずれにも法的責任が及ぶ可能性があります。経営者は当然のことながら、店舗運営に携わるすべての人が、風営法の内容を正しく理解し、適切な営業管理を行うことが重要です。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設