うつ病を理由に離婚できる?慰謝料、親権、養育費についても解説
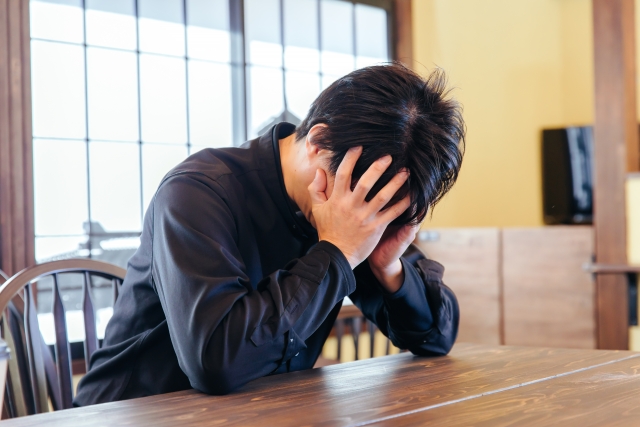
全国20拠点以上!安心の全国対応
60分3,300円(税込)
離婚とあわせて不貞慰謝料でも
お悩みの場合は無料相談となります
※
※
記事目次
配偶者がうつ病にかかってしまったとき、離婚を考える方も多いのではないでしょうか。
うつ病の配偶者と長年寄り添っていくことには大きな負担を伴うことが多く、離婚を考えてしまうのはやむをえないでしょう。
今回は、うつ病の配偶者との離婚にあたって気をつけるべきポイントや離婚の進め方について解説します。
離婚できる条件とは
離婚を決意した場合、夫婦双方の合意があればどのような離婚原因であろうと離婚することができます。
しかし、離婚について合意できなければ、離婚裁判により離婚を成立させることになります。
離婚裁判では、法律上定められた離婚原因がなければ、離婚が認められません。
それでは、裁判で離婚が認められる離婚原因にはどのようなものがあるのでしょうか。
民法770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
⑴ 配偶者に不貞な行為があったとき。
⑵ 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
⑶ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
⑷ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
このように、裁判で離婚が成立するための離婚原因は、相当限定されていることが分かります。
うつ病を理由に離婚できるケース
それでは、配偶者がうつ病に罹っていることで、離婚が認められるのでしょうか。
うつ病を理由に離婚できるかについて具体的に解説していきます。
回復し難い精神病(改正前民法770条1項4号)
離婚原因を定める民法770条には、「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」という離婚事由が規定されていました。
ここでいう「回復しがたい精神病」とは、統合失調症や双極性障害(躁うつ病)などのうち、その程度が強度であるものが該当しやすい傾向にありました。
他方で、アルコール依存症、薬物依存症、軽度のうつ病などの症状では、「回復しがたい精神病」とは認定されづらい傾向にありました。
もっとも、裁判上では、単に回復しがたい精神病であることのみをもって離婚が認められるのではなく、これまでの看病の状況や具体的方途についても考慮した上で、離婚を認めるかどうかの判断がされています。
具体的には、①従前から精神病に罹った配偶者のために協力して婚姻関係維持のために尽くしてきたか、②離婚後に生活費等を支払う、配偶者に代わる保護者を探すなどの生活保障を確保したか、といった要件が必要となっていました。
これらの要件が不十分であると、たとえ回復しがたい精神病に罹っていたとしても、裁判所は離婚を認めない可能性がありました。
この規定は、配偶者が回復しがたい精神病に罹っていることにより、長期間の看病や援助を行うことが困難である状況にある他方配偶者に対応するために設けられていました。
しかし、近年の医療技術の発達により、うつ病などの精神疾患も治療により回復が見込まれることも多く、回復の見込みがない精神病に罹っていると判断できないケースが増えています。
また、精神病に罹っている配偶者との離婚を容易に認めることで、差別を助長するとの批判も多いです。
そのため、従来は、回復しがたい精神病に罹っていることが離婚原因にあたるかどうかは、改正前民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として判断されることが多かったのが実情です。
そのため、令和6年に民法が改正され、改正前民法770条1項4号に規定されていた「回復しがたい精神病」という離婚原因は削除されることとなり、今後は、うつ病などの精神疾患が離婚原因になるかどうかは「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」という要件の中で判断されることになります。
その他婚姻を継続し難い重大な事由に該当する
改正後の民法770条1項4号では、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」が離婚事由として定められています。
条文だけを見ると、要件が抽象的でどのような場合に該当するのかわかりづらいと思いますが、具体的には、婚姻生活を回復できる見込みが無く、今後婚姻関係を継続し難いといえる状態にあることが必要です。
そして、うつ病を理由に離婚できるかの判断にあたっては、うつ病の程度に加え、暴力や暴言等の婚姻生活を破綻させる行動の有無・程度、別居期間、子供の有無、今後の生活環境等の夫婦に関わる様々な事情を考慮することになります。
暴力や暴言もあいまって夫婦関係が破綻したケース
昭和63年高裁判決では、精神疾患に罹った配偶者に対する離婚請求が認められました。
この事案では、配偶者が躁うつ病と診断され、投薬治療を行うことで回復すると見込まれていたところ、その症状が良くなる気配が無く、躁うつ病を理由に入退院を繰り返しました。
また、同配偶者は、その頃から、躁うつ病に起因して暴力を繰り返すようになりました。
この事案では、長年、配偶者が躁うつ病に罹り再三にわたって入退院を繰り返していたものの、裁判当時は既に退院しており、その病状もかなり回復しているとして、改正前民法770条1項4号の回復し難い精神病にはあたらないと判断しました。
しかし、躁うつ病に起因して幾度となく暴力を繰り返し、それにより他方配偶者が離婚を決意したこと、子も含め精神病に罹った配偶者の療養看護に消極的な態度を示していたことなどを考慮し、夫婦関係はもはや破綻しており、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚を認めました。
この事案では、うつ病の病状だけでなく、それに起因した度重なる暴力も大きな要素として考慮されていることが分かります。
精神疾患に加え、暴力により夫婦関係が破綻したケース
昭和45年の最高裁判決では、精神疾患を患っている配偶者との離婚にあたって、うつ病の配偶者の実家に資産があり、自身の生活に余裕がないにもかかわらず配偶者の治療費を長年支払い続け、離婚した後も援助を続けることを申し出ていたこと、子供を自身が引き取るとしたことなどが考慮され、離婚請求が認められました。
この判決では、うつ病の配偶者の今後の療養や生活等について具体的方途を講じたことが有利に考慮されていることが分かります。
この事案は旧民法770条1項4号が削除される前のものですが、「婚姻を継続し難い重大な事由」による離婚請求の場合も同様に適用される考え方になるものと思われます。
うつ病の配偶者と離婚を考えた方がいいケースとは
配偶者がうつ病になってしまったとしても、本当に離婚して良いのか迷うことも多いと思います。
しかし、離婚のタイミングを逃すことで、かえって取り返しがつかない状況に陥ってしまうかもしれません。
そこで、配偶者がうつ病に罹った場合に離婚を考えた方がいいケースを解説します。
子供に悪影響が生じている場合
親がうつ病に罹っていることにより、子供にも少なくない影響が生じます。
うつ病に限られるものではありませんが、親の様子や夫婦の不仲といった異変に子供は容易に気づくものです。
そのような場合には、子供が親に甘えたり自分の感情をうまく表現できずにストレスを抱え込んでしまうことも多いです。
それに伴い、子供が親のうつ病を受け入れることができずに、親を強く拒絶するようになってしまうこともあります。
そのような場合には、うつ病の親と子を引き離して生活することも状況によっては必要になるでしょうから、配偶者との離婚も検討せざるをえないかもしれません。
家族の生活が苦しくなった場合
夫婦のどちらか一方のみが働いて収入を得ている家庭に特に多いと思いますが、働いている配偶者がうつ病に罹ったことで仕事を辞めるなどして、家計が苦しくなるケースがあります。
その場合には、他方の配偶者が働いて家計を支えたり、借金をする必要に迫られることもあるでしょう。
しかし、十分な貯蓄がある家庭であればよいですが、そのような事情も無い場合には、これまで働いた経験が少ない他方配偶者は、家族を十分に支えるだけの収入を得ることが難しいケースが多いと思います。
こういった状況が続くと、いつか生活が破綻してしまうかもしれません。
自分や子供が生活することができなくなるくらいであれば、早めに離婚を検討すべきといえるでしょう。
自身の精神状態にも悪影響が生じている場合
夫婦は毎日一緒に生活していく以上、他方配偶者に大きな影響を受けるのは当然のことです。
その配偶者がうつ病に罹り、日々悲観的な言葉を投げかけてくると、自身も精神的に追い詰められてしまうことが多いでしょう。
また、うつ病に起因して暴力や暴言を繰り返すこともあるかもしれません。
さらには、うつ病の配偶者のために努力して生活していく中で、相手には自分がいないと生きていけないなどと思い込み、知らないうちに共依存の状態に陥ることもあります。
そのような状況が続くと、かえって自分もうつ病などの精神疾患に罹ってしまう可能性があります。
自身の精神状態に限界を感じている方は、そういった事態に陥る前に離婚を検討すべきです。
夫婦生活を続けることが苦痛になっている
婚姻生活は基本的に生涯続いていくものですが、円満な夫婦生活を築いていくうえでは、お互いのことを思いやり、ある程度自分を犠牲にすることも必要になるでしょう。
しかし、うつ病に罹った配偶者のために自分を犠牲にして努力していくうちに、夫婦としての心のつながりも途絶え、もはや一緒にいたくないと感じてしまうこともあると思います。
そのような状況に陥ったにもかかわらず、過大なストレスを抱えて夫婦生活を続けていくとなると、他方の配偶者にとってもストレスとなり、かえってお互いのために離婚した方が良いケースもあるでしょう。
このような場合には、無理をせずに離婚の検討も必要になるでしょう。
うつ病の配偶者と離婚するための手順とポイント
それでは、いざうつ病の配偶者と離婚することを決意した場合に、どのように離婚を進めていけば良いでしょうか。
以下では、離婚をするための手順とポイントを解説します。
離婚するための手順
離婚は、お互いの合意があれば問題なく成立します。
そのため、まずは夫婦間で話し合いをして、協議離婚を成立させることになります。
離婚協議を行ったものの、うつ病の配偶者が納得しない場合には、夫婦双方の合意が無い以上、協議離婚はできません。
その場合には、家庭裁判所に離婚調停を申立てることとなります。
離婚調停も、協議離婚と同様に夫婦の離婚に対する合意を目指す手続きとなりますが、他方配偶者と直接顔を合わせる必要がなく、調停委員が間に入って話し合いを進めていくことになるため、柔軟な解決を図ることができます。
離婚調停も不成立となった場合には、離婚裁判を申立てることとなります。
すでに解説した通り、裁判で離婚が認められるためには、法律上定められた離婚事由が必要となり、民法770条1項4号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の有無を主張立証する必要があります。
しかし、うつ病のみを理由とした離婚は認められづらいのが実情です。
そのため、配偶者がうつ病に罹って離婚を検討している方は、事前に弁護士に相談してみると良いかもしれません。
次に、配偶者のうつ病により離婚するためのポイントを解説します。
証拠を確保する
離婚調停でも離婚が成立しなかった場合には、離婚裁判を行うことになります。
そして、離婚裁判では、法律上定められた離婚事由を証明するための証拠が原則として必要になります。
また、離婚調停であっても、相手方を説得するために一定の証拠があった方が良いでしょう。
うつ病による離婚に必要な証拠の例としては、以下が挙げられます。
・うつ病に関する医師の診断書
・うつ病の治療経過が分かる資料
・配偶者がうつ病に罹っている期間の配偶者の言動などが分かる音声データや動画
・暴力や暴言がある場合には、診断書や暴行や暴言の状況が分かる音声データや動画
すでに解説したとおり、病状の程度にもよりますが、うつ病に罹っていることのみをもって「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断される可能性は低いというのが実情です。
そのため、上記のように、自身や子供への暴力や暴言など、うつ病とあいまって婚姻関係破綻の原因となった事情を証明するための証拠も確保しておく必要があります。
離婚協議では、冷静に話し合う
離婚協議は基本的に大きなストレスがかかることが通常です。
そもそもうつ病に罹っている状況では、感情の起伏が激しく、逆上して無理な要求を突き付けてきたり、黙り込んでしまうことも多いです。
また、精神的に追い込まれることで自殺してしまうケースもあります。
このようなことから、うつ病の配偶者との離婚協議は難しくなることが比較的多いです。
そのため、配偶者がうつ病に罹っている状況でスムーズに離婚協議を進めるためには、冷静に、かつ相手方に配慮しながら話し合うことが重要です。
配偶者と話し合う中で、急に黙り込んだり、怒り出したりした場合は、その日の話し合いを中断し、冷却期間を設けるべきでしょう。
とはいえ、ご自身で離婚協議を進めることに不安を感じる方も多いと思いますし、上記のように当事者同士で話し合うことで相手方を感情的にさせてしまうことが多いです。
そのような場合には、代理人として弁護士が離婚協議を行うこともできますので、まずは弁護士に相談してみると良いでしょう。
話し合いが難しければ、調停を申立てる
上記のように、うつ病の配偶者との離婚協議には、困難を伴うことが多いです。
そのような状況で離婚協議を続けていても、かえってご自身も精神的に病んでしまい、離婚協議を進める意欲も減退してしまうかもしれません。
そのため、離婚協議が難しいと判断した場合には、早急に離婚調停を申立てるべきです。
すでに解説したとおり、離婚調停も基本的には離婚に向けた話し合いであることは離婚協議と変わりませんが、相手方と顔を合わせることもなく、調停委員が間に入って離婚の話し合いを進めていくことになります。
調停委員は、夫婦双方の意向を聞きながら、場合によっては相手を説得するなど、離婚の成立に向けて仲介してくれる存在です。
そのため、当事者のみでの話し合いよりも精神的負担は軽減されることも多く、うつ病の配偶者としても感情的になる要因も少なくなることが多いといえます。
離婚を有利に進める方法
離婚といっても、決めるべきことが多く、精神的にも大きな負担を伴うものです。
そのような状況の中で、自分に有利に離婚を進めることは容易ではありません。
そこで、以下では、少しでも離婚を有利に進める方法について解説します。
慰謝料について
配偶者のうつ病により慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
うつ病に罹ること自体、本人の意思により左右できることはありませんので、基本的に配偶者がうつ病であることをもって慰謝料を請求することはできません。
しかし、配偶者が、自分の意思で法律上保護されている「平穏な夫婦生活を送る権利」を侵害したといえる場合には、「不法行為」として慰謝料請求が認められることになります。
そして、以下の場合には、不法行為として慰謝料請求が認められる可能性があります。
①不貞行為があったとき
不貞行為は、法定離婚事由として定められていますが、不貞行為によって平穏な夫婦生活を送る権利が侵害されたといえる場合には慰謝料を請求できる可能性があります。
②悪意の遺棄
悪意の遺棄についても法定離婚事由として定められています。
悪意の遺棄とは、夫婦の同居・扶助・協力義務に違反することを意味しますが、生活費を渡さない、不貞相手と同居する、家事や育児を放棄するなどといった事情があると悪意の遺棄に該当する可能性があります。
③DVやモラハラ
配偶者に暴力を振るう、長期間に渡り罵倒され続けるなどといった事情がある場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
このように、配偶者がうつ病であることに加え、上記のような事情がある場合には慰謝料を請求できる可能性があります。
どのような場合に慰謝料が請求でき、どのような証拠が必要になるかなど、まずは弁護士に相談してみるといいでしょう。
親権について
子供がいる夫婦が離婚する場合、どちらが親権を得た方が良いか考える必要があります。
親権を決めるにあたっては、子供の健全な育成のために夫婦のどちらが親権を得るべきかという視点で考えなければなりません。
そのため、配偶者のうつ病の程度が重く、十分な監護養育が困難である場合には、他方の配偶者が親権者となることができる可能性があります。
他方で、うつ病の程度が軽い場合には、子供の監護養育に支障がないことも多いです。
その場合には、これまでの監護実績等を考慮してどちらが親権者にふさわしいかを判断することになりますので、日常的に子供のために最善な監護環境を整えることを意識しておくのが良いでしょう。
養育費について
うつ病の配偶者に対して、養育費を請求することはできるのでしょうか。
養育費とは、親の扶養義務に基づき子供が自立するまでに必要になる費用をいいます。
そのため、うつ病の配偶者であっても、原則として養育費を支払わなければなりません。
もっとも、養育費の支払義務は、支払義務を負う親が自身の生活を維持できることが前提となるため、その親の経済状況等の事情が考慮されることになります。
そのため、うつ病を原因として失職したり、収入が激減した場合には十分な養育費を請求することが難しくなる可能性があります。
適正な養育費の金額を算定するためには専門的判断が必要になることがありますので、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
財産分与について
配偶者がうつ病であったとしても、財産分与をする場合には、原則的に夫婦の共有財産を2分の1ずつとすることとなります。
うつ病の配偶者が、離婚後の生活保障として多めに財産分与を求めてくるケースもありますが、原則として2分の1ずつの分与となることに変わりはありません。
もっとも、うつ病の配偶者が離婚を拒否している場合には、多めに財産分与することで離婚に応じてもらうといった対応が必要になることもあります。
配偶者のうつ病の治療のためにできること
うつ病の配偶者と離婚することを検討している方は、うつ病を理由とする以上は配偶者がうつ病でなければ離婚しなかったと考えている方はほとんどではないでしょうか。
うつ病に罹る原因としては、ストレス、元来の性格上の問題、遺伝など様々な要因がありますが、現在では薬物療法に加え、環境を整えることで症状の改善を目指す精神療法により病状の改善が期待できるとされています。
そのため、うつ病の配偶者との離婚を検討している方は、まずうつ病の配偶者を病院に通わせ、うつ病の原因を探り、婚姻関係を継続しながらうつ病の改善を図ることができるかどうか今一度見つめ直してみるのが良いかもしれません。
自分がうつ病になった場合
これまでは、配偶者がうつ病に罹っていた場合について解説してきました。
それでは、自分がうつ病になってしまった場合には、離婚にあたってどのような問題が生じるのでしょうか。
慰謝料
自分がうつ病になってしまった場合に慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
既に説明したように、慰謝料を請求するためには、法律上保護された権利を侵害されたことが必要となります。
そのため、単にうつ病に罹ったことだけをもって慰謝料を請求することは基本的にできません。
もっとも、うつ病を発症した原因が、配偶者の不貞行為やモラハラ・DVによるものである場合には、不法行為として慰謝料を請求できる可能性があります。
また、その場合には、単なる不貞行為やDV・モラハラよりも、うつ病に罹ったという事実が精神的苦痛がより大きいことを示すことから、より高額な慰謝料を請求できる可能性があります。
親権
既に説明したように、うつ病に罹ったことだけをもって親権を獲得できないということにはなりません。
特に、軽度のうつ病の場合には、子供の監護養育に支障がないことも多いため、監護能力に問題がないと判断される可能性も十分にあります。
うつ病に罹ったからといって、それだけで親権を獲得できないことにはなりませんので、今後の親権を巡る協議の中で有利に話し合いを進めていけるように準備を進めていきましょう。
まとめ
今回は、うつ病を理由とした離婚について解説しました。
うつ病の配偶者との離婚協議は、そもそも話し合いに応じてくれない等困難を極めることも多いです。
だからといって、協議を諦めてしまっては、将来のご自身の生活が苦しくなったり、かえって自分もうつ病になってしまうこともあります。
自分だけで抱え込む必要はありませんので、諦めてしまう前に、まずは弁護士に相談することを検討しましょう。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設


















