悪質なクレーマーに悩む企業の方へ|法的措置による解決方法について弁護士が解説
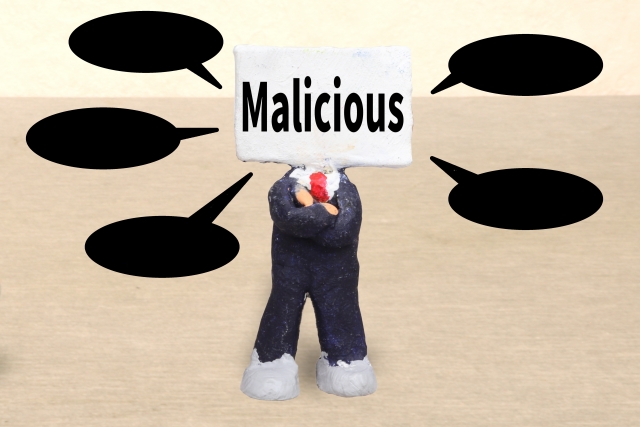
相談
面談無料
東京スタートアップ法律事務所まで
記事目次
クレーム対応でよくあるお悩み
「悪質なクレームにどう対応したら良いかわからない」
「クレーム対応で従業員が疲弊している」
「顧客からの理不尽な要求にも従ってしまう」
上記のようなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
企業を経営されている方にとって、お客様の意見は企業発展の上では極めて重要なものです。
しかし、近年はその域を超えて、企業に対して理不尽な要求や嫌がらせを行うクレーマーが増加しています。
一昔前までは、企業と顧客を結ぶ連絡手段は、直接の店舗での対応、電話やメールなどでしたが、インターネットが発展した現代においては、それらの他にSNSや口コミサイトなど多方面に渡り、それらに対してクレーマーが加害行為を行うことも想定されるような状況です。
ただ、顧客の意見ではあるため、受け入れた方がいいのか、それとも別の手段を取るべきなのかで悩まれる企業の方も多くいらっしゃると思います。
今回の記事では特に理不尽な要求や嫌がらせがあった場合に、企業側で取ることができる法的措置について、解説していきます。
クレーマーに対する法的措置とそれぞれのメリット・デメリット
悪質なクレーマーに対して、企業側で取ることができる法的措置について、大きく分けると民事の法的措置と刑事の法的措置が考えられます。
民事の法的措置
まず、企業としては、民事の手続きとしてクレーマーによる加害行為に対して、訴訟をして決着をつけることや、仮処分を行うことが考えられます。
仮処分とは、企業側がクレーマーの加害行為を禁止してもらうよう裁判所に要請することです。
通常であれば、訴訟をして加害行為を辞めてもらうという手続きを取ることになるのですが、訴訟の提起をしてから約1か月後に第1回の期日が開かれて、そこで禁止行為の存否を争うことになります。勿論その後クレーマー側が争うとなると、その分時間がかかることになります。
ただ、当然企業側として求められているのは、現在の加害行為を除去することが一番必要なものであると考えられるため、それだけの期間加害行為を止めることができないということは、企業側の損害拡大にも繋がりかねません。
それに対して、仮処分であれば、一定の要件や担保金を納めることで、訴訟よりも短期間に結論が出ることになり(早ければ1週間程度で結果が出ます。)、加害行為の禁止を認めてもらうことが可能となります。
つまり、訴訟よりも極めて短期間の間にクレーマーへの対応が可能となります。
もっとも、担保金を供託する必要があるため、その分の費用がかかる点はデメリットかと思われます。
他方、訴訟という方法を取ることで、加害行為の差し止めのみならず、損害の賠償を求めることが可能となります。
仮処分はあくまでも暫定的な措置であるのに対して、訴訟であれば当該行為を止めるだけでなく、損害賠償として企業が被った金銭的損害を求めることも可能となります。
時間などはかかるものの、終局的な解決を求める場合には、訴訟も選択肢に入れる必要があります。
もっとも、クレーマーからの要求によって企業側がどのような損害を被ったのかという点を主張・立証する必要があり、その点が困難であるケースも多くあります。
後ほどどのような立証や証拠が必要であるかは解説しますが、この困難さ故に敗訴するリスクがあることを忘れてはなりません。
そのようなリスクを出来る限り回避するためには、損害賠償の請求ではなく、差し止めのみを訴訟で求めることや債務不存在確認(クレーマーからの要求に応じる義務がないことを裁判所に認めてもらう訴訟です)も視野に入れる必要があります。
企業の損害ではなく、クレーマーの加害行為を止める側を優先されるのであれば、これらの訴訟を提起することも想定されるといいでしょう。
刑事の法的措置
民事での法的措置とは別に、企業側は悪質なクレーマーに対して刑事告訴の手続きを取ることも考えられます。
一般的には、
①脅迫罪(「ネットで晒す」「店を壊す」等の害悪を告知する行為)
②強要罪(「土下座をしろ」「〇〇を辞めさせろ」など、脅迫や暴力を用いて法的義務のない行為をさせる行為)
③恐喝罪(「誠意をみせろ」など、脅迫や暴力を用いて、金銭などを脅し取る行為)
④威力業務妨害罪(店舗で騒ぐ、何度も電話をかけてくる等で、企業の人の意思を制圧し、業務を妨害する行為)
⑤不退去罪(企業側からお引き取りするよう伝えているにも関わらず、店舗などに居続ける行為)
などが、クレーマーに関わる犯罪として考えられます。
これらの行為がある場合には、警察への相談や、場合によっては刑事告訴を行い、処罰を求めることが考えられます。
特に告訴が受理された場合には、民事以上に強制力のある手段によって警察が捜査をすることになり、クレーマーへの逮捕などに繋がる可能性もあるため、クレーマーへの対応としてはかなり強いものとなることが期待できます。
もっとも、警察が告訴状の受理をした場合には、捜査機関に対する捜査協力等が必要となるため、企業側も負担が多くのしかかります。
クレーマーを訴える際の注意点
民事であれ刑事であれ、クレーマーに対して法的措置を取る際には、十分な検討を踏まえて適切な対応を行わなければ、空回りしてしまう可能性もあります。
次は、クレーマーに対して法的措置を取るため注意すべき点等について解説していきます。
労力がかかる
民事であっても刑事であっても、かなりの労力が必要となります。
クレーマーの実際の行為を証拠として残すこと、企業側の損害について具体的に証拠を整えること、弁護士へ依頼する場合には、弁護士探しや弁護士への相談などが考えられます。
また、民事において、仮処分の審尋期日では通常、担当者が裁判所まで行き、裁判官に対して仮処分が必要であることを伝える必要が生じることが考えられ、裁判の際は裁判所に対して、企業側の主張が認めてもらえるように、何度も裁判所とのやり取り(書面によるものが主なものです)を行う必要が生じることが想定されます。
刑事であっても、前述の通り捜査機関への捜査協力のために捜査機関へ出頭し、取調べを受ける必要など様々な点で時間や労力がかかることが想定されます。
そのため、それだけの労力をかけるだけのクレームであるのかについては、よく検討する必要があります。
関係の修復が難しくなる
法的手続きを取ると、企業側とクレーマーとの間の関係は決定的に決裂することになります。
もし、そのクレーマーが元々企業側の優良顧客である場合などは、法的手続きによってある種当該顧客との関係の修復が難しくなることを意味します。
法的手続きとして裁判所や警察を巻き込むことになる以上、当然想定されることではありますが、当該顧客との関係性を踏まえた上で、法的措置を取るか否かは検討する必要があると考えます。
証拠の準備が必要となる
法的手続きは、証拠の有無によって結果が大きく左右されることになります。
そのため、証拠の収集などは必要不可欠となります。
証拠にも大きく分けると二種類のものが考えられ
①クレーマーの加害行為を裏付ける証拠
②企業側の損害を裏付ける証拠
があります。
①については、加害行為の録音、メールのやりとり、防犯カメラ映像などが考えられます。メールや防犯カメラは事後的に取得することは可能ですが、他方録音はその加害行為が行われているその場でしか取れない証拠です。
その分証拠としての効果は大きいため、クレーマーの対応などは全て録音を取るよう日頃から徹底することが必要となります。
②については、実際に対応した従業員の対応時間、壊された備品の修理費用や新たに買い直しをした費用などが考えられます。対応時間は電話の時間やメールへの返信に要した費用など、通常業務を超えて対応が必要となった部分については損害賠償を請求できる余地があります。
また、破損した備品関係は、修理の見積もりや同種のものを取得する際にかかる費用を販売会社に問い合わせるなどの時間が必要となります。
クレーマー対応について弁護士に相談するメリット
法的措置を取る際には、クレーマーによる加害行為の内容、クレーマーとの関係性、対応にかかる費用、対応にかかる時間、敗訴のリスクなど様々な要素を踏まえてどうするのか決める必要があります。
また、実際に動いたとしても、企業だけで進めてしまうと、証拠が不十分であったり法的に必要な情報が欠けていたりすることにより、時間と労力だけがかかってしまい、結果が得られないという結論にもなりかねません。
そのため、初期対応の時点から法律の専門家である弁護士に依頼し、実際に動くべきか否かや、どのような手段を取って対抗すべきであるかなどを適切に判断してもらうことが重要となってきます。
また、弁護士を入れることによって、クレーマーへの対応を全て弁護士が窓口として対応できるようになるため、クレーマー対応に貴重な企業資源を使うことを最小限に食い止めることもできますし、従業員がクレーマーへの対応をせずに済むことになるため、従業員の精神的負担を軽減することにも繋がります。
更に、実際に弁護士が間に入ることで、クレーマーに対する抑止効果も期待できるため、法的措置に進むことなく解決に繋がる可能性も期待できます。
当事務所でのサポート内容
当事務所では、顧問サービスを企業様へ提供しており、担当弁護士をつけることで、日頃の企業における法律問題について、包括的なアドバイスを行うことが出来ます。
本稿におけるクレーマーへの対応という点においても、発生当初から法的なアドバイスを行い、適切な対応や証拠収集などの期待が出来ます。
そして、実際に法的措置を取る場合であっても、日頃からコミュニケーションを取っている担当弁護士が企業様の代理人として、クレーマーへの対応のみならず関係各所(裁判所や警察など)の対応を行うため、漏れなく安心して適切な対応ができるようになります。
また、顧問サービスを利用されていない企業様であっても、スポットでの相談も行っております。
クレーマーへの対応は初動の対応をどれだけ早く行うことができるのかによって、結果が大きく左右されますが、当事務所では電話やZoomでのWeb相談を受け付けており、早期に相談をすることで、適切なアドバイスやその後の代理人としての対応を期待することができます。
クレーマー対応でお困りの場合は東京スタートアップ法律事務所まで
本稿では、クレーマーへの対応方法や、弁護士へ依頼するメリットなどについて解説しました。
特に、クレーマーへの対応は適切な対応を初動から早急に行うことが、損害拡大の防止や、賠償責任を追及することにも繋がります。
もし、クレーマーの対応でお困りであったり、どのような対応がいいか悩まれている方は、ぜひ一度東京スタートアップ法律事務所までお問合せ下さい。
相談
面談無料
東京スタートアップ法律事務所まで
- 得意分野
- 企業法務、ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設











