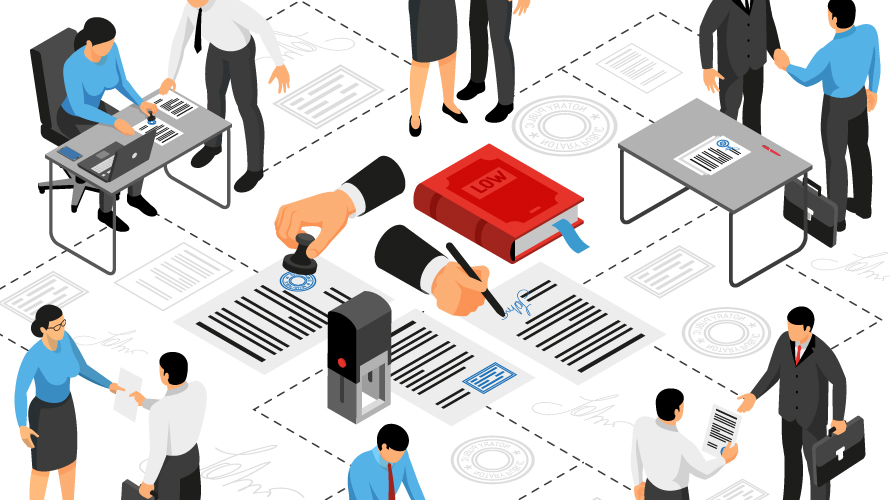企業が知っておくべき消費者契約法の基礎知識

全国20拠点以上!安心の全国対応
記事目次
自社の商品・サービスを広めていくにあたって、気を付けておかなければならない法律として、「消費者契約法」という法律があります。
この法律に反するような事を起こした場合には、契約が取り消されたり、無効になったりするのみならず、時にはインターネット上のニュース配信サイトなどのメディアにて、法律違反が報じられ、企業の信用に大きなダメージを負うことになります。
このページでは、消費者契約法という法律について、事業者として知っておくべきことについてお伝えします。
消費者契約法の概要
まず、消費者契約法というのはどのような法律でしょうか。
消費者契約法は、平成12年5月12日法律第61号交付され、平成13年4月1日から施行された法律です。
この法律の運用をするために、消費者契約法施行令(平成19年政令第107号)・消費者契約法施行規則(平成19年内閣府令第17号)が制定されています。
この法律が存在している理由は消費者契約法第1条が定めているので、噛み砕いて解説します。
前提として、当事者間でどのような契約を結ぶかについて、民法では契約自由の原則という理論のもと、どのような内容の契約を結ぶのも自由とされます。
しかし、契約自由の原則は絶対のものではありません。当事者間に圧倒的な情報量の差があるようなケースにまでこれを認めていると、片方の当事者にとって不利・不平等な契約が締結される恐れがあります。そこで、法律で契約自由の原則を多少修正する必要があるのです。
企業と消費者が取引をするにあたっては、企業の有している情報と消費者の有している情報の質や量には大きな差があることから、企業が自社に有利に契約を締結することは難しくありません。
このような場合に、消費者に契約の取消しや無効を主張をする権利を与えることで、消費者の生活や経済の健全な発展に寄与するために制定されたのが、「消費者契約法」です。
また、被害の発生や拡大を防止するために「適格消費者団体」が事業者に不当な行為の差止請求をすることも認め、その実効性を担保しようとしています。
法律の内容としては大きく、総則と呼ばれる定義などの共通事項を規定した部分があり、締結した契約を取り消すことができる場合の規定、契約内容が無効になる場合の規定、適格消費者団体に関する規定が置かれています。
消費者契約法に違反するとどうなるのか
具体的な規定について見る前に、この法律に違反した行為を企業がすると、どのような事になるのか、というイメージを持っておいてください。
1. 契約が取り消されたり無効になったりする
まずは、契約が取り消されたり無効になったりします。
取消しというのは、一旦成立した契約が、消費者が取消権を行使することによって、契約開始時点からなかったものとして取り扱われることです。
無効というのは、たとえ契約書等に記載されている事項でも、効力が生じていない、と法律上評価されるものです。
2. 裁判で負けてニュース配信サイトに掲載された例
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190621-00000173-kyodonews-soci
契約が取り消されたり無効になったりするのは、あくまで当事者間における民事上の効力にとどまるのですが、消費者契約法違反をしたことをニュース番組などのメディアが報じることがあります。
たとえば、2019年6月12日に、家賃保証を業務にしているフォーシーズ株式会社がマンションの借主と結んだ連帯保証契約書中に「追い出し条項」というものを定めていた件で、適格消費者団体である「消費者支援機構関西」が提起した差止訴訟において、大阪地裁が原告の訴えを認め、当該契約書内の一部の条項の差止めを命じた裁判が広く報じられました。
3. 裁判を起こされただけでもニュースになることも
裁判を起こされた段階で報道されるケースもあります。裁判を起こされただけですと違法行為があったかどうかはわからないのですが、一般の視聴者はその企業が違法行為を行なったと解釈しかねません。
個別の契約の取消し・無効、若しくはその請求は、直接的に企業に大きな影響を与えなくても、ニュースで報じられると会社としての信用を失う可能性があります。
社会からの信用を失った結果、取引先や顧客から敬遠され、事業の継続が困難になるような事態が起こり得ます。
そのため、消費者契約法を遵守することは、非常に重要であるという認識が求められます。
消費者契約法で取消しができるとされているもの
それでは、消費者契約法ではどのような行為によって契約が締結された場合について取消しを認めているのでしょうか。取消しの対象となり得る行為は以下の通りです。「なり得る」としているのは、以下に掲げる行為によって消費者が「誤認」したり「困惑」したりし、その結果契約締結に向けた申込みまたは承諾の意思表示が必要とされているからです。
1. 不実告知
「重要事項について事実と異なることを告げること」を言います(消費者契約法4条1項1号)。
例えば、ある機械を販売するにあたり、実際にそのような効果が存在しないにもかかわらず、「この機械を取り付ければ電気代が安くなる」とを告げる行為がこれに当たります。
2. 不利益事実の不告知
契約の目的(契約の対象となる物品、権利、提供するサービスなどを指します。)に関して重要な事項について、消費者にとって不利益となる事実があるにもかかわらず、意図的、若しくは重大な過失によりその事を告げなかった場合です(消費者契約法4条2項)。
たとえば、不動産を購入してもらうに当たって、隣に将来マンションが立って邪魔になることがわかっているにもかかわらず、「日当たりがよい」「眺望がすばらしい」というような文句で当該不動産を販売することがこれに当たります。
3. 断定的判断の提供
契約の目的(契約の対象となる物品、権利、提供するサービスなどを指します。)に関して、将来のその価額や将来その消費者が受け取ることになる金額など、将来における変動が不確実な事項について、確実であると告げた場合をいいます(消費者契約法4条1項2号)。
たとえば、ある不動産の購入を検討している消費者に対して、「確実に値上がりする」というような情報を伝えて契約させた場合がこれにあたります。
4. 過量契約
消費者が通常必要とする分量を著しく超えることを知りながら、過剰な分量の契約を締結させることを言います(消費者契約法4条4項)。
たとえば、一人暮らしのあまり外出しない高齢の女性に、何十着もの着物を購入させるような行為がこれにあたります。
5. 不退去
住居や就労場所において営業を受けた際に、その消費者が事業者に対し、退去してほしいということを告げたにもかかわらず当該事業者が退去せずに消費者を困惑させて契約させた場合をいいます(消費者契約法4条3項1号)。
なお、退去をしてほしいと告げたにも関わらず退去しなかった場合に、不退去罪という犯罪が成立する可能性もあるので、契約が取り消されるのみならず、刑事責任を問われる場合があることもあわせて知っておきましょう。
6. 退去妨害
店舗に来店をした消費者が、帰りたいということを告げたにも関わらず、帰らせずに消費者を困惑させ、商品を購入させた場合がこれにあたります(消費者契約法4条3項2号)。
こちらも、度を越した場合には監禁罪という犯罪が成立する可能性があり、刑事責任を追う場合があるということを知っておきましょう。
7. 不安をあおる告知
社会経験の乏しい消費者がその進学・結婚・容姿などに関する願望の実現に強い不安を抱いているのに乗じて、その不安をあおって、まともな理由もないのにその商品やサービスが当該消費者の願望実現のために必要であると告げて契約をさせた場合です(消費者契約法4条3項3号)。
たとえば、無料の就職セミナーに招いた上で、「今この有料セミナーを受けておかないと就職できない」などと告げて不安にさせて契約をさせたような場合です。
8. 好意の感情の不当な利用
社会経験の乏しい消費者に恋愛感情などの好意を抱かせ、相手も同様の感情を持っていると誤信しているものと知りながら、その契約を締結しないと両者の関係が終わると告げて契約させる場合をいいます(消費者契約法4条3項4号)。
少しわかりにくいのですが、例えば「デート商法」などといわれる、恋愛感情を利用して、「二人の将来のために必要だから…」などと告げて契約をさせるものをいいます。
9. 判断力の低下の不当な利用
加齢や病気により判断力が低下していて生活に不安を抱いている人に対して、その不安をあおって、まともな理由もないのにその商品やサービスがなければその人の生活の維持が困難であると告げて契約をさせた場合です(消費者契約法4条3項5号)。
たとえば、高齢者の方に老後資金についての不安をあおって投資用マンションを購入させる行為がこれにあたります。
10. 霊感等による知見を用いた告知
霊感のような合理的に実証困難な能力による知見をベースに消費者の不安をあおって、相手に契約させることです(消費者契約法4条3項6号)。
たとえば、「あなたには霊が取り付いているので、その例を成仏させるためにもこの壺を買いなさい」と言ってその壺を購入させる場合です。
11. 契約締結前に債務の内容を実施
消費者が契約の申込みや承諾をする前に商品やサービスの提供を行うことで、契約を迫ることをいいます(消費者契約法4条3項7号)。
たとえば、さお竹を契約前先にカットしてしまい、切った以上は契約しなければ困る、と迫る行為がこれにあたります。
また、義務の一部を履行したことなどをもって損害が出たなどと主張し、代金の一部の支払いを求める行為もこれにあたります。
以上のような行為があった場合、一定の要件のもと、消費者が取消権を行使することができます。
消費者契約法で無効とされているもの
次に、事業者と消費者との間で締結された契約内容が「無効」とされるケースについて見ていきましょう。
1. 事業者は責任を限定する条項
事業者の責任、若しくは契約締結前にはわからなかった欠陥により発生した消費者の損害について事業者は責任の全部又は一部を負わないとし、又はその事業者がその責任の有無を決定することができる条項のことをいいます(消費者契約法8条1項各号)。このような条項は無効です。
たとえば、スポーツジムの契約をした際に、「施設利用に際して発生した損害については事業者の故意又は過失によるものも含めて責任を負わない」と規定する条項や、「施設利用に際して発生した損害については、その責任の所在の有無は事業者の裁量にて決する」と規定する条項がこれにあたります。
2. 契約後の解除権を放棄させる条項
契約締結後に、事業者が契約内容通りの義務を果たさない場合や目的物に契約締結前にはわからなかった欠陥があった場合、消費者は本来、債務不履行や瑕疵担保責任を理由に当該契約の解除をすることができます。
この解除権を放棄させ、又は事業者に解除できるかどうかの決定権を与える条項は、無効になります(消費者契約法8条の2各号)。
3. 成年後見制度の利用を原因とした契約解除
加齢や病気により判断能力が鈍ってきた際に、その人のためにその人に代わって契約などの法律行為をするための制度として「成年後見制度」があります(他にも類似した制度として「保佐」、「補助」があり、いずれも審判によって開始されます。)。
本来、契約締結後に成年後見を開始する場合でも契約の効力は有効です。しかし、契約締結後に成年後見・保佐・補助開始の審判を受けたことのみを理由とする契約の解除を定めた条項は、無効です(消費者契約法8条の3)。
たとえば、高齢者が一人で居住する賃貸マンションにおいて賃貸借契約を締結する際に、「成年後見を開始すると契約を解除することができる」、と契約書に定める場合がこれに当たります。
ただし、消費者側に物品やサービスなどの提供義務がある契約については、成年後見等の開始によってそれらの提供が難しくなってしまうので、例外として認められています。
4. 平均的な損害額を超えるキャンセル料に関する条項
契約当事者がその契約を解除したり、その契約に定められた義務に違反した場合、一方又は双方の当事者に損害が発生する可能性があります。
そのため、契約が解除された場合の損害賠償の額や、契約違反があった場合の違約金の額を定めておく場合があります。
しかし、その金額が通常発生する平均的な金額を超える場合、超過部分については無効とされます(消費者契約法9条1号)。
また、消費者が金銭の支払い義務を果たさない場合には遅延損害金が付加され、その年利を契約条項で定めるケースがあるのですが、遅延損害金について年利14.6%を超える場合には、超過部分については無効とされます(消費者契約法9条2号)。
たとえば、家賃の支払いについて、「支払期限を過ぎて支払われたかった場合には年30%の遅延損害金を支払う」、という内容の規定がある場合には、14.6%を超える部分については無効とされます。
5. 消費者の利益を一方的に害する条項
消費者が何もしなかったことをもって契約の意思表示があったとみなす条項や、その他消費者の権利を制限しまたは加重する条項で、消費者の利益を一方的に害するものも無効となります(消費者契約法10条)。
少し曖昧な規定ですが、たとえば、掃除機の購入時におまけとしてもらった健康食品について、継続して購入しませんという意思表示をしなければ、継続購入したものと取り扱う、というような条項が想定されます。このような条項は無効となる可能性が高いです。
無効となる場合の処理ですが、契約そのものがなかったものとなるのではなく、当該消費者契約法に違反する条項のみが無効とされるので、契約自体は存続します。
適格消費者団体による差止訴訟を知ろう
もし、これまで述べてきた取消事由や無効事由があった場合、消費者側は自身が締結した契約を取り消したり、違反が生じている条項の無効を主張したりできます。
しかし、事業者の方は数多くの消費者と同じような勧誘方法をしていたり、同じフォーマットの契約書を使っていたりするので、個々の契約を取消し、個別の条項を無効とするだけでは、次なる不当な契約に対する抑止としては十分機能しない場合もあります。
また、個々の消費者がそれぞれで契約の取消しや無効を主張し、場合によっては事業者に対して支払った金銭の返還請求をすることは、大きな負担となります。業者が任意に取消しや無効を認め返金に応じるとは限りませんし、交渉に応じない場合は裁判を起こさざるを得ませんが、1件あたりの被害金額がそれほど多くない場合には、個々の被害者が裁判を起こすことに適さない場合があります。
そこで、「適格消費者団体」という消費者の公益に関する団体を国で認定して、適格消費者団体は、同様の被害が多数発生しているような場合には、被害を受けている消費者のためにに差止請求を行うことができます(消費者契約法13条以下)。
つまり、事業者の側は、消費者契約法違反の状態が多数発生している場合には、個々の消費者から契約の取消しや金銭の返還請求だけでなく、適格消費者団体から差止請求をされる可能性があることを知っておきましょう。
消費者契約法に違反しないために
では、企業としては、消費者契約法に違反しないため、どのような対策をすればよいのでしょうか。
1. 社内にきちんと周知・徹底をする
まずは、消費者にその企業の商品・サービスを販売するにあたって、社内の営業マンやインサイドセールスの担当者に、たとえ契約が取りたくても消費者契約法上やってはいけない行為があるということ、やってはいけない行為の中身についてきちんと周知・徹底をすることです。
これまで述べてきた禁止される行為の中には、契約を取りたいがためについやってしまいがちな行為も含まれています。
自社の商品やサービスの販売にあたって、契約に至る通常の手続についてきちんと観察して、消費者契約法が禁止している行為に抵触する行為を行うおそれがあるような場合には、「何をやってはいけないか?」ということを明確にすべきでしょう。
必要に応じて、研修の内容にやってはいけない行為を盛り込んで、理解をしているかどうかをきちんとチェックしたり、文書などで営業を担当する従業員がいつでも見られることができるようにしたりしておくことが肝要です。
2. 専門家に相談できるようにして体制として消費者契約法に違反しない
どのような行為・契約が取消し、無効の対象になるかについては上述しましたが、実際に消費者契約法、施行令や規則の条文は非常に細かく、また前提として民法などの基本的な知識が必要になることもあります。
特に、個々の条項が無効になる無効事由については契約書の設計が非常に重要です。また、勧誘については後で契約の取消事由の有無が問題とならないように重要事項説明書を作成しておくのも良いかもしれません。いずれにせよ、消費者を相手にする契約では、知らず知らずのうちに消費者契約法やその他の法律に違反している事態が発生しかねません。
そのため、消費者契約法を含む契約に関する法律問題に詳しい弁護士と密に相談できる体制を整えて、業務が法律に触れないように仕組みを作っておくことが重要です。
争いが起きてから対処することも重要ですが、事前に弁護士に相談し、消費者との間で法的問題が発生する可能性を極力減らしておく方が効果的です。
消費者契約法に詳しい弁護士であれば、契約書の作成・チェック、社内体制構築の助言、問題が発生した際の交渉から裁判手続までを一貫して対応できます。
消費者を相手にする事業をお考え、現在行なっている企業様は、消費者契約に強い弁護士を確保しておくことを推奨します。
まとめ
このページでは、消費者契約法の概要、違反した場合の効果、その対策についてお伝えしてきました。
事業者と消費者との契約について不当な取扱いをされた消費者の救済に重きを置いている法律ですが、事業者側はしっかりと理解して対策を講じておくことが大切です。
- 得意分野
- 企業法務、ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設