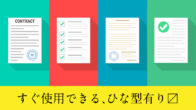雇用契約書とは?記載事項や労働条件通知書との違い、作成時の注意点を解説

全国20拠点以上!安心の全国対応
記事目次
雇用契約書を適切に作成することは、労使間トラブルを回避する上で非常に大切です。しかし、雇用契約書を作る必要性は感じつつも、具体的にどのような書面を作ればいいかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、正社員やパートなどの雇用形態や業務内容によって異なる雇用契約書の書き方について、雛形も紹介しながら解説します。
雇用契約書とは
雇用契約書とは、使用者(会社側)と労働者(従業員側)との間で、労働に関する取り決めをまとめて交わす契約書のことをいいます。
雇用契約書の作成は法律上の義務ではなく、絶対に作成しなければいけないわけではありません。
前提として、「雇用契約」とは「使用者が、労働者が労働したことの対価として報酬を支払う契約」のことをいい、法律上は合意だけで効力が発生するのがルールです(民法第623条)。
労働契約法では「労働者と使用者は労働契約の内容についてできる限り、書面により確認するものとする」として、会社は雇用契約書を「作成することが望ましい」とされていますが、雇用契約書を作成しなくても会社が罰を受けることはありません。
雇用契約書と労働条件通知書の違い
雇用契約書と似た書類に「労働条件通知書」があります。
「労働条件通知書」は、労働する場所や時間、給料等の条件を記載した書類で、内容は雇用契約書とほぼ同じです。
しかし、労働条件通知書は、労働基準法で「入社時に労働条件について書面で明らかにしなければならない」と定められており(同法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条)、会社は従業員に労働条件通知書を交付することが義務付けられています。
もし、会社が労働条件を書面で明示していない場合は、30万円以下の罰金が科されることになります。
雇用契約書が会社と従業員が契約の条件をお互いに合意して署名押印する書類なのに対し、労働条件通知書は、会社が従業員に対して雇用条件を一方的に通知する書類であるという違いがあります。
しかし、雇用契約書と労働条件通知書は、記載された労働条件に関する内容は同じなので、雇用契約書を取り交わせば、労働基準法が求める署名による労働条件を明示するという義務もクリアすることができます。
雇用契約書に書くべき事項
雇用契約書には労働条件を記載しますが、会社が書きたいことだけを書けば良いわけではありません。雇用契約書には、必ず書くべき事項が法律で定められています(労働基準法第15条)。
1.絶対書かなければいけない5つの事項(絶対的明示事項)
書面で明示して交付しなければいけない内容を「絶対的明示事項」といいます。雇用契約書には、絶対的明示事項として、以下の5つの内容を必ず記載します。
①労働契約の期間
労働契約に期間の定めがあるか否かについて記載します。
正社員であれば、通常は期間の定めのない雇用形態となります。契約社員やパート・アルバイトの場合は、雇用期間の定めがある契約になるので、その旨を記載することになります。
②就業場所・業務の内容
事業所などの勤務場所と、職種を含めた業務の内容について記載します。
基本的には入社直後の就業場所や職種を記載すれば問題ありません。
転勤や職種異動の可能性がある場合は、将来のトラブル防止のために、会社の転勤・異動命令に従う必要がある旨を合わせて記載しておくことをおすすめします。
③始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する事項
勤務開始時間と終業時間、所定労働時間を超える労働の有無を明記します。
フレックスタイムやシフト勤務などを採用する場合は、その勤務時間についても記載しておきましょう。
休憩時間、休日、年末年始休暇などは法律に則って記載するよう注意が必要です。
交替制勤務をする場合には、交替の期日や順序に関しても記載する必要があります。
④賃金の決定・計算・支払方法等に関する事項
給与金額、給与の計算方法(月給制・日給制・時給制など)、給料日、支払方法(手渡し・振り込みなど)を明示します。指定の給料日に遅れると遅延損害金が発生するので、給与の支払い日には遅れないよう注意が必要です。
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)
退職時の申し出方法、退職希望日を申し出る期限、解雇の条件について明示します。
解雇の条件については、懲戒解雇など規定が多くなりがちで就業規則に必ず記載する事項なので、「就業規則の定めによる」と記載してもよいでしょう。
なお、上記の労働条件は、従来は書面による明示が必要でしたが、2019年4月から、従業員が希望した場合は FAX・メール・LINEのようなSNSメッセージ等(出力して書面を作成できるものに限る)で明示してもよいことになりました。
2.書面にせず口頭でもよい9つの事項(相対的明示事項)
口頭での説明も認められるけれど十分に説明すべき事項、できれば書面化した方が望ましい事項を「相対的事項」といいます。雇用契約書には、可能な限り、これらも盛り込んでおくことが大切です。
①昇給に関する事項
昇給の有無や、昇給がある場合の基準や条件、時期を記載します。
②退職手当に関する事項
退職手当金の制度の有無、退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当が支払われる場合の金額の算出方法、支払い方法、支払い時期などを記載します。
③臨時に支払われる賃金・賞与など に関する事項
業績に応じて支払われる賞与・ボーナスや報奨金等の制度の有無、ある場合の回数、基本給何カ月分など基準がある場合はその旨を記載しておきます。
④労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
社員食堂がある場合は利用負担額を記載します。また、業務を遂行する際に必要な道具や制服の購入費が発生する場合は、その旨を記載します。
⑤安全衛生に関する事項
会社側は、従業員の安全や健康の確保のために、労働基準法・労働安全衛生法に基いて就業規則を定め、健康診断を年に一度受診させるなどの対応を取ることが義務付けられます。就業前の機材の安全確認などが必要な場合はその旨も記しておきましょう。
⑥職業訓練に関する事項
会社の規定に職業訓練の受講などがある場合は記載します。
⑦災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
従業員が勤務中に怪我をした場合や、病気になった場合に、会社がとるべき補償制度(療養・傷害・休業・遺族補償など)について記載します。
⑧表彰、制裁に関する事項
表彰や制裁の制度がある場合は記載します。表彰の例としては、会社や社会への貢献や勤続年数に応じた表彰などが挙げられます。
⑨休職に関する事項
産休や育休などの法定の制度以外に、誕生日休暇等の会社固有の休職制度がある場合は記載しておきましょう。
正社員の雇用契約書の雛形
雇用契約書は、雇用契約の内容や就業規則に応じて変わります。就業規則の内容と異なる雇用契約を締結すると将来的なトラブルの原因となり、就業規則の条件を下回る部分の労働契約は無効と判断される可能性があります(労働契約法第12条)。
雇用契約書の雛形(テンプレート)を紹介しますが、あくまでも参考にとどめ、ご自身の会社の就業規則や、個別の契約内容に応じてアレンジしてください。
株式会社●●(以下「甲」という)と、●●(以下「乙」という)は、以下の通り雇用契約を締結する。
甲、乙は上記の通り契約成立を確認し、各自1通を保管する。 ●●●●年●月●日 甲 住所 東京都●●区●●町●●
氏名 株式会社●●●● 印 乙 住所 東京都●●区●●町●● 氏名 ●● ●● 印 |
厚生労働省は労働条件通知書のモデル書式を公開しているので、併せて参考にしてみてください。
雇用契約書を作成するときの注意点
雇用契約書は、会社と従業員が契約の条件をお互いに合意して署名押印する書類なので、作成する場合は、双方が契約内容を理解して合意したことを証明するために、署名押印して2通作成し、会社と従業員の双方が1通ずつ保管しましょう。
後々雇用条件を巡って従業員との間でトラブルが発生した場合に、雇用契約書が存在していれば、双方が合意した証拠になります。
正社員の雇用契約書
正社員の雇用契約書はほとんど見直しをしていないという会社も多いですが、画一的な働き方を想定した内容では、社会の現状に合わないケースもありますので、アップデートを目的とした確認は定期的に行うことをおすすめします。
特に多いトラブルとしては、求人票や面接時に聞いていた内容と提示された労働条件が違うといったものです。
求人票と提示する条件が異なる場合は、事前に説明を行った上で雇用契約書を交わすことで入社後のトラブルや早期退職を回避できる可能性が高まります。
アルバイト・パートの雇用契約書
パート・アルバイトに対しても、雇用契約書は必ず作成しなくてはいけません。
パート・アルバイトは、正社員と異なり、雇用期間に定めがあり、労働時間も短いのが通常です。給与は時給制であることが多いのも特徴です。
パート・アルバイトの雇用契約の記載事項は、基本的には正社員と同じですが、特に契約期間・契約更新の有無・契約更新の条件についてはトラブルの原因になりやすいため、必ず明示しましょう。
加えて、パートタイム労働法では、以下の4点を明示することが義務付けられています。これに違反した場合は10万円以下の罰金が科されることになります。
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 短時間就労者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
※ここでは、雇用契約書や労働条件通知書など、労働基準法で定められた労働条件を書面で明示した書類をまとめて「雇用契約書」として説明しています。
契約社員の雇用契約書
契約社員に対しても、雇用契約書は必ず作成しなくてはいけません。
パート・アルバイトと同じく雇用期間に定めがあるため、契約期間・契約更新の有無・契約更新の条件については必ず明記しましょう。
契約を更新する際は、改めて契約を交わすことになるので、その都度労働条件を明示する必要があります。
また、契約を自動的に更新することで、雇い止め時に無期雇用契約に準じた手続きが必要となるケースや、契約が通算5年を超えると無期雇用契約に転換する必要があります(※本人の希望による)。
意図せず有期雇用契約のメリットが享受できないといったことのないよう、契約の更新については特に注意して対応しましょう。
契約社員との雇用契約については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご確認ください。
※ここでは、雇用契約書や労働条件通知書など、労働基準法で定められた労働条件を書面で明示した書類をまとめて「雇用契約書」として説明しています。
労働条件通知書はメールやSNSでも交付できる
以前、労働条件通知書の交付は、実際に紙で書面を交付する方法で行わなければならないとされていました。
もっとも、2019年4月1日に労働基準法が改正されたことによって、現在では、本人の希望があればメールやSNS等の電子的方法での交付も可能となりました。
なお、これは、あくまでも本人の希望がある場合に可能なものなので、本人が書面の交付を希望した場合には書面で交付する必要があることには留意が必要です。
雇用契約書や労働条件通知書に関するトラブル例と対処法
雇用契約書や労働条件通知書に関してよくあるトラブルとそれへの対処法についてご説明します。
①雇用契約書がない場合の労働条件の確認方法
企業には雇用契約書の作成が義務付けられていないため、就職先の企業によっては雇用契約書がないという可能性もあります。
他方で、労働条件通知書を交付することは企業に義務付けられているため、雇用契約書も労働条件通知書もないということはないはずです。
そのため、雇用契約書がない場合には、労働条件通知書で労働条件を確認するようにして下さい。
②雇用契約書の内容と就業規則の内容が異なる場合
雇用契約書の内容と、業規則の内容が異なる場合には、労働者に有利な内容が優先されることになります。
労働契約法第12条では、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」と定められています。
そのため、実際にサインした雇用契約書の内容が就業規則よりも労働者にとって不利なものであった場合、労働者としては、就業規則の基準で取り扱うよう企業に求めることができます。
③雇用契約書や労働条件通知書を紛失等した場合
雇用契約書や労働条件通知書を受け取ったものの、紛失した等の理由で確認ができなくなった場合、まずは企業に相談して再発行をお願いすることが考えられます。
もっとも、これは心理的に難しいという場合、内定通知書等に労働条件が記載されていないか確認してみる方法もあり得ます。
または、就業規則を確認し、認識していた労働条件との違い等あれば会社に問い合わせてみましょう。
雇用契約書の作成を弁護士に依頼するメリット・デメリット
雇用契約書の作成を弁護士に相談するメリットとして以下の3点があります。
- 雇用契約の内容の適法性をチェックしてもらえる
日本では、労働基準法をはじめ労働者を保護する法律が整備されています。法定労働時間や残業代、解雇の条件や有期雇用契約の労働者の不利な扱いの禁止など、雇用契約上も注意すべき事項は多くあります。弁護士に相談・依頼すると、雇用契約の内容が法律に違反していないか、リーガルチェックを受けることができます。
- 従業員の雇用形態に合致した雇用契約書を作成やアドバイスが受けられる
正社員・パート、アルバイトなど、雇用形態によって雇用契約書に記載すべき内容は異なります。特に有期雇用契約については、一定条件をクリアした有期雇用社員に無期転換を申し込む権利が発生する制度である「無期転換ルール」が認知されてきたことにより、雇用条件への関心が高まっています。こうした雇用形態別の状況や、会社ごとの就業規則の内容を踏まえて、適切な雇用契約書を作成してもらったりアドバイスを受けたりすることができます。
- 雇用契約書の作成や適法性の判断を任せて業務に集中できる
雇用契約書の作成は、適法であることを前提に、自社の就業規則や、従業員の雇用形態を踏まえて作成することが求められます。また、将来的な労使間トラブルの発生を未然に防ごうと思うと、作成に係る負担は大きくなりがちです。法律の専門家である弁護士に相談・依頼すれば、そうした法的側面や書類作成を任せ、万一トラブルが発生した場合に備えることができるので、経営陣が本来の業務に集中できるというメリットがあります。
一方で、弁護士に相談・依頼する場合には、費用がかかります。弁護士の相談費用の目安としては、30分5000円、1時間1万円程度が相場です。雇用契約書の作成については、5万円~10万円が目安といえますが、複雑でボリュームが大きい場合は20万円以上かかる場合もあります。
ただし、弁護士費用については事務所によってかなり差があることから、まずは法律相談などを利用して、見積もりを依頼してみることをおすすめします。
まとめ
今回は、雇用契約書の作成方法について、正社員の場合、パート・アルバイトの場合の注意点などについて解説しました。
雇用契約書は、雇用形態に応じて記載すべき内容が異なるので、書くべき内容を適切に記すことが大切です。
東京スタートアップ法律事務所では、豊富な企業法務の経験に基づいて、お客様の会社の状況に合った雇用契約書の作成やご相談に対応しております。また、雇用契約書の作成にとどまらず、実際に労使間トラブルが生じた場合の対応や、就業規則整備など、全面的なサポートが可能です。雇用契約書の作成方法をはじめとする相談等がございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。
- 得意分野
- 企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
- プロフィール
- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務