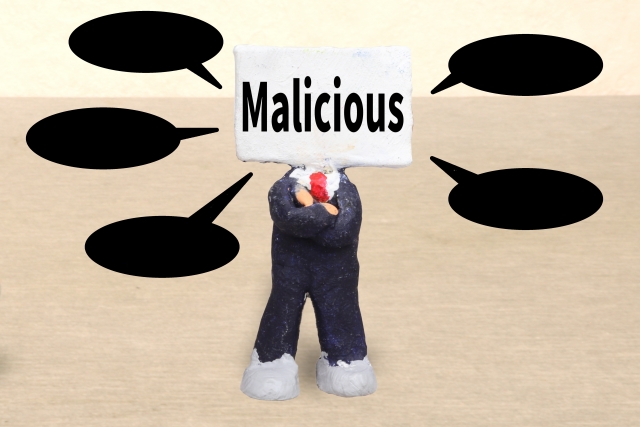クレーム対応を弁護士に依頼するメリットとは? 相談すべき状況について解説

相談
面談無料
東京スタートアップ法律事務所まで
記事目次
近年、顧客による悪質なクレームや、いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が社会問題化しています。
具体的には、クレームに際して担当者へ暴言を吐く、物を投げつけるなどの暴力行為、不当な金品の要求、執拗な長時間の苦情や土下座の強要、SNSへの晒し行為といった、常軌を逸した例が報告されています。
このような悪質クレームは、従業員の就業環境を害し心身に大きな不調をもたらすだけでなく、企業にも重大な時間的・経済的損失を与えるものです。スタートアップ企業などでも、悪質なクレーム対応に過度な時間と労力を割かれ、本来の業務に支障が出てしまうケースが少なくありません。
執拗なクレーム対応に追われて本業に手が回らない――
そのようなお悩みを抱えていないでしょうか。
悪質なクレームへの対処においては、早めに専門家である弁護士に相談することが非常に効果的です。
自社では解決できず延々と続いていたクレームでも、弁護士に対応を依頼することで迅速に解決できるケースが多いです。
本記事では、クレームの中でも正当な主張と悪質なクレームの違い、そして弁護士に依頼すべき状況や弁護士に依頼するメリットについて解説します。
クレームとは
クレームとは、法律上の定義がある訳ではありませんが、一般的には、企業の提供する商品やサービスに対して、顧客から寄せられる苦情や要求のことをいいます。
多くの企業では、お客様対応の一環としてクレーム対応を行い、顧客の不満を解消するとともにサービスの改善につなげています。適切に対応されたクレームは、企業にとって貴重なフィードバックとなり得ます。
もっとも、悪質なクレームは、その対応のために、企業に対して時間的・経済的に多大なリソースの費消をもたらすことになります。
正当な主張と悪質なクレームの違い
では、正当なクレームと悪質なクレームの違いはなんでしょうか。
一般に、社会通念上妥当と認められる範囲の苦情や要望であれば、それは正当なクレームと言えるものが多いです。
例えば、商品の欠陥や、サービスの不備に対する改善要求や適切な補償の要求は、企業側も真摯に受け止め対応すべき正当な主張と言えます。
こうした正当なクレームの中には、結果的に商品やサービスの改善・改良につながる有益な指摘も含まれます。
一方で、悪質なクレームとは、一般的にはその要求やクレームの態様が社会通念や法の範囲を逸脱したものをいいます。
悪質クレーム(カスタマーハラスメント)は、端的に言えば顧客等からの著しい迷惑行為です。具体的には、担当者への暴言・恫喝、執拗な長時間のクレーム、因縁をつけて過大な金銭や物品を要求する行為、土下座の強要など、その内容は度を超えています。
これらはもはや企業への苦情対応の域を超えて、嫌がらせや恐喝に近い行為であり、企業側の誠意ある対応では解決が難しいのが実情です。
悪質なクレーマー(いわゆるモンスタークレーマー)は最初から正当な解決を求めておらず、理不尽な要求を通そうとすることや、企業や担当者を必要以上に困らせること自体が目的となっている場合もあります。
正当なクレームには誠意をもって対応することが重要ですが、悪質なクレームに対しては企業として毅然とした対応を取る必要があります。
近年はこのような悪質クレームへの対策が「カスタマーハラスメント対策」として各企業の重要課題となっており、厚生労働省が対応マニュアルを公表するなど社会全体で取り組みが進んでいます。
クレーム対応を弁護士に依頼すべき状況
悪質クレームは、対応の失敗が単なる顧客トラブルにとどまらず、企業の評判リスク(レピュテーションリスク)・法的リスクに直結するケースもあります。
近年は、SNSや動画配信サービス等を通じて、クレーム対応の一部始終を録音・録画され、一方的に編集された上で公開されるケースも増えています。
このような「晒し型カスハラ」は、企業のブランドイメージを大きく損なう恐れがあります。
場合によっては、炎上騒動にまで発展し、取引先や顧客の信頼を失いかねません。
また、カスタマーハラスメントの対応を誤ると、労働問題へ波及するリスクもあります。
従業員が心身に不調をきたし、休職や離職を余儀なくされれば、企業にとって大きな人的損失となります。
さらに、企業がクレーム処理の体制を整えていない場合、「安全配慮義務違反」として損害賠償請求の対象となることもあります。
このように、クレーム対応は単なる「顧客満足の問題」ではなく、「企業の持続可能性を左右する経営課題」でもあるのです。
だからこそ、法的な知見と冷静な判断が求められる場面では、専門家である弁護士を活用し、適切な対応を構築していくことが非常に重要です。
では、企業がどのような状況になったときに「弁護士に相談・依頼すべき」と判断すべきでしょうか。
一般的なクレーム対応の範囲を超えており、社内だけでは解決が難しい以下のようなケースでは、早期に弁護士への相談を検討するのが望ましいです。
クレームの頻度が多い・執拗に要求を繰り返す
クレームの頻度や執拗さが異常なケースは、弁護士に依頼を検討すべき状況の一つです。
例えば、非常に神経質なクレーム客が次々と要求を変えながら頻繁に電話やメールを送り続けてくるケースがあります。
あるいは、些細なミスをことさらに取り上げ、過大かつ対応困難な要求を執拗に繰り返すような場合もあります。
このようにクレームが延々と続いて解決が見えない状況では、社内でどれだけ丁寧に対応しても相手が納得する可能性は低く、対応にかける労力ばかりが増大してしまいます。むしろ、クレーム対応に社内の人員と時間を取られるほど本来業務に支障が出てしまい、二次的な損失が広がる恐れもあります。
クレーム対応が長期化・常態化している場合は、弁護士という法律に精通した第三者に間に入ってもらい、法的な視点で早期に決着を図ることを検討すべきタイミングと言えるでしょう。
暴言・暴力・不当な要求をされている
クレーム対応の中で暴言や威圧的な言動、あるいは物理的な暴力に及ぶ兆候がある場合は、直ちに弁護士への相談を検討すべきです。
実際に人格を否定する暴言を浴びせたり、怒って物を叩きつける・投げるといった行為は、もはや通常のクレーム対応の範囲を超えています。
また、「賠償金として◯◯万円支払え」「担当者を土下座させろ」といった不当な要求も同様です。
このような行為は従業員の心身に深刻な負担を与えるだけでなく、場合によっては脅迫罪や強要罪などに該当する可能性すらあります。
企業側だけで対応し続けるのは危険な場合もあり、早期に法律のプロである弁護士を介入させることで、法に則った毅然とした対応(例えば、必要に応じて警告や法的手段など)を取ることもできます。
弁護士が窓口に立つことで、クレーマー側もこれ以上エスカレートすれば法的な不利益が及ぶと認識しやすくなり、事態の沈静化が期待できます。
損害賠償請求をされている
クレームの結果、損害賠償を請求されている場合も、速やかに弁護士に相談すべき状況です。
具体例としては、自社の商品・サービスが原因で相手に経済的損失や健康被害を与えてしまい、賠償金を要求されているケースが典型例です。
損害の発生が事実であれば適切な補償は必要ですが、その額や範囲については法的に妥当なラインがあります。
法外な金額を要求されている場合や、自社に過失があるか不明な段階で高額な賠償を迫られている場合、法律の専門家の判断が不可欠です。
この点、弁護士であれば、請求の法的根拠や適否を判断し、正当な範囲での賠償交渉を行うことができます。
自社だけで対応して安易に要求に応じてしまうと、必要以上の支払いをしてしまったり、後から次々と追加要求を受けるリスクがあります。
逆に正当なクレームであるのに放置すれば、訴訟に発展して損害が拡大する恐れもあります。
損害賠償が絡むクレームについては、早期に弁護士に相談し、適法かつ適切な対応方針を立てることが重要です。
クレーム対応を弁護士に依頼するメリット
上記のような場面でクレーム対応を弁護士に依頼すると、企業としてさまざまなメリットがあります。逆に言えば、無理に自社対応を続けることによるデメリットを回避できるとも言えます。
クレームは、対応が場当たり的になってしまうことで問題が深刻化するケースが少なくありません。そこで、企業としては、単に起きたクレームにその都度対応するのではなく、あらかじめ想定されるクレーム事案への対応方針や、社内のエスカレーションフローを明確に定めておくことが重要です。
弁護士は、過去の判例や他社の対応事例を踏まえた上で、貴社にとって実効性のあるクレーム対応マニュアルや社内ガイドラインの整備をサポートすることも可能です。また、従業員向けの対応研修や、リスク対応時の初動対応の指導など、日常的な体制強化の面でもお手伝いできます。
日常の業務に追われていると、「今はまだ問題が顕在化していないから後回しでよい」と判断しがちですが、クレームは突発的かつ予測不可能なかたちで現れるものです。いざというときに慌てないよう、弁護士と連携して、平時から備えを講じておくことが企業防衛として非常に有効です。
ここでは、弁護士に依頼する主なメリットを5つご紹介します。
法に則った対応ができる
弁護士に依頼する最大のメリットの一つが、法律のルールに則った対応ができることです。
自社でクレーム対応を行う場合、どうしてもお客様対応として相手に寄り添った姿勢を取らざるを得ず、理不尽な要求にもある程度譲歩してしまいがちです。
クレーマー側も「お客様は神様だ」という前提で接してくるため、企業側が「法律ではこのようになっています」と正論を述べても、「法律の話をしているわけじゃない!」などと怒りをエスカレートさせる場合も多いです。
また、場合によっては「誠意を見せろ」「筋を通せ」といった法律とはかけ離れた主張で非難されるおそれもあります。
しかし、弁護士であれば、そもそもクレーム相手の要求が法的に妥当な主張かどうかを判断できるため、クレーム相手との間の理不尽な要求に対して、対等な立場で話し合うことが可能です。
弁護士は法律の専門家として客観的に事案を把握し、あくまで法的に自社が負うべき責任範囲に限って対応します。
したがって、法的根拠のない過剰な要求については毅然と断り、必要であれば判例や条文を示して反論することで、ルールに基づいた解決へと導くことができます。
企業にとって不当な要求を受け入れてしまうリスクを減らし、適正なラインで問題を収束させることができる点で、弁護士に依頼する意義は大きいと言えるでしょう。
第三者として客観的な立場からの意見・交渉ができる
弁護士が介入することで、第三者ならではの客観的な視点でクレーム対応が行えます。
社内の担当者だけでクレーム対応を続けていると、どうしても感情的になってしまったり、冷静な判断が難しくなることがあります。
また、クレーム相手にとっても、例えば単に謝罪を繰り返し直接的な解決案を提示する権限のない担当者などと直接やり取りするより、外部の法律のプロが間に入った方が、具体的な解決に繋げられるというメリットがあります。
実際、企業の担当者が「法律ではこうです」「過去の裁判例でもそのような要求は認められていません」などと説明しても、相手はなかなか納得しないかもしれません。
しかし、弁護士が間に立ち、法律や裁判例に基づく筋道だった説明をすることで、初めて相手も冷静に聞く耳を持つ可能性があります。
説得力のある説明ができるという点は、弁護士に依頼する大きなメリットです。弁護士は法律の専門知識だけでなく交渉のプロでもありますので、感情的な対立を避けつつ客観的事実に基づいた主張を展開し、円満な解決に向けた交渉を進めることが可能です。
また、弁護士が介入することで企業側・顧客側双方に「第三者が入っている」という緊張感が生まれます。
これにより、顧客側も感情的なエスカレートを自制しやすくなり、企業側も冷静に対応方針を検討できるようになります。結果として、問題解決への道筋が立てやすくなるでしょう。
合意書の締結等により将来のトラブルを防止できる
弁護士に依頼することで、最終的な解決策を法的に確実な形でまとめることができます。
クレーム対応の結果、こちらが何らかの金銭支払いをしたり、商品の交換・修理対応をする場合には、必ず「これ以上の請求はしない」といった清算条項を盛り込んだ合意書(和解書)を取り交わす必要があります。
この合意書の内容が不十分だと、せっかく一度は解決したはずのクレームが再度蒸し返され、「やはり納得できない。もっと補償しろ」と追加の要求を受けてしまうリスクがあります。そうなれば、また対応に追われるという堂々巡りに陥ってしまいかねません。
弁護士はこのような合意書の作成について専門的なノウハウを持っています。
解決にあたっては、将来にわたって紛争を蒸し返させないための条項を盛り込んだ合意書を用意し、双方に署名・押印してもらうことが重要です。弁護士が間に入れば、法律上、有効かつ漏れのない和解条項を整えることができるため、後になって「聞いていない」「そんな約束は無効だ」などと言われるリスクを低減できます。
また、合意書を交わしておけば、仮に相手が後から不満を言い出しても「契約上それ以上の請求はできないはずです」と毅然と対応できます。将来のトラブルを防止し、「真の意味での問題解決(紛争の終結)」を図るためにも、弁護士による最終合意書の締結サポートは大きなメリットです。
スムーズな解決が可能となる
弁護士に依頼すると、クレーム問題の早期解決が期待できる点もあります。
自社だけで対応していると、相手のペースに巻き込まれてやり取りが長期化し、「いつになったら終わるのか…」と担当者が疲弊してしまうケースがあります。
しかし、弁護士が対応を代行することで、それまで延々と続いていたクレームが意外なほど早く収束に向かうことがあります。
弁護士が事実関係を整理し法的に論点を絞って交渉するため、話が堂々巡りすることなく核心的な解決策の提示へと進みやすくなるためです。
また、弁護士が介入した途端にクレーム客の態度が軟化し、要求を取り下げてくることも少なくありません。
「今後は弁護士が対応しますので、直接の連絡はお控えください」と通知することで、クレーム客とのやり取りの窓口を一本化できます。
これにより、社内の誰それに執拗に電話がかかってくる、といった事態も収まり、問題解決までのプロセスがスムーズになります。
弁護士という第三者が入ることでクレーム客に心理的圧力がかかり、「これ以上ごねても無駄だ」と悟って矛を収めるケースもあるのです。
さらに、弁護士は解決に向けた具体的な手段(内容証明郵便による警告や、必要に応じて訴訟提起の準備など)を迅速に講じることができます。解決までの道筋が明確になり、結果的に問題の長期化を防ぐことにつながります。
企業の心理的負担や労力を削減できる
弁護士への依頼は、企業側の心理的負担や時間・労力の大幅な削減にも直結します。
繰り返しになりますが、悪質なクレーム対応に社内の人員を貼り付け続ければ、本来やるべき業務がおろそかになり、業績にも悪影響が出かねません。いくら労力と時間を割いても解決できないクレームに振り回されていては、他の重要な仕事に支障が出てしまいます。
そうして疲弊した結果、新たなミスやクレームが発生してしまっては本末転倒です。
弁護士に依頼することで、従業員への負担を減らすことが可能です。
一旦弁護士に任せてしまえば、以降の対応はすべて弁護士が窓口となりますので、社内の担当者は本来の業務に集中できます。
また、やや内容は重複しますが、現場担当者のストレスからの解放というメリットも見逃せません。理不尽なクレームへの対応を続けていると、担当者は次第に強いストレスを感じるようになります。
仕事である以上はある程度のストレスは避けられませんが、もし社内のクレーム処理が職場のストレスの大半を占めているとしたら、従業員の労働管理や健康管理の点からも、すぐに解決すべき問題といえます。
そのようなクレーマー対応は弁護士に任せることで、担当者からストレスの大部分を取り除くことができます。
従業員の精神的負担が減れば、職場環境も大きく改善され、生産性の向上や人材流出の防止にもつながります。
つまり、従業員を守るという意味でも、弁護士に依頼する意義は大きいのです。
当事務所がサポートできること
東京スタートアップ法律事務所では、以上のようなクレーム対応に関するお悩みに対し、企業の代理人として法的なサポートを提供しています。
具体的には次のようなサービスを通じて問題解決をお手伝いします。
交渉代理:
弁護士が貴社の代理人としてクレーム相手との交渉窓口になります。
以後の連絡や要求はすべて弁護士経由となるため、担当者の方が直接対応する必要はありません。法律の専門家が間に入ることで、法的に筋の通った主張を行い、有利な解決へと導きます。
合意書(和解書)作成:
解決にあたって取り交わす合意書の作成をサポートします。
弁護士が和解書を作成することで、将来にわたりクレームが蒸し返されないよう万全の内容にすることが可能です。金銭の支払いなどが伴う場合でも、「これ以上一切請求しない」ことを明文化し、紛争の終結を確実なものとします。
クレーム対応に関するアドバイス:
悪質なクレームへの初期対応方法から社内対応の見直しまで、幅広くアドバイスいたします。
現在直面しているクレーム事案についての具体的な対処法はもちろん、再発防止のための社内ルール整備などについても弁護士の視点で助言いたします。
クレーム対応でお困りの場合は東京スタートアップ法律事務所まで
悪質なクレーム対応は、企業にとって大きな負担であり頭痛の種です。
しかし、一人で悩む必要はありません。
クレーム対応に強い弁護士に相談することで、必ずや解決への道が開けます。
東京スタートアップ法律事務所には、企業のクレーム対応に精通した弁護士が在籍しており、スタートアップ企業から中小企業まで多数のご相談・ご依頼を承ってきた実績があります。
法的に適切な解決策の提案はもちろん、経営者や担当者の精神的負担を軽減する心強いパートナーとしてサポートいたします。
悪質なクレーム対応でお困りの際は、ぜひ東京スタートアップ法律事務所までお気軽にご相談ください。
貴社の状況に応じた最善の対処法をともに考え、迅速・円満な問題解決を実現いたします。相談予約やお問い合わせはお電話・メールで承っておりますので、まずは一度ご連絡ください。貴社を悩ませるクレーム問題を解決するため、私たちがお力になります。
相談
面談無料
東京スタートアップ法律事務所まで
- 得意分野
- 企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
- プロフィール
- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務