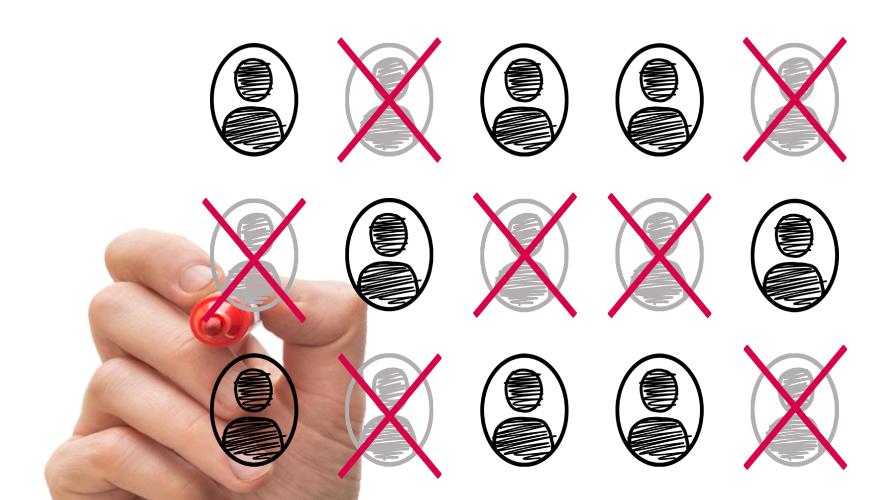事業場外みなし労働時間制における残業代の取り扱いと注意点を解説

全国20拠点以上!安心の全国対応
記事目次
事業場外みなし労働時間制は、事業場外の施設で従事する時間は使用者の具体的な指揮監督が及ばず、実労働時間の算定が困難なため、労働者が予め定めた所定の労働時間働いたとみなす制度です。新型コロナウイルス拡大防止のために導入する企業が急増したテレワークとの相性が良いことでも知られていますが、残業代の扱いを巡り、労使間のトラブルに発展することもあるため注意が必要です。
今回は、事業場外みなし労働時間制の概要や採用の条件、フレックスタイム制や裁量労働制との違い、残業代・休日出勤・深夜手当等の扱い、採用する際に注意が必要なポイントなどについて解説します。
事業場外みなし労働時間制とは
事業場外みなし労働時間制は、外回りの営業職、旅行会社の添乗員、新聞記者等、会社の外(事業場外)での業務が多い職種で労働時間の算定が難しい場合に採用できる便宜的な労働時間の算定制度です。テレワークや在宅勤務との相性も良いと言われていますが、導入するためには一定の要件を満たす必要があります。事業場外みなし労働時間制の概要と導入の要件について説明します。
1.事業場外みなし労働時間制の概要
事業場外みなし労働時間制は、事業場外(社外)で業務に従事し、労働時間の算定が困難な場合に、一定の労働時間働いたものとみなすことができる制度です(労働基準法38条の2第1項)。
法律用語の「みなす」とは、性質の異なる事柄を法律上、同一のものとして扱うという意味です。例えば、みなし労働時間が1日8時間とされていた場合、実際に働いた時間に関わらず8時間働いたものとして扱うことになります。極端な例を挙げると、営業職が7時間程度の勉強会のために遠方の顧客先を訪問した際、顧客の事情により勉強会が急遽中止となり実働時間がほとんどなかった場合でも、8時間働いたものとして扱われます。
2.導入が認められる要件
事業場外みなし労働時間制を導入するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事したこと
- 労働時間の算定が困難であること
「労働時間を算定し難いとき」については、使用者の労働者に対する具体的指揮監督権が及んでいるかに否かにより判断され、業務時間、場所、業務内容に関する労働者の裁量の幅や会社からの指示や管理の程度等の事情が考慮されます。社外での労働だとしても、会社からの指揮監督が及び、労働時間の算定が可能である場合には、事業場外みなし労働時間制の適用は認められません。事業場外みなし労働時間制の適用が認められない具体例として、以下のようなケースが挙げられます。
- 使用者の支持を受け、その指示通りにルートセールスをし、業務終了後は会社に戻り、その日の訪問先と訪問時間を日報に入力することが義務付けられている
- 外勤中心の営業職で直行直帰が認められているが、会社から支給された携帯電話を所持し、常時、携帯電話で上司の指示を受けながら業務を行っている
- 在宅勤務が認められているが、在宅勤務中は勤務管理システムの「着席」ボタンをクリックすることが求められており、作業中のPC画面がランダムに撮影されるなどシステムにより監視されていて、自由に会社との通信を切断することができない
上記のようなケースでは、労働時間の算定が困難であるとは言えないため、事業場外みなし労働時間制の適用は認められません。
フレックスタイム制・裁量労働制との違い
事業場外みなし労働時間制と似ている制度として、フレックスタイム制、裁量労働制などが知られています。これらの制度の違いを知りたいという方もいらっしゃるかと思いますので、各制度の概要と違いについて説明します。
1.フレックスタイム制との違い
フレックスタイム制は、一定の清算期間(1か月以内で労使協定で定めた期間)の総労働時間を予め決めておき、その清算期間内で日々の始業・終業時刻や労働時間を従業員が自由に決定できる制度のことです(労働基準法第 32 条の 3)。一般的には、必ず出勤する必要があるコアタイムと自由に出退勤できるフレキシブルタイムに分けて運用されます。事業場外みなし労働時間制と同様に、柔軟な働き方ができる制度として知られていますが、異なる点も多いです。
フレックスタイム制は、事業場外みなし労働時間制と違い、1日に所定時間働いたとみなされるわけではないため、清算期間内で決められた総労働時間、働く必要があります。また、事業場外みなし労働時間制は、導入の要件として事業場外で業務に従事することや労働時間の算定が困難であることが求められますが、フレックスタイム制ではこのような要件はないため、内勤の従業員にも適用することが可能です。
2.裁量労働制との違い
裁量労働制は、事業場外みなし労働時間制と同様に変則的な労働に対応するみなし労働時間制の一種です。みなし労働制には以下の3種類があります。
- 事業場外みなし労働時間制:営業職や添乗員等、事業場外で労働する者であって、労働時間の算定が困難な業務(労働基準法第38条の2)
- 専門業務型裁量労働制:研究開発やデザイナー等、業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難な業務(同法第38条の3)
- 企画業務型裁量労働制:事業の運営に関する企画・立案・調査・分析の業務(同法第38条の4)
事業場外みなし労働時間制は、専門業務型・企画業務裁量労働制とは異なり、対象が特定の職種に限定されていません。そのため、全従業員を対象にテレワークや在宅勤務を導入した場合は全従業員に対して適用することも可能です。
残業代・休日出勤・深夜手当等の扱いと注意点
事業場外みなし労働時間制を導入したら残業代は一切払わなくてよいと勘違いしている方もいらっしゃるようですが、それは間違いです。事業場外みなし労働時間制における残業代や休日出勤・深夜労働手当の扱いや注意点について説明します。
1.残業代について注意が必要なケース
事業場外みなし労働時間制では、原則として、所定時間働いたものとみなされるため、残業代の支払いは不要です。従業員が所定時間以上働いたことを証明した場合でも、残業代を支払う必要はありません。
ただし、労働基準法第38条の2第1項但書には、労働者を保護するために、以下のような規定が設けられています。
“当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。”
つまり、所定労働時間が8時間の場合でも、業務を遂行するために平均で9時間半かかるなら、9時間半働いたとみなされるというわけです。この場合、法定労働時間である1日8時間を超過した1時間半分の残業代を支払う必要があります。
2.休日出勤・深夜労働の割増賃金の支払いは必要
事業場外みなし労働時間制を導入している場合でも、休日出勤や深夜労働(22時~翌日5時までの労働)に対しては、基礎賃金に対して以下の掛け率の割増賃金を支払う必要があります。
- 休日出勤:法定休日の労働に対しては35%、それ以外は25%
- 深夜労働:25%
事業場外みなし労働時間制においても、休日出勤や深夜労働の時間を把握して割増賃金を支払う必要があるという点はしっかり認識しておきましょう。
出張中の休日については、使用者からの具体的な指示がなく、自由に休養できる場合は労働時間とみなされないため、割増賃金の支払いは不要です。ただし、休日を挟む出張中は出張先に滞在しなければならず、従業員が仕事のために拘束されているように感じて不満を持つ可能性もあるため、手当や日当等を支給することが望ましいでしょう。
事業場外みなし労働時間制の未払い残業代を巡る裁判例
元従業員が会社に対して未払い残業代の支払いを請求した裁判で、事業場外みなし労働時間制の適用要件である「労働時間を算定し難いとき」に該当するか否かが主な争点となった裁判例を2つご紹介します。
1.営業職の時間外割増賃金を巡る裁判
最初にご紹介するのは、元従業員が退職した会社に対して未払いの時間外割増賃金を請求した裁判例です(東京地方裁判所平成17年9月30日判決)。
この裁判の被告である会社は、原告が営業職であったことから、労働時間を算定するのが難しく、所定労働時間労働したものとみなされるべきだと主張しました。しかし、この会社では、営業日報により訪問先と訪問時間の報告が義務付けられており、また会社から貸与された携帯電話により外勤中の行動が把握されていました。また、会社は営業職と他の職種を特に区別することなく始業時刻、終業時刻を定めており、遅刻・早退については、1時間単位で欠勤扱いとされていました。
裁判所は、そのような状況を総合的に判断し、本件では、原告が自ら労働時間を管理していたとはいえず、労働基準法第38条の2第1項に規定する「労働時間を算定し難いとき」に該当するとは認められないとし、被告である会社に対して、時間外割増賃金の支払いを命じました。
2.派遣添乗員の時間外割増賃金を巡る裁判
次にご紹介するのは、登録型派遣添乗員が派遣元の会社に対して未払いの時間外割増賃金を請求した裁判例です(最高裁判所平成26年1月24日判決)。
原告である添乗員の海外ツアー期間中の労働時間は、原則として8時~20時まで(休憩を除き11時間)で、賃金は日当1万6千円と定められていましたが、実際の労働時間は11時間を超える日もあったそうです。被告である派遣会社は、派遣添乗員の業務は事業場外労働であるという理由で時間外割増賃金の支払いを拒否しました。しかし、この会社では、日程表やマニュアルにより具体的な業務の内容を指示し、これらに従った業務を行うことを命じていました。また、ツアー中には、添乗員に対し、携帯電話を所持して常時電源を入れておき、ツアー参加者との間で契約上の問題やクレームが生じ得る旅行日程の変更が必要となる場合には、会社に報告して指示を受けることを求めていました。ツアー終了後にも、添乗日報等により業務遂行の状況に関する詳細な報告を求めていました。
最高裁判所は、そのような状況を総合的に考慮し、本件が、労働基準法第38条の2第1項に規定する「労働時間を算定し難いとき」に該当するとは認められないと判断し、会社側が敗訴しました。
3.「労働時間を算定し難いとき」の判断基準
上記2つの裁判の原告の職種は、営業職、添乗員と、いずれも事業場外みなし労働時間制に適していると考えられている職種ですが、裁判所は、業務に関する指示、業務報告の体制、勤務の実態等を総合的に考慮した結果、事業場外みなし労働時間制の適用要件である「労働時間を算定し難いとき」に該当すると認めませんでした。
この2つの裁判例は、業務の性質等や業務に関する指示・報告の方法等に照らして、使用者の指揮監督下に置かれており、従業員の自由裁量がほとんど認めらないというケースでは、事業場外の労働であったとしても事業場外みなし労働時間制の適用は認められないことを示しています。
事業場外みなし労働時間制を導入する際の注意点
事業場外みなし労働時間制を導入する際、労使間トラブルを起こさないためにはどのような点に注意すればよいのでしょうか。事業場外みなし労働時間制を導入する際の注意点について説明します。
1.就業規則の整備
事業場外みなし労働時間制は、就業規則の絶対的必要記載事項の一つである始業・終業時刻の定めの例外となるため、就業規則で事業場外みなし労働時間制についての規定を設ける必要があります。
また、残業に関するトラブル防止のために、時間外や休日深夜の労働は原則禁止とし、必要な場合は事前に使用者による許可を得るという規定を設け、就業規則に明記するとよいでしょう。
2.労使協定と労働基準監督署への届出の必要性
事業場外みなし労働時間制を導入する際、労使協定を結ぶことは法律上、必ず必要とされる要件ではありません。労使協定は、労働基準法第38条の2第1項但書に規定されている「みなされる時間」を補完し、労使協定がある場合は労使協定で定める時間を「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とするという位置付けです。
ただし、事業場外労働のみなし労働時間制では、通常必要な労働時間に関する労使間の認識の違いによるトラブルが起こりやすいため、労使協定を締結しておくことが望ましいでしょう。
なお、労使協定で定める「みなし時間」が法定労働時間を超える場合は、労働基準監督署に「事業場外労働に関する協定届」を届け出なければいけません。
3.事業場外勤務と内勤が混在する場合の注意
外勤と内勤が混在する場合、両方の労働時間を合わせて、「みなし時間」と考えることは可能なのでしょうか。原則として、事業場外みなし労働時間制における「みなし時間」は、事業場外(社外)での労働時間のみに適用され、事業場内での労働時間は別途管理することが求められます。例えば、営業職で客先への直行は認められているが、1日の客先訪問が終了した後は職場で日報を入力することが義務付けられている場合、職場での日報入力を行う時間は「みなし時間」とは別に管理する必要があるのです。日報入力を含めた時間を1日の所定労働時間としたい場合、事業場外みなし労働時間を5時間として、所定労働時間を8時間とした労使協定を締結する等の方法もあります。ただし、実態は1日の客先訪問が5時間で終わることは稀で、平均8時間程度かかっていたという場合は、日報入力の時間は法定労働時間を超えることになるため、残業代の支払いが必要です。
まとめ
今回は、事業場外みなし労働時間制の概要や採用の条件、フレックスタイム制や裁量労働制との違い、残業代・休日出勤・深夜手当等の扱い、採用する際に注意が必要なポイントについて解説しました。
近年、事業場外みなし労働時間制の適用要件は厳格化し、残業代を支給せずに長時間労働を強いられた労働者が未払い残業代の支払いを求めて会社を訴えた裁判では、労働者側が勝訴するケースが増えています。事業場外みなし労働時間制を導入する際は、「労働時間を算定し難い」の要件を満たすことが非常に難しいため、労使間トラブルを確実に回避するためにも、労務問題に詳しい弁護士のアドバイスを受けながら慎重に進めることをおすすめします。
東京スタートアップ法律事務所では、労務問題に関する豊富な知識と経験を持つ弁護士が、様々な企業のニーズに合わせたサポートを提供しております。お電話やオンライン会議システムによるご相談も受け付けていますので、労務問題や企業法務に関する相談等がございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。
- 得意分野
- 企業法務、ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設