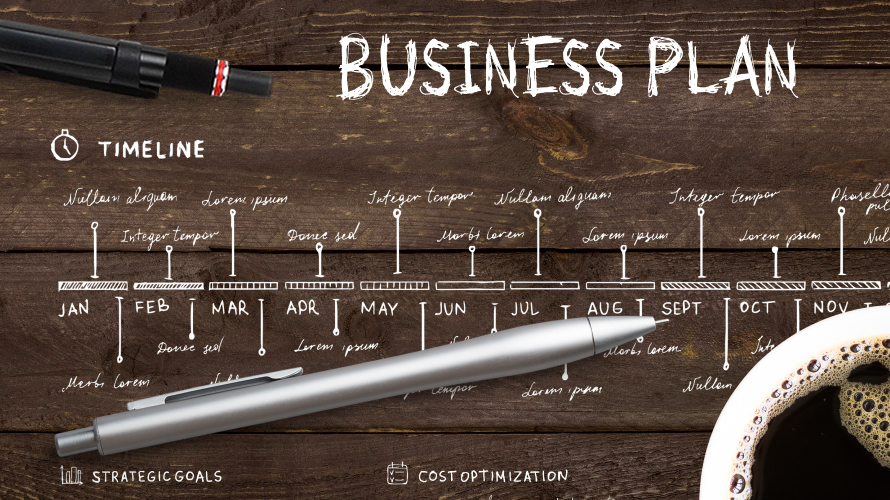2019年から有給休暇義務化|企業が押さえるべき働き方改革と罰則

全国20拠点以上!安心の全国対応
記事目次
近年、「働き方改革」により、労働環境を取り巻く法制度の変更が続いています。労働者が心身をリフレッシュしてワークライフバランスを保つために、2019年4月1日から年次有給休暇(以下「有給休暇」といいます。)の取得が義務化されました。
しかし、正社員やパート職員など、さまざまな働き方をする社員がいると、有給休暇を社員に何日付与すればいいのか、違反した場合はどうなるのかなど、お悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、有給休暇の取得の義務化に対応して、会社側が取るべき対応について解説したいと思います。
2019年から年5日間の有給休暇取得の義務化がスタート
日本では、労働基準法39条で、労働者が有給休暇を取得する権利が定められています。これによると、労働者は、
- 雇入れの日から6か月間継続して雇われていること
- 全労働日の8割以上を出勤していること
という2点を満たしていれば、年次有給休暇を取得できるとされています。
しかし、有給休暇を取得するにあたっては、労働者が使用者(会社側)に請求するのが原則となっていたため、日本では同僚への配慮や仕事を休むことへの後ろめたさから、有給休暇の取得率は、厚生労働省の調査によると2000年に50%を下回って以降、ここ20年は50%前後とほぼ横ばいで推移しており、取得率がなかなか上がっていないのが現状です。
このような状況を改善するため、「働き方改革関連法案」が2018年に成立し、有給休暇の取得についても労働基準法が改正され、より確実に有給休暇を取得できるようになりました。
具体的には、改正前は年次有給休暇を取得させなければならない日数について使用者に義務はありませんでしたが、2019年4月1日から、使用者は10日以上の有給休暇が付与される全ての労働者(管理監督者や有期雇用労働者を含みます。)に対して、年5日間の有給休暇を、時季を指定して取得させることが義務付けられました。
有給休暇取得義務化の対象になる従業員とは
上記のように、有給休暇取得が義務付けられましたが、すべての労働者が対象になるわけではありません。
対象になるのは、有給休暇が10日以上付与される労働者に限られます。つまり、雇い入れられた日から6か月間継続して勤務し、その間の全労働日の8割以上を出勤している労働者が対象になります。
では、契約社員やパート社員はどうなるかなど、具体的な例を見ていきましょう。
1.入社後6か月が経過した正社員・フルタイムの契約社員
フルタイム勤務の労働者であれば、正社員でも有期雇用の契約社員でも、入社後6ヶ月間継続して勤務し、出勤率が8割以上であることを条件に、有給休暇義務化の対象になります。
2.入社後6か月が経過した週30時間以上勤務のパート社員
パートタイム労働者(以下「パート社員」といいます。)であっても、勤務時間が週30時間以上であれば、入社後6か月間継続して勤務し、出勤率が8割以上という条件を満たせば、有給休暇の付与日数が10日となるため、有給休暇取得義務化の対象になります。
3.入社後3年6か月以上が経過した週4日勤務のパート社員
週の所定労働時間が30時間未満で週4日勤務するパート社員であれば、入社後3年6か月間継続して勤務し、直近1年間の出勤率が8割以上であるとの条件を満たすことで、年間10日の有給休暇を取得する権利が生じますので、有給休暇の取得義務化の対象になります。
4.入社後5年6か月以上が経過した週3日勤務のパート社員
週の所定労働時間が30時間未満で週3日勤務するパート社員の場合、入社後5年6か月間継続して勤務し、直近1年間の出勤率が8割以上であることとの条件を満たすことで、年間10日の有給休暇を取得する権利が生じます。この場合にも、有給休暇取得義務化の対象となります。
なお、パート社員の勤務日数が週2日の場合は、有給休暇の付与日数が最大で年7日、週1日の場合は最大で年3日となるので、「有給休暇が10日以上付与される労働者」という条件を満たさず、有給休暇取得義務の対象になりません。
有給休暇取得義務化の内容とは
2019年4月1日からスタートした有給休暇の取得義務化ですが、有給休暇を取得させる方法としては、次の3つがあります。
- 使用者が時季を指定して有給休暇を取得させる
使用者には「労働者ごとに、有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して有給休暇を取得させる」ことが義務付けられました。これは、基準日から1年間に有給休暇消化日数が5日未満の社員には、5日に達するまでの残日数について会社側が日程を指定して有給休暇を取得させなければならないということです。
基準日は有給休暇を会社が付与した日なので、通常は従業員が雇い入れられた日の6か月後の日を指します。例えば、4月1日に入社し、全労働日の8割以上出勤して6か月が経過した場合には、10月1日に有給休暇が付与され、この日が基準日となります。この基準日から1年間に、会社は5日の有給休暇を社員に取得させる義務が生じ、その後も毎年10月1日を基準としてその基準日から1年間に5日の有給休暇の取得義務が生じることになります。 - 労働者が自分の意思で有給休暇を請求して取得する
労働者が既に自らの意思で基準日から1年の間に5日以上の有給休暇を請求して取得している場合は、使用者(会社側)が時季指定をする必要はなく、またすることもできません。ただし、労働者の有給取得日数が5日未満の場合は、5日に達するまでの残日数は使用者が時季を指定して取得させる必要があります。 - 労使協定で、計画的に取得日を決めて有給休暇を取得する(計画年休)
労使協定で、計画的に取得日を決めて付与した年次休暇の日数(計画年休)は、その日数を有給休暇取得義務の対象となる5日から差し引かなければいけません。
有給休暇義務の抜け道になるか?中小企業が取れる2つの対応
働き方改革で行われた法令改正の中には、大企業が先に施行され、中小企業には猶予を与えるものもありますが、有給休暇取得義務化については猶予期間がなく、企業規模を問わずに一律に導入されました。しかし、中小企業の場合は余剰人員がそんなにたくさんいないケースもありますので、労働者(従業員)の有給の取り方によっては、業務の遂行が困難になることもあります。使用者(会社側)としては、次の2つの方法を参考に、対策を考えてみてはいかがでしょうか。
1.個別指定方式
従業員がいつ有給休暇を取得するかを本人の自由に任せることを原則として、従業員ごとに有給休暇の消化日数が5日以上かを確認し、5日未満になりそうな労働者について、会社が有給休暇の取得日を指定する方法です。
メリットとしては、会社は従業員との話し合いで指定日を決めることができるため柔軟性が高く融通がききやすいことがあげられます。
反面、デメリットとしては、従業員ごとの有給休暇の管理に手間がかかること、従業員の自由に任せると、5日に達するまでの残日数分について1年間の期間の終盤にまとめて有給休暇を取得させるなどしなければならないため、業務に支障がおよぶリスクがあります。
2.計画年休制度の導入
会社が従業員代表と労使協定を締結し、従業員の有給休暇のうち5日を超える部分の日程をあらかじめ決めておく方法を「計画年休制度」といいます(労働基準法39条6項)。
この制度のメリットとしては、有給休暇を年5日以上付与した従業員については有給休暇の取得日の指定義務対象外になるため、個別の管理の手間が省けること、業務に支障が少ない時期を踏まえて会社全体や部署別に特定の日を有給休暇にする、従業員ごとに有給休暇の取得日を決めるなどして、様々なパターンで運用できることがあります。
デメリットとしては、従業員代表との話し合いを踏まえた労使協定が必要になり、一度決めた有給休暇取得日は、会社都合で変更できないため、業務の見通しが立てにくい場合にはかえって運用が硬直的になることがあります。
3.中小企業が取るべき方法は?
中小企業がどちらの方法を取るべきかについては、会社の状況によっても異なります。
既に従業員の多くが年5日以上の有給休暇を取得しているような会社では、従業員の自由に任せる範囲が広い個別指定方式が向いていると言えるでしょう。有給休暇の取得が5日未満の従業員にのみ個別に有給休暇取得日を指定できるので、会社としても柔軟な対応ができるからです。
一方、従来有給休暇の取得率が低く、多くの従業員が年5日以上の有給休暇を取得していないような会社では、計画年休制度のほうが向いていると言えます。労働者の自由に任せていると、有給休暇を取得しないまま期限が迫り、まとめて休むことで業務に支障が生じるリスクが高まるため、あらかじめ労使協定に基づいて年末年始など休みやすい時期に有給休暇を消化させるなどの対応を取ることができるからです。
有給休暇取得義務化に違反した場合の罰則とは
有給休暇の取得義務に違反した場合、つまり会社が対象の従業員に年5日の有給休暇を取得させなかった場合は、30万円以下の罰金が科せられます。この違反は、労働者ごとに成立すると考えられています。そのため、従業員100人に対して違反があった場合は、最大3000万円以下の罰金に処せられる可能性があると理論上考えられます。
実際の罰則の運用は、今後の労働基準監督署の実務によりますが、違反しないようご注意ください。
就業規則にも注意!有給休暇義務化で企業が忘れてはならない手続きとは
1.就業規則への記載
今回の法改正の内容は、就業規則に盛り込む必要があります。
具体的には、会社が有給休暇を10日以上有する労働者に、その内5日について基準日から1年以内に時季を定めて付与し、労働者がその有給休暇を取得しなければならないことや、労働者自身の請求や計画年休で有給休暇を取得した場合は指定の対象外になること、また会社が指定した有給休暇日に、従業員が働こうとした場合は会社が就労を拒めることなどを記載します。
2.有給休暇の記録の作成
上記の就業規則への記載に加え、会社は、従業員に有給休暇を付与した年月日、付与した有給休暇の日数、基準日について労働者ごとに記録した年次有給休暇管理簿を作成して、3年間保存しなければなりません。
まとめ
使用者(会社側)が労働者(従業員側)に有給休暇を取得させなければいけないルールについて、様々なケースや方法があることがお分かりいただけたかと思います。
しかし、特に中小企業の場合は、労働基準法改正の運用を誤ったり、管理が不十分だと、社員が一斉に有給をとるなどして、業務そのものに支障をきたしたり、場合によっては会社が罰金を受ける恐れも生じます。
有給休暇の取得は労働者の権利ですし、社員の健康やワークライフバランス確保のためにも、労働基準法改正による有給休暇取得義務化の制度を有効に利用したいものです。有給休暇の取得義務化の運用でお悩みの場合には、専門家である弁護士にまずはお気軽にご相談ください。
- 得意分野
- 企業法務、ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設