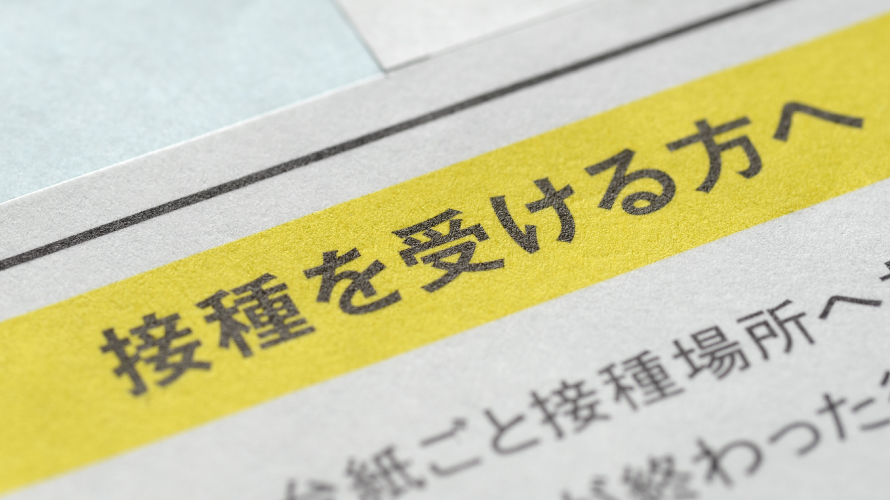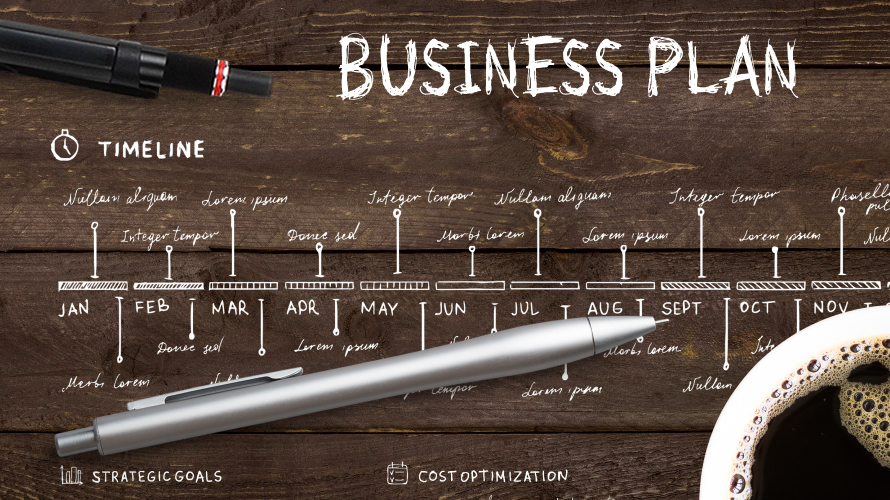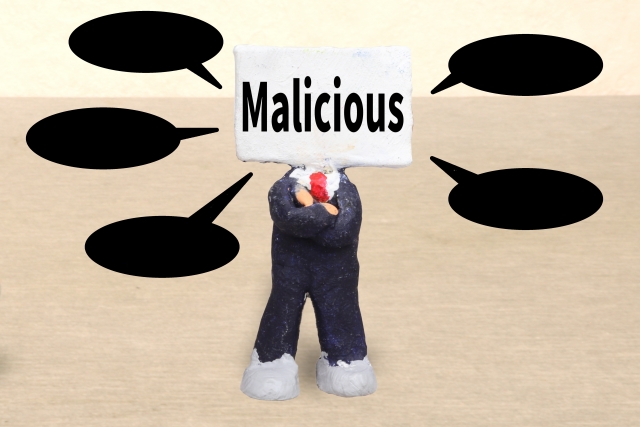カスハラとは?企業が行っておくべきカスハラ対策の必要性について弁護士が解説

相談
面談無料
東京スタートアップ法律事務所まで
記事目次
カスタマーハラスメント、いわゆる“カスハラ”は、近年、大きな社会問題となっています。
そのような状況から、ついに2025年6月、企業側にカスハラ対策を義務付ける法改正がなされました。まだ施行前であり、今後、国から指針が公表されることとなっています。
したがって、どういった言動がカスハラとなるのか、企業側としてはどういった措置を講じていけばいいのか、などといったことについては、今後公表される指針よって明確化される予定です。
もっとも、これまでに厚生労働省から公表されている「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の考えは維持されているものと想定できますので、マニュアルやこれまでの事例を参考に、今から準備し始めてみてはいかがでしょうか。
今回は、法改正の中身にも触れつつ、「そもそもカスハラってどういうことを言うの?クレームと何が違うの?」といったことや、なぜ企業においてカスハラ対策が急務となっているのか、カスハラ対策を行わないとどんなことになってしまうのか、などについてご説明いたします。
カスハラとは
これまで、カスハラを定義した法律はありませんでしたが、2025年6月4日に可決・成立した労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の改正法(以下、「改正法」といいます。)によって、カスハラは、「職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの(顧客等言動)により当該労働者の就業環境が害されること」と定義されています
出典元:厚生労働省「令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について」
他方、改正法成立前に国から公表された「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、カスハラについて、「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義されていました。
改正法における「社会通念上許容される範囲を超えたもの」であるかどうかという点については、どういうものなのか、条文を読んだ限りでははっきりしませんが、顧客等の言動の内容及びその手段・態様に着目して総合的に判断することが適当であると考えられるとされていますので(出典元:厚生労働省「女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化について(案)」)上記の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の考えが基本的に維持されていると言えるでしょう。
したがって、顧客等の要求の内容が妥当なものではない場合は、それを実現するための手段・態様が穏当なものであっても、カスハラになる可能性が高くなると考えられます。
また、逆に、要求の内容が妥当なものであったとしても、それを実現するための手段・態様が非常に悪質な場合にもカスハラになる可能性が高くなるものと考えられます。
カスハラの具体例
では、具体的にどのようなカスハラがあるのでしょうか。
どういった業種の企業なのか、どういった形で顧客と接するのかなどによって起こりやすいカスハラの態様は異なって来ると思われますが、以下で、想定されるカスハラの具体例をみてみましょう。
暴行・傷害
顧客等から従業員に対し、物理的に攻撃を加えるカスハラがあります。従業員だけでなく、他の顧客にも危険が及ぶ可能性があるので、注意が必要です。
- 接客態度が悪いなどとクレームを入れる際に、殴る、蹴るなどの暴行を加える
- 商品にキズがあったとして商品を投げつける
- 従業員を壁に押し付ける
- 要求を拒否する従業員の首を絞める
暴言・脅迫
暴力行為は伴わないものの、従業員に対し暴言を吐くというカスハラもよく見られる形です。
また、個人が簡単にSNSへの書き込みや動画配信ができるようになった現代では、「晒す」という脅しの形のカスハラも増えてきています。
- 「馬鹿野郎!」「くず!」などと暴言を吐く
- 「お前の会社のことSNSに書いてやるからな!」などと脅す
- 「ぶっ殺してやる」と言って詰め寄る
- 人格を否定するような暴言を吐き、従業員を罵倒する
不当な要求
企業側に落ち度があったとしても、そのことに絡めて過剰な金銭や土下座を求めたりする場合だけでなく、あたかも企業側に落ち度があるかのように言いがかりをつけ、何らかの対応を求める場合もあります。
- 対応にミスがあったことを理由に土下座を求める
- 落とした携帯電話が故障したのは店のせいだと言いがかりをつけて金銭を要求する
- マスクをつけていない他の顧客について、入店拒否するように求める
- 契約にない送迎など、契約内容を超えた過剰な要求をする
継続的な要求
製品の使い方の説明など、要求の内容が問題ないようなものであったとしても、同じ説明を繰り返し求め続けたり、暴言を吐いたりするわけではないものの無言電話を何度もかけ続けたりというカスハラの形もあります。
- 電話を執拗に何度もかけ続ける
- 長時間にわたり店員を拘束し居座り続ける
- 何度も来店し、その度にクレームを言い続ける
- さまざまな部署に複数回のクレームをいれる
上記に具体例として挙げたものだけではなく、特定の従業員へのつきまとい行為や盗撮などもあり、色々な形でのカスハラが考えられます。
そして、例えば、殴る、蹴るなどの暴力行為がある場合、たとえクレーム内容に妥当性があったとしても、カスハラに該当するのは当然ですが、暴行罪(刑法第208条)、傷害罪(刑法第204条)などの犯罪行為となる可能性が高い行為です。
また、暴力行為がなかったとしても、カスハラの手段・態様によって、脅迫罪(刑法第222条)や恐喝罪(刑法第249条)、名誉棄損罪(刑法第230条)、不退去罪(刑法第130条)など他の犯罪に該当する可能性もあります。
刑法だけでなく、軽犯罪法に抵触し得ることもあるでしょう。
いずれにしても、犯罪になり得るような悪質性の高いカスハラに対しては、迅速に、毅然とした態度で対応していくことが求められるでしょう。
企業がカスハラ対策を行うべき理由
カスハラ対策を行わないことで、企業によって良いことはありません。
まず、カスハラに漫然と対応していると、顧客とのトラブルが長期化・深刻化してしまう可能性が上がります。その場限りで“とりあえず”の対応を繰り返していると、最終的にどう解決すべきなのかが見えません。問題が長期化するだけでなく、訴訟に至ってしまうなど、より深刻化してしまうおそれがあります。
また、それだけではありません。カスハラは、直接対応する従業員に過度な精神的ストレスがかかることが当然予想されます。その結果、本来の業務に集中することができず業務遂行に支障が出るだけでなく、更に深刻な場合には、従業員が体調不良に陥ったり精神疾患を招くこともあり、求職や退職につながってしまうことも考えられます。企業にとって、貴重な人材を失いかねないのです。
更に、カスハラをしている顧客だけでなく、他の顧客との関係にも影響が出ることも十分に考えられます。「あそこのお店にはよく怒鳴っているお客が来ているから怖い」、「お店の人がお客さんに殴られて怪我をしたらしい」などとして会社のイメージが下がったり、「あの会社はカスハラを見て見ぬふりをして、従業員を大切にしない会社だ」などとして信用を失いかねません。今は、良い噂も悪い噂もSNSであっという間に広まってしまいますので、より問題が大きくなってしまうおそれが常にあるのです。
このように、企業にとって、カスハラの対策を行うことは、従業員を守るだけでなく、自社のイメージや信頼を守り、ひいては他の顧客や将来的な顧客を守ることにも繋がるのです。
対策義務がある
2025年6月4日、カスハラ対策を企業など雇用主側に義務付ける改正法が国会で可決・成立しました。これまでは、企業(雇用主)にカスハラ対策の法的義務はなく、各企業が独自に対策を講じているに過ぎない状況でした。
しかし、昨今、カスハラがさまざまな場面・企業等において発生し、大きな社会問題となってきたことを背景に改正の議論が進んだ結果、今回の改正法が可決・成立することとなりました。
改正法において、企業が負う義務は以下のとおり定められています。
| 第33条 (職場における顧客等の言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) 第1項 第2項 第3項 |
| 第34条 (職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務) 第1項 第2項 第3項 |
改正法の施行はまだ先(早い場合、2026年秋頃の可能性もあります)となりますが、事前に対応していくことが重要です。改正法が施行されれば、必要な措置を講じていないなど、違反が認められた場合は、厚生労働大臣から勧告を受け、勧告に従わなかったときにはその旨を公表されることもあります(改正法第42条第2項)。
また、そもそも、労働契約法第5条によって、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定められており、雇用主側は、従業員に対し、安全配慮義務を負っています。カスハラによって、従業員が心身を故障してしまうこともあり、そういった場合には、従業員が雇用主に対し、安全配慮義務違反に基づいて損害賠償責任を問う可能性もあります。したがって、改正法施行前であっても、カスハラ対策を講じることは、企業等雇用主側の責務となります。
カスハラは従業員のパフォーマンスを低下させる
改正法において、カスハラは労働者の就業環境が害されることを要件の一つとしていることからも分かるとおり、カスハラは、顧客等の対応しなければならない労働者(従業員)がまず直接的に影響を受けます。
実際に暴力を振るわれて怪我をしてしまうこともありますし、カスハラによって精神的にも少なくないストレスを受けることにより、業務に身が入らなくなり本来の業務が疎かになってしまったり、そもそも就業すること自体が怖くなってしまい休みがちになってしまう、配置換えをせざるを得ない、といったことも考えられます。
さらに、カスハラを受けていることを企業側が把握しているにもかかわらず、サポートしたり、適切な指示を出したりといった対応もしてくれないとなると、企業と従業員との信頼関係も揺らいでしまうこととなるでしょう。
そうすると、必然的に従業員のパフォーマンスは低下してしまいます。そして、それだけにとどまらず、休職や退職の原因ともなっていってしまいます。
カスハラ対応に時間と労力を割かれる
カスハラは、暴力を振るわれるといった一時的なものもあれば、執拗に無言電話をかけてきたりするような継続的なものもあります。
しかし、いずれにしても何らかの対応を強いられてしまうものです。カスハラをする顧客に対し、複数の従業員で対応しなければならない場合も多くあります。そうすると、カスハラ対応に追われる複数の従業員の本来の業務がストップしてしまったり、後回しになったりしてしまいます。
また、それだけでなく、警察への通報・相談などが必要な場合もあり、更に従業員の業務量が増えてしまいます。
つまり、カスハラ対策を行い、カスハラが発生した場合の社内フローなどをしっかりと決めておかないと、全てが後手後手に回り、余計に時間や労力を持って行かれてしまうのです。
対策を行わないと企業の社会的信用が低下する
カスハラ対策を行っていないと、適切かつ迅速にカスハラの対応ができないだけではありません。
カスハラの対応に人員を割き、時間を取られてしまうことで、他の顧客に対するサービスが疎かとなったりすることもあるでしょう。そうすると、他の顧客としては、きちんとしてサービスを受けられないという疑念がわき、そこから顧客離れが始まるおそれもあります。
会社に対する悪い印象などをSNSで拡散されてしまう可能性も十分あり、一度悪い噂が広まってしまうと、傷ついたイメージを回復するのは非常に困難です。
また、そもそもカスハラを適切に対処していない、犯罪にも当たり得るようなカスハラに対し、その場しのぎで相手の要求を飲んでいるような企業については、そういった事態を知った社会からの信用が低下する事態に繋がります。
カスハラ対策について弁護士に相談するメリット
最近では、独自に対策をしている企業も多く見られるようになりましたが、改正法の成立により、カスハラ対策は企業の法的義務となりました。
「これまでの社内の体制で十分なのか?」「今までは、特に大きな問題となったことがなかったのでまだ何も取決めをしていないからこれから全て決めていかなければならないけど、どうすればいいのか?」「今まさにカスハラの対応に困っている!」など、各企業で状況が異なり、悩みもさまざまあるでしょう。また、業種によって、起こりやすいカスハラも異なってきます。
弁護士に相談することによって、そういったあらゆる悩みについて、それぞれの企業に即した形で、適切なアドバイスを法的観点から受けることができます。
また、事前の体制整備について助言を行うだけでなく、実際にカスハラ事案が発生してしまった後の対応についても、アドバイスを受けることができます。法的観点からのアドバイスを受けことで、法的根拠のない過剰な要求等に毅然とした態度で対応をすることができるでしょう。そして、仮に訴訟に発展した場合には、代理人となって訴訟対応を任せることも可能です。
その他にも、社内研修を開催し、カスハラに対する従業員の関心を深めることを助長することもできます。
そして、何よりも、「いつでも弁護士の相談できる」という体制を整えることで、従業員が安心して働くことができるようになり、従業員の企業(雇用主)に対する信頼も高まるのではないでしょうか。
当事務所のサポート内容
東京スタートアップ法律事務所では、カスハラ対策についてご依頼いただければ、
- 社内研修の資料作成及び研修の実施
- カスハラ対策に関する社内体制整備の助言
- カスハラの相手との交渉代理や交渉に関するアドバイス
など、法律の専門家として法的な観点からサポートいたします。
また、カスハラ対策に関することに限らず、顧問契約についても常時ご依頼を承っています。
カスハラでお困りの場合は東京スタートアップ法律事務所まで
カスハラについて現在進行形で困っている、今回の改正法でどういった措置を講じればいいのかよくわかない、など、カスハラに関することでお困りの場合は、是非一度、東京スタートアップ法律事務所までご相談ください。
貴社の状況に応じて、臨機応変に、あらゆる角度から問題解決のお手伝いをいたします。
相談
面談無料
東京スタートアップ法律事務所まで
- 得意分野
- 企業法務、ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設