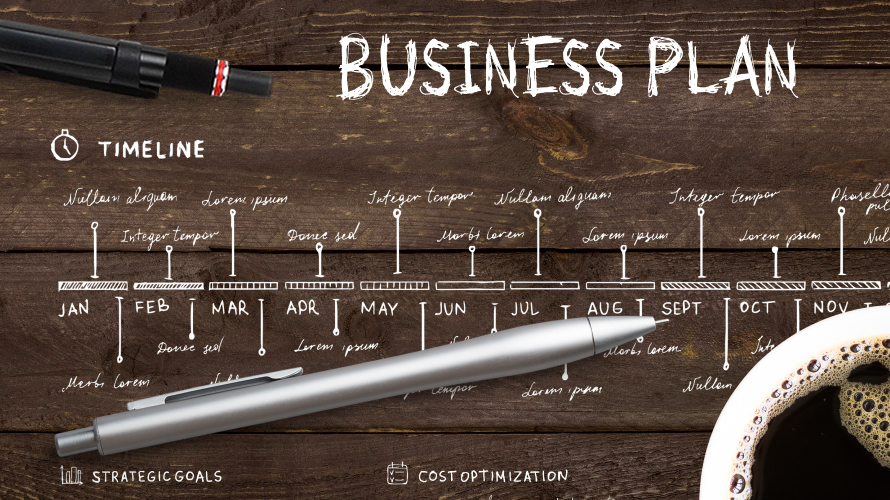企業が弁護士に相談すべき従業員トラブル|労働問題に強い弁護士の選び方

全国20拠点以上!安心の全国対応
記事目次
働き方改革関連法等の施行以来、日本の労働環境は大きく変わり、また、会社に対する従業員の心身の健康への配慮の要請も高まっています。
過去には、うつ病で休職していた従業員が休職期間満了を理由として解雇されたことについて、うつ病の発症が会社の過重な業務に起因する労災にあたるとして解雇の無効と安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償を求めた裁判で、会社は業務の軽減などの対策を講じるべきであったのに怠ったとして従業員の請求を全面的に認める最高裁判例が出されるなど(最高裁第二小法廷平成26年3月24日判決「東芝事件」)、会社側が取るべき対応も高度化しています。
会社は、従業員の安全に配慮し、適切な労働環境を整えなければいけませんが、一方で従業員から不当な要求を受けた場合は毅然とした対応をしなければ、会社の存続自体も危うくなってしまいます。このような場合は、社内だけで解決しようとするのではなく、弁護士など外部の専門家のアドバイスを受けることにより後々の不利益を回避できる場合が多いでしょう。
そこで今回は、会社が直面する労働問題や、従業員とのトラブルが発生した場合の弁護士の選び方などについて解説します。
企業が直面する労働問題の典型例
労働問題とは、使用者(会社であることが多い)と労働者(従業員)の間で、雇用関係について生じるトラブルの総称をいいます。内容は多岐に渡りますが、ここでは会社側が直面しうる労働問題の典型例について解説します。
1.会社のルールに関する労働問題
①就業規則の作成
就業規則は、従業員が働く上での労働条件や守るべきルールを定めた規則のことです。常時10人以上の従業員を使用する事業所において、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出ることが義務付けられています(労働基準法第89条)。就業規則には、労働時間、休憩休日、賃金、解雇事由といった必ず就業規則に記載しなければならない絶対的必要記載事項(労働基準法第89条1号~3号)、退職手当や臨時賃金、職業訓練といった制度がある場合には就業規則への記載を必要とする相対的必要記載事項(労働基準法第89条3号の2以下)、会社の理念や就業規則の施行日、改正日といった附則など就業規則に自由に記載することができる任意的記載事項があり、記載すべき事項か否かはその内容によって異なります。就業規則は、労使間の紛争を未然に防ぐ役割を担うとともに、紛争が発生した場合には会社を守る根拠となります。
②雇用契約書の作成
会社が従業員を雇い入れる場合、賃金や労働時間など一定の労働条件(具体的な項目については労働基準法施行規則第5条1項を参照)を明示することが労働基準法で義務付けられています(労働基準法第15条1項)。雇用の際の労働契約書の作成は義務ではありませんが、労働条件のうち、労働契約の期間、更新する場合の基準、就業の場所、従事すべき業務、労働時間、賃金、退職に関する事項(労働基準法施行規則5条1項1号~4号)は、書面による明示が義務づけられているため(労働基準法15条1項)、上記の条件を労働条件通知書という書面で交付するか、雇用契約書を作成して記載する必要があります。
就業規則の作成義務や労働条件の明示義務に違反すると、30万円以下の罰金に処せられる可能性があり(労働基準法第120条1号)、その内容が労働基準法に違反すれば、違反部分が無効になる可能性があります。また、未払い残業代や解雇などの場面で後々問題になるおそれもあります。
③コンプライアンス
コンプライアンス(法令遵守)は、最近特に重視されています。会社が法令遵守の体制を整えず、運用が適切でない場合は、従業員に内部告発や公益通報をされるおそれがあります。
昨今は従業員によるSNSでの不適切な発言や発信などがコンプライアンス上の問題となることもあります。企業に対する社会的な評価に影響する重大な問題に発展する可能性もあるため、従業員に対するコンプライアンス教育を徹底するなど、未然に防止するための対策を講じることが大切です。
2.賃金に関する労働問題
①未払い残業代の請求
退職した従業員から未払いの残業代の請求をされた場合にこれを無視して、放置するようなことがあると、労働基準監督署の事情聴取や立ち入り調査が入り(労働基準法101条、104条の2)、法律に違反する行為がないか確認されることがあります。場合によっては、労働基準監督署から雇用主に、残業代を請求した従業員だけでなく、全従業員に対しての未払い残業代の支払いが命じられたり、労働審判を申し立てられる等して訴訟等対応をしなければならなかったりと、大きなトラブルに発展する可能性もあります。しかし、不要な残業についての残業代の請求や、不適切な計算に基づく残業代請求に応じる必要はありませんので、請求された内容を検討し、適切に対処する必要があります。
②歩合給制の残業代
営業職やタクシー運転手など、歩合や出来高払い制の賃金体系の従業員から残業代を請求される場合があります。タクシー運転手のケースで、通常の労働時間の賃金と時間外及び深夜の割増分の賃金が明確に区別されていない場合は、会社が残業代込みの歩合給を払っていた場合でも残業代の支給とは認められず、会社は割増賃金を支払わなければならないという裁判例があります(最高裁第二小法廷平成6年6月13日判決)。歩合制の場合は、歩合給部分と割増賃金部分を明確にするなど、特に契約条件に注意する必要があります。
③名ばかり管理職の残業代
管理職(監督管理者)とは、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」をいいます(労働基準法第41条2号)。管理職に当たる人は、労働時間や、休憩・休日の規制が適用されないため、深夜労働に対する深夜割増賃金を除き、残業代が発生しません。しかし、飲食店の店長など、名目が管理職であるだけで残業代や、本来管理職でも支払われるべき深夜手当が支払われなかったことが問題になりました。管理職か否かは、①職務内容、企業の経営に関わる重要な事項についての関与の程度や部下に対する労務管理上の権限の有無といった観点から統轄的な立場にあるか否か、②労働時間についての裁量権の有無、③職務内容や管理職の責任に見合った管理職手当による残業代分の補填といった給与面での待遇がきちんとなされているかの3点に留意し、経営者と一体的立場にあるかを実態に即して個別に判断すべきとされています。
3.解雇に関する問題
①不当解雇
解雇は、会社が従業員との労働契約を一方的に解約することです。解雇するために従業員の同意は必要ありませんが、会社が自由に解雇できるわけではありません。解雇する際は客観的・合理的な解雇理由があり、社会通念上相当でなければならず(労働契約法第16条)、これを欠く解雇は解雇権の濫用として無効とされます。また、解雇の方法についても、労働契約の中途解約である普通解雇(経営上の理由で解雇する整理解雇はこれに含まれます。)なのか、懲戒処分としての懲戒解雇なのかなど、理由に応じて判断する必要があります。また、解雇に向けて、事前に解雇以外の対策を講じなければ不当解雇として訴えられる可能性があります。
②うつ病等を原因とする社員の解雇
病気やけがで働けない場合は、解雇の理由になり得ますが、特に慎重な手続きが必要です。具体的には、労働基準法で病気やけがで休職中の期間及びその後30日間は解雇が制限されており(同法第19条1項)、障害者雇用促進法では、心身の障害をもつ従業員に会社が合理的な配慮をすることが義務づけられています(同法第5条)。実際、被害妄想などの精神的不調で約40日間にわたり欠勤をした社員を就業規則に基づいて諭旨退職の懲戒処分としたケースで、欠勤は就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤に当たるとはいえず、会社は精神科医の診断を得て休職させるべきだったとして解雇を無効とした裁判例があります(最高裁平成24年4月27日判決「日本ヒューレット・パッカード事件」)。このように、メンタル疾患の従業員への対応は特に注意を要します。適切な手続きを経ることなく解雇した場合、従業員から不当解雇だとして訴えられて会社側が多額の損害賠償責任を負うおそれもあるため、慎重な対応が求められます。
③試用期間中の解雇
試用期間は、従業員の資質等を知り、採用の最終的な決定をするための期間です。試用期間中は解約権(解雇することができる権利)が留保されているとして、会社には通常よりも広い解約権(解雇することができる権利)が認められています。しかし、試用期間といえども労働契約はすでに成立しているため自由に解雇できるわけではなく、通常の解雇と同様、本採用を拒否するための客観的・合理的な理由が存在し、社会通念上相当でなければなりません(労働契約法16条)。また、試用期間中であっても、試用開始から14日を超えて解雇する場合は、通常の解雇同様に少なくとも30日前の解雇予告か解雇予告手当の支払いが必要です(労働基準法21条但し書4号)。
4.労働災害に関する問題
①安全配慮義務
安全配慮義務とは、従業員が働くにあたって、会社側が従業員の生命や健康を危険から守るよう配慮すべき義務を言います。安全配慮義務の内容はさまざまで、従業員の職種や仕事の内容など、具体的状況によって異なるものとされています。そのため、安全装置や防犯設備の設置と言った設備上の配慮だけでなく、従業員の労働時間や業務内容が過大ではないかの把握など、人的な面での配慮も求められます。
安全配慮義務は会社の経営者だけではなく、現場で従業員を指揮する管理職にも課されているため、管理職が安全配慮義務を果たせるよう適切な研修等を行うことも大切です。
②労災でけがをした社員への対応
業務上けがや病気をした従業員が休職中及び復職後30日間は、解雇は禁止されます(労働基準法第19条1項)。ただし、天災等で会社の事業を継続できなくなった場合(ただし、労働基準監督署の除外認定が必要です。)、と、労働基準法75条によって補償を受ける従業員が療養開始から3年たっても治癒しない場合に打切補償としてその従業員の平均賃金の1,200日分を支払う場合(労働基準法81条)は、例外的に解雇をすることができます。また、労災保険金との関係では、療養開始から3年が経過した日に傷病補償年金を受けている場合は療養開始後3年を経過した日に、3年を経過した日には受給していなかったがその後に傷病補償年金を受けることになった場合は傷病補償年金を受けることになった日に、打切補償が支払われたとみなされ、解雇できることになります。しかし、労災で解雇禁止の例外に当たらないのに解雇した場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられるので注意が必要です(同法第119条)。
③下請会社の事故
元請会社と下請会社は本来別の独立した会社(事業者)なので、下請会社の従業員の業務上の事故について元請会社は責任を負わないのが原則です。しかし、元請と下請の間に、実質的な使用関係や間接的指揮命令関係がある場合は、元請会社が下請会社の従業員に安全配慮義務を負う場合があります。その場合は、元請会社も被害を受けた下請会社の従業員に対して、損害賠償責任を負う可能性があります。
5.犯罪行為やセクハラ・パワハラに関する問題
①犯罪行為
会社内での不正行為に限らず、社員が業務に起因して犯罪行為をする場合というのも発生する可能性があります。窃盗、横領、背任など会社の業務に関する金融犯罪、会社の飲み会や社員旅行での強制性交等罪や社内での盗撮、通勤途中の痴漢、業務中の車の事故など、類型は多岐にわたります。犯罪行為は要件を満たせば懲戒解雇事由になり得ますが、当該従業員の解雇にとどまらず、会社として被害者や社会的に何らかの対応を取ることが求められる場合もあります。会社の評価や取引先との関係にも影響するので、注意深い対応が求められます。
②セクハラ・パワハラ
セクハラやパワハラは、それらを行った従業員について、態様によってはそれ自体が犯罪行為になることもあります。また、企業側が自社の役員や従業員による、他の従業員に対する嫌がらせや不当な圧力を放置していたり、被害を受けている従業員からの相談や苦情を受けたのに配慮を欠く対応をしたりすると、会社は債務不履行に基づく損害賠償請求(民法第415条)や、使用者責任に基づく損害賠償請求(同法第715条)をされ、訴えられる可能性があります。
③マタハラ
昨今、ハラスメントの中でもマタハラが問題視されています。平成28年に男女雇用期間均等法及び育児介護休業法が改正され、平成29年1月1日から、ハラスメントの発生防止の措置をとることが会社に義務付けられ、女性の妊娠や出産を理由にした左遷等は、男女雇用機会均等法(第11条の2)や育児・介護休業法(第25条)に違反するとして問題になります。
④リモートハラスメント
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、2020年頃から在宅勤務やテレワークを導入する企業が急増しました。在宅勤務やテレワークの増加と共に問題となったのが、リモートハラスメントです。リモートハラスメントとは、リモートワーク中のパワハラやセクハラなどのハラスメント行為を意味します。
リモートハラスメントは、周囲の人の目が届きにくく、エスカレートしやすい傾向があるため、被害を受けた従業員が相談できる窓口などを設置するなど早期発見のための対策を講じることが大切です。
従業員とのトラブルを弁護士に依頼すべきケースと手続きの流れ
従業員とのトラブルが発生した際に、社内で対応すると、お互いの感情がぶつかり合い、さらなるトラブルに発展するリスクがあります。リスクを避けて、トラブルを円満に解決するためには、弁護士などの専門家の立ち会いのもとで話し合いを進めることをおすすめします。弁護士への依頼を検討すべきケースについて説明します。
1.訴訟外で従業員と交渉する場合
解雇した元従業員から解雇の無効を主張されたり、退職した元従業員から未払い残業代の請求を求める内容証明郵便が届いたりする場合があります。このような場合は、会社側の資料をもとに元従業員の主張を確認して対応方針を決定します。元従業員との交渉においては、会社が保有する資料をもとに、主張すべき事実を提示して話し合いを進めていくことになります。
合意に達すれば、合意書を作成し、本問題の事実関係、合意に至った内容、双方の口外禁止条項、これ以上の請求がないという清算条項などを記載して双方が署名・押印して1通ずつ保管します。合意に至らなければ、以下で説明する労働審判や、裁判に至る可能性があります。
元従業員から、労働問題について内容証明郵便などの書面が届いた場合は、まずは弁護士に相談して、客観的な証拠資料に基づく事実の確認と会社の主張の方針を決め、早期の円満な解決に向けたプランを検討しましょう。
2.労働審判になった場合
労働審判は、裁判官1名、労働者側と使用者側の専門知識を有する者2名の計3名で、原則3回以内の期日で当該事案に関する審理をし、適宜調停成立を試み、調停が成立しない場合に労働審判を行うことで問題を解決しようとする手続です。
労働審判の対象になるのは、「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」(労働審判法1条)で、具体的には解雇や未払い残業代請求、セクハラ・パワハラ、労災に関する問題など、会社と従業員に関する個別の労使紛争です。
申立てから平均2ヶ月半で約70%のトラブルが解決しており、迅速な解決方法として非常に有効です。ただし、予想される争点を整理して証拠を集め、従業員との話し合いの経緯などをまとめた答弁書を提出したり(労働審判規則16条)、審判の期日では事実関係や法的主張を尽くさなければいけませんし、指定された第1回目の期日に欠席したり、期日を変更したりすることは原則認められておらず、第1回目の期日を代理人だけで対応することは許されません。そのため、争点に関する事実や証拠は答弁書で詳細に全て記載する必要があります。
労働審判になった場合は、弁護士に相談して適切な対応を依頼すべきです。
3.団体交渉になった場合
団体交渉には、会社内の労働組合から申し込まれるケースと、ユニオン(社外の合同労働組合)から申し込まれるケースがあります。正当な理由なく団体交渉を拒否することは「不当労働行為」として労働組合法7条2号で禁止されているので、会社は団体交渉を申し込まれた場合は応じなければなりません。特にユニオンは社内の労働者だけではなく、同業種や隣接業種の会社の労働者が集まって組織されていたりすることから、強硬な場合もあり、1回の団体交渉が長時間に及ぶ場合もあります。指定された時間に必ず応じる必要はありませんが、むやみに延期したり、時間制限を設けたり、2回目以降は応じないなどとすると、誠実をもって団体交渉に当たらなければならないという誠実交渉義務に反し、不当労働行為と判断されます。
人事権が社長のみにあるような中小企業の場合は、社長も出席しなければならず、人事部がある場合はその担当が出席をします。弁護士に委任しても、弁護士しか出席しないとなるとやはり不当労働行為とされるおそがあるので、会社側の責任者の出席は必須になります。団体交渉で不用意な発言をすると、相手に言質を取られて不利な交渉を進められるリスクもあり、慎重な対応が求められます。専門の弁護士に相談し、あらかじめ会社の主張を整理し、反論を準備しておくなどの対応をとることが重要です。
労働問題で弁護士に依頼した場合の費用の相場
弁護士に相談したいけれど、どの程度の費用がかかるのか事前に把握しておきたいという方もいらっしゃるかと思います。労働問題で弁護士に依頼した場合の費用の相場について、説明します。
1.相談料
弁護士に法律相談を依頼した場合の初回の相談料の相場は、1時間1万円程度です。2回目以降の相談料は弁護士によって異なりますが、概ね1時間1万円から2万円程度が目安です。
2.顧問契約の場合の弁護士費用の相場
弁護士と顧問契約を結ぶと、会社で生じる労働問題などのトラブルや心配事について継続的に相談をすることが可能です。
顧問を依頼した場合、会社の規模やサービス内容等によって料金は異なりますが、月額で5万円~30万円程度の費用がかかります。
顧問契約を検討している場合は、自社の業務や生じうる労働問題を踏まえて、法律相談などで実際に話をした上で決定することをおすすめします。
3.個別の労働問題を依頼した場合の弁護士費用の相場
個別の労働問題を弁護士に依頼した場合、依頼段階でかかる着手金、事件が終了した場合の成功報酬、裁判などのために出廷した場合の日当や交通費、印紙代や郵送代などの実費がかかります。
着手金の相場としては、10万円から30万円程度になることが多いようです。
成功報酬は、事件解決で得た経済的利益によって変わりますが、固定報酬だと20万円~50万円、経済的利益の割合に応じて決められている場合は、減額した金額の10~30%が相場のようです。
日当は、審判や裁判に出廷したごとに1回3万円~5万円としている場合や、出廷する裁判所までの所要時間や距離で基準を決めている場合もあります。
郵送代や印紙代などの実費は、弁護士に依頼しなくても発生する費用です。
以上の費用は、顧問契約を締結している弁護士・法律事務所に依頼すると、多少のディスカウントをしてもらえるケースがあります。
企業側の労働問題に強い弁護士の探し方
企業側の労働問題に強い弁護士を探す場合は、次のような方法が考えられます。
- 経営者の知人や身内などからの紹介
以前その弁護士に依頼したことがあるなどの経緯があれば、弁護士の人となりや対応方法を聞くことができるので、ニーズに合った弁護士を探しやすいです。 - インターネットでの検索
労働問題を扱う弁護士は、企業側の問題に強い弁護士と、従業員側に強い弁護士がいます。検索する際は「企業 労働問題 弁護士」、「会社側 弁護士」など、企業側のニーズに合った弁護士に関するキーワードを用いましょう。
弁護士を選ぶ際は、労働問題の実績が豊富であることを重視しましょう。インターネットで検索する場合は、実績や説明のわかりやすさを見るとよいでしょう。知人や身内から紹介を受けた場合も、その弁護士の公式サイトはご自身の目で確認しておくことをおすすめします。
上記のように、弁護士に依頼すると着手金や報酬金などの費用が発生するため、まずは法律相談に行き、その弁護士の説明がわかりやすいか、質問にはっきり回答するかなど、ご自身のニーズに合うか判断してください。
そして、弁護士費用が明確か、後から認識していなかった追加料金が請求されないかなども合わせて確認しておきましょう。
企業が抱える従業員とのトラブルを弁護士に依頼するメリット・デメリット
労働問題は、多くの場合、従業員や元従業員からの主張・請求から始まります。企業が労働問題を弁護士に依頼するメリットは、主張や請求があった段階で相談、依頼することで、早期の解決を望める点です。
また、頻繁に変わる労働関連法規や裁判をフォローし、適切な根拠に基づいた主張ができること、客観的な証拠や資料に基づいた反論ができることも大きなメリットです。
さらに、会社側の代理人として交渉してもらうことができるので、対応に係る負担を大きく減らすことも可能です。
反対にデメリットとしては、前述したような費用がかかることです。また、弁護士選びに失敗し、労働問題の経験が浅い弁護士や、方針が合わない弁護士に依頼すると、会社側の求めている主張をうまく行えない結果、期待していた問題の解決に至らない場合もあるので、依頼する場合は相談・質問を十分にして、信頼できる弁護士を選任してください。
まとめ
今回は、企業側が抱える労働問題の具体例や、対策のポイント、従業員とのトラブルが発生した場合の弁護士の選び方などについて解説しました。
会社に法務部がある場合でも、外部の弁護士に頼むことで客観的なアドバイスを受けられたり、最新の法令や情報に基づいた適切な主張ができたりするケースもあります。労働問題の対策を誤ると、労働審判や裁判など対策に労力を要するだけでなく、外部に知られると会社の評判や株価にも影響する恐れがあります。労働問題は早期の対応が重要です。
東京スタートアップ法律事務所では、数多くの会社の顧問をしており、企業側の代理人として弁護活動をしています。また、労使間の紛争を予防する手段についても心得ておりますので、労働問題でお悩みの会社の方は、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
- 得意分野
- 企業法務、ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設